「本居宣長」小林秀雄 超訳
「本居宣長」-24章(2022/2/24)※小林秀雄の「本居宣長」を毎月少しずつ読む共読サロンを主催しています。ご興味ある方はこちらからお問合せ下さい。
https://peraichi.com/landing_pages/view/demian
「本居宣長」-1章
小林秀雄が宣長の旧跡に赴いた話。伊勢松阪の人で「鈴屋遺跡」の名で今も残る。(宣長は学問しながら眠くなると気に入りの鈴を鳴らしながら勉強していて、自身の教室を鈴屋と呼んでいた)
彼の墓は二つあり、当時の習慣に沿ったお寺のものと遺言状で自分の好みの仕立てにして欲しいと頼んだ心の墓がある。七尺四方に石を敷き、丸い塚を土で固めて芝で覆う。粗末にしてくれと何度も言いながら、大好きだった山桜にはこだわった。いい桜を吟味して、枯れたら植え替えてくれと頼み、それだけでは足りずに花ざかりの桜の絵を描いている。
細かく簡素にどんな葬式を上げるかを書き連ねるところ実はこれがまさに宣長らしい文体で小林秀雄は「この、ほとんど検視人の手記めいた感じ」が
宣長の文体だと書いている。
自分と妻の戒名も国学風に自分でつけたいと決めてしまった。
彼はこの遺言書を書いて後秋の半ばから冬にかけて桜の歌を300首も詠んだ。桜狂いであった。(翌年11月に71歳で没)
前年には春に実際に吉野山に行き、桜を多く詠んだ「吉野百首詠」を書いているが、秋の夜長に寝付けぬ時に桜を思って歌を詠みこれを「まくらの山」と呼んでいる。
61歳の時に詠んだ歌が自画像と共に有名だ。
「しき嶋の やまとこころを ひととはは朝日ににほふ 山さくら花」
「本居宣長」-2章
宣長がこのように死後の事を考えることは弟子たちには日頃の教えと違うように思われた。養子の大平は一緒に国学風の墓地を立てる土地を見に行った時に日頃「無き後の事思ひはかる」は「さかしら事」と教えられていたじゃないですかと意義を申し立てたが黙殺されたと日記に残している。
宣長の熱烈な弟子だった平田篤胤も彼の辞世の句をとても大事に扱っていたが小林秀雄には辞世の句も墓も単にこうしたよという程度のことに思われ、
むしろ彼のそのような思考が最も近い人にも伝わっていなかったことが面白く感じられるという。
どうしてかというと、彼は自分の生活感情に沿った文体でしか自分の思想を表現できなかった。だから後世の研究者達も彼の思想の不備や混乱が目につくことは変わらないらしい。
小林秀雄は、村岡典嗣氏の研究が最も優れていると考えているが思想構造という側面からアプローチしていてやはりどうしても悪戦苦闘している。
宣長はきっと単に「自分はこう思う」と言っただけだったのだ。
だがそれがあまりに日本の思想に重要な事件だった。
だから彼の遺言からこの本を始めたのはいわば劇のような彼の思想の幕切れを見て彼の肉声から多く語っていこうと思っていることを伝えたかったからだ。
宣長の最初の著述は「葦別小舟(あしはけをぶね)」という。
『万葉集』巻11-2745 寄物陳思 の
港入りの 葦別け小舟《をぶね》 障《さは》り多み
我《あ》が思ふ君に 逢はぬころかも
から取られている。
障害物が多くてあなたに逢えないと漕ぎはじめた舟最後まで漕ぎ手は一人という姿は変わらなかった。処女作にその人の天びんが現れるというけれど
幕切れまで彼の思想の演じられる様が現れているのである。
https://art-tags.net/manyo/eleven/m2745.html

「本居宣長」-3章
宣長は松阪の商家小津家の出身だった。
小津家は代々木綿業者で、曾祖父頃から江戸に出店を持ち有力な富豪となっていた。
「玉かつま」という宣長の随筆に「伊勢国」という文があって、
にぎやかで旅人も多く実りも多い、江戸に手代を置いて国で遊んでいるあるじも多く上辺はそうでもないが内々はおごりてまこと少なしと書いている。
宣長は1730年生まれ。
11歳の時に父が江戸の店で死に、弟1・妹2とともに母お勝の手で育てられた(ので、頭が上がらない)。19歳で紙商今井田家に養子にやられるが、21歳で戻る。学問に打ち込むことが叶わなかったため離縁したようだ。
本居家を継ぐために養子で入った義兄は宣長22歳の時に江戸の店で病死し家業は倒産した。
書を読むことが好きで商いに疎い事から母から医師の道を勧められ23歳で京都に行き医学と儒教を習い、のちに松阪で小児科医を開業した。
医学は生活の手段であり、彼にとって大事な学問でなく医学で生計を立てることは男らしくないことだったが家を没落させることも道から外れるので
力の及ぶ限りそちらもやろう、と述べている。
同時代、宣長の初期の思想に影響した伊藤仁斎は周囲から医学を生業とすることを進められたがガンと断っており、本書では両者の言い分が併記されているので味わってみて欲しい。
宣長の書いた「六味地黄丸」の広告文も面白い。
薬というのは素材と丁寧な製法が大事で、それを丁寧に作ったのだ云々とくどくどしく書いていてこれで売れたのだろうかと心配になる(笑
宣長は丹念に帳簿を残しており、帳簿を「済世録」と名付けた。没年まで印し続けている。
学問の著作では決して「済世」という言葉は使いたがらなかった彼である。
最も忙しかったのは52歳の年、病家448件、調剤8165服、謝礼96両だそうだ。この頃も門人は随分増えていただろう。
講義中も外診の為、度々中座したと伝えられている。
「本居宣長」-4章
宣長69歳の年に加賀藩(石川県)から士官の話がきた。
加賀藩藩校である明倫堂が落成し、国学の学頭にというのだが、松阪居住で、京都くらいまでなら行っても良いからそれで良ければ的な返事を書いてそこまでになっている。
彼の学びは名誉心など全く育まなかった。
宣長の一番弟子大平が宣長の学問の由来を書いた「恩頼図」というものがある。
系譜は多岐だがその中心に
「父主念佛者ノマメ心」と
「母刀自遠キ慮り」と
書かれている。
彼は儒教も学び、国学も読んでいたが特に和歌が好きで色々と読んで師もなく学んでいた。
京都で医学を学んでいた頃に契沖の「百人一首改観抄」を読んで「歌まなびの筋の良し悪し」を知ったと書いている。契沖の著を読み漁った。
だがこの頃の日記に書かれているのは国典にも通じた学者だった景山の儒教の教室で水を得た魚のように時を過ごす彼の遊んでいるのか学んでいるのかという様だ。
他愛無い水のことが書かれ国文学には触れられてもいない。
(つまり小林秀雄は魚としての宣長の魅力を何とか掴まえようとしているのである)
「恩頼図」
http://www.norinagakinenkan.com/nor.../kaisetsu/onraizu.html
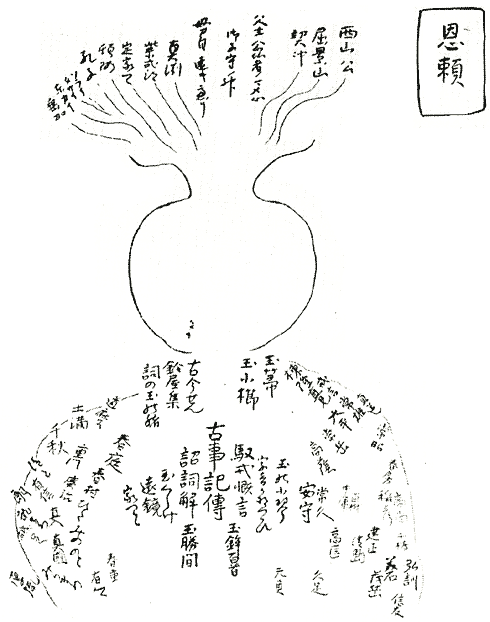
「本居宣長」-5章
宣長の遊学時代に友人にあてた手紙が八通遺されている。
宣長が仏説に興味を寄せていることに文句を言われた時には仏氏の言も儒墨老荘諸子百家皆これを好み、信じ楽しむと返し(「好信楽」と小林秀雄はまとめている)
和歌を好むのを難じた者へは儒教こそ「天下を治め民を安んずる」聖人の道で孔子でさえも実現できなかったのにどうしてそれをもって自分を生かせるかと返している。
宣長の思想の種と言うのは簡単だが
71歳の時に
聖人は しこのしこ人 いつわりて よき人さびす しこのしこ人
という歌を詠んでおり、生涯崩れない彼の態度だった。
彼にとって問題で切実だったのは相手が儒学を自ら掴んでいるか、ただ儒学につかまってしまったに過ぎないのかということであった。
「本居宣長」-6章
宣長は契沖の「百人一首改観抄」からどんなことを学んだか。それは古歌や古言にはその「本来の面目」があるということである。
もののあはれを初めて体系的な形で提唱した「柴文要領」という著では
「やすらかに見るべき所を、さまざまに義理をつけて、難しくことごとしく註せる故にさとりなき人は、げにもと思うべけれど、返ってそれはおろかなる註なり」と言っている。
この事を宣長は契沖が初めて開いた「一大明眼」と呼んでいる。
契沖も宣長も歌をたくさん詠んだ。
少年時代から生涯の終わりまで「面白からぬ」歌を詠み続けている。
彼は「他のうへにて思ふと、みづからの事にて思ふとは、深浅のことなるもの」と述べ、歌の学問に歌を詠むことが必須と考えていた。
そしてこれは学問についても同じで契沖が至った方法を使うということでなく同じように見る目を自分事として得たのである。
だから、晩年弟子たちに「学びやうの法」を書いて欲しいと乞われいやいや「うひ山ぶみ」を書いたのだが一向気が進まないと冒頭で書き、詮ずるところ年月長く倦まず怠らず励みつとむることが肝要、などと述べることになる。
宣長は「考へ」とは「むかへ」の意だと言っている。
(かむかふ→むかえるという言葉という)
古人が考えたように考えられる、自らのこととするということ。このことが宣長の考える学問であり、このことを彼は契沖から学んだのだった。
「本居宣長」-7章(2020/10/28)
この章は宣長が「学問の基本姿勢」のようなものを感化され、影響を受けた
契沖の生い立ちをたどり、契沖がそこにたどりついた流れを考察している。
契沖の父は加藤清正の臣の家系だったが加藤家が改易された時に没落し、浪人して北越に没した。契沖は末っ子だったが兄の如水は長子として家を再興しようと奔走したが果たせず、最後は摂津の契沖の元に身を寄せて契沖の仕事を助けて死んだ。
宣長が最初に衝撃を受けた伊勢物語の注釈書(勢語臆断)も如水が写して世に出たもので、自身の死の直前まで如水の挽歌を遺している。
契沖は高野山で出家して10年修行し25歳で阿闍梨位を得ているが、その後放浪して自殺企図したり苦悩をずっと抱えて生きた。
高野山で修行中に出会った20歳上の国学者、下河辺長流と友誼を結び長く交流している。
長流が水戸藩から頼まれて果たせず病死してしまった万葉集の注釈を引継ぎ「万葉代匠記」として仕上げた。
代匠とは代わりにという意味で、「かのおきな(長流)がまだ若かりし時、かたばかりしるしおけるに、おのがおろかなるこころをそへて、萬葉代匠記と名づけてこれをささぐ」と序で書いている。
兄の死を悼むのも、失意に死んだ父に手向けるのも、士官の道が途絶えて父母兄妹を失った苦しみの中でも契沖は歌を詠んだ。
その表現について小林秀雄は長流にとって歌は心を慰めるものだったかもしれないが、契沖にとっては「心を見つける道」だったと書いている。
例えば契沖の歌はこうで、
葛か(枯)れし 冬の山風 聲(こえ)たえて 今はかへさむ ことの葉もなし
それに返した長流の歌は
冬かれん 物ともみえず ことの葉に いつも玉まく 葛のかへしは
というもの。
もちろん失意にあって、嘆きの歌を送っているのは契沖なのだが長流はそれに生命と言葉の力と希望で返しているように見える。「玉巻く葛」というのは本来は初夏の季語で地を這い木に巻いて蔓を伸ばす葛の先の巻葉のことなのだ。
だが、このあくまで心情をそのまま述べる契沖に小林秀雄は宣長の「好・信・楽」へ通じるものを見た。
宣長が驚き書写した契沖の「勢語臆断」では、在原業平が病で死にそうになった時に詠んだ
つひにゆく 道とはかねて 聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを
について、
人は死のうとする時には悟ったようなことや大仰なことを書いてしまうものだし、普段の時にはふざけたり飾ったようなことも書ける。
だが、今はという時の歌こそ心のまことを表していて、ここには一生のまことが表れている、と書いている。
この契沖の注釈を宣長は晩年に「やまとだましひなる人は、法師ながら、かくこそ有けれ」と絶賛した。
最後にこの章は契沖の遺文で終る。
契沖は「万葉代匠記」の褒賞として水戸公から白銀千両、絹三十匹を賜ったがお寺の費えに当ててしまったようだ。
遺文でも水戸公から毎年頂いている手当は自分の無力で頂いてきたもので、
本意でないのでお返しして欲しいと書いている。
質実な一生であった。
「本居宣長」-8章(2020/11/26)
7章で取り上げた契沖の書簡に「さるにても閉口候はば、いよいよ独り生れて、独り死に候身に同じかるべき」という表現があって面白い。特にこの時代の基盤、戦国というものに繋がっているように感じられる。
(泉州誌の編纂を指導していたいわば弟子筋の石橋新右衛門直之に送った書簡にある文。書かれたのは元禄八年=1696年、契沖56歳、亡くなる6年前の手紙だ。)
応仁の乱(1467年)以来100年以上、日本のどこかで戦争が起こっていない時はない、まさに戦国時代だった。
戦国を一貫した風潮を「下剋上」と言ってもいいと思う。
(下剋上の言葉が初めて現れる二条河原の落書は1335年。
此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨
召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)
生頸 還俗 自由(まま)出家
俄大名 迷者
安堵 恩賞 虚軍(そらいくさ)
本領ハナルヽ訴訟人 文書入タル細葛(ほそつづら)
追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧 下克上スル成出者(なりづもの)・・・)
大言海で「下剋上」の言葉を引くと「此語、でもくらしいトモ解スベシ」とある。随分乱暴かも知れないが、実力が虚名を制すると考えれば健全といってもいい動きだ。
乱世は「下剋上」の徹底した実行者秀吉によって一応のケリがついた。その秀吉が残した辞世の句は
つゆとをち つゆときえにし わがみかな なにはのことは ゆめのまたゆめ
というもので、もはや克つべき相手のいなくなった嘆きとも取れる。この後が家康の時代だとは彼も悟っていただろうが、己に克つという心の戦いへと時代が移っていくことは彼の意識外だったかもしれない。
中江藤樹が生まれたのは秀吉が死んで10年後のことだ。藤樹は弟子に学問こそが天下の第一等、人間の第一義であり、他になすべきことなく、剣戟にも良知で向かうと述べた。秀吉は手紙に「てんか」と著名したが、藤樹は天下を心の世界に向けたのである。
藤樹の在世中に門人によって作られた「藤樹先生年譜」が遺っている。9歳の時に祖父が彼を育てるために連れに来て、両親は拒んだものの無理やり連れて行った。それでも藤樹は物に愛着せず、父母を離れても哀しまずそれでいてよく父母に孝を示したとある。
藤樹が13歳の時に大雨で飢饉となり農民が土地から逃げようとしたことがあった。その時に法によってこれを留めようとした祖父に須トという罪人が切りかかり、祖父は彼を槍で刺し殺した。須トの子がこれを恨んで火矢を屋敷に射掛け、討ち入ろうとしたことがあったが、藤樹は全く恐れず一人屋敷の周りを巡回したという。14歳の時に祖父の家に家老らが夜に来て終夜話し込むのを隠れて聞いていたことがあったが、何ら常人と変わることなく落胆したことが記されている。後祖父母が死に、近江の父も死んで母のみ残った。母のもとに戻ることを願ったが容れられず、脱藩して村に還り酒を売って母を養った。彼は「全孝の心法」を説いた。母を養う事と学問とがつながっていて、これは朱子学でも陽明学でもない。
(藤樹の『孝経啓蒙』に「身の本は父母なり。父母の本は之を推して始祖に至る。始祖の本は天地なり。天地の本は大虚なり。」という言葉があり、すべての徳行の元が孝にあると考えていたようである。)
藤樹は何かの真似事ではなく「體認」し「體察」し、言葉には「ヅント」したものがあれと繰り返し教えた。林羅山が幕命により法印に叙せられた時、彼は非常な廃仏家だったが、あっさりと剃髪した。藤樹はこれに激しく怒り、朱子の言っている鸚鵡(オウム)と同じではないかと激しく書いている。彼らが直接ぶつかることはなかったのだが、林羅山の私塾は湯島聖堂まで発展して残り、私学と官学の別としてお互いの血脈は長く後に影響を残した。藤樹の理想主義や学問の純粋性、対する羅山は学問の実用性を証した。
藤樹は11歳で初めて「大学」を読み、「天子ヨリ以て庶人ニ至ルマデ、アニ是に皆身ヲ修ムルヲ以テ、本ト為ス」の名高い言葉を読んで感涙したとある。藤樹は後に「大学解」を著し、地位は海や河の地形のようなもので、身は水のようであり、身において何ら変わることはないと書いた。
「下剋上」の経験は人に世間の「位」の力を借りられず、ただ我が「身」を頼む生活を教えた。これに適応し、流され、ただ外側の物として経験した人にとっては、平和が来れば今まで名ばかりのものだった因襲を新たに成り上がったものが更新したにすぎなかった。それこそ家康のしたことである。しかし、この「下剋上」の荒涼に生まれ、内面を掘り下げた藤樹は、自然に時の勢いから孤立していったのである。藤樹は時代の問題を彼自身の問題として感じ、それに生きた。戦国の生活を実りとした最初の思想家と言っていい。彼なら「下剋上」を「でもくらしい」と解いた大言海の解もよく理解しただろう。そしてもっと大事なのは、その時代の誰も彼の孤立を放っておかなかった。「下剋上」の荒れ地に実った思想は誰もがやって来た痛切な経験に通じていたのである。「藤樹先生年譜」を読めばわかる。藤樹から単に知識を学んだ人の手によって書かれた文体ではない。
「本居宣長」-9章(2020/12/19)
宣長を語ろうとして、契沖からさらに藤樹にまで遡ったのは、慶長の頃から始まった新学問の初心に触れたかったからだ。国学は官学として形式化して固定化していくが、絶えずそれに抗し、また一般人の生きた教養と交わった学者たちは皆藤樹の志を継いでいる。
藤樹の考えは「良知説」と言われる。藤樹は「 ❛ 独 ❜ ハ良知ノ殊称、千聖ノ学脈」と述べた。それを重ねていけば「聖凡一体、生死やまず、故に之を独という」というところにたどりつける。藤樹の学問は己を知る事に尽きる。真知は普遍的だが、これを得るのは各自の心法、心術によるのだ。
藤樹以降、国学は急速に発展して進歩し、多様になり精細になっていく。今日の我々から見ても理解できるような客観性や実証性というようなものが、学者たちの仕事の上に現れてくるようになる。だが、この時代の国学の生態というもの、大切にしていたものを探るにはそれでは足りない。今に言う客観性を最も明瞭に意識していたと見なされる人、例えば熊澤蕃山も「天地の間に己一人生て在りと思うべし」と言っている。藤樹が ❛ 独 ❜ と言ったこと、契沖が「独り生れて、独り死に候身」と言ったことに通じる燃え上がるような主観は決して死ななかったのだ。現代から見れば儒学は主観的で、国学は客観的と映るようだが、その差はあいまいなものだ。
蕃山は藤樹が書を読まずして三年心法を練ったと述べた。古書を離れて学問を考えられないのは言うまでもないことだが、何故そんなことをしたのか。それは、書の真意を知るためだった。学問の豪傑たちは皆、仁斎は「語孟(論語・孟子のこと)」を、契沖は「万葉」を、徂徠は「六経(詩経・書経・礼記・楽経・易経・春秋のこと)」を、眞渕は「万葉」を、宣長は「古事記」を突き詰めていったのだ。ここに今日から見た客観的か、主観的かなどの判断を当てるのは、中身を空洞化する勝手な誤解なのである。
藤樹は論語のまとまった訓詁に関しては「郷党篇」についてのものしか残さなかった。32歳の秋に論語を講じていてこの郷党篇に大いに感得触発があったと残されている。普通に読めば郷党篇は退屈な書だ。日常生活の細かな孔子の挙動が書かれているだけなのである。他の章での孔子の道に関する発言は豊かで人の耳に入りやすい。それ故かえって様々に解釈ができる。だから、藤樹は郷党篇にその答えを見たのだ。
藤樹がそのまま信じた四書の原典を伊藤仁斎は批判した。大学は孔子の書ではないとする画期的な研究を行った。仁斎は六経は書のようで、語孟は書法のようだと書いている。つまり孔子と孟子を自分の血脈にした結果、「中庸」や「大学」の原典としての不純が見えたという性質のものだったのだ。仁斎は、書を読むのに「学んで之を知る」道と、「思いて之を得る」道とがあると考えた。この初学においては「学んで知り」、書が「含蓄して露さざるもの」を読みぬく「思いて得る」ところの境地は、藤樹や蕃山が使った「心法」という言葉と同じものなのである。
この「心法」というものは単なる心の工夫というものではない。仁斎の息子の東涯は、仁斎も若い頃に白骨の観法(仏教の観法で自身や他者の身体が腐敗・白骨化していく様を観想し、そこへの執着を断つこと)を修したと語っている。だがやがて、宋儒が「明鏡止水」に極まることを仏教や老子と一緒だとして拒絶するに至った。
そしてそれは字義の意味や客観性を追求するところにあるのではない。彼は註脚を脱して直接語孟にその論拠を求めることにとても苦労したと何度も書いている。材木屋の倅であった彼は、先人の註脚の世界を空しく模索した。しかし後には、ひたすら字義に通じていこうとする学者たちとはむしろ正反対の字義を忘れる道を行った。そして彼は「独り語孟の正文ありて、まだ宋儒の註脚あらざる国」にたどり着いたのだ。そのことを彼は「熟読精思」とか、「熟読玩味」とか、「体験」とか、「体玩」と色々に言ってみているのである。
「本居宣長」-10章(2021/1/18)
仁斎は「童子問」の中で論語を「最上宇宙至極第一書」と書いている。論語の註解は仁斎の畢生の仕事で、67歳の時に最初に書き始めて後、79歳で没するまで推敲し続けた。仁斎が開いた学校「古義堂」文庫の仁斎自筆本を見ると、稿を改める度に巻頭に「最上宇宙至極第一書」と書き、書いては消し、また書いてと迷っている様子が明らかに窺えるそうだ。
仁斎の死後10年ほど経って「論語古義」息子の東涯によって刊行された。その冒頭には「最上宇宙至極第一書」の言葉はない。仁斎は門生のそんな大袈裟な言葉はいかがなものかという意見を入れて削除したという。論語が聖典であるというのは当時の通念だった。だがその通念で済ませてしまっている人に、何と言ったら通じただろう。その突き抜けたが故の躊躇いなのである。
仁斎の一番弟子は荻生徂徠という。仁斎の「大学定本」「語孟字義」に彼は感動した。徂徠は仁斎に手紙を書いた。「ああ、茫々たる海内、豪傑幾何ぞ、一に心に当たるなし。而して独り先生に向かう」。仁斎も、「卓然独立して、倚る所無き」学者、雑学者ではなく聖学に志す豪傑は少ないのだと書いた。藤樹の開いた「独」の学脈である。仁斎の「古義学」は徂徠の「古文辞学」に発展した。仁斎は「住家の厄」を離れよと言い、徂徠は「今文」「今言」を以って古文、古言を視るなと繰り返し言った。徂徠は「学問は歴史に極まる」と極限したが、それは今日でいう歴史意識や相対性ということではない。道を問えぬ者が、歴史に問えるわけはないのだ。
「世は言を載せて以て遷り、言は道を載せて以て遷る。道の明らかならざるは、職として之に是れ由る」と徂徠は書いた。歴史を考えるとは意味を判じねばならぬ昔の言葉に取り巻かれることだ。そして生き方や生活の意味合いが時代によって変わるから、如何に生くべきかという課題に応えることは難しくなる。道は明らかに見えてこない。だがそれでも道は「古今を貫透する」と徂徠は考えた。徂徠の著作には言わば変わらぬものを目ざす「経学」と、変わるものに向かう「史学」との交点への鋭い直覚があった。仁斎は「人の外に道無く、道の外に人無し」と言ったが、徂徠ならこの人を「歴史的人」と言っただろうか。それが二人の学問が朱子学という理を究める学問からの転回点となったのだ。
学問は歴史に、歴史は文章に極まるとまで仁斎は言わなかったが、仁斎の心法、読書の工夫を受け継いで徂徠が書いたのもまた独特な告白だ。徂徠の経学つまり四書五経の学問は「憲廟」つまり徳川綱吉公のおかげだというのだ。それは綱吉公の命でお小姓衆に四書五経を素読(意味の説明をせず、先生が読んだ通り生徒は繰り返し復唱してその通り読んでいく)した時のことだ。夏の暑い日、連日、明六時(午前5~7時)から夜四時(午後10時)まで15時間にもわたって素読していた。最初の内は素読で間違えたところを咎めたりなどしていたが、後には疲れて吟味も適当になる。読むものはただ口に任せ、吟味する自分もただ書物を眺めしていて、読むものがページをめくったのに、自分はめくっていないというようにうつらうつらと本文を見ていると、あそここに疑が出現してきて、これを種にして内容に合点できることとなった。だから、註に頼れば早く会得できてよさそうなものだけど、自己の発明というものに勝るものはないと悟った。これは愚老の懺悔だけれど、弟子へも皆そのように教えているというのである。
これが生活にとても便利な日常の道具である言葉としてでなく、例えば岩に刻まれた意味不明の碑文ででもあったなら、誰だって「見るともなく、読むともなく、うつらうつらと」眺めるという態度を取らざるを得ないだろう。ただそこには岩の凹凸と違って、確かな精神の印があって、だけど判じ難いからその姿を眺めるのである。これが徂徠の「世は言を載せて以て遷る」という考えの生まれた種だ。これは世という実在に言葉という符丁がいつも貼られているという意味ではない。徂徠は「辞は事と嫺う(習熟する)」と言った。それは決して歴史に至る通路、道具として歴史資料があるというのではない。「文章」が歴史の権化と見えるまでこれを眺めるだけが必要だったのだ。思い描くのに上手下手はあるだろう。しかし、我々は「海」を埋めて「山」とすることはできても、「海」という言葉を思い出しながら「山」と言う事はできないのである。
「本居宣長」-11章(2021/2/12)
徂徠は歴史を「事物当行之理」でも、「天地自然之道」でもないというはっきりした考えを持っていた。後世、使いやすいように出来上がっているものではないのだ。その考えは、過去を惜しみ、未来を希い、現在に生きている普通人の感覚に紐づいたもので、そこから離れなかったのが「古学」の力なのだ。仁斎にも徂徠にもあったのは、儒学史の展望などというものではなくて、幼少から慣れ親しんだ学問の思い出から派生しているものなのである。
藤樹はそれを「学脈」と呼び、仁斎はそれを「血脈」と呼んだ。血脈とは仏教の法燈を守るという意味合いの用語から来ている。彼らが博士家・師範家から学問を解放できたのは、古い学問の対象を変えたり、新しくしたりといったことではなく、過去の遺産をそのまま蘇生したのである。学問的な遺産は世襲の家業に独占されていた。だから、直接過去の遺産を精神的遺産として自分に呼びかける声として聞いたのである。そしてそれが、新しく斬新な独創的な仕事となった。それがいかに自然に、邪念を交えずに行われたかを私は思わずにはいられない。
そろそろ長い括弧を閉じなければならない。学問の「学」とは象(かたど)り倣(なら)うことであって、宣長が学問論の「うひ山ぶみ」で言うように、「物まなび」である。「まなび」は勿論「まねび」であって、学問の根本は模倣にある。正確な認識を基本とする「科学」とは全く性質が異なるのだ。宣長を語ろうとして、長く藤樹まで遡ったのも、この「まなび」の精神の糸を辿りたかったからだ。「恩頼図」風な宣長の仕事の解体とは違う意図をがある。学問を純化する彼らの目的は、古書を出来るだけ上手に模倣しようとするところから来る。古書はあくまでも現在の生き方の手本だった。そして、模倣される手本と模倣する自己との対立と緊張した関係がそのまま彼らの学問なのである。認識や観察といった現在の自己を棚上げできるやり方ではない。
宝暦二年、宣長23歳で学問のために京都に上った時には、彼の学問の興味はほとんど万学に渡っていた。19歳で紙商いの今井田家の養子になる少し前に法号を授けられているし、神書の類のものも読み漁ったと後年回想している。在京中の宣長の書簡に「好ミ信ジ楽シム」という言葉がしきりに出てくるが、宣長が求めていたのは如何に生きるべきかという「道」だった。彼はどんな道も拒まずに雑学したが、他人の説く道を自分の道とすることはできなかった。自己の生きた理解力でしかそれに当たれず、その自身の「好信楽」を書簡で「風雅」と呼んだのである。決して一般にいう風流の意味ではない。
宣長は(京都の)堀景山の塾で初めて学問上の新気運に接した。それは仁斎によって「卑しければ則ち自ずから実なり、高ければ必ず虚なり、故に学問は卑近を厭うことなし。卑近をゆるがせにする者は、道を識る者にあらざるなり」、「人の外に道なし」、あるいは進んで「俗の外に道なし」とまで言われ、徂徠によってさらに徹底された。その独創は彼らの学派に徹底されず、むしろ急速に弛緩してしまい、宣長も彼らを批判することになる。しかし徂徠自身を批判したことは一度もない。宣長は徂徠の見解の最後の一つ手前までことごとくわが物とした。徂徠自身の信念や見解自体は彼のものではなかったが。学問とは物知りに至る道ではない、己を知る道であるとは、恐らく宣長のような天才にはほとんど本能的に掴まれていたのである。
「本居宣長」-12章(2021/2/12)
宣長は「玉かつま」で「自分は道の事も歌の事も、あがたいのうし(縣居の大人=賀茂真淵のこと)の教えによって、古い書をただ考え悟れるのみであって、家々の秘め事などは一つも知らない。すべてよき事は世に広げたいとのみ思うので、自分で考えて悟ったことはみな書に書きあらわして露ほども残さなかった。物学ばんと思う人はそれを読めばすべて足り、他にはない」と書いている。これは70歳の頃書かれたいかにも宣長らしい言葉だが、晩年の淡々とした平明な語調に、彼の青年期の学問や動機が逆に照らされて見えるようなのである。
「あがたいのうし」とは言うまでもなく賀茂真淵のことだ。宣長が真淵に名簿を送って正式にその門人となったのは宝暦14年(宣長35歳、真淵68歳)であり、真淵はこの年から縣居を号し、5年後に亡くなった。宣長は自ら「縣居大人之霊位」と書した掛軸を作り、忌日には書斎の床に掲げて、終生、祭を怠らなかった。この二人の関係についてはいずれ触れる。
しかし、宣長の学問の基本は真淵に入門する前にすでに出来上がっていた。有名な「物のあはれ」論がそれである。宣長は京都留学時代の思索を「あしわけ小舟」と題する問答体の歌論にまとめたが、覚書風の稿本は、箱底に秘められていた。稿本の紹介者の佐々木信綱氏によれば、大体在京中に成ったものと推定されている。
「物のあはれ」と言う代わりに、情、人情、実情、本情などの言葉が主として使われているが、「歌ノ道ハ、善悪ノギロンヲステテ、モノノアハレト云事ヲシルベシ、源氏物語ノ一部ノ趣向、此所ヲ以テ貫得スベシ、外ニ子細ナシ」と断言されている。「石上私淑言」と「紫文要領」は宝暦13年(宣長34歳で成っている。恐らく「石上私淑言」で未定稿だった「あしわけ小舟」を書き直そうとしたのだが、果たされなかった。しかし、「物のあはれ」論は巻初で整理されたし、「紫文要領」では源氏の本質論という明瞭で完結した形を取れたのである。
宣長の学問上の開眼は、契沖の仕事によって得られた。契沖の大明眼を語る宣長の言葉はすべて「あしわけ小舟」からの引用だった。契沖はその新しい精神を考えあぐねて「俗中之真」と語ったが、古歌と上代を愛するに至ったいきさつを語った形跡はない。彼の著作の折々にばら撒かれている所懐、言わば彼の沈黙を宣長は直覚したのだ。宣長は、和歌は鬱情を晴らし、思いを述べ、四時の有様を形容する大道であると述べたが、決して我が国の大道というものではないとも述べている。だが、歌の大道を徹底的に分析したなら、その先に新しい道が自ずから開けるに違いない。宣長は「物のあはれ」論というあしわけ小舟の舵を取ったのである。
「本居宣長」-13章(2021/3/25)
通説では「もののあはれ」の用例は紀貫之の土佐日記まで遡る。貫之たちが船出する時に別れを惜しんで歌をやり取りしている時に、自分の酒を飲んでしまった船頭が早く行こうと言い「もののあはれ」の分からない奴だというように書かれている。これは当然、こう言えば当時どのようなことか通じたのだ。紀貫之は古今集の序に「人麻呂は死んだけれど歌の事はとどまっている」と宣言した。歌が伝統となって整理された始めなのである。宣長もここから「もののあはれ」論を始めた。
宣長はこのように書き始める。「古今序に、やまと歌は、ひとつ心を、たねとして、万のことのはとぞ、なれりける、とある。この心といふがすなはち物のあはれをしる心也・・」(石上私淑言)
ある人が宣長に、俊成の有名な「恋せずば 人は心も なからまし 物のあはれも これよりぞ知る」という歌の「あはれ」とは何かと問うた。そして、さらに続ける。「もののあはれを知るのが人の心があるということで、もののあはれを知らなければ心がないということなら、あはれはあはれと言うしかないのじゃない?」と。
宣長は、「はっきり解ったように思ったけれど、説明する言葉がない。思いめぐらすほどにいよいよ意味が深いように思われて、古書や歌などの用例などをおろおろと思い見るけれども、多様な使われ方だ。和歌はもとより、伊勢源氏(の物語)まであはれの一言でカバーできる。孔子が三百の詩はすべて思無邪(思い邪無し)の一言でカバーできると言ったのと同様のことだ」(あはれ弁)と書いた。宣長29歳の頃の文だ。
貫之にとって「もののあはれ」という言葉は歌人の言葉で、船頭の言葉ではなかった。宣長は違う。言ってみれば船頭から素朴に「もののあはれ」とはと聞かれ、考え始めたようなものだ。宣長は「古今集」真名序の「幽玄」などという言葉には目もくれず(或事関神異、或興入幽玄。と真名序にある)、仮名序の言う「心」を、「もののあはれを知る心」と断ずれば足りるとした。歌学が俊成の「幽玄」、定家の「有心」というように、細分化して衰弱していく歴史が見えていたのである。「あはれ」という語を洗練するのではなく、歌語の枠から外し、ただ「あはれ」という平語に向かって放つという道を宣長は行った。貫之は「土佐日記」で船頭はもののあはれも知らないでと書きながら、船頭の取り交わす生活上の平語のリズムから歌が自ずと生れてくる様が観察されている。貫之は特に注目しなかったが。
(土佐日記「一月九日」のこのあたりはどうか。宇多の松原の絶景を下手な和歌が全く表せず、物寂しい皆の気分を船頭のざれ歌が和らげる感じが描かれている)
http://www.manabu-oshieru.com/daigakujuken/kobun/tosa/08.html
この辺りで「源氏物語」の味読による宣長の開眼に触れなければ、話は進まない。
宣長は源氏を評して、「やまと、もろこし、いにしへ、今、ゆくさきにも、たぐうべき文はあらじとぞおぼゆる」(玉のをぐし)と言う。異常な評価である。冷静な研究者の言とは言えないくらいだ。逆に言えば宣長は「源氏」を異常な物語と読んだのだ。
「すべて人の心というものは、唐の言葉にあるように、一方に言い切れるものではなく、深く思うことについてはとやかく、くだくだと、めめしく、乱れ、定まりがたく、さまざまの曲折や影が多いものを、この物語は余すところなく細かに書き現すこと、曇りなき鏡に映して向かい合うようだ・・」と書いて、先の「やまと、もろこし」云々の言葉に続く。
これは宣長の終生の人間観につながった。「大方人のまことの情というものは、女子供のごとく、未練に愚かなる物なり。男らしく、きっとして賢きは、実の情にあらず、うわべをつくろい、飾りたるものだ。実の心の底を探ってみれば、いかに賢い人もみな女子供に変わることはない。それを恥じて包み隠して行き間違うのだ」(紫文要領)。このことはいずれ触れるが、今はそこまで広げない。
名歌は素晴らしい器のようなものだ。それを見れば美しさは分かる。だが、それを見て似せて作ろうとしてもそのようにはならない。「源氏」は物語の道をその表現力によって語っている。それは器の細工師の器の作り方を見て、それを真似るようなものだ。そうすれば器は同じように作ることができる。「源氏」は物語の道を語ることで、歌の道とは何かという宣長の問いに答えたのである。言うまでもなく、「源氏」をそこまで踏み込んで読んだ人はいなかった。
源氏物語の「螢の巻」で、長雨に降りこめられて絵物語を読む玉鬘を源氏が訪れて物語について話し合う場面がある。ここを紫式部の物語の本意について語ったものとみて、全文詳しい評釈を宣長は書いている。現代からしたら深読みのしすぎだということになるかも知れないが、古典の意味を再生させる名手のゆえんはそのようなところにあるのだ。
物語に夢中になる玉鬘を、空言が多いと知りながら読ませるなんてさぞかし上手に書かれてるのでしょうね、と源氏はからかう。玉鬘はへそを曲げ、「嘘をつきなれた人はそんな風に汲み取るのですね、私はただ本当のことと思えるだけですのに」と返す。源氏はこれはとんだ悪口を言ってしまった、物語こそ神の代より世にあることを記し続けてきたのだから、と冗談めかす。宣長はそこに紫式部の「下心」を読んだ。
玉鬘が物語を「まこと」と信じるその「まこと」は、道学者や生活人の「まこと」と「そらごと」との区別を超えたものだ。宣長はそれを「そら言ながら、そら言にあらず」と述べる。作者は心が動き、その思いが「心にこめがたくて、言い置きはじめる」のだ。宣長は注釈でも書いている。「人に語っても、自分にも人にも何の益もなく、心の内に閉じ込めておいても何の悪いこともないようなのだけれど、これは素晴らしいと思い、あるいは恐ろしいと思い、悲しいと思い、切ないと思い、嬉しいと思うことは、心の中で思うだけでは留めがたく、必ず人に語り、聞かせたくなるものなのだ」「その心のうごくが、すなわち、もののあはれを知るというものなり、さればこの物語、もののあはれを知るよりほかなし」と。だが、先を急ぐまい。
「本居宣長」-14章(2021/4/20)
宣長はあくまでも源氏の会話に作者紫式部の下心を追おうとする。自分の書く物語が「わざとの事」と本当に考えていたのは式部であって、源氏ではない。式部の日記から推察すれば、「源氏」はかかれているうちから、周囲に読まれたものらしいが、制作の意味合いについての式部の明瞭な意識は時流を抜いていた。
源氏はこう言う「深きこと、あさきことのけぢめこそあらめ、ひたぶるに、そらことといひはてむも、ことの心、たがひてなん有ける」。宣長はそれに対して、「文章詞(漢文か、かなか、など)の深浅こそあっても、心は深さ浅さのけじめがあるべきではない。直接そうは書いていないが、“けぢめこそあらめ”という表現に言外に表れている」
この宣長の評釈は、今の言葉で言えばはっきりした文学様式論による物語弁護である。物語を知るには「その時の習い」を知る必要があり、源氏こそ「その時の習い」を意識的に生き、自己の内的表現の素材にまで高めた物語だった。源氏の歴史的位置を、外側から計り、指すことは出来ようが、この位置について精一杯の体験を語り、これを完成した姿に創り上げたのは、式部の自己の内部の出来事に属する。その物語が後世に向かって扉を開き、そのまま人の心の変わらぬ深処を照らすものと宣長には映ったのだった。
「もののあはれ」という言葉の意味合いについての宣長の細かい分析を見ていこう。
「あはれ」も「物のあはれ」も同じことだと(玉のをぐし)と宣長は言う。物は「物言う」「物語る」「物見」などのように広く言う時に添える言葉がついてちょっと変化したものだ。
では、「あはれ」はどのように使われてきたか。
「阿波禮という言葉は、さまざま言い方は変わりたれども、その意は皆同じ事にて、見る物、聞く事、なすわざにふれて、情(ココロ)の深く感ずることを言うなり。俗には、ただ悲哀をのみ、あはれと心得たれども、さにあらず、すべてうれしとも、おかしとも、たのしとも、かなしとも、こひしとも、情に感ずる事は、みな阿波禮なり。」(石上私淑言)
「あはれ」と使われるものがいつのまにか、「哀」の字を当てて特に悲哀の意に使われるようになったのは何故か。
「うれしきこと、おもしろきことなどには、感ずること深からず、ただかなしき事、うきこと、恋しきことなど、すべて心に思うにかなわぬ筋には、感ずること、こよなく深き技なるが故」と宣長は考える。新古今から「うれしくば 忘るることも 有なまし つらきぞ長き かたみなりける」(清原深養父)を引いて、嬉しいのは情が浅いからだと言っている。この考えは宣長の「物のあはれ」を理解するうえで、極めて大事だ。問題は、人の情の一般的な性質にある。何事も、思うにまかす筋にある時、心は、外に向かって広い意味での「行為」を追うが、内に顧みて心を得ようとはしない。意識は「すべて心にかなはぬ筋」に現れるとさえ言えるだろう。ココロが行為の内に解消し難い時、心は心を見るように促される。
宣長が「あはれ」を論ずる本と言う時考えていたのはその事だ。生活感情の流れに身を任せていれば、ある時は浅く、ある時は深く、おのづから意識される、そういう生活感情の本性への見通しなのである。だから彼の論述は、感情論というより、むしろ認識論とでも呼びたいような強い色を帯びている。だから宣長の課題は、「物のあはれとは何か」ではなく、「物のあはれを知るとは何か」であった。
宣長はまた、情と欲とは異なるものだとも言っている。
「欲ばかりにして、情にあづからぬ事あり、欲よりして、情にあづかる事あり。また情よりして、欲にあづかる事あり。情ばかりにして、欲にあづからぬ事あり。
この内、歌は、情より出づるものなれが、欲とは別なり。欲より出づるものも、情にあづかれば、歌ある也。
さて、その欲と情との分かれ目は、よくはただ願い求む心のみにて、感慨なし、情は物に感じて感慨するもの也。恋というものも、元は欲より出づれども、深く情に渡るもの也」(あしわけをぶね)
「情」は定義されていないが、「欲」ではないというはっきりした限定は受けている。「情」の特色は、それが感慨であるところにあるので、感慨を知らぬ「欲」とは違う。「欲」は実生活の必要なり目的なりを追って、その為に己を消費するものだが、「情」は、己を省み、「感慨」を生み出す。生み出された感動は認識を誘い、認識が感動を呼ぶ動きを重ねている内に、豊かにもなり、深くもなり、ついに「欲」の世界から抜け出て自立する喜びに育つのである。
ここから宣長は源氏物語の「帚木」の「雨夜の品定め」と言われる有名な文を使った質問者からの問いを載せている。「指くひ女」と「木枯らしの女」という女性の「マメなる(誠実な)」型と「あだなる」型を持ち出して論評しているのだが、紫式部は明らかにマメなる方を擁護して、あだなる方をいましめていないか?あだなる方が「物のあはれ」の本意なのではないか、と。
宣長によれば、どちらが良いかと揺れ動き悩むところにあるし、その時に源氏はまた話題に上らない藤壺の人柄に、足らないところも過ぎるところもなく本当にありがたいと思いを馳せる。そして後に
「夕霧」で、夕霧と女二宮の中を聞いた源氏が紫の上に、自分の死後は君の心も誰かの所に行ってしまうかもしれないなと話しかけると、後に紫の上は自分の心ながら良き程にはいかにして保てばよいか、難しいと言わせている。
(興味深いことに、そう悩む紫の上は貞淑を守り、藤壺はそうでなかった)
宣長が、「物のあはれを知る」という言葉で念頭に描いていたのは、現実にはありがたき理想であった。現実に照らして程よく調整される理想などはない。源氏物語に「物のあはれ知り過ぐす」という用例があるが、その言葉の意味合いは、どんな事にも物のあはれを我が知り顔でけしきばんで口出しするような行き過ぎたことを指していて、かえって物のあはれを知らない人がそうなるのだ、と説明する。だから誠に物のあはれを知っていた紫式部は、その「本意」を押し通そうとしなかった。押し通そうとするのは我執で、それが無心無垢に通ずる「本意」を台無しにしてしまうからなのである。宣長は紫式部のことばを引く。
「すべて男も女も、わろものは、わづかにしれるかたの事を、のこりなく見せ尽くさむと思えるこそ、いと惜しけれ」
「本居宣長」-15章(2021/5/22)
そういう次第で、宣長の論述を素直にたどると「物の哀れを知る」という言葉が「道」として扱われていることが分かる。補足になるが、「品定」の巻の佐馬頭の言葉に「ことが中に、なのめなるまじき、人のうしろみのかたは、物の哀しりすぐし、はかなきつゐでのなさけあり、おかしきにすすめるかた、なくてもよかるべし、と見えたるに・・」とある箇所がある。この文は例えば、谷崎潤一郎氏の現代語訳によれば、「女の仕事の中で、何よりも大切な、夫の世話をするという方から見ると、もののあはれを知り過ぎていて、何かの折に歌などを詠む心得があり、風流の道に賢いというようなところは、なくてもよさそうに思えますけれども・・」となる箇所だ。
谷崎の解釈が普通なのだが、宣長はそう読まなかった。宣長は文中の「もののあはれ」という言葉を「うしろみの方のもののあはれ」と解した。「物のあはれということは、万のことにわたって、何事にもそのことごとについてあるものだ。故に、うしろもにかたのもののあはれと言われる・・」
これはいわば無理は承知で、でも「あはれ」の概念の内包を深く突き詰めようとして、その外延が広がっていくということになったのだ。折口信夫は宣長の「もののあはれ」が、王朝の用語例をはるかに超えて宣長自身の考えをはち切れる程押し込んだものであることに注意を促している。「うしろみの方のもののあはれ」、宣長の言葉で言えば「世帯を持って無益な出費をしてしまったときに、これはもったいなかったななどという事をわきまえ知るなどは、事の心を知る也」ということになるが、世帯向きの心構えまで押し込めてしまっては、はち切れそうにもなる。もちろん宣長も気づいている。そして説明を試みるが、うまくいかない。うまくはいかないが、決して誤魔化してはいないのである。
説明するのに、「あはれ」には「理(ことわり)」があるなどという。「あはれ」の理は事実のうちにはないが、事実の照明を受けて崩れるようでは理が立たない。そんな例として「うしろみの方のもののあはれ」を取り上げてみるのだが、物語の本意を考えていくと「うしろみの方のもののあはれを知る人は、もののあはれを知らぬ人」などという事になってしまう。そして火は薪も焚けるが、家も燃やせるなどと説明していくとさらに苦しくなる。
ここで押さえたいのは、宣長は、説明に窮するほど「もののあはれ」を単なる一情趣を超えさせようとして心を砕いたということだ。この努力が宣長の「源氏」論に一貫しているのであって、そこを見失えば宣長の論述は腑抜けになってしまうのだ。宣長は歌、物語の「本意を尋ねれば、あはれの一言にてこれを覆うべし」と断言している。今風に言えば「文芸は感情の表現だ」ということになるだろうが、宣長が「情」と書いて「こころ」と読ませるときに、単純に理性と感情を退避させるような現代の心理的な考えで取ってはならない。歌や物語のうちから「あはれ」という言葉を拾い上げることで始まった宣長の「情(こころ)」についての思考は、「情(こころ)」という一つの分裂しない直感なのである。
言うまでもなく宣長は、「情(こころ)」があいまいで不安定であることを知っていた。それは「とやかくやと、くだくだしく、女々しく、乱れあいて、定まりがたく」、決して「一方に、つきぎりなるものにはあらず」と知っていたが、これを本当に納得させてくれたのが「源氏」だった。宣長は素直に考えた。「人の「情(こころ)のある様」が、いわゆる「そら言」である物語によって開かれているのは何故か。それこそが「まこと」ではないかと考えたのである。
「源氏」は単に見聞された事実の記録ではない。紫式部が源氏の君に言わせているように「世にある人の有様の、見るにも見飽きず、聞いても聞き足りない」味わいの表現なのだ。人は事物を知覚した時、その知覚だけで停止することはない。対象との縁を切らずに育っていく。この「見るにも見飽きず、聞いても聞き足りない」という言葉を宣長は名言だと考えた。そしてそれは「源氏」で「味わいを知る」とも表現されている。「万のことを、心に味わう」のが、「事の心を知る、物の心を知る、もののあはれを知る」ということだと書く。確かに漠然としている。だが、「情(こころ)」の曖昧な働きがそのまま生きている証拠でもある。「情(こころ)」が「感(うご)」いて、事物を味わう様を外から説明することは難しくとも、内から生き生きと表現することは出来るのであって、現に誰もが行っていることだ。ほとんど意識しないで行っている。そこでは、事物を感知することはすなわち事物を生きる事であろうし、その表現に我々が影響されるとすれば、見る事とそれを語ることとの区別もなくなってくる。
宣長はその表現の妙を「無双の妙手」と呼んだけれど、彼は詩人としてその後を追おうとしたわけではなく、学者としてその後を追った。だからそれは子どもでも知っている「見るにも見飽きず」という姿で、その純粋な情(こころ)の動きが一筋に育ったなら、「源氏」の成熟を得るはずだ。それは歌人が特別な表現の国に閉じこもるようなものでなく、成熟した意識の内に童心が表れるかと思えば、子供らしさの内に大人びたものが見える、そういうようなものの姿だと私は思っている。
説明の補足と言ってここまで書いてきたが、心に浮かぶままにもう一つ補足めいたことを書こう。それは浮舟入水の下りだ。薫の君と匂宮の君とに迫られて川に身を投げるのだが、どちらかを選べば反対のあわれを知らず、身を捨てることで両方のあはれを知ったのだと最初「柴文要領」で書いていた。相当強い発言だったが、後に「玉の小櫛」になると削除してしまう。これも「うしろみの方のもののあはれ」と同じで、ささやかな言葉の解釈がはち切れそうになったのだ。
内省家の薫の君と、行動家の匂宮の君との鮮やかな性格の対比は誰もが言う事だが、逆に言えば性格など持ち合わせないような浮舟という「生き出でたりとも、怪しき不要の人」を作り出す道具立てにすぎなかった。川に身を投げた後、出家して生きていた浮舟を薫の君は見つける。そして便りを出すが、浮舟にはもう応答する元気がない。ぼうっとあらぬ方を見るだけで使いの子供は手ぶらで帰る。薫の君はどう考えたらよいか分からず、「誰かが彼女を隠してしまったのだろうか、匿っているのか」とつぶやく。その一言で「源氏」の長編の糸はぷっつりと切られてしまう。
宣長はここの評はあっさりと終え、歌を一首詠んだ。
「なつかしみ またも来て見む 摘みのこす 春野のすみれ けふ暮れぬとも」
宣長には最後、式部が自分の織った夢に食われてしまったように、主題に殉じたように映ったのではないかと思う。「もののあはれ」を十全に知るには、浮舟のように「一身を失う」こともある。そういうものだと言いたかった宣長の心を推察しなければ、彼の「もののあはれ」論は読んでいないに等しい。この物々しい解釈を七十近くなって終える頃には、「なつかしみ 又も来て見む」という穏やかな歌に変じた。浮舟もまた子供であるが、子供は何も知らないとは本当のことだろうか。浮舟の背後に姿を隠す紫式部、その声に応じて宣長は「なつかしみ 又も来て見む」と歌っただろう。
「本居宣長」-16章(2021/6/24)
「螢の巻」の中の源氏と玉鬘との会話に、宣長は式部の物語感を執拗に読み取ろうとしたことは既に書いた。会話中の源氏の一番特色ある言葉をもう一度書く。
「神代より世にある事を、日本紀などはその一部にすぎず、物語の方に詳しく書かれているのでしょうね」
この源氏がたわむれに言う言葉に紫式部の自信が隠れていると宣長は解したが、では、冗談の挙母を脱がせてみるとどんな意味合いが表れるか、注釈で宣長はそこまで書かなかった。が、それは彼には十分に感得されていただろう。宣長は「螢の巻」の物語論に着目した最初の「源氏」研究者だったが、彼が現れるまで800年の歳月が流れたとは今日から思えば不思議なことである。
更級日記の作者は、少女時代叔母から源氏五十余巻をもらい、「一の巻よりして、人もまじらず、几帳のうちにうち臥して、ひき出でつつ見る心地、后の位も、何にかはせん」と言ったが、この無邪気だが率直な気持ちがこの物語の流布の原動力だっただろう。
俊成女作とされる「無名草子」は「源氏」評論の最も古いものとされているが、「さてもこの源氏作り出でたることこそ、思へど思へど、この世一つならずめずらかにおもほゆれ。」と言っている程度で、あとはそこから引き返して、あはれとか、めでたしとか、作中人物の品定めをしているに過ぎない。それはつまり「源氏」が現れてから200年経っても、批評は一向進歩しておらず、むしろ批評など少しも必要としない愛読者がいただろうことを語っている。
それよりも、誰が言い出したか分からないが、紫式部堕地獄伝説が、源平大乱の頃にはすでにはっきり出来上がっていたことの方が大事だと思う。上流男女の乱脈な色恋の道を語った罪により作者は地獄にいるだろうから、供養してやらなければならないという伝説である。時代の通念に従って物語を婦女子の玩具として軽蔑しながら、知らぬ間にその強い魅力のいけどりになっている知識人の苦境を正直に語っているようだ。
「源氏」についてのまともな文学上の批評は、俊成の有名な歌合判詞「源氏見ざる歌詠みは、遺恨のことなり」から始まったと言われる。
※※六百番歌合
複数の題に二首の歌を競わせて遊ぶが、「草の原」という表現に対して、聞きなれないという評が多かったものに批判して言った言葉。
枯野の題で歌は下記。
見し秋を何に残さん草の原ひとつに変る野辺のけしきに
「源氏」は花宴の巻で朧月夜が詠んだ下記のもの。
うき身世にやがて消えなば尋ねても草の原をば問はじとや思ふ
※※
王朝文化が総崩れしていた時代に、「古今」以来の勅撰集の流れに新生命を吹き込もうとしていた俊成の審美眼はひどく気難しいものだったが、「源氏」の高度な文体はこれに十分応えるものと見えた。ただそれだけのことで、低級とされた物語の類の中でなぜ「源氏」だけが格別なのか、なぜ作者は日常生活の起伏を物語るのにあれほど精緻な文t内を必要としたのかといった疑問は俊成には必要なかった。言うまでもなく定家も父親である俊成の流儀に従い、この「源氏」批評の流儀は宣長が、「今世中にあまねく用ふるは湖月抄なり」と言った江戸期の「湖月抄」まで続くのである。
武家の世となり、和歌も少数の帰属仲間の内輪ごととなれば、その参考書もこれに準ずるわけで、やがて「古今伝授」が現れれば「源氏伝授」が言われるようにもなる。もはや婦女子の玩具どころではない。研究注釈がされて、すべて故事来歴を踏まえた物語であるということになり、たとえ怪しげなところがあっても、「花鳥余情」(一条兼良)のように「かような事は、国史なども、記し落とすこともありぬべし。この物語に書ける上は、疑うべきにあらず」とまで言うことになる。所謂「準拠説」というものの正体だった。かつて「更級日記」の作者は、「光るの源氏の夕顔、宇治の浮舟の女君のようにこそあらめ」と願ったが、勝手な動機を物語に持ち込む点では、公家たちの準拠説もさして変わりはない。
定家は「源氏」を評して「狂言綺語といえども、鴻才の作る所、之を仰げば弥さかに高く、之を鑽すれども弥さかに堅く」(明月記)と書いた。「狂言綺語」という通念は堅固だ。まずこの観念を何とか始末しなければならない。狂言綺語を「ただ、いと、まことの事とこそ、思い給えられけれ」と言った玉鬘の、無邪気に口ごもった鑑賞法はどこに行ってしまったのか。どこにも行きはしなかった。ただ、玉鬘の言葉を、「君子はあざむくべし」と評した宣長に、拾い上げられるのを待っていただけの話だ。「この物語りを読むは、紫式部に会いて、まのあたり、かの人の思える心映えを語るを、くわしく聞くに等し」(玉のをぐし)という宣長の言葉は、では何を準拠として言われたかを問うのは愚かだろう。宣長の言葉は、玉鬘とほとんど同じように無邪気なのである。
宣長は「およそ準拠という事は、ただ作者の心中にある事にて、後にそれをことごとく考え当てるにも及ばぬことなれども、古来の沙汰あることゆえ、その趣を色々と言うなり。緊要の事にはあらず」(柴文要領)と述べた。準拠の説についてこのようにはっきりした考えを持つことは、誰にもできなかったのである。契沖も眞渕も「湖月抄」の自由な批判から「源氏」に近づいたのだが、そこまで言い切ることはできなかった。宣長がやってのけたことは、作者の「心中」に飛び込み、作者の「心ばへ」を掴んだら離さないという端的なことだった。宣長は作者と同じ向きに歩いた。「およそ準拠という事は、ただ作者の心中にある事」とは、その歩きながらの発言なのである。
宣長は在来の準拠の沙汰に精通していたし、「河海抄」を「源氏」研究の至宝とまで言っている。しかし、注釈者たちが物語の準拠として求めた王朝の故事や儒仏の典籍は、物語作者にすれば、物語に利用され終わった素材に過ぎない。ところが彼らは、これらを物語を構成する要素とみなし、これらで「源氏」を再構成できると信じた。宣長が彼の「源氏」論で極力警戒したのは、研究の緊要ならざる補助手段の、そのような越権なのである。
その扱い方は徹底して慎重だった。それは紫式部の日記にも及ぶ。日記には式部の気質が現れるが、「物語」に現れた作者の「心ばへ」は、「日記」に現れた式部の気質の写しではない。「跡かたもなき」式部の物語の世界は、彼女の「世に有りし」生活世界を超えたものだ。宣長は、言語表現という問題に直面した。この大きな問題は宣長の仕事と共に発展するので、またそこに立ち返らなければならないことになるだろう。
紫式部が創作のために、昔物語りの「しどけなく書ける」形式を選んだのは、無論「わざとの事」だった。彼女は、紫の上に使える古女房の語り口を演じて見せたのだが、この名優はなり切って演じつつ、演技の意味を自覚した深い自己を失いはしなかった。物語とは「神代より世にある事を、記しおきけるなり」という言葉はそこから発言されている。それには「史記」という大事実談が居座った当時の知識人の教養などとは何の関係もない。式部は我知らず、国ぶりの物語の伝統を遡り、物語の生命を、その源泉で飲んでいる。
物語りは、どういう風に誕生したか。「まこと」としてか「そらごと」としてか。愚問であろう。「かたる」とは「かたらう」事だ。相手と話し合うことだ。「かた」は「こと(言)」であろうし、「かたる」と「かたらう」とどちらの言葉を人は先に発明したか、誰も知りはしないのである。世にない事、あり得ない事を物語る興味など、誰に持てただろう。そんなものに耳を傾ける聞き手がどこに居ただろう。語る人と聞く人とが、互いに想像力を傾け合い、世にある事柄の意味合いや価値を、言葉によって協力し創作する。これが神々の物語以来変わらぬ、いわば物語の魂であり、式部は新しい物語を作ろうとして、この中に立った。これを信ずれば足りるという立場から、「日本紀などは、ただ、その一部にすぎない」と言ったのである。この「日本紀」とは、らがて六国史となる正史、「日本書紀」を指す。「これら(物語)にこそ、みちみちしく、詳しきことはあらめ」という言葉の「道々しき」とは、「三史五経の道々しきかた」(帚木」という用例に従って解せばよいのだが、もし、周囲の知識人の世界が、彼女の自然な心に、その人為的に歪められた姿を映し出していなければ、式部にはそんな反語めいた言い方をする必要は、少しもなかったのである。
「本居宣長」-17章(2021/7/26)
「帚木」(源氏物語第二章)の冒頭に出てくる、唐突で研究者の間でも色々と議論されている箇所に、最初に注目したのも宣長だった。
「光源氏、すばらしい名で、青春を盛り上げてできたような人が思われる。自然奔放な好色生活が想像される。しかし実際はそれよりずっと質素じみな心持ちの青年であった。その上恋愛という一つのことで後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと、異性との交渉をずいぶん内輪にしていたのであるが、ここに書く話のような事が伝わっているのは世間がおしゃべりであるからなのだ。自重してまじめなふうの源氏は恋愛風流などには遠かった。好色小説の中の交野少将などには笑われていたであろうと思われる。」(与謝野晶子訳)
「螢の巻」の源氏と玉鬘の会話に「物語の大構想論」を読み取ったのと同じ宣長の注意力が働いている。前の一巻目「桐壺」とは特に関係のない内容で、「源氏の壮年のことを、取り全て一つに評じる」、恋物語の「序のようなもの」だと述べている。
「世間がお喋りだからだ(語り伝えけん、人の物言いさがなさよ)」という表現で、光源氏の心中も知らない「おしゃべりな世間」の人の言う事を真に受けないで欲しい、「交野少将」(交野物語という原文は残っていないが、一夜の契りを結んだ娘を一度きりしか訪れず、その娘が投身自殺をはかるという筋の物語の、好色な主人公のこと)並みの人物と思って欲しくない、自分が語るところを信じて欲しいと聞き手に語りかける語り手の、周到さが伺える。
このような事を繰り返し書くのは、この陰影と含蓄で生きているような、決心し、逡巡し、心中の読者に相談しかけるような文体、表現構造が、「源氏」の作者の技法の本質的なもので、さらに宣長の源氏という人物の評価に直結しているからである。
「源氏」の語り手の女房は、さらに念でも押すように続ける。あなた方の「目慣れた」昔物語りの主人公とは、恐らく大変違った人間を語ることになるだろう、「桐壺」に仄めかしたように、暗いといってもいいほど大変真面目な恋物語で、「好色」ではまったくないのだが、その本性を引き違えてたやすい相手でない人にのめり込んだりする困った性向もあるのだ、などなど。「あだなる」とか「まめなる」といった浅い基準では評価できないという宣長の考えは、この「帚木」の一文を踏まえたものでもある。
源氏を辛辣に品定めした最初の人は契沖だった。「源氏の薄雲にことありしは、父子については何の道があるか。君臣についてはまた何の道があるか。匂宮と浮雲にした振る舞いは、朋友について何の道があるか。・・春秋(古代中国東周時代の歴史書)の褒貶は、善人の善行、悪人の悪口を記して、これはよし、かれはあしと見せたればこそ、勧善懲悪あきらかなれ。源氏物語は、一人の上に美悪相交われる事を記せり。春秋等とは比較にもならない」。言葉が烈しくなっているのは、幾百年もそう語られたように、「源氏」の持つ教訓的価値という考えと絶縁せざるを得なかったためだ。「紫式部がこの物語を書くに、人に悪い影響を与えようとは思わなかったろうけれど、女性である故に一部始終好色について書いたから、損ぜられる人もいただろう。それを聖主君臣などに準えて書ける所に叶わずして罪を得て、地獄に落ちたものと思われる」。物語を儒教的に意味があるとそのまま読まない注釈家より、世間の俗説の方がマシだというのだ。では契沖はこの物語をどう読んだか?というと、「定家卿が言うように、詞花言葉を翫ぶべし」と言っただけで口を噤んだ。
契沖は、万葉に精神を集中していただけで、決して「源氏」を軽んじていたわけではないが、真淵となると様子が変わってくる。真淵ははっきりと「源氏」を軽んじた。「皇朝の文は古事記である。その中に上代、中代の文が混じってあるが、上代の文に及ぶものはない。中代とは飛鳥、藤原などの宮のことを言う。奈良に至っては劣り、弱くなり女様となりて、古の雄々しくして雅たる事は皆失せたり。かくてのち下りて、ついに源氏の物語までを下れる果てとす。かの源氏より末に文というものは無くなった。その文も拙く、誤りばかり書かれている」。
真淵の考えでは、平安期の物語にしても、「源氏」は「伊勢」「大和」の下位に立つ。その二つはまだ「古き意」があって、人を教えようとするような小賢しいところはないが、「源氏」となると、「人の心に思わんことを多く書き、事に触れては女房などの説教がましいことが無きにしも非ず。世が下っては心狭く、邪にのみなりたる頃の女心からは、そういう事を言い思えるのだろう」という。仕事は田安宗武(江戸八代将軍吉宗の次男、江戸御三家田安家初代頭首)の命令によるものだった。真淵は気の進まないまま「古月抄」の書入れ本を差し出すのにも数年費やしたらしい。
とはいえ、実際に「源氏」の注釈をやってみると、源氏より末に物語はなくなったという問題に直面する。文体は華美だと褒めてみるのだが、それは紫式部の本意ではないだろう。では本意はどこかというと、「帚木」の「品定め」に現れていると見た。女性論が「実は式部の心をしるした」ものだけれども、万葉のますらをぶりを深く信じていた真淵には「源氏」のごとき、「手弱女のすがた」をした男性の品定めなど話にならない。だから、紫式部が「この英才をもって男であったなら、貫録を表し、万世の鏡ともなったろうを、父親の嘆いたと同様、惜しい事だ」とする。しかし、多くの女性を巧みに描いた語り口には、男性にできない妙があり、婦徳をいかんなく表現している。「人情の分所」というものが物語られているというのだ。
真淵の「新釈」の仕事が完了したのは、宣長の「あしわけ小舟」が描きあげられたのと同じ頃である。「柴文要領」はその数年後だから、ほぼ無関係と見て良いだろう。ただ、宣長を語るうえで真淵は無視できないので、その源氏観に触れていおいた。
上田秋成も真淵の門下で後に宣長と論争をすることになる。「柴文要領」の十数年後に「ぬば玉の巻」を書いたが、宣長の「柴文要領」を読んでいたかは分からない。光源氏については秋成は「情け深く」「よろづ行き渡れる」人物と一見思われるが、実は「執念深く、ねじけた所のある」人物で、「かかる心汚き人の、世の政を執るは眉がひそめられ」「自身を周公になぞらえるなど片腹痛」く、須磨の左遷にも無反省で、「善と悪が打ち混じるものを書き出しても何の益があるだろうか」、ただ詞花言葉をのみ翫ぶべしと言われるのも道理である、などと契沖の言い方まで踏襲して書いている。
「源氏」の詞花言葉については、恐らく秋成は真淵より鋭敏だった。彼が「源氏」を読んで「雨月物語」を書いたことは、その序を読んだだけでも明らかだ。「もろこしにさえ、比べ挙げるには稀で」「たぐいなき上手の筆」と文才は称えたが、物語の「大旨」を考えると難しいことになる。「螢の巻」に、「これら(物語)にこそ、本意がある」という言葉があるが、空言書く者の華美な表現であって、そんな事を考えていたはずはない。我が国の「人の教」というものは、元は「もろこしの聖の君の教」が始まりだが、教えを学ぶというのは古例を広く知るだけのいたずら事だ、だから「おのづからなる大和魂」は物学ばぬ人にのみとどまっている。式部は恐らくそのことを知っていたが、なにぶん女性の身の事だから「女々しく、所々行き合わず、思いかねては深きに過ぎ、賢しらに耽ってあれこれと言う」のが愚かだと言うのだ。
これもまたついでなのだが、現代で最も「源氏」に関心を寄せた谷崎潤一郎の随筆に、光源氏の人物が秋成と大変よく似て映っていたようなのが面白い。例えば須磨に流されて詠んだ歌も、本心ならば随分虫がいい話だし、口を拭っているのだとすれば白々しいにもほどがあると言いたくなる。紫式部が源氏の肩を持ちすぎて、物語に出てくる神様まで源氏に遠慮して依怙贔屓しているのが癪に障る。「なら源氏物語が嫌いなのか、それならなぜ現代語訳をしたのかという質問が出そうだが、源氏という人物は好きになれないし、源氏の肩ばかり持つ紫式部にも反感を抱くが、物語を全体として見てその偉大さを認めない訳にはいかない」。秋成と同じように、作家と批評家の分裂が起こったと言えそうだ。
「細雪」は「源氏」現代語訳の仕事の後で書かれた。谷崎氏が「源氏」の現代語訳を試みた動機は、「源氏」の名文たる所以をその細部にわたって確認し、これを現代小説家としての自分の技法に取り入れようとするところにあったに相違ないだろうと私は思っている。それでも「源氏」の作者の「女々しき心」で書かれた人物批評の「おろかげなる」様は書いておかねばならなかった。谷崎氏の「源氏」経験は、今日の文学界では大変孤独な事件なのである。我が国の近代文学の二大先達である鴎外と漱石は「源氏」へ全く無関心だった。「帚木」冒頭にあるように、「光源氏、名のみことごとしう」と言えるだろう。
「本居宣長」-18章(2021/8/20)
余談はこの辺で切り上げようと思うが、宣長の手に渡った契沖の「定家卿が言う、詞花言葉を翫ぶべし」についての宣長の態度について触れたいというのが余談に見せた私の下心である。契沖はほんの片言で触れたに過ぎないし、真淵のような大才にもそう見えていた。だがこの片言の奥に実はどれ程の重みがあるのか。宣長の源氏開眼は、研究というよりむしろ愛読によった。
坪内逍遥の「小説神髄」は、我が国最初の小説論としてよく知られている。作家は、小説の作意を、娯楽、あるいは勧善懲悪に発するという迷夢から醒めて「小説の旨とする所は、専ら人情世帯の描写にある」事を悟るべきだ。その点で、(宣長の)「玉のおぐし」の物語論は卓見で、「源氏」は「写実派」小説として、小説の神髄に触れた史上稀有の作である、と。この意見は有名だが、逍遥が「源氏」や宣長の著作に特に関心を持っていたとも思えないし、小説一般の時の勢いに乗った上での思いつきではあり、だからこそ力強いものとなった。写実主義とか現実主義と呼ばれる漠然としてはいるが、強い考えの波に乗り、詩と袂を分かった小説が文芸の異名となるまで急速に成長していく、文芸界の傾向のうちに私たちはいる。
「源氏」は逍遥の言うように写実派小説でもなければ、白鳥の言うように欧州近代の小説に酷似もしていないが、そう見たい人にそう見えるのは如何ともし難い。鴎外によっても望まれた現代語訳という「源氏」への架橋は、今日「源氏」に行く一番普通の道になったが、通行者はその街道が写実小説と考えられた「源氏」にしか通じていないことは気にかけない。これは古典の現代語訳、西洋文学の邦訳の効用とは切り分けられるはずなのだが、言葉より言葉の表す実物の方を重んずる現実主義の底流の強さを考えなければ、どんな観点も設けずただ文芸作品を自由に味わったと思われながら同様のちぐはぐな語り口で体験を語った潤一郎、白鳥の感想が合点できないのだ。時勢にとやかく言いたい訳でなく、無意識に自分がある位置を意識することが、宣長の仕事を理解するうえで、どうしても必要だと思う。
専門化し進歩した「源氏」研究から、私も多くの教示を受けているが、そこには「詞花を翫ぶ」というよりも、むしろ詞花と戦うといでもいうように思わざるを得ない。研究者は、作品感受の門を素早く潜ってしまい、作品理解のための歴史学的社会学的心理学的などなどの、しこたま抱え込んだ補助概念の整理という別の出口から出ていってしまう。それを思うと、言ってみれば、「詞花を翫ぶ」感性の門から入り、知性の限りを尽くしてまた同じ門から出てくる宣長の姿が浮かび上がってくる。出てきた時の彼の自信に満ちた感慨が、「物語というものの趣きをばたずね」て、「物のあはれということに、気づく人のないのは、なぜだろうか」という言葉となる。
「源氏見る人は多けれど、その詞一つも我が物にならず、・・源氏に限らず、すべて歌書を見るに、その詞一つ一つ、我が物にせんと思いて見るべし」(あしわけ小舟)とは、宣長が抱いていた基本的な考えだった。宣長の最初の「源氏」論「柴文要領」と同じころに、「手枕」という二次創作を書いているということは見過ごせない。
「源氏」には六条御息所という女性が、物の怪の役を振られて物語の運びに深く関係して出てくるが、夕顔の巻で突然に光源氏の枕元に出てきて、読者も光源氏もしょの正体が分からない。もちろんそういう風に物語はかかれているのだが、この女性と光る減のの間にあった過去の情交について何も書かれていない。もちろんそれは、物語の趣向なのだが、「源氏」の詞に熟達しよう、我が物にしようとする努力であって、そこからほとんど自動的に生じたのが、宣長の掴んだ「物のあはれという気づき」である。宣長の「源氏」理解は、享受と批評という人為的な区別を必要としなかった。
「歌がたり」とか「歌物がたり」という言葉は「源氏」時代から普通にあったが、宣長は「源氏」だけを特別視した。歌ばかり見ていにしえの情を知るのではなく、物語を見ていにしえの歌を学べば、そのいできたる元がよく明らかになってよいと述べている。「源氏」はただ歌をまとめ、歌詞によって洗練されて美しくなった物語ではない。情に流され無意識に傾く歌と、観察と意識とに向く世語りとが離れようとして結ばれる機微が、ここに異常な力で捉えられているのだと宣長は見た。
例えば、源氏の君と紫の上の恋愛で、歌はどんな具合に応答されるのか。歌ばかり見て、恋情を知るのは末なのだ。二人は色々な事件が重なるにつれ、自他の心理を分析し尽くし、意識的な理解は行くところまで行く。だが、あるいはまさにそのゆえに、互いの心を隔てる言うに言われぬ溝を感じる。孤独がどこから来たのか知ることが出来ないまま歌を詠む。その意識の限界から詠まれるような歌はどこから来るのかは作者だけが掴んでいる。
研究者の道は、この「源氏」の体験の充実を確かにしていく道に繋がっていると宣長は信じた。それを迷わすもの、河海抄から紫家七論までそうされてきたように、「いましめの心」を持って見ることを、宣長は「魔」と強い言葉で呼び、「物のあはれ」をさますと警告した。
光源氏という人間は、本質的に作中人物であり、作を離れては生きる余地はない。宣長はこれを認識した最初の学者だったが、その個性的な認識を徹底した点で、最後の人だったとも言える。光源氏を、「執念く、ねぢけたる」とか、「虫のいい、しらじらしい」とかと評する秋成や潤一郎の言葉を宣長が聞いてもどうということはないだろうが、「源氏」を理解するという視点では、冗談に過ぎないとははっきり言っただろう。宣長は「源氏」を論じて、この種の品定めを一切しなかった。「雨夜の品定」に式部の女性観を見るのは構わないが、「源氏」の作者としての式部がそこにどんな趣向を意識したのかは別の話だ。「雨夜の品定」の、自由で繊細な実際生活に立つ人物評は挫折している。いや挫折させたのが作者の趣向であり、「極意」だったのである。
(14章を参照ください)
「いましめの心」という表現は広義だが、彼はこれを「もろこしの書の習気のうせぬ間は、この物語の意味は分からない」と表現した。式部は当時の一流知識人として儒仏の思想に通じていたに違いない。素直に受け入れてもいただろう。しかし、そういうものの影響から「この物語の意味」を知ることは不可能であることを、宣長はよく見ていた。宣長の言う「あはれ」というのも広義の感情だが、宣長は事物に触れて動く「あはれ」と、「事の心を知り、物の心を知る」事、すなわち「物のあはれを知る」事とを区別したのも、不安定で曖昧な現実の感情経験が、詞花言葉の世界で完成するという考えに基づいている。宣長は光源氏を「物のあはれを知る」という意味を宿した、完成された人間像と見た。そしてこの像の裏側に、何か別のものを求めようとは決してしなかったのである。
歌人にとって、まず最初にあるものは歌である。歌の方から現実に向かって歩き、現実を照らし出す道だ。逆は無い。これは宣長が式部の心に成り代わったかのようにして悟った方法であり、思想の知的構成によるものではない。それはいわば直接聞いた声であり、それが人間性の基本的な構造に共鳴することを確信したのである。宣長はそれを「いましめの方」から確信したのではなかったが、この確信から出発すれば「いましめの方」に向かって自由な視点が開けていた。
「・・この世の恩愛につながれて生死を離れることができないものを、あはれと思われるのが仏の心であり、儒道も同じである。物語は教誨の書ではないため、ただその目の前の物のあはれを知り、仏の慈悲、聖人の仁義の心も物のあはれと知るゆえに、一偏にかたよることなく書くのである。・・孔子ももしこれを見れば、三百篇の詩を差し置いて、必ずこの物語を六経に連ねられることだろう。孔子の心を知る儒者は、私の言葉を虚構だとは言わないはずである」
「本居宣長」-19章(2021/9/23)
「三十歳になった頃に縣居の大人(賀茂真淵)の教えを受け始めた。真淵が諭すには、まず漢心を離れて、真実の古意を尋ねなければならない。そのためには、万葉を明らかにすべきだ。私は万葉を極めて年老いてしまったが、今から怠りなく学べば神の御典(古事記)を読み解くことができるだろう。世の中ではいきなり高いところに登ろうとして低きところも得られない者が多い。まず低いところを固めてこそ、高みに登ることができるのだ。この諭しをありがたく思い、万葉集に心を染めて深く考えてみると、世に言う古事記の説明は、みな漢心の影響を受けて、本来の意を離れていることがよく分かった」(玉かつま)
これは晩年の宣長が「縣居の大人の御さとし言」として回想したものだ。学問の要は「古言を得る」という「低きところ」を固めるにある、そう真淵に言われただけで宣長が感服したはずはない。その事は宣長は早くから契沖に教えられていた。真淵自身、オリジナルとは言っていない。真淵が壮年期、郷里を去って身を投じた江戸の学問界は、徂徠学が盛りだった。「心法理屈の沙汰」の高みに心を奪われてはならない、「今日の学問は低く平たくただ文章を会得することにとどまる」(徂徠先生問答集)、これが古文辞学の学則だった。だがその学則の真意も、現れてくるものの豊かさを悟るのにも、大きな才能を要する。真淵は万葉にそれを行った。仁斎の「体現」という言葉をそのまま、真淵の万葉体現と表現してもいい。
「万葉を読むには、今の点本で意を求めずに、五度読むべし。そうすれば、訓例も語例も前後に相照らされて、自然に覚えることができる。その後、意味をざっと吟味することを一度して、その後写しと今本を比べて字の異なるところを書いておき、無点で読む。最初は難しいが、本当に難しくて読めない所だけ点本を見る。それを数度実施して後、古事記以下和名抄までの古書を何となく見る。古事記、日本書紀、あるいは式の祝詞、代々の宣命の文(天皇の命令を和文で書いたもの)などを見て、また万葉の無点本を見れば、大半が明らかになるだろう。そうして今の訓点の良し悪し、誤字脱字なども気づいたり疑ったりできる。千万の疑いを心に置けば、書はもちろん、諸国の方言俗語までも見たり聞いたりするごとに気づきがある。また思いめぐらして、思わぬところに定説を得ることもある。そうなれば、点本は却ってうるさく思うだろう」(真淵著:万葉解)
宣長は「源氏」を体現したのだから、真淵の教えが分からなかったはずはない。もっとも宣長の宝暦13年の「日記」にも、「5月25日、岡部江師(真淵を指す)当所新上屋(旅籠の名前)一宿、初めて対面す」とあるだけで、二人の間でどんな話が交わされたかは分からない。幸い宣長の残した回想文があり、いかにも宣長らしい、何気ない名文だ。
「京都にいる頃、百人一首の改観抄を人に借りて見て、初めて契沖という人の説とそのとても優れていることを知り、この人の書物を次々に求めて読んだが、すべて歌学びの筋の良し悪しけじめを、よくわきまえることができた。今の世の歌詠みの思いは大方心に適わないが、自分の歌の様子も今の世に背くわけでもなく、咎められることはなかった。後に江戸に上った人から、最近出たものだと『冠辞考』というものを見せられ、賀茂真淵の名も初めて知った。ざっと見ると、思いもかけないことが書いてあり怪しく思うが、立ち返って今一度見ると所々はそういう事もあるかも知れないと思い、また読むといよいよそうかと思わされ、徐々にその内容を信ずるようになった。後に思い比べれば、契沖の説は及ばないことが多いように思う。私の歌学びはそのようだ。さて道の学びはどうかというと、二十歳頃より神書の筋の物をあれこれと読みはしたが、京都に上った時にやはり集中して学びたいと思うようになった。しかし、契沖の歌論になぞらえて考えれば、今の世の神道者の説は誤っているだろうと思われ、師と頼む人も見つからず、いかに古への真実を考えられるだろうかと思う所にかの『冠辞考』を得て、この大人を慕う心が日に日に切になっていった。一年ほどたった頃にこの人が田安の殿のお仕事で伊勢の辺りを尋ね巡られたと知り、この松阪の里にも二三日留まられたとのことだったが、露知らず、後に聞いてなんとも口惜しく思い、帰り際に一日お越しになると知ったのを待ち構えて、ウキウキと急いで宿に伺い、ついにお会いすることができ、生徒の名簿に入れて頂いて教えを受ける事ができることになった」(玉かつま)
宝暦13年は、宣長の仕事の上で一転機を画した年だとは誰もが言う事である。宣長は「源氏」による「歌まなび」の仕事が完了すると、ただちに「古事記伝」を起草し、「道まなび」の仕事に没入した。文学の古典に関する講義を彼は松阪に帰ってから終生続けるが、彼の「日記」によれば「神代紀開講」とあるのは、真淵入門とほとんど同時である。だが、準備していない者に好機は訪れないものだ。
「歌まなび」と「道まなび」の二つの間に、宣長にとって飛躍や矛盾はなかった。私たちの持っている学問に対する実証性、合理性、進歩性に関する通念は、宣長の内に「物のあはれ」を論じる筋の通った実証家と、「神ながらの道」を説く混乱した独断家を、美点と弱点の混在、円熟と未熟の対立を見させてしまうのである。
宣長が回想で追っているのは、書物という対象に己を捨ててのめり込む精神的作業のようなものだが、実際に何が起こったのかという意味では説明を欠いている。真淵の冠辞とは、普通枕詞と呼ばれる。「記紀」「万葉」などから、枕詞340余りを取り出して、五十音順に並べてその語義を説いたものが『冠辞考』である。長流も契沖もこの特殊な言葉を枕詞と呼んで研究していたが、綿密かつ組織的な研究で、画期的だった。刊行まもなく松阪にいた宣長が読んだというのだから、よっぽど評判だったに違いない。実際その是非について様々な議論が学会を賑わしたが、宣長のこの書の受け取り方はそのような評判の外にあって、何か孤独なものが感じられる。宣長の関心はその真淵の精神にあったのではないか。専門家の調査によると『冠辞考』にはかなり無理な法則が用いられているが、そのまま「古事記伝」の中に採用されているという。そうには違いないとしても、無理を信じさせた真淵の根本思想の方に私の興味は向くのだ。
真淵がこの古い言葉づかいを改めて吟味しようとした頃には、枕詞はほとんど死語と化して、ただ古来伝世の用例として踏襲されていた。死語は生前どんな風に生きていたのか。例えば万葉随一の達人である人麻呂は、彼の歌ったように「言霊のたすくる国」に喜びの内に生きていたはずなのである。
枕詞とは何か。
「誰か人が得たいと思っても、後の世の習わしから思い計れば違ってしまうことも多いだろう。その人はひたすら上代の世の心ことばを知るべきだ。例えば冠を仰げばその位を知り、顔を見ればその人を知り、衣を見てその姿を知るときに、それは虚ろに知るようなものである」と真淵は言う。定義しようとすれば、生態が逃げてしまう。だから冠辞(=枕詞)とは、「ただ歌の調べの足りないのを整えることから起こり、詞を飾るもの」であると。上代では人の心は素朴で言葉も少なく、装いも簡素だった、それがやがて「身に冠あり、衣あり、靴あり、心にうれしみあり、悲しみあり、恋しさあり、憎しみあり」ということになる。言葉に慣れ、これを弄ぶ後世の人は、詞の飾りの発生が、身の装いと同じく、いかに自然で生活に必要であったかを忘れている。
冠辞が普通5音から成っているのも、和歌が五七調から成っているからであり、真淵に言わせれば「おのづから天つちのしらべ」に乗らざるを得なかった。歌が短歌の形に整備された万葉の頃となっても、「おもふこと、ひたぶるなるときは、言たらず」という状態は依然続いていて、それを土台にして冠辞が発展したというのが真淵の考えだ。
真淵は、「冠辞考」を書くに際し、当時普通に使われていた枕詞という表現を捨て、師の荷田春満が言い出した冠辞という言葉を用いた。「枕詞という表現は、古い雅な言葉とは思えず。まくらは夜のもので冠は昼のものとして用いられる。物の上に置くことを冠らすというのも古から今に通じる」としか説明していない。あまり理由になっているとも思えず、「おもふこと、ひたぶるなるときは、言たらず」という考えが根底にあるのだと思えば頷ける。彼はこうも言っている。「心ひたぶるに、言の少なきを思えば、名は後にして、言は先にあるべし」。
古くは「源氏」にも枕言(まくらごと)という言葉は見えるが、真淵はこれに触れて冠辞の性質に言及している。自分が冠辞と呼びたい上代の言葉には、源氏に言うように「故事を引用して今の思いを言う」ような性質は全くないのだ。「思うこと、ひたすらな時は、言葉が足らず、詞が足りなければ思う事を末に言い、不足した言葉で冠らす」。適切な表現が見つからない場合、自身の調べを整えるのが先決であり、思う事を言うのは末だ。この必要に答えてくれる言葉なら不足していても構わないだろうし、むしろそうなるだろう。言語表現に鋭敏な歌人は「言霊のたすくる国」「言霊の幸ふ国」を一歩も出られない。冠辞とは、「かりそめの冠」を、「いつとなく身につけ始めた」かのように用いられた用例であり、歌人はそこに工夫は出来ても、脱出はできないのである。
冠が頭につくように、「あしびきの」という上の句は「このかた山に」という下の句にしっくりと似あう。真淵の用語で言えば、「おこすことば」と「たすけことば」という別々のものが、互いに映しあうが、それは決して露わではない。それは今のメタファーの価値に似たようなものと言ってもいいだろう。どの国の文学史でも、詩が散文に先行してきたが、私たちは言葉の意味を理解する前に、言葉の調べを感じていたのだ。今私たちが慣れ親しむ散文にも、よく見れば遠いメタファーの残骸が散っている。言葉はどんなに豊かになっても、生活経験の多様性を覆いつくすことはできないのだから、言語構造には至るところに裂け目があり、暗がりがある。「おもふこと、ひたぶるなるときは、言たらず」という真淵の言葉は、そう解する事もできるだろう。
このような、未熟と呼んでも、詩的と呼んでもいい傾きを言語の疾患だと考えることはできない。そこには共同作業があって、誰にも共通の知覚を求めたいという願いを、内に秘めている。この秘められた知性の努力がメタファーを創り出し、言葉の隙間を埋めようとする。メタファーとは、いわば言語の意味大系の成長発展に、初動を与えたものだ。
ちなみに宣長の冠詞に関する考えは、言葉の意味合いと、今日誰もが使っている事とを考えれば「枕詞」という表現で別段子細ないという意見である。
「これを枕と言うのは、頭に置くためと誰もが思うけれど、そうではない。枕は頭に置くものではなく、頭を支えるためのものだ。頭だけでなく、すべて物の浮いて間の空くところを支えるものを枕と言うのだから、名所を歌枕と言っても、一句言葉の制限あるところに使う名なのだと知れば、枕詞と言うのもそのように理解できるだろう」
「本居宣長」-20章(2021/10/28)
宣長だけでなく、松阪の名もない医師に英才を発見して真淵も嬉しかったようだ。帰って祝いの宴を開いたと言われている。そこから「万葉集」に関する文通による質疑応答が始まる。真淵の死の前年まで五年間、万葉集12巻分にわたる「万葉集問目」として残されている。難訓難釈に関し私案を交えており、真淵も常に「是は難しい」「疑いがある」と率直な態度を取っていた。
真淵は明和六年(1770)十月に死ぬ。真淵は明和四年にようやく「万葉六巻までを終えた」と宣長に伝えている。彼は、「万葉集」の伝わる形に不信を抱いていた。今の一、二、十三、十一、十二、十四、の六巻だけが、上代より奈良の始めまでの歌を橘諸兄により選ばれたものと信じていた。
この「万葉集」の元型と思われるものの訓釈だけでも、急いで仕上げておきたかった。しかし、宣長宛ての所感を見ていくと、老衰の疲れと世間の俗事とでままならないのだと何度も書いている。
最後の手紙(明和六年五月九日、宣長宛)から最後の部分を引いておこう。
「私たちの神代の政については古い歌に残っています。古事記はその書でありますが、歌は口調の限りがあり、助辞には略されているところがあります。また、漢字で書かれており、全てが分かるわけではありません。ただ、祝詞宣命から助辞は見えると言うこと、私はまだ言っていないことであり、とても感服しました。・・宣命をまず見て、古事記の考を問われる必要があるとのこと、まず万葉から入り、歌文を理解して古事記の考を成すべきであるというのが私の本意です。
天下に、大を好んで大を得る人はいません。なので、私は小を尽くして大に入るべく、人の代を尽くして神代を伺うべきだと思って今まで励んできました。小を尽くし人代を尽くすこと、先師は早く亡くなり、同門に人無く、孤独の中でここまで成してきましたが、老いも極まり、記憶も失われ、才の乏しい事が恨めしい限りです。・・」
宣長は入門とともに、「古事記」原本の校合を始め、真淵から「古事記」の書入本を度々借りて「古事記伝」の仕事を進めていた。そして質疑は、「万葉」から「宣命」に入り、「古事記」を問おうとする段になって師の訃報に接したのである。宣長の日記には、同門から手紙で訃報を受け「哀惜堪えられず」とある。真淵の力は「万葉」に尽きたのだった。
「万葉集の歌は、およそますらをの手ぶり也」という真淵の説は、宣長の「物のあはれ」の説とともに、よく知られているが、これも宣長の場合のように、真淵の「万葉」味読の全体験を、何とか包んでいるものであって、それを思わなければただの説にすぎなくなる。「ますらをの手ぶり」にもいろいろある。宣長宛の手紙から引けば、「風調も、人によって色々である。古雅有り、勇壮悲壮有り、剛屈有り、寛大有り、隠幽有り、高く和やかなものあり、艶で美しいものあり、これら人の生得の違いによるのであり、いずれをも得たる方に向かうべきものである」。
そして、人により時期によりとりどりの風調に分かれているものの目指す頂上が人麻呂という抜群の歌人の調べだということになる。「柿本朝臣人麻呂は、いにしえになく、後になく、一人で荒魂和魂至らないところはない。その長歌の勢いは風雲に乗りて空を行く龍の如く、言葉は大海原に八百の潮の湧くが如し。短歌の調べは葛城の兵の強弓を引き鳴らすかのよう。深い悲しみを言う時は、ちはやぶるものも涙させるであろう」
「ますらをの手ぶり」という表現は、知的に識別できる観念ではないので「万葉集大考」が批評というより、歌の形になったものもっともなことなのだ。真淵の「万葉」批評が、「万葉」賛歌の形をとったのは、彼の感情に根差している。私たちの平凡な気分にも快不快は伴うことを考えると、感情とはすべて価値感情であると言えるだろうが、「万葉」に向かう真淵の感情がはっきりと「万葉」崇拝という方向を取ったのは、学問の目的が人がよにいきる意味、すなわち「道」の究明にあるという当時の学問の血脈によるのだ。
「高きところを得る」という真淵の予感は、「万葉」の訓詁という「低きところ」に、それも冠辞だけを取り集めて考えを尽くすという一番低いところに成熟した。その成果を取り上げ「万葉」の歌の様式を「ますらをの手ぶり」と呼んだとき、真淵は「高く直き心」を見ていたのに違いない。彼は自信をもって言う。「千代にも変わらぬ天地に孕まれ生れる人、いにしえの事は心、言葉の外にある。しかしいにしえを自分の心と言葉に習わし得たならば、身体こそ後の世にあれども、心と言葉が上代に帰らないことがあろうか。生きとし生けるもの、心も声も、すべていにしえも今も無いものなのに、習慣や賢しさで異なってしまうものだから、立ち返ろうとして難しいことがあろうか」(万葉集大考)
ところが、真淵は宣長にはこう言っている。
「文字を用いる時代より後に書かれる文は堅い。それ以前のものと思われるほめ言など、飛鳥藤原の人は使わないが、古事記にも、日本書紀にも、祝詞にもあるのを見たまえ。このことをよく見れば、上古の人に風雅で広大な心を知ることができる。
・・これを考えると人麻呂などの及ばないことを知る。今は文字にのみ寄る故にその文は悪い。故に古事記の文は大切である。これをよくふまえて考えるようにして欲しい。先にも言うように、工夫がましいことを憎むのでただ文事に入る。ついにその実を言わんとすれば、老衰存命ただ暮れに及べば術無し・・」
真淵はただ老衰と「万葉考」の重荷だけを担っているのではない。彼の苦しみはもっと深い所にあったことを、この書簡を読むものは思わざるを得ない。さらに言えばその苦しみは、当人にも定かではなかったのではないか。「ただ文事に入る」という文事とは、「万葉」であろう。「ついにその実を言わんとすれば、老衰存命ただ暮れに及べば術無し」とは何か。もし「ますらをの手ぶり」と言ったのでは、「その実」を言った事にならないのなら、彼の言う「実」とは一体何なのか。そう問われているのはむしろ真淵自身ではなかったか。「道」とは何なのか。人麻呂の「いにしえになく、後になく、一人であるすがた」と語った、明確な像が揺らぐのである。
真淵は「道」ではないものははっきりかたれたように思う。「ますらをの手ぶり」とは思えないものを、「手弱女のすがた」と呼び、これを例えば「作細(さくさい)」にして「鄙陋」なる意を現すとでも言っておけば捨て去ることができたが、「ますらをぶり」をどう処理したものかは難しい。真淵はこれを「高く直きこころ」「雄々しき真ごころ」「天土のままなる心」「ひたぶるなる心」と様々に呼んではみるのだが、安心できない。上古代の人の風雅はいよいよ弘大なる意を蔵するものと見えてくる。
真淵晩年の苦衷を本当によく理解していたのは、門人の中で恐らく宣長ただ一人だったのではないか。真淵の前に立ちはだかっているのものは、実は死ではなく、「古事記」という壁である事が、宣長の眼にははっきり映じていなかったか。宣長はすでに「古事記」の中に踏み込んでいた。彼の考えがどこまで熟していたかは分からないが、入門の年に起稿された「古事記伝」は、この頃にはもう四巻まで浄書されていた。「万葉」の、「みやび」の「調べ」を尽くそうとした真淵の一途な道は、そのままでは「古事記」という異様な書物の入口に通じてはいない、そこには一種の断絶がある、そう宣長には見えていたのではなかろうか。
二人は「源氏」「万葉」の研究で、古人たらんとする努力を重ねるうちに、我知らず各自の資質に密着した経験を育てていた。「万葉」経験と「源氏」経験とは、まさしく経験であって、二人の間で交換できるような研究ではなかったし、繰り返せるようなものでもなかった。弟子は妥協はしなかったが、議論を戦わす無用をよく知っていた。宣長は質問を、師の言う「低き所」に、考証訓詁にはっきり限り、そこからできるだけのものを学び取れば足りるとした。意識的にそうしたというより、内に秘めた自信から、おのずとそうなったと思われるが、それでも、真淵の激情を抑えるのは難しかったのである。
真淵がまず非難したのは、宣長の歌である。歌を批評してもらおうという気持ちは、恐らく宣長にはなく、詠んだものの添削を請うという、当時の門下生の習慣に従ったまでの事だと思われる。真淵にしてみれば、古詠を得ようとせずに「万葉」の意を得ようとするとは考えられぬことであり、平然と同じ風体の歌を送り届けてくる弟子の心底を計りかねた。
「これは新古今の良い歌は置いて、中に悪いものを真似ようとして、ついに後世の連歌よりも悪くなっている。一つも取るべきはない。これを好むというならば、万葉の質問もやめて欲しい。万葉は何の用にも立たないことになる」
だが宣長は、気にかけなかった様子である。「万葉」の質問を止めるどころか、まもなく「万葉集重載歌及び巻の次第」と題する一文を送り、歌集成立の問題について質問をしている。これは、契沖に従って、全二十巻を家持私選と主張して、真淵の説に真っ向から反対したもので、時代、部立、書き様から見て、選は前後二回行われたものとし、これによって現行本の次第も改めるべきものとする意見である。
これが真淵を怒らせた。「これは私の意と異なります。いまだ万葉その他古書の事は知らない内に意見を立てることは信じがたいことです。もしそうしたいということなら、私に尋ねるのは無用の事でしょう。私の答えにも、千万の古事であるから小事に誤りもあると思いますが、大意はよく考えて述べています。信じられない気持ちが露わでありますから、これまでのようにお答えはしないことにします。もしこの上ご質問なら、あなたの考えを皆書いて質問して下さい。万葉について私に一向説明することなく、質問するだけであれば答えられません。信じて頂けないようですから、お返事も無益なことですが、お約束したこともありますので、このように返答します。」
これではほとんど破門状である。公平に見て、真淵の説がよく考えられた定説とは言えないし、宣長の提案がそこまでおかしいものだったとも思えない。「万葉」は橘諸兄の選だという真淵の考えは、上代の「高く直きこころ」を映し出した「万葉集」の元型というものを、どうあっても想定したいという願いによって育成された固い信念だった。これを否定するはっきりした根拠も示さず、「二十巻ともに家持の選」と書き送ってくる宣長の態度が、真淵には心外だった。しかし、真淵の激情の依って来るところは、恐らくもっと深い所にあった。
真淵は「巧みなるは卑し」と宣長の歌の後世風を難じている。宣長側の書簡が残っていないので推察になるが、宣長もたびたびの詰問に、当たらず触らずの弁解はしていたらしい。だが、真淵は容赦しなかった。「貴兄は、いつまでそんな眠たいことを言っているのか。前の友がいるから捨てがたいとは、論ずるにも足らないことです。三十年以上前江戸に下った時、皆が異端と私の説を悪く言いましたが、意に止めず、十年も経った頃にはその人達は皆門人に入りました。世間をはばかる歌人は多いですが、一時は人気を得ても最終的には功も立てず亡くなっていくものです」。
真淵は疑いを重ねてきたのである。この弟子は何かを隠している。従えないのではない、従いたくないのだ。「信じ給わぬ気、露わ」と断ずる他なかったのである。
「本居宣長」-21章(2021/11/27)
破門状を受け取った宣長は、「縣居の大人の御前にのみ申せる詞」と題する一文を古文で草し直ちに真淵に送った。私の考えは端的で、宣長は複雑な自己の心理などにかかずらう興味は無かったと思う。宣長のあたかも再入門の誓いのごとき姿を見て、真淵にももう余計なことを思う必要はなかっただろう。意見の相違よりもっと深く、学問の道が二人を結んでいた。
宣長は明和四年(1767年)の秋「草庵集玉箒」を刊行した。「草庵集」は二条家の歌道中興の歌人と言われる頓阿の歌集であり、宣長はその中から歌を選んで詳しく注した。宣長最初の注釈書だ。早速真淵から詰問が届く。「私の所では源氏までを見せて後世の歌書は禁じている、歌も学も悪く、立つ所が低いからだ、頓阿など歌才はあると言っても、囲みを出るほどの才ではない。前にあなたに見せられた歌の低いのも立つ所が低いからだ・・云々」
宣長は詰問を予期していただろう。だいぶ後になるが、「続草庵集玉箒」も刊行しており、この仕事に自信があったのである。「古事記」「万葉集」を目指す学者の仕事ではないというような考えは彼には少しもなかった。「玉箒」の序文で名言している。「このふみ書ける様、言葉をかざらず、今の世のいやしげなるをも、数多交えている。これは、もの読み知らぬ童まで、聞き取りやすかれと思ったからだ」。有名な「草庵集」の註解は色々書かれてきたが、宣長に気に入らなかったのは、皆「事ありげに、あげつら」う解釈ばかりに偏っていること、契沖によって開かれた、歌をじかに味わい、接してその意を得ようとする道を行ったものがないことだった。真淵は契沖の道を知っていたが、「童」までがその対象だとまでは考えを進めていなかったのだ。
宣長は頓阿を大歌人と考えていたわけではない。新古今に比べればはるかに劣ると書いている。しかし、衰えた中で優れる頓阿の歌は、衰えている現代の歌壇の中で、一番手近で有効な詠歌の手本になるはずだと考えた。この実際家としての面は、恐らく宣長の仕事の中心的な動機をなしている。宣長は「古事記伝」もほとんど完成した頃に、「古今集遠鏡」を書き上げているが、彼の思想を理解する上で新古今を明るみに出した有名な仕事よりも大事だと私は考えている。
「古学」「古道学」の大家である宣長に「古今集」の現代語訳があると言えば、意外に思う人もあるかもしれないが、「遠鏡」とは現代語訳の意味である。宣長に言わせれば「古今集の歌どもを、ことごとく、今の世の俗言(ぞくごと)に写せる」ものである。宣長は歌集の在来の註解書に不満を感じていた。注釈は進歩したが、それは歌の情趣の知的理解の進歩にすぎない。歌の鑑賞者は「物のあじわいを、甘し辛しと、人の語るを聞」き、それで歌が分かったと言っているようなものだ。この人のあまり気づかない限界を破るためには思い切った処置を取らねばならない。歌の説明を詳しくする道を捨てて、歌をよく見る道を教えねばならない。どうしたら良く見えるかという説明も無益だ。直に「遠めがね」を読者に与える。歌を説かず、歌を写すのである。
「遠き代の言の葉の、くれない深き心映えを、安く近く手染めの色に写して見るのに例えれば伝わるだろうか」というのが宣長の考えだ。「遠めがね」の徹底したやり方は原本で味わうほかないが、「初学び」のため、「もの読み知らぬ童」のために、大学者が円熟した学才を傾けたのは面白いことだ。真淵と宣長の大きな違いは明らかだと思うが、宣長の和歌史論として最も詳細な「あしわけ小舟」から深めてみたい。
まず歴史性が強調され、歌が「人情風俗につれて、変易する」のは自然な事で、「この人の情に連れるということが、不変の和歌の本然と知るべし」と言い切る。もちろん変わらないところもある。人の顔でも「目が二つ、耳が二つ」など変わらないが、「言うに言われぬ所に変わり目がある」ところに万人の表情があるのだと気づくはずだ。歌でも同じで、例えば「昔は春が来ると言った事を、今は行く春とも言う、―昔花咲くと言った事は、今も花咲くと言」う。
変わらない所ははっきり言えるが、世の移り変わりと共に移る歌の体については、誰もが正確な叙述を欠くのである。宣長は、歌の歴史には「変わる所」と「変わらない所」の二面性があると言っているのではない。歌を味わう事と、歴史感覚とでも呼ぶべきものを錬磨するのは、同じ事だと言っているのである。歌を味わうとは、その「えも言われぬ変わり目」を確かめるという一筋を行くことであって、「変わらざる所」を見つけ出して良し悪しを判ずるということではないのである。
宣長は「新古今」を重んじた。「この道の至極にして、この上なし」「歌の風体を全備しており、後世の歌の善悪勝劣を見るに、新古今を的にして、この集の風に似るのが良い歌だ」。随分はっきりした断定で、これだけ見れば真淵の万葉主義に対して宣長の新古今主義と言われるのも最もなようだが、それは当たらない。何故かというと、この宣長の断定は、今まで述べてきた意味合いでの真淵には見られない歴史感覚に立ってのものだからだ。
「記紀」にある上代の歌は「上手という事もなく、皆想う心を種として、自然に詠んだ」。その内次第に、「良い歌を詠もうという心」が自然に生じ、「万葉」の頃になると、「真の情を詠む事と巧みさを目指す事と大方半々になる」その後漢文も主流であり、詠歌が歌道という一つの道だという自覚は容易に得られなかったが、「古今」の勅撰によってようやくその機が訪れた。そして、「何事も世世を経て全てが備わる。聖人の教えも三代の聖人を経て周に至って整った。歌の道も世世を経て、新古今に至って全てが備わったのであり、この上良し悪しを言うのは邪道である」。
宣長が「新古今」を「この道の至極」と言った意味は、求めずとも情と詞とが均衡を得ていた「万葉」の幸運な時が過ぎ、詠歌が次第に意識化してついに情と詞ともに意識的に求めねばならない頂きに登り詰めた姿を言う。この姿は越えがたいと言っているのであって、完全だと言っているのではない。「歌の変易」だけが「歌の本然」であるとする宣長の考えの中に、歌の完成完結という考えはないのである。
もし真淵の「万葉」尊重が、「新古今」軽蔑と離す事ができないと言えるなら、宣長の「新古今」尊重は、歌の伝統の構造とか組織というようなものと離す事ができない。和歌の歴史とは、詠歌という一回限りの特殊な事件の連続体であり、そのつかみどころのない生な歴史像が「新古今」を直知することにより、味わうことができるのである。宣長は真淵が「万葉」に帰れと言うように、「新古今」へ帰れとは決して言わなかった。むしろ詠歌の手本として危険であると警告しているのである。
「本居宣長」-22章(2021/12/20)
「うひ山ぶみ」を書く頃になると宣長は真淵の亜流をはっきり意識して、「今の人は口にはいにしえ、いにしえと猛々しく言うけれど、古の定まりをわきまえていないから・・」と笑う。詠歌とは長い伝統の上を今日まで生き続けてきた、具体的な言葉の操作である。「今の世」「今の心」の、それも歌道の衰退した現在の現れという、実際的な問題である。この宣長の考えは、「あしわけ小舟」「うひ山ぶみ」を通じて一貫している。詠歌の手本として「新古今」は危険だし、「万葉」は「時代が過ぎている末の世の人の耳には遠く、心に感ずる事が少ない」。そうなると定家の言うように三代集(「古今和歌集」、「後撰和歌集」、「拾遺和歌集」のこと)を手本にせよという考えは動かない。が、絶対というわけでもなく、初心者などには難しいのでまずは噸阿の「草庵集」などから題を手本にして詠むといいのではないかとも書いている。
彼の歌は大部分後世風で、新古今風のものとは言えない。古学者がなぜ後世風の歌を多く詠むのかという質問にもかれははっきり答えている。「古風は詠むべきこと少なく、後世風は詠む事多きが故なり。」つまり、自分が後世に生まれ合わせたからだというのだ。では、和歌ではなく俳諧が今日の言葉を使っているのだから、そちらを選ばないのかという問いには、「連歌俳諧浄瑠璃小歌童謡の類は皆和歌の内の支流であって、これに対するものとして和歌を論ずるべきではない。その中に雅俗があるのであり、なぜ雅を捨てて俗を取り、本を置いて末を求めねばならいないのだろうか。されども、これもその人の好みに任せるべし」と。その人の好みにまかすべし、という言葉はここだけでなく文中いくつも出てくる。「詩が勝ると思えば詩を作るべし。歌が面白いと思えば歌を詠むべし。詩歌は現代の状況に遠く俳諧が今日の世情に近いと思えばそれに倣うべし。また詩歌俳諧みな無益と思えば、何でも好むに従うべし」。もちろん、学問の方法まで自分の好みに従ってくれるとは夢にも思っていない。
このあたりで宣長が自分の見解の説明に苦労している見本を示してみよう。
「今は人の心、偽り飾る事多ければ、歌もまた偽り飾る事多いのが、人情風俗につれて変わっていく自然の理にかなうことである。この人の情に連れるということが、万代変らぬ和歌の本質と知るべきである。そうであれば、和歌を心掛ける者は、とにかくまず今の人情に従って、偽り飾りながらも、古い歌を学び、古代の人の詠じた歌のように詠まん詠まんと心がければ、その中に自ずから、常に見聞きする古歌古書に心が変化して、古人のような心のように移り変わるものである。その時は、まことの思う事をありのままに詠むというものになるだろう。これは、古の歌の真似をして、飾り作って詠み、見習うのではそのようにならない。これが和歌の功徳というもので、自身の心が変容していることが必要だ。後世の歌は偽り飾っていてまことではない、古代の質朴なものが実情だと言って、今の世で思う事をありのままに詠んだならば、見苦しい歌しかできないだろう。今の人情に偽り飾ることが多いと嫌がりながら、そのありのままに詠むというのは心得違いなのだ。私が教えるのは、この裏である。私が教えるのは、今の偽り飾ることが多い心情のまま、昔の人の真似をして詠み習い、昔の人のように自然になっていくということだ。ここが氷と炭ほどに違うところだ。」
明らかに宣長は、当時歌を論ずる人の間の通念に対して物を言っているのだが、残念ながら馬鹿の一つ覚えの通念に表も裏もないのである。歌が、人情につれて変化するのは「自然の理」とも呼んでいいほど分かり切ったことだが、この変化を変化として素直にありのままに受け入れることが大変難しい。歌を論ずる人々は、変化に被せた偽り飾るという言葉に、知らぬ間につまずいているのではないか。現在に生まれ変わろうと願っている過去の歌詞の資源に出会おうと道を開いておかなければ、詠歌の未来に向かう道も閉ざされるだろう。この考えは、伝統主義とは言えるが、復古主義とは言えまい。
だが面倒はその先にある。古歌を学ぼうと努力している内に、古歌に「心が変容させられ」るということが起こる。「その時は、まことの思う事をありのままに詠むと言えるものになる」。ここに「和歌の功徳」という宣長の考えが出てくる。もちろん、心の変容が歌の目的ではなく、歌は歌であるので十分であり、心が知らぬ間に歌に変化させられるという、歌固有の働きの問題が宣長の歌学の問題なのである。
「和歌は言辞の道なり。心に思う事を程よく言い続くる道なり」という宣長の言葉は、歌は言辞の道であって、人情や性情の道ではないというはっきりした言葉と受け取らねばならない。歌は「人情風俗につれて変化する」が、歌の変化は、人情風俗の変化の写しではない。私たちの現実の性情は変化して消滅する他ないが、この消滅の代償として現れた歌は、別種の生を受けて死ぬことはないだろう。「心に思う事」は、これを「程よく言い続くる事」によって死に、歌となって生まれ変わる。歌の功徳はその歌の誕生と一緒だから、「心に思う事」のうちに現れるはずはない。これを念頭に置けば宣長はこう言っていることになる。
―もし、「心に思う事を、程よく言い続くる」、詠歌の手続きが正常に踏まれて、詠歌が成功するなら、誕生した歌の姿は「まことの思う事を、ありのままに詠むというものになる」と。
詠歌にあっては、「言葉第一なり」という宣長の考えは大変強い。「古人とて歌は、とかく思う心をほどよく言い整うるものなり。ならばその心は、自然と求めずしてある。思う心があって後に、歌を詠む。ならば求めるところは、言葉を整えるところにある。今は、心と言葉共に求めて歌を詠む。必ずしも心に思わなくても、題を取るなどして、心と言葉を求めて詠む。題を取ってまず情を求め、その後言葉を整える。この時情を求めることが先にあるけれども、そもそも情は求めるものではない。情は自然に起こるものだからだ。ただ求めるのは言葉である。この故に、言葉を整えるのが第一というのである」
そしてこの「言葉第一なり」という考えを突き詰めると、もっと強い言葉が必要になってくる。
「詠歌の第一義は、心を静めて妄念を止むるにあり」という。「心を静めるということが、難しい。沈めようと思ってもとかく妄念が起こり、心が散乱する。それを静めるのに大秘訣がある。まず妄念を退けて後に案じようとすれば、いつまでも妄念はやまない。だが、妄念が止まなければ歌はできない。心が散乱して妄念が競い起こる中で、妄念を静めることを差し置いて、詠もうと思う歌の題などに思いをやり、趣向のよりどころ、言い回しの端、縁語などに少しでも手掛かりができれば、それを取り放さないように心のうちに浮ばせておいて案ずれば心がまとまって、次第に妄念は退いていく。このように情詞について少しの手掛かりを元にして案じてゆくのである」
これは普通誰しも経験するところで、何も詠歌の大秘訣でもないのだが、宣長がそう言いたかった事、着目しているところは、歌人の言語意識の不徹底にあったことは明らかだろう。「情は自然に起こる」というだけでは足りない。自然に起こる心はそのままでは「心散乱して、妄念競い起こる」状態を抜けられるものではない。言葉という「手がかり」がなければ、心は始末がつけられないものだ。思う心を「程よく言う」では言い足りない。乱れる心を「しづむ」「すます」「定むる」というべきだ。「石上私淑言」では、「胸にせまる悲しさを、はらす」と、同じ意味合いで「はらす」という言葉が使われている。悲しみを詠むとは、悲しみを晴らすことだ。悲しみが反省され、見定められなければ、悲しみは晴れまい。言葉の「手がかり」がなくて、どうしてそれが人間にできるだろう。「とかく歌は、心騒がしくては、詠まれぬものなり」という言葉に続けて、かりに宣長が「心騒がしくては、常の言葉さえ無きものなり」と書いていたとしても、私は少しも驚かないだろう。
「本居宣長」-23章(2022/1/27)
「歌」「詠」の字は、古来「うたふ」「ながむる」と訓じられて来たが、宣長によればもともと声を長く引くという同義の言葉である。後の分析ではさらに詳しく、これに「なげく」が加わる。「なげく」も「長息(ナガイキ)」を意味する「なげき」の活用形であり、「うたふ」「ながむる」と元来同義なのである。
「ああ、はれ、あはれ」という生の感動の声は、この声を「なげく」「ながむる」事によって歌になる。歌の本質をそんな所に求めた歌学者はいなかったのである。だから、分かりにくいことも宣長は承知していたのだが、その説明から分かるのは、「ただの詞」より「歌」が先で、「歌」よりも声の調子や抑揚が先だという考えだ。「ただの詞」という概念が分かりにくければ、「ただの詞と異なる」とされているものが「歌のかたち」と呼ばれていることに注目するといい。宣長に言わせれば歌とはまず何をおいても「かたち」なのだ。その「かたち」は「文(アヤ)」とも「姿」とも呼ばれている表現であり、歌とはそういう「物」として誕生したという宣長の考えはまことにはっきりしている。発達した歌の形式に慣れた今の人の心にはまず「ただの詞」があり、それを「文(アヤ)」によって装飾する歌という技術が発達したという通念がある。宣長の考えはまずこの通念と衝突せざるを得ない。
もちろん宣長は、「ただの詞」に表現性がないと考えているわけではない。ただ、通常言葉は目的がある。実生活上の様々な目的を持って意図を伝えたり、物事を指示したりすればそれで消費されて終わってしまう。歌人は、何かの手段として言葉を使わない。有用性を離れて自立する言葉の表現性を目指す。それが「歌の道」であることを、宣長ほどよく見抜いていた人はいなかった。
「ただ心の欲する通りに詠む、これ歌の本然なり」という明白な考えに立ち返ってみようとすれば、「歌の道」の問題は、「言辞の道」というその源流に触れざるを得ない。そうすれば、歌とは何かという問題を解くに当たり、「うたふ」という言葉がどういう意味合いで用いられる言葉として生まれたかを探るところに、一番確かな拠り所があると悟るだろう。激情の発する叫びも呻きも歌とは言えない。だが、私達は混乱した動きには耐えられないように出来上がっているから、無秩序な叫び声が無秩序なままに放っておかれる事はない。私たちが思わず「長息」をするのも、内部に感じられる混乱を調整しようとして、極めて自然に取る私たちの動作だろう。そこから歌という最初の言葉が「ほころび出」ると宣長は言うのだが、このような問題について正確な言葉など誰も持ってはいない。ただ、言葉は決して、頭脳というような局所の考案によって生まれでたものでないという宣長の言語観の基礎にある考えは銘記しておいた方がいい。
宣長の「源氏」論の課題は、「あはれ」とは何かではなく、「あはれを知る」とは何かであった。人の実の情を知るを、物の哀れとを知ると言うのだと言っているが、人の実の情は知りがたい。こんなに不安定なものはないからだ。宣長は次の事に注目している。「心に深く感(あはれ)と思うことあれば、かならず長息(ながいき)をするので、そこから転じて物に感じることを、やがてナゲクともナガムルともいう」「物思う時は常よりも、見る物聞く物に心が止まり、ふと見る雲霞木草にも目がついてつくづくと見る。物思う事をナガムルというのだったのが、後には必ずしも物を思わなくてもただ物をつくづく見る事をそのように言うようになった」。
長息するという意味の「ながむる」が、つくづく見るという意味の「ながむる」に成長する、それがそのまま歌人が実情を知る、その知り方を現すと宣長は見るのである。歌道の極意は「もののあはれを知る」ところにあるが、それは情に溺れる「あだなる事」にも、溺れまいとして分別を立てる「まめなる事」にも全く関係ないという考えが宣長の源氏論にはあった。耐えがたい悲しみを行動や分別のうちに忘れる便法を歌道は知らない。悲しみをそっくり受け入れてこれを「なげく」という一筋、悲しみを感ずるその感じ方の工夫という一筋を行く。誰の実情も、訓練されなければ、その「かたち」をつくづくと見る事が出来る対象とはならない。私達が理解している「意識」という言葉と宣長が使った「物」という表現を使って、「歌とは、意識が出会う最初の物だ」と、そう言いたかった宣長を想像してみてもいいだろう。
ここでもう一つ、「あしわけ小舟」から引用しておきたい。
「悲しみ強ければ、自ずから声に文(アヤ)があるものだ。その文(アヤ)というのは、泣く声の、オイオイという様にある。これは表現が巧みだという程の事はないが、自然なだけでもなく、そのオイオイという声に文(アヤ)をつけて泣くことで、心中の悲しみを発するのだ。外から聞く人の心にはその悲しみはまた大いに深く感じられる。こういう事は愚かなようだけど、そうではない。唐では喪に服する礼の定まっているのも、実情を導く仕方として聖人の知は深きものだと思われる。」
突き詰めていけば、礼とは、「実情を導く」その「仕方」だと彼は言う。それならこれは、言葉なき歌だとも言えるわけだ。礼を言えば楽を言った聖人の言葉は深い。誰も、各自の心身を吹き荒れる実情の嵐の静まるのを待つ。叫びが歌声になり、震えが舞踏になるのを待つのである。捕らえどころのない悲しみの嵐が、自ずから文(アヤ)ある声の「カタチ」となって捕らえられる。宣長に言わせればこの「カタチ」は、悲しみが己を導く「仕方」を語る。これがそれしか語らない純粋な表現であり、模倣も繰り返しも出来る悲しみのモデルといってもいいものに出会うということが、各自の内部に起こる。もしそうでなければ、喪という共通の悲しみを予感し、己の悲しみを発し、これを相手と分かつ道がどうして開かれるだろう。礼は聖人の知恵の発明ではない。そう見抜いたのが聖人の知恵だ、と宣長は言うのである。
宣長は、その歴史観、特に言語観の上で、真淵に比べると余程柔軟なものを持っていた。真淵の言う「低き所」とは、古語の注釈や古語の語釈という地道な根気のいる仕事を指すのだが、宣長はこの道をいよいよ低くその底辺まで行ったと言ってもよい。彼は、「古今集」の雅言を、そっくり今行われている俗言に写してみるというところまで行かなければ承知しなかった。宣長が我が国最初の古典の現代語訳者となったのは、「古事を得んとする」一筋の願いに駆られていたからであった。純粋で、かえって分かりにくいかもしれないが、今日ではごく当たり前となった古典の現代語訳の仕事の動機を思えば足りるだろう。宣長の著作を読むと、その仕事がどんな形を取ろうと皆、古典や伝統というものへの愛情や信頼という源泉からあふれて一筋の流れをなしているのがよく感じられる。現代人の心や反省は、現代的教養の色眼鏡を通してなされるから、古典との生きた関係を自分の手で断ちながら、それに気づかぬということもあるのである。
宣長は「古今集遠鏡」を書いた動機についてこう言っている。「さとびごとに写したのは、物の味を自ら舐めて知れるように、古の雅言みな、己が腹の内のものとしなければ」云々。また、「すべて人の語は、同じく言うことも、言いざま、勢いに従って、深くも、浅くも、おかしくも、憎々しくも聞こえる技であり、歌はことに心の有る様を、ただに打ち出す趣のもので、その詞の口の言いざま、勢いの端々も耳に聞きとらないでは分からないもので、詞の様をよく味わい、詠む人の心を推し量り、その勢いを写すべきなのだ」。
言語化、「己が腹の内のもの」になっているとは、どういう事か。それは、日常生活の中で、日常言語をやり取りしているというその事なのだから、あえて考えてみることなどあるまい。それは、言語というより、言語活動と呼ばれる生活そのものを指すのである。語の内に含まれて変わらない意味などというものは無いのであって、語り手の語り様、聞き手の聞き様によって、語の意味は変化してやまない。それでも互いに語ることができるのは、語の「言いざま、勢い」によると宣長は言う。その全く個人的な語感を互いに交換し合い、即座に翻訳し合うという離れ業を、私たちは我知らず楽しんでおり、暗黙の裡に相互に合意や信頼に達してすらいる。宣長はそこに「言霊」の働きと呼んでいいものも感じ取っていた。
宣長は「古意を得る」ための手段として、古言の訓詁や釈義の枠を、思い切って破ったのだ。古言をただ判読するだけでは足りない。古言と私たちとの間にも、普段の会話のような語り手と聞き手の関係を創りあげなければならぬと考えた。それは出来るはずだ。「万葉」に現れた「言霊」という古言の本義を問うのが問題ではない。現に誰もが経験している俗言の働きという具体的なものとしっかり合体して、この同じ古言がどう転義するか、その様を見るのが肝心なのである。
契沖も真淵も、非常に鋭敏な言語感覚を持っていたから、決して辞書的な語釈に安んじていたわけではなかったが、語義を分析して本義正義を定めるということは、彼らの学問ではまだ大事な方法だった。ところが宣長はそんなことはどうでもいいと言い出す。
「語釈は緊要にあらず。―最初はいかなる言葉も知りがたきことだが、強いて知らなくても事欠くことなく、知りてもさほど益はない。諸々の言葉はその元の意味を考えるよりは、古人の用いるところをよく考えて、どの言葉は何の意味に用いたということを、よく明らかにして知ることを要とすべし。言葉の使い方を知らねば、その文意は分からず、自ら物を書くにも、言葉の使い方が分からない。それなのに、今の世古学の輩は、ひたすら言葉の元の意味を知る事だけを心掛けて、用いる意味をなおざりにする故に、書を解し誤り、自らの歌文も、用い様を違えてしまっていることが多いのだ」
宣長のはっきりした語調に注目して欲しい。契沖、真淵を受けて「語釈は緊要にあらず」と言う宣長の踏みだした一歩は、巨人の肩から踏み出した一歩だったのである。
「本居宣長」-24章(2022/2/24)
古学の目指すところは、宣長に言わせれば、「古事を得ること」、あたかも「物の味を、みづからなめて、しれるがごと」き親しい関係を、古言との間に取り結ぶことであった。それは、結ぼうと思えば、誰にでもできる、私達と古言の間の、尋常な健全な関係なのである。だから、古言の根元を掘って行けばその語根が見つかり、その本義が定まるという学者達のやり方が気に入らない。気に入らないというか、古学には向かないということを感じ取っていた。宣長が着目したのは、古言の本義よりもむしろ転義だった。古言がどんな対象を新たに見つけて、どのように転義し、立ち直るか、その現在の生きた働き方の中に、言葉の過去を映し出して見る人が、言語の伝統を自ら味わえる、そういう考えなのだ。
そういう考えが土台になって、「詞の玉緒」という「てにをは」の研究が書かれた。宣長50歳の時の作だが、若い頃からこれが大事だとは早くから考えていた。「てにをは」は、漢字の助字のようなものだと言う人もあるが、それは大変な間違いである。助字は「文章の余勢のようなもの」で、無くても「文章は、聞こえる」ものだが、「てにをは」は一字違えても文章は分からなくなる。「てにをは」は、詞という玉を貫く緒と考えられた。また、文という衣を縫う縫い手に例えて、すばらしい布でも縫いが悪ければよい着物にならないというようなことも書いている。「てにをは」の姿は、語意より文意、文意より分の勢いへと宣長の眼を動かしていき、語の「用い方」「いいざま」「いきおい」が強調されていく。
言語の問題を扱うのに、宣長は言語という「物」に外から触れる道を行かず、言語を使いこなす私たちの心の働きを内からつかもうとする。「詞の玉緒」では、「万葉」から「新古今」に至る詠歌の作例が検討され、「てにをは」の「ととのえ」が発見され、それは「いともあやしき言霊のさだまり」と表現される。古言はいつのまにか今の言葉に移り変わるが、言語機能の基本的な構造は変わりようがなく、これが恐らく私たちの心の本質的な連続性に見合うものだというのが宣長の考えだった。
真淵にとっての「万葉」と宣長にとっての「源氏」は、互いに交換できるような研究対象ではなかった。一方は歌であり、他方が物語であることが、二人に深く作用したのは当然だ。「紫文要領」から再度引く。「歌ばかりを見て、古の情を知るのは末である。物語を見て、古の歌を学ぶのは、古の歌の出で来る由を良く知るため、本が明らかになる」。宣長が「紫文要領」でまず注意したのは、「古来の注釈書」によって「源氏」を読んではならないということだった。注釈書では、まったく種類が異なるのに、儒家仏書の道徳論の影響を受けているからだ。そのような一切の先入観を徹底して捨ててみた時に、宣長は「源氏」に、歌の姿ではなく、「人の情(ココロ)のあり様」を見た。
「見るにもあかず、聞くにもあまる」ところを、誰も「心にこめがたい」、こんな分かりやすいことはない。そしてそれは根本的な人生経験だろうが、その人生という主題が語られるとき、ただ「心にこめがたい」という理由で人生が語られると、「人の情(ココロ)のあり様」が見えてくる、そんな風に語られるというのである。宣長はそんな風に「源氏」を詠んだ。誰にとっても生きるとは、物事を正確に知るということではなくて、ただ生きられる物事なのである。そしてその世界は喜怒哀楽の色に染められて、まるで人の表情をしているかのようにして出会う。
宣長は、経験という言葉は使わなかった。だからここでもう一度引用することになるが、「万のことを心に味わって、心にわきまえ知る、これが事の心を知る、物の心を知るということだ。―わきまえ知り、それに従って感ずるところが、物のあはれなのである」(紫文要領)。そうすると、「もののあはれ」はこの世に生きる経験の本来の有り様のうちに現れる。この「まこと」「自然」「おのづからなる」などと色々に呼ばれる「事」の世界は、また、「言(こと)」の世界でもあったのである。
「本居宣長」-25章(2022/2/24 今回は二章読みました)
真淵は「やまと魂」という言葉を、万葉歌人等によって詠まれた「丈夫(ますらお)の、雄々しく強き、高く直き、心」という意味に解した。そして「古今」の「手弱女(たおやめ)のすがた」に変ずる「下れる世」となると、人々は「やまと魂」を忘れたと考えた。
しかし、「やまと魂」とか「やまと心」という言葉が上代に使われた形跡はなく、真淵の言う「手弱女のすがた」となった文学の内に、どちらも初めて現れてくる言葉なのである。「やまと魂」は「源氏」に出てくるのが初見、「やまと心」は、赤染衛門の歌(後拾遺和歌集)にあるのが初見で、王朝文学の崩壊とともに文学史から姿を消す。だから、真淵は「手弱女」の用語を拾って勝手に「丈夫」の言葉に仕立てたと言ってもいいのだが、真淵は特に気にしていないようだ。
「源氏」の中の「大和魂」の用例は一つしかなく、「乙女の巻」で「才(ざえ)を本としてこそ、大和魂の世に用いられる方も強くあるものだ」と書かれ、才(ざえ)は広く様々な技芸を言うが、ここでは夕霧を元服させて大学に入学させる時の「文才(もんざい)」、学問を指して言われている。学問というものを軽んずる向きも多いが、やはり学問という土台があってこそ、大和魂を世間で強く動かすこともできると言っている。才は学んで得た知識、大和心はこれを動かす知恵に関係するといっても良さそうである。
試しに真淵の注釈を見ると、この文について次のように書いている。「この頃はもっぱら漢学をもって天下を治める事となっていて、このように書かれたのだろう。されど皇朝の古には、皇威盛んで民は安まり、天地の心に任せて治め、民を従えていた。人の心をもって作られる理学にてこの国が治まるわけではないことを偏に信ずる余り、臣に世を取られることとなった。そのような事まではこの時代の人には分からないし、女性が思い計れることでもない」。真淵らしく面白い文だが、これでは注釈とは言えまい。下れる世に女の手によって成った物語への不信の念が露骨で、「大和魂」という言葉のここでの意味合いなどに、まったく注意が払われていない。
もう一つ、「今昔物語」に、「明法博士善澄、強盗に殺されること」という話がある(明法博士は、法律博士と理解してOK)。ある夜、善澄の家に強盗が押し入った。善澄はスノコの下に隠れ、強盗の狼藉を見ていたが、彼等が去ると後を追って門前に飛び出し、おのれ等の顔は皆見覚えたから、夜が明けたら検非違使に訴えて片っ端から捕まえてやる、と門を叩いてわめき立てたので、これを聞いた強盗達は引き返してきて善澄を殺してしまいました。物語の作者は付言して「善澄は才はめでたかったが、大和魂が無かったために、このような幼いことを言って死んだのだ」と。
これを見るとさらにはっきりするが、机上の学問に比べられた生活の知恵、死んだ理屈に対する生きた常識という意味合いである。両者が折り合うのは難しいと「今昔物語」の作者は言いたいのである。すると源氏君の方は何の事はない、ただ折り合うのが理想だという意見になるわけだが、作者式部の意見となればこれはまた別だ。主人公にそう言わせておいて、すぐに続けて大和魂の無い学者等について語り始めるわけだ。夕霧の大学入学式の有様がおかしく語られ、善澄のような博士達の、「ちょっと彼らの目の前で話をしても博士らは叱る、無礼だと言って何でもないこともとがめる。やかましく勝手気ままなことを言い放っている学者たちの顔は、夜になって灯がともったころからいっそう滑稽なものに見えた。まったく異様な会である。」(与謝野晶子訳)と、ずらりと並んで面白い。これはこの作者の辛辣な筆致の代表のものだが、作者の眼は「大和魂」の方を向いていると見るのが自然だ。
赤染衛門も歌で「大和心し 賢くば・・」と歌っているが、意味からすれば単に「心し 賢くば」でいいわけで、実際「源氏」の中でも、特に「才」に対して使われる時でなければ単に「心かしこし」なのである。大和心、大和魂が、普通いつも「才」に対して使われているのは、元は漢才(からざえ)、漢学に対抗する意識から発生した言葉である事を語っているが、当時の日常語としての意味合いは、「から」に対する「やまと」よりも、技芸、知識に対して、これを働かす心映えとか人柄とかに重点を置いていたと見てよいように思われる。
宣長も真淵のように、「大和魂」という言葉を己のものとして、一層強く勝手に使用した。「うひ山ぶみ」で、「やまとだましいを堅固(かた)くすべき」と繰り返し強調し、その「やまとだましい」は「神代上代の、諸々の事績の上に備わる」「皇国の道」「人の道」を現す心という意味と述べる。「玉の小櫛」を見ても、「やまとだましい」という言葉の注はないが、宣長は真淵とは比較にならぬほど「源氏」を熱心に、慎重に読んだ。真淵と違ってこの言葉の姿は忠実に受け止められて使われたと見て差し支えない。
後年宣長は還暦を迎え、自画自賛の肖像を作った。その賛が名高い「しき嶋の やまとごころを 人とはば 朝日ににほふ 山ざくら花」の歌であった。彼は国学の専門家としてよく知っていたこの古言を取り上げたまでであったが、儒家が多くを占める学会では耳障りな新語と聞こえただろうし、国粋主義を唱えるために思いついた標語とも映った。上田秋成のような鋭敏な神経にはもうそれだけで我慢ならず、これを批判している。
標語を思いつくとか掲げるというのは、宣長の学問の方法からしても、その気質からしても、まず考えられない。彼は、和学とか国学という言葉を嫌った。漢学を分けて漢学と言うなら分かるが、自らの国のことはただ学問と言うべきだ、と書いている。とうぜん我が国の古典を明らかにする、我が国の学者の心構えを、特に「やまと魂」と呼ぶには当たらないのである。
彼の歌論に、「姿は似せがたく、意は似せやすし」というものがある。諸君は驚くだろう。なぜなら、普通は逆で意は似せ難く、姿は似せやすいと思い込んでいるからだ。意味を理解するのは必ずしも容易ではないが、意味も分からず口真似するなら子供にもできるではないかと言いたいだろう。言葉とは、ある意味を伝える不調にすぎないという俗見は、根強い。しかし、よく考えて見よ、例えばある歌が麗しいとは、歌の姿が麗しいと感じることで、その麗しい姿を言葉が作り上げている。人生の生々しい味わいは、美しいとは限らないが、弁舌とは反対に寡黙や沈黙に人を誘う。漢学は言が良く言葉巧みだが、それにたじろぐ必要はない。宣長はそれを「やまと魂」が固まりさえすれば、と言う。「やまと魂」という言葉を、彼も「才」に対して使っているのである。
「本居宣長」-26章(2022/3/24)
真淵は宣長に「工夫がましき事を憎む故に、文の事に入りぬ」と宣長に書き送ったが、この教えはしっかり宣長に受け継がれた。この文の事とは、古意を知るためにまず古言を知るということで、「古の大義」というようなものではなく、言葉の「姿」と切り離せないものだった。しかし人の批評はどうしても、似せ難い姿よりも、似せ易い意を手がかりに起こってくる。真淵の「ますらをぶり」を取り上げ、宣長の「やまと魂」という言葉を取り上げるのはそのような理解であって、篤胤はつまりそういう簡単な論じ方をしているのである。
春満、真淵、宣長、篤胤を国学の四大人と呼ぶのは篤胤の門下に始まる。篤胤の古道は、宣長の「直毘霊」の祖述から始まったが、「霊の真柱」で独特の神道を説くに至った。宣長は、我が国の神典の最大の特色は、天地の理などはもちろんの事、生死の安心もまるで説かないというところにあると考えていた。それは教学として筋の通せるようなものではなかったが、そのような道なき道を捉えた「直毘霊」の非凡な着想に、篤胤は深く心を動かされた。そして新しい発想をそこから広げ、天地の初発から人魂の行方に至るまで、古道に照らして誰でも納得がいくように説かねばならぬと考えた。宣長の門下であった堤朝風という人が、「霊の真柱」の序を書いているが、その中でこれは「しきしまの大和心を固むるふみ」と言っている。宣長の「やまと魂を固める」という言葉とは、言わば逆の向きに使われているのだ。「直毘霊」には「やまと心」という言葉すら出てこない。
宣長も真淵も「文事」の限りをつくした人で、そこで「やまと魂」という言葉は捉えられた。真淵の言う「調」と、宣長の言う「姿」とは恐らく文事において重なり合っていたのだが、篤胤の仕事ではこの文事の経験というものが全く脱落している。だから、「やまと魂」の古意が「雄武を旨とする心」と分かれば、「源氏」の如き文弱の書はどうでもよいということになるのである。
篤胤は言う。「とかく道を説き、道を学ぶ者は、人の信ずる信ぜぬに、少しも心を残さず、一人も信じていないとしても、独立独行、一人で操を立て、一人で真の道を学ぶ、これを漢言で言えば真の豪傑とも、英雄とも言い、また大倭魂とも言うのである」。このように、わかりやすく説教して勉学を求めないところが、多数の人を惹きつけて、篤胤神道は一世を風靡した。そして、「やまと魂」という言葉はその標語のような働きをしたのである。標語として働くためには、古言はその「意」だけを残して、その「姿」を失わなければならなかった。
宣長は契沖を「やまとだましひなる人」と呼んだが、これは「ますらをの心なる人」という意味ではない。「古今集に、病して心弱くなる時に業平の読む、つひにゆく 道とはかねて 聞しかど きのふけふとは 思はざりしを。契沖は、これこそ人の真の心にて教えにも良い歌である。後世の人は死の際にことごとしい歌や、道を悟ったような歌を詠むが、真実味がない。業平の一生の誠実さがこの歌に現れ、後世の人は一生の偽りを現して死んでいくのだと言ったが、契沖法師は法師でありながら、やまとだましひなる人とはこのような人を言うのだ。契沖法師は世の人に真を教え、神道者、歌学者などは偽りを教えている」。
「本居宣長」-27章(2022/3/24 今回は二章読みました)
契沖は「史伝に和歌を善く作ると言われる人物は業平一人」とか、「土佐日記はわずか一巻の中に三か所も業平を引き、紀貫之に慕われていたことが分かる。貫之に慕われるというのは、天下の歌人に慕われるということだ」と言っている。この史伝は「三代実録」だが、歌の上手は無学なのが当たり前という風に「善作和歌」という言葉と並べて「略無才学」と述べている。嵯峨天皇の頃より漢学が重視され、才学は勅撰漢詩集で知られるような時代となっていた。「万葉集」は序文を必要としなかったが、続万葉集としての古今集は「やまと歌」の本質や価値や歴史を改めて説く序文を必要としたのである。説き終わり、勅撰を祝い、貫之は「人麻呂なくなりにたれど、歌の事とどまれるかな」と言ったのだった。
「古今」の歌風を代表するのは、六歌仙と言われる人達の歌であり、六歌仙の先頭に立つのは業平だ。契沖が激賞した業平の代表作を分かり切った名歌と言わず、もう一度読んでみよう。―「つひに行く 道とはかねて 聞きしかど 昨日けふとは 思はざりしを」―叙事でも叙情でもない、反省と批評から歌が生まれていること、「古今」のその骨格が透けて見えてこないだろうか。
このような作歌の過程に、反省や批評が入りこんでくる傾向を、貫之は「心余る」という言い方で言った。「月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ わが身ひとつは もとの身にして」も業平の有名な歌だが、貫之はこれを上げて「在原業平は、その心余りて、言葉足らず、しぼめる花の色なくて、匂い残れるがごとし」と言った。この歌の評には、契沖も宣長もこの貫之の評を引いている。ところで、この「月やあらぬ」の歌は、「古今」で読むより「伊勢」で読んだ方がいいように思う。歌集に入れられると、いかにも「言葉足らず」という姿に見えるのだが、「伊勢」のうちで同じ歌に出会うとそうは感じないのが面白い。この微妙な歌物語の手法が「源氏」で大きく完成するのである。読者の同感が得られるだろうか。得られるならそういう心の用い方でまた、「つひに行く」の歌を見てもらうとどうだろう。「心余りて」というように見えないだろうか。作者が歌っているというよりむしろ物語っている、と感じるのではないか。
宣長が「物のあはれ」を論じて、歌学を根底からやり直そうとした時、まずそのきっかけを「古今」の「仮名序」に求めた事は、すでに書いた。「やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなりける」と貫之は言ったが、歌の種になる心とは、物のあはれを知るという働きでなければならないと宣長は考えた。そして宣長は「物のあはれ」という言葉を「土佐日記」から拾い上げたのである。
周知のように「土佐日記」は、女が書いたという体裁になっている。「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとしてすなり」という書き出しは有名で、当時男の日記はすべて漢文で書かれていたから、そう断らなければならなかったと解されているが、本意は分からない。第一女らしい文体とも言いかねるし、女だから唐詩は書けないと断っている程度なのだ。やはり貫之の関心の集中したところは、新しい形式の和文を書いてみるという点にあったのではないか。
彼が「古今集」の「仮名序」を書いたのは、これより三十年ほど前だった。序と呼ばれる漢文の文体を和文に仕立て上げるというこの仕事は、全く先例のない仕事で、よほどの困難が伴ったはずだ。慣例に従って漢文で書けば何の造作もないことだったはずで、貫之にとって和文は、和歌に劣らぬ、ある意味では一層難しい興味ある問題として常日頃意識されていたのだろう。
和歌と和文の問題といっても、今日の言葉で言えば詩と散文の問題だというさっぱりした話にはならない。日本の文学が誕生以来背負ってきた宿命的な荷物が漢文なのだ。私たちが持っている最高の詩集「万葉」にしても、詩の表記には万葉仮名が用いられながら、題詞や注の散文は感じで書かれているのである。当時の歌人たちがこのような二重性にどのような言語感覚で処していたのかは明らかでないが、詩の表現の上であれほどの高みに達していた彼らが、日本語による散文という問題に全く無意識であったとは思えない。
「続日本紀」の選者は、「和歌の体」が失われ、「古語」を「野」に求めねばならない時勢を嘆いたが、時勢はまたそれで、「和文の体」の成立を準備してもいた。だから「土佐日記」の有名な書き出しはその意識につながる。「女もしてみむとてすなる」この日記は、「男もすなる日記といふもの」つまり、漢文体で書かれた散文に対抗して書かれたのではないのだ。対抗するものがあればそれはむしろ、和歌の体であった。和歌では現すことができない、固有な表現力を持った和文の体が目指されていたのである。
歌は必ずしも文字を必要としないが、文字がなくて、文はない。歌の力は言葉が音声の力を借りて調べを作るところにあるが、黙読を要求している文章に固有な魅力を言ってみるならそれは、音声の拘束から解放された言葉の身軽さにあるだろう。これは言葉が、己に還り、己を知る動きだとも言える。貫之が和文制作の実験に自分の日記を選んだのは、方法を誤らなかった。何の奇もないが、自分には親しい日常の経験を、ただ伝えるのではなく統一ある文章に仕立て上げてみるということが、平凡な経験の奥行きの深さをしっかり捉えることに繋がっている。
「源氏」が成ったのも、詰まるところはこの同じ方法の応用によったというところが、宣長を驚かせたのだ。宣長は「古今」の集成をわが国の文学史における、自覚とか、反省とか、批評とか呼んでいい精神傾向の開始と受け取った。その一番目立った現れを、和歌から和文への移り行きに見た。この受け取り方の正しさを保証するものとして、宣長は「源氏」を読んだ。それが「古今」の「手弱女ぶり」という真淵の考えに宣長が従わなかった最大の理由だ。「やまと歌は、人の心を種として」と貫之は言ったが、から歌と比較してのやまと歌という言葉は「万葉」時代からあった。やまと歌の種になる心が、自らを省み、「やまと心」「やまと魂」という言葉を思いつかねばならないという事が「古今」時代からのことなのである。そうなるには、から歌は、作者の身分や学識を現すかも知れないが、人の心を種としてはいないという批評がまずなければならない。
「本居宣長」-28章(2022/4/22)
宣長は、「源氏」の本質を「源氏」の原文のうちにじかに掴んだが、その素早い端的な掴み方は、「古事記」の場合でも、全く同じだった。
大事なのは、原文の「文体(カキザマ)」にある。「文体(カキザマ)」の一番簡単な形として、「古事記」「日本書紀」という「題号(ナ)」が並んでいるだけで、その姿の違いが見えるという。「古事記」は文字通りで素直に受け取れる名前だが、「日本書紀」は余計な意識を働かせた名だ。国号の別など無いのに何故わざわざ日本などとつけて、何に対する名なのか、という。
明らかにここから感じられるが、宣長には健全なものは、何の奇もない当たり前のものだ。それが、大事な判断になるとキッと顔を見せるのである。
「古事記」と「日本書紀」では、選録上の意図がまるで異なる。宣長は、これを詳しく、確かに語った最初の学者である。「古事記」はただ古の事を伝えた古の言葉を失わないことを旨としたものだが、「日本書紀」となると、この「古事記」のやり方が、「あまりに飾りなくて、かの漢の国史などに比べれば浅く聞こえる」という見地に立ったものだ。そこで、「更に広く事柄を加え考え、年紀を立てなどし」たところは良いが、正史としての体裁を整えるのに熱中したために、わが国の古伝古意を漢文体で表す無理には気づかなかった。その「日本書紀」が「表に立て」られ、「古事記」が「裏になりて私物の如く」扱われた理由が、体裁の良し悪しにあったとは哀しいことである。「もし漢にへつらう心がなければ、それに似ずとて何事かあらん」。
「古事記伝」という画期的な仕事は、非常に確実な研究だったので、本文の批評や訓読だけでなく、総論的に述べられた見解も、今日の学問の進歩をもってしても、ほとんど変わっていないようだ。しかし、それはそれとして、そのような学問を残した宣長の心の喜びや嘆きの大きなうねりが分からないでは、宣長の言う「学問の本意」が分かったとは言えないだろう。宣長の眼は静かで冴えていたが、傍観者の眼ではない。宣長は「古事記」の内にいて、これと合体していた。
宣長はこう言っている。「記の本を起こし賜いし天武天皇の元年は申の年なりしに、その選録された元明天皇の和同元年も申の年なり、恐れ多いことだが、私宣長がこの古事記伝著し始めた今の明和元年もまた申の年に当たる」と。これは「古事記伝」の注釈にあるのだが、注を書きながら浮かんできた実感をそのまま記したのだろう。「密かに奇しく(不思議に)思う」と書く実感、まず天武天皇の志がしっかりと信じられなければ自分の仕事は無かったという思いだったと言ってもいいだろう。
さて、宣長の言う「文体(カキザマ)」だが、序と本文でまるで違うところから、序は安麻呂のではなく後代の作とする人もある。名は挙げていないが、宣長にそう書き送ったのは真淵だった。だが、宣長は序とはいえ元明天皇への上奏文だったための形式で、それを差し引いて考えたらよいという。それよりも、その当時の常識にそって飾って書かれた「序」が、本文は常識を破ったものだと書いている所が大事だと述べている。「序」を引いておこう。
(梅原猛訳 古事記序文を載せます)
天皇は「私の聞くところによると、『多くの氏族たちが昔から伝えてきた帝紀や本辞は、すでに真実と違って、虚偽を多く加えています』ということだから、今のときにその誤りを改めておかないと、幾年も経たないうちに、その本当のことがわからなくなってしまう。これは、国家の組織の根本となるもので、天皇の徳化の基礎をなすものである。だから、帝紀を撰び記し、旧辞をよく調べて判断し、偽りを除き、真実を定めて、後世に伝えよう」とおっしゃいました。時に舎人があり、姓を稗田、名を阿礼と申しました。年はちょうど二十八歳。生まれつき賢くて、目で文章を見れば口で誦むことができ、耳で言葉を聞けば心にきちんと記憶しておりました。そこで天皇は、阿礼に自らお言葉を賜って、天皇日継および先代旧辞を繰り返し誦み習わせになりました。しかしながら、天皇が亡くなられて、御世が変って、この仕事はその後行われませんでした。
時移り今上天皇(元明天皇)の時代になり、旧辞の誤り違っている事、先紀の誤り乱れている事を直そうとし、和銅四年九月十八日に、臣安麻呂にお命じになり、「天武天皇が自らお命じになった、稗田阿礼の誦む旧辞を撰び録し、献上せよ」と仰いましたので、仰せのままに事細かに採録いたしました。
という次第である。
宣長はこれに、わざわざ「ここの文の様を思うに、阿礼はこの時存命だったと思われる」と注を付けている。文中に明記されてはいないが、序の内容から明白な事を改めて書くまでもなかっただろう。であれば、特に書かなくてもいいようだが、さらに阿礼が存命だったとすれば、この和銅四年には何歳であったかと詮議している。序文ではちょうど二十八歳と書かれていて、天武の何年の事だか分からないからはっきりしたことは言えないのだが、天武の頃に実現を見ずに終わったことからして、御世の末の方と考えるとすると、天皇崩御の時に二十八歳だと考えれば、和銅四年には五十三歳になる、云々。ここに尋常でないこだわりが表れていて、それは「序」を読む宣長の波立つ心と繋がっている。安麻呂が「古事記」を撰ぶにために篤かったのは、生身の人間の言葉であって、文献ではないと安麻呂が語るのを聞き、宣長は言っている。「御世が変わった後、そのお志を継ぐ御業がなければ、それほどに貴い古語も阿礼の命ともろ共に果てて無くなってしまうところだったものが、なんと喜ばしいことか」、だからわざわざ年は二十八歳であるなどと特に断ったのだと宣長は考えたと私は思っている。
ここまで述べたように宣長は「序」の語るところをそのまま信じ、「古事記」の特色は、一切がまず阿礼の誦み習いという仕事にかかっている、そこにあったと真っ直ぐに考える。旧事を記したどんな旧記が用いられたのかと問うよりも、なぜ文中に「旧事」とはなくて、「旧辞」とあるかに注意せよと言う。「辞の字に眼をつけて、天皇の思われる大御意は、もっぱら古語にあることを悟るべし」。
そして、元明天皇が引き継がれたところの文では、「稗田阿礼が誦む所の直後の旧辞を選録して・・」となっていて、元の帝紀という言葉を省いて旧辞という言葉のみを残している。これは、「旧記(ふるきふみ)の本(まき)を離れて」、阿礼という「人の口に移」された旧辞が古事記の素材であると安麻呂は考えているのだとするのだ。それは、「もっぱら古語を伝える事を趣旨とした書であれば、もとの語のままに、一文字も違えず仮名書きにすべき」ものだったが、まだ安麻呂はカナを知らなかったのである。
わが国の歴史は、国語の内部から文字が生まれて来るのを待ってはくれず、帰化人に託して外部から漢字をもたらした。それは歴史から見れば、日本語を漢字で書くというできない相談が持ち込まれたのだということになるが、そのような反省は後のことで、まずは初めて見る文字に驚き、何はともあれ使ってみただろう。そして漢字の働きが明らかになるにつれて、国語と国字は固有であるということが切実になってきたと考えてよい。安麻呂がはっきりと語っているのはそういうことだ。
(梅原猛訳 古事記序文)
しかし古い時代の言葉も意味も飾り気がなくて、漢文のように言葉を飾り対句を使って書き表すことは、たいへん難しいのです。全部訓字で書き表すと、そのきらびやかな言葉は、簡素な日本の意味を書き表すことができません。また逆に、まったく音字だけで書きますと、文章がたいへん長くなってしまいます。だから今は、一句の中に音読みと訓読みを交えて用いたり、またあるいは一つの事柄を記すのに、訓字まじりで記すこともございます。そして、言葉の意味のわかりにくいのは注で明らかにして、わかりやすのはことさらに注をしませんでした。
宣長の注には、「この文を見れば阿礼が誦める語のとても古いことが知られて貴い」とあり、「言のみならず、意も朴なりとあるをよく思うべし」と言う。ただ、漢文の表現力に対して卑下して言ったのではない。そう言う他ない味わいがあるということであって、私達は知らぬ間に国語を用い、それに準じて思考や感情の動きを整えていた。そのことを宣長は「貴し」と注したのだ。
それで表記に苦労したのだが、音訓を併用した所以外は訓で記録されているのは何故か。
「字のままに読めば、語は違っても意は違わないこと、皆が知っている古語で読み誤ることも少ないだろうということと、カナ書きは長いので、簡約な方を用いた」。表記法の基礎となるのは漢字の和訓(山を書いてやまと読み、川と書いてかわと読ませる)であるというのが、古事記の本文で用いられた考えである。「古事記」中には、多数の歌が出てくるが、その表記は一字一音のカナ書きで統一されている。阿礼の誦んだところは、物語であって歌ではなかった。宣長なら「源氏」のように、と言ったであろう。安麻呂の表記法を決定したものは、与えられた古語の散文性であったと言っていい。
宣長は「古事記」を考えるうえで、稗田阿礼の「誦習(よみならい)」を、非常に大切な事と見た。「もし語に関わらずして、ただ理のみ旨とするのなら、記録を作る時にまず人の口に誦習わせることは無用ではないか」と彼は強い言葉で言う。宣長は稗田阿礼がアメノウズメノミコトの後である事に注意しているが、篤胤のように「女舎人(ひめとね)」とは考えなかった。柳田國男氏は「阿礼」は「有れ」であり、「御生(みあ)れ」即ち神の出現の意味だ、これは神懸かりの巫女を指していると言う。折口信夫氏は「古事記」を「口承文芸の基本」と呼んでいる。この素直な考えは、わが国の文学の始まりを考える上で祝詞と宣命が目安になるという宣長の考えと繋がっている。
あるまとまった言葉が、社会の一部の人々の間にでも、保持されていくためには、その言葉にそれだけの価値、いわば威力が備わっていなければならない。毎年の祭りに唱えられる一定の祝詞を、失わぬよう、乱さぬよう、口から口へ熱意をもって守り伝えるところに、村々の生活秩序の要があり、政治の中心があった。何時からあったかは誰も知らないが、村の初めは、世の初めであったろうし、世の初めは天から神々が下って来て言葉が下され、これに応じて神々に申し上げる言葉が唱えられるところにしかなかっただろう。折口氏の詳しい説があるが、ここでは略し、神から下される詞が祝詞であり、神に申し上げる詞が宣命だと言っておけば足りる。
宣長の祝詞の研究は真淵の仕事を受けて整備・発展させたが、宣命の研究は宣長に始まっている。宣長が宣命に着目したのは大変早く、古事記伝の仕事の準備中に真淵に質疑を書き送っている。「万葉」では歌の口調にはばまれ、「記紀」では漢文のふりに制されて、現れにくかった助辞(てにをは)が、祝詞・宣命にははっきり表れているという宣長の発見は、真淵を驚かせた。
宣長はこの国語の独特の基本的構造を「いともあやしき言霊のさだまり」と呼んだ。これにより国語はわれわれの間を結び、「いきほひ」を得、「はたらき」を得て生きるのである。「古事記伝」の「訓法(ヨミザマ)の事」の中には、本文中にある助辞の種類がことごとく挙げられ、詳しく説かれているが、漢文風の文体(カキザマ)のうちに埋没した助辞をどう訓むかは古事の世界に入る鍵だった。この「あやしき言霊のさだまり」が文字を知らぬ上代の人々の口頭によってのみ伝えられた事への宣長の関心は深い。祝詞・宣命を研究した宣長の名著「歴朝詔詞解」から引こう。
「そもそもこれらを漢文に記さず、元の語のままに記したのは、歌は言うまでもないが、祝詞も神に申し、宣命も百官天下の公民に宣聞(のりきか)しめるものであるから、神または人の聞いて心に感じるべく、その詞に文(あや)をなして麗しく作られるものであり、一文字も読み違えてはならない故に、通常の事のように漢文様には書き難かったのである」
文字を知らない昔の人々が、唱え言葉や語り言葉の内に、どのような情操を長い時間をかけて、細心に育んて来たか。そういう事について、文字に馴れきってしまった教養人たちは、どうしてこうも鈍感に無関心なのだろうか。宣長はこの感情を隠しきっていないのである。
「本居宣長」-29章(2022/5/26)
「神代史の新しい研究」に始まった、津田左右吉氏の「記紀」研究は、今までにない徹底したいわゆる科学的批判が行われたという事で名高いものだ。
「記紀」は、六世紀前後の大和朝廷が、皇室の日本統治を正当化するために書かれたもので日本民族の歴史というようなものではないという結論を導いている。
津田氏は、「宣長が古事記伝を書いてから、古事記の由来について、一種の偏見がある」と言っている。この偏見が宣長のどの考えを言っているかというと、「古事記」は、阿礼の「誦習(よみならい)」つまり、阿礼が漢文で書かれた古書を国語に読み直して、書物を離れてこれを暗唱したところに成り立ったとする考えだ。
宣長は阿礼を、大変な記憶力を持った人物と受け取っているようだが、「生まれつき賢くて、目で文章を見れば口で誦むことができ、耳で言葉を聞けば心にきちんと記憶しておりました。」とは、普通に博覧強記の学者と解すればいいわけで、特に暗唱に長じた人と取る必要はない。その気で読んでいるから、序に使われている「辞」という言葉も、耳に聞く言葉という意味に読むので、普通に読めば帝紀と本辞旧辞という風に対照して使われているのだから、目に見える文字に写された物語と呼んでいいはずだ。阿礼は古い記録を手掛けて「古事記」を仕上げたが、その記録の多くは「古事記」の書きざまと大差ないものだったろう。漢字で国語を写すという無理が、それぞれ勝手な工夫で行われて来たのだろうから、古い記録は当時すでに難解になっていたに違いない。そこで阿礼という聡明な学者がやったのは、宣長が「古事記」を訓んだのと同じ性質のものだったわけで、誦むは訓む、誦習は解読の意と解するのが正しい。阿礼の口誦を信じた宣長は、上代には書物以外にも伝誦されていた物語があったように考えているらしいが、そのような形跡はいささかも文献の上に認められないし、便利な漢字を用いて記録として世に伝えられているのに、何を苦しんで口うつしの伝誦んどする必要があるだろうか。要するに宣長の誤解は「古事記」に現れた国語表現というものを、重く考えすぎただけのことだというのである。
一方、「古事記伝」という宣長の学問の成績については無視できず、感嘆のほかないと言っている。すると宣長の学問は、偏見から出発しなければ、それほどの成績のあがらないものであったということか。問う人の問い方に応じて、平気で、いろいろに答えるところに歴史というものの本質的な難解性があるのか、歴史学から見ると宣長の古学が偏見から出発している姿に見えるというところに、歴史の奥行とでも言うべきものが感じられて面白い。
宣長が「古事記」の研究を、「これぞ大御国の学問(モノマナビ)の本なりける」とかいているのを読んで、彼の激しい喜びが感じられないようでは仕方がないだろう。宣長は吟味すべき資料、何かを証する文献ではなかった。津田氏の指摘する「辞」という言葉も、定義が求められたわけではなく、耳を澄まし、しっかり聞こうとする宣長の期待に「古事記」の文が応じたということだ。阿礼が「古事記」を書くに当たり読み習ったのは「帝紀及び本辞」であったと「古事記」の序はいう。津田氏は「書紀」の天武紀に川嶋皇子に「帝紀及び上古諸事を記すよう命ず」とあるのを引き、「本辞」とは「上古諸事」すなわち旧事の記録の意味と解する。宣長はこれが逆になり、同じ川嶋皇子への勅から、「古事記」の場合「旧事と言わず、本辞旧辞と言う」のは、古語や口誦との関係を思っての事と解する。
津田氏の考えは「辞」の字義の分析の上に立つ理詰めのものだ。宣長の考えは、読者として古事記を信じて向かい合う立場から離れない。古書は普通漢文で書かれているというのは、改めて言うまでもない分かり切ったkとおだと誰もが考えている。読み書きを覚えるということは、漢文の書籍に習熟するよりほかになかったという言語生活上のどうにもならない条件に深く思いを致すものがない。それが、宣長が切り開いた考えだ。この考えに彼を導いたのは、「古事記」というただ一つの書だった。
「奈良の御代のころに至るまでも、万葉などの歌の集(フミ)すら、端の言葉はみな漢文なるを見ても知るべし」という。宣長の言い方を引けば「かならず詞を文(アヤ)なさずても有るべきかぎりは、みな漢文にぞ書きける」となる。この宣長の考えははっきりしたもので、仮名によって古語のままに書くという国語の表記法は、詞の文(アヤ)を重んずる韻文にだけ発達したと見た。ここで「詞の文(アヤ)」というのは、文字を知らなかった日本人が育て上げた国語の音声上の発音を言い、漢訳が利かない。固有名詞はこの文(アヤ)の価値が極端になった場合とみてよかろう。国語はまず歌から生まれたというのが宣長の考えだった。
漢字を迎えた日本人が漢字に備わった強い表意性にまず動かされたことは考えられるが、表音性に関しては極めて効率の悪い感じを借りて、詞の文(アヤ)を写そうと自然に考えたとは思えない。不便を忍んでも何とか写したいという欲求から生まれるので、歌うだけでは不足で、歌集が編みたくなる、そういう時期に表記の工夫は一応整備されるが、それでも同じ歌集の中でまるで抗するかのように、可能な所は詞の文(アヤ)を成さないところでも、漢文で書かれている異様さに着目すべきだと宣長は言いたいのだ。
「大御国にもと文字は無く、上代の古事も直に人の口に言い伝え、耳に聞き伝わるものを、やや後に外国より書籍というものが渡ってきて、それを日本の言葉で読み、その文字を用い、その書籍の言葉を借りて日本の事も書き記すことになった」。わざわざこのようなことを古事記伝に書いているのも、この悪戦苦闘と言っていい経験を私たち現代人はほとんど失ってしまっているからだし、これを想い描くということが、宣長にとっては「古事記伝」を書くというその事だった。宣長は上代人のこの言語経験が、上代文化の本質を成し、その最も豊かな産物が「古事記」であると見ていた。その複雑な「文体(カキザマ)」を分析して、その「訓法(ヨミザマ)」を判定する仕事は、上代人の努力の内部に入り、上代文化に直に参加することに他ならないと考えていたのである。
この努力の出発点は上の引用にあるように、「書籍というもの」を「日本の言葉で」読み習うというところにあった。漢字漢文を訓読によって受け止めて、ついにこれを自国語のうちに消化してしまうという鋭敏で執拗な知識は、恐らく漢語に関して日本人独自のものである。
例えば上代朝鮮人も、自国の文字も知らず、格段の文化的背景を持つ漢語を受け取ったが、その自国語への適用は成功せず、棒読みに音読される漢語によって教養の中心部は制圧されてしまった。ハングルの発明もずっと後の事だし、日本の仮名のように、漢字から直接生み出されたものではない。和訓の発明とは、一字で一語を表す感じが、形として視覚に訴える性質を素早く掴まえて、同じ意味合いの日本語を連結することだった。だから漢字は日本で文字としての本来の性質を変えてしまう。形は保存しながら実質的には日本文字と化したのである。
「古事記伝」から引いてみよう。「皇天とある字を、アメノカミと訓むのは、古意には必ず天神とあるのを考えれば、この訓はよい。だが、それを以て皇天=天神だと考えてはいけない。書紀を見るにはつねのこの違いをよく思う必要がある。そうしないと漢意につかまってしまう」。
漢語の言霊は、一つ一つの精緻な字形のうちに宿り、蓄積された豊かな文化の意味を語っていた。日本人は自国語のシンタックスを捨てられぬままに、訓読という独特な書物の読み方が生まれた。書物が訓読されるということは、尋常な意味合いでは音読も黙読もされなかったという意味だ。原文の持つ音声など初めから問題ではなかった。眼前の漢字漢文の形を目で追うことが、その邦訳語邦訳文をそこに思い描くことになる、そういう読み方をしたのだ。これは、まとまな外国語の学習法ではない。この変則的な仕事を許したのは漢字独特の性格だったが、何の必要があってそんな作業をしたのかを思うと、彼我の文明水準の大きな差を思わざるを得ない。
優れた文物の輸入という実際的な目的に従って漢文も受け取られたに相違なく、漢文によって何が伝達されたのか、その内容を理解して応用の利く知識として吸収しなければならぬ。その為に、宣長が言ったように「書籍というもの」を「日本の言葉で」読み習う事が近道だったというわけだ。意識的に選んだというより、圧倒的な漢字に屈従した、豊富な語彙がそっくりそのまま流れ込んで来るに任せたという事だっただろう。そしてそれを整理して理解するという努力が我が国上代の教養人というものを仕立て上げ、その教養の質を決めた。これが、日本の文明は漢文明の模倣で始まったと誰もが口先だけで言っている言葉の中身を成すものだった。
知識人たちは自国の曖昧な口頭言語から思い切りよく離脱して、漢字漢文の模倣に走った。そして模倣の上で自在を得て、漢文の文体(カキザマ)にも熟達し、正式な文章と言えば漢文の事と誰もが思うようになる。そこまでやってみて、知識人の反省的意識に初めて自国語の姿がはっきり映るということが起こったのだろう。知識人は自国の口頭言語の伝統から意識して一応離れてみたのだが、伝統の方で彼を離さなかったというわけである。しかし、日本語を書くのに漢字を使ってみたのだと簡単に言えることではない。漢字は日本語を書くために作られた文字ではない。口誦のうちに生きていた古語が漢字で書かれると変質して死んでしまうという苦しい意識が目覚める。どうしたらよいか。
この日本語に関する、日本人の最初の反省が「古事記」を書かせた。日本の歴史は、外国文明の模倣によって始まったのではない。模倣の意味を問い、その答えを見つけたところに始まった。「古事記」はそれを証明している、宣長はそう見ていた。したがって、序で語られる天武天皇の意図は「古語」の問題にあった。「古語」が失われれば、それと一緒に「古の真のありさま」も失われるという問題にあった。宣長はそう見て取った。彼の見解は正しいのだ。ただ、正しいと言い切るのを現代人は躊躇うだけだろう。「ふるごと」とは「古事」でもあるし、「古言」でもあるという宣長の真っ正直な考えが子供じみて見えるのも、事実を重んじ、言語を軽んずる現代風の通念から眺めるからである。だが、この通念が養われたのも、慎重に育まれた現代語の力を信用すればこそだ、と気づいている人は極めて少ない。
「本居宣長」-30章(2022/6/28)
天武天皇の修史の動機は、実際問題に即したものだった。すなわち、諸家に伝えられた書き伝えが正実に違うものになっているので、正しいものを後世に残さねばならないということであった。この見方は日本書紀と同じであるが、この書き伝えの誤りが何によって起こったか、どのように改めるかという事に関して「古事記」選録の場合更に特別な考えが加わっている。それは、上代の日本国民が強いられた言語経験に基づいていた。宣長に言わせれば「その上代の習いとして、万の事を漢文に書き伝えるということは、そのたびに、漢文に引かれて元の語とはだんだん違っていってしまうために、後にはついに古語は失われてしまうと思われて哀しまれたのだ」という事だった。
もちろん、「古事記」選録に関する詳しい事情が後の研究で何かはっきりしたということは特にない。ただ、壬申の乱を収束して新国家の構想を打ち出さなければならなかった天武天皇には、修史の仕事は、新憲法制定のように緊急であった事は間違いではないだろう。
上代の社会組織の単位を成していたのは、氏族であった。大化の改新は、改新であって革命ではなかった。唐風の政治技術を学び、皇室や豪族の個別的支配権を否定し、公地公民制に基づく律令国家の統治体制を整えたが、古くから続いて来た社会秩序の基礎構造に変動があったわけではない。天皇家と氏族という古い風俗習慣に溶け込んだ伝統的思想だった。そして皇室の神聖な系譜と諸家の出自の物語を改めて制定し、国民の側に受け入れられたとしたら、物語の経緯が大体自分たちに親しい伝承の上に立つものだったからだろう。それであれば宣長の直感の通り、古い言い伝えが人々の生活のうちに生きていたことを認めざるを得ない。
漢字の渡来以来、日本人は、言い伝えと書き伝えの間に、訓読という橋を渡して往来してきたが、その成果と言える和漢混交文という文体がしっかり現れるのは、「平家物語」まで待たねばならない。それまでの間、そしてもちろん「記紀」の時代にはそんなことは思いもよらず、外国語の特殊な学習法である訓読を研鑽するのに多忙だった。これにかまけていたから、訓読という橋を渡って気づく、言語構造を隔てる断絶という裏面の経験は意識に上らない。だが、一旦意識されると自国の言葉の伝統の姿が鋭く目覚めることになり、これが「古事記」着想の中核になったのだ。この新しい自覚が古くからの言伝えと出会い、これと共鳴するということがなければ「古事記」の選録はなかた。そしてこのような事件はその後、もう二度と起こりはしなかったのである。
「然るに上古の時、言意並に朴にして、文を敷き句を構うること、字に於て即ち難し」という彼の言葉は複雑な文化意識を汲んだ告白だった。ところがこの告白は、純粋な漢文で書かれたのである。この事は彼の仕事が一つの実験であったことを明らかに語る。この実験は、言ってみれば傑作の持つ孤立性のようなものがあり、そういう所に宣長の心が惹きつけられていたのを、「記紀」の「書紀の論ひ」を見ながら感じるのである。
「古事記伝」で説かれている訓法は、今日の研究者から見ても、限られた資料しかない宣長とそう多く正しいことが分かるというものではない。漢文の訓読などというものは、今日でも不安定なもので、当時どのように訓読されていたか、直接明かすような資料がなければ正確には分からない。だからそれは、一種の冒険ということになるのだが、そのことを恐らく宣長はよく知っていた。
宣長が「古言のふり」とか「古言の調(シラベ)」と呼んだのは、資料をすべて集めれば見えるというよりも、内証が熟したと言うの方が適切かもしれない。「古言」は発見されたかもしれないが、「古言のふり」は発明されたのだ。だから、訓法の一番難しい微妙な所では、いつも断案が下されている。まず文の「調」とか「勢」とか「さま」とか呼ばれる全体的なものの直知があり、そこから部分的なものへの働きが表れる。だから、「云々とのみ読んでは、何とかやことたらはぬここちすれば」ということになる。
一例を引くと倭建命の物語がよいだろうか。征西を終え京に帰ってきた倭建命は、また上命により休む間もなく東伐に立たねばならない。伊勢神宮に参り、倭比賣命に会って心中を打ち明ける話で、宣長が所懐を述べている有名な箇所は、多くの研究者達に縷々引用されている。
宣長はその個所をこのように読んだ。
「天皇既(はや)く吾(あ)れを死ねとや思ほすらむ、何(いか)なれか西の方の悪人等(まつろはぬひとども)を撃(と)りに遣(つか)はして、返り参上(まいのぼ)り来(こ)し間(ほど)、行く時も経(あ)らねば、軍衆(いくさびと)どもをも賜はずて、今更に東の方の十二道の悪人等(まつろはぬひとども)を平(ことむ)けには遣(つか)はすらむ、此れに因りて思惟(おも)へば、猶吾(あ)れはやく死ねと思(おも)ほし看(め)すなりけりとまをして、患ひ泣きて罷ります時に、倭比賣の命、草薙剣を賜ひ」云々。
「既所以思吾死乎は、ハヤクアレヲシネトヤオモホスラムと訓べし。所以を、ユエと訓みては語穏やかならず、オモホスと云うには、字あまりたれども、下に所思看(オモホシメス)とあると、相照らして思うに、ここも必ず然あるべきところなり。既クは、ここはいかで早速(ト)くと願う意味の波夜久(ハヤク)にて、死(シネ)と云にかかれり、下に吾既(アレハヤ)ク死(シネ)とあるにて心得るべし。」
「所思看は、オモホシメスナリケリ訓べし。下に、ナリケリということを添うるは、思い決めて嘆き賜える辞なり。上に、既く吾を死ねとや所思(オモホ)すらむとあるは、まづ大方にうち思い賜えるさまを詔へる所なる故に、夜(ヤ)と言い良牟(ラム)と言いて、決(サダ)めぬ辞なり、さて事のさまに因(ヨ)りて、よく思いめぐらし見るに、左右(カニカク)に早く死ねと所思(オモホ)すに疑いなしと、終(ツヒ)に思い定め給える趣きの御言なり、よくよく文(コトバ)のさまを味いてさとるべし」
ここで明らかなように、訓は、倭建命の心中を思いはかるところから、定まってくる。「いといと悲哀しとも悲哀き」と思っていると、「なりけり」と訓み添えねばならぬという内心の声が聞こえてくるらしい。証拠はと問われれば、他で例があるが、阿礼の語る所を安麻呂が聞き落としたに違いないと答えるだろう。これでは証拠は要らぬということになりかねないが、ここで繰り返すのが、まず「阿礼が語」を「漢(カラ)のふりのまじらぬ、清らかなる古語」と定めて、という意味だ。今日では謎めいた符合に見えようとも、その背後には古人の「心ばへ」であると言っていい古言の「ふり」がある。
凡庸な歴史家たちは、外から与えられた証言やら証拠やらの権威から、なかなか自由になれないものだ。証言証拠のただ受身な整理が、歴史研究の風を装っているのは、ごく普通のことだ。宣長は、心のうちに何も余計なものを貯えているわけではないので、その心はひたすら観察し、批判しようとする働きで充たされて隅々まで透明なのである。ただ、何が知りたいのか、知るためにはどのように問えばよいのか、これを決定するのは自分自身であるというはっきりした自覚が、その研究を導くのだ。
「古事記伝」が完成した寛政十年に歌を詠んでいる。
古事の ふみをらよめば いにしへの てぶりこととひ 聞見るごとし
これは、ただの喜びの歌ではない。「古事記伝」終業とは、遂にこのような詠歌に至ったという事だった。これはそのような、「聞見る如き」気持ちにはその気になればなれる、とただ言っているのではない。学問の上から言っても、正しい歴史認識というものは、そういう所にしかない、という確信が歌われているのである。
証言が現存すれば過去は現在に蘇るというものではない。古人が生きた経験を、現在の自分の心のうちに迎え入れて、これを生きてみるという事は、歴史家が自力でやらなければならないことだ。そして、過去の姿が歪められず、そのまま自分の現在の関心のうちに蘇ってくると、これは自ずから新しい意味を帯びる。
過去の経験を、回想によってわが物とするのが歴史家ならば、過去の経験は遠い昔のものでも、最近のものでも、他人のものでも、己自身のものでもいいわけだ。それなら、総じて生きられた過去を知るとは、現在の己の生き方を知る事に他なるまい。
歴史を知るとは、己を知る事だという、このような道が行けない歴史家には、言わば年表という歴史を限る枠しか掴めない。倭建命の「言問ひ」は、宣長の意(ココロ)に迎えられて、「カク申し給える御心のほどを思いはかり奉るに、いといと悲哀(カナ)しとも悲哀(カナシ)き御語にざりける」という、しっかりした応答を得るまでは、息を吹き返したことなど、いっぺんもなかったのである。歴史を限る枠は動かせないが、枠の中での人間の行動は自由である。倭建命の「ふり」をこの点に据え、今日も働いているその魅力を想いめぐらす、そういう誰にも出来る全く素朴な経験を、学問の上で、どれほど拡大し或いは深化する事ができるが、宣長の仕事は、その驚くべき例を示している。
「本居宣長」-31章(2022/7/26)
「古事記」は、文学としては興味あるものだが、歴史として信用するわけにはいかないと考えるのが今の常識だ。「古事記」の神代の巻は荒唐無稽な内容なので、近世の歴史家達にとっても当惑の対象だった。「大日本史」は神武から始まっているし、幕命で「本朝通鑑」を記した林家も、神代の巻は敬遠して、神武から始めざるを得なかった。
このような時世に新井白石はただ一人正面からこれに取り組んだ。そして、上代に文字がなく、漢字を使って国文を作ることの困難や、「古事記」の序文に注目して、上古の記載では「その義を語言の間に求めて、その記す所の文字に拘るべからず」と言っている。これは宣長と同じ考えであるが、その先が違ってくるところが面白い。
それは、神代の記載をそのまま受け取ってはならないという考えで、そのまま受け取るから荒唐無稽な事と全否定するか、秘説と考えて肯定するかの二つしかないことになる。歴史家は「多く聞きて、疑わしきを欠く」という君子の慎重な態度を学び、記載から「朴質の言」が透けて見える。幼稚な表現から何が言いたかったのか、実は何を表現しているのか推定するのは難しくないと言う。「その詞をもって、その意を害する事なからんは、その書を読むことの要旨とすべきもの也」ということになる。宣長では決して離れる事のなかった「詞」と「意」とが離れるのである。
白石の「神とは人也」という言葉は今日とても有名だ。全く反対の考えの白石に触れることで、宣長の考えを説こうというつもりなのである。白石の「古史通」は、江戸期の古代史研究の高峰として「古事記伝」と並び称されることが多いのだが、そうするには仕事の性質があまりに違いすぎる。
「記紀」の神代の記述に出てくる、神々による最初の事件といえば、イザナギノミコト、イザナギノミコトのいわゆる「国生み」である。この神々の奇怪な行為も、「神は人也」と思い定めて分析していけば、人の行動の比喩、白石の言葉で言えば「形容(カタドリ)」に過ぎない。白石に言わせれば二柱の男女神は優れた男女の武将を指すので、船を率いて島を攻めた時に左軍の将と右軍の将となって攻め、その際の勝敗の出来事を述べているのだというのである。
では、言語格類はどう求められるか。例えば「高天原」は、漢字にこだわらず古語によって義を紐解くならば、高は古にいう所の高國で、「常陸風土記」にある多可郡を言い、天は海、原は上なので、古語に「タカアマノハラと言いしは、多可海上の地と言うがごとし」ということになる。こう簡単に決まるのも、天上に人が住めるわけがないと考えるからだ。宣長の吟味はひどく慎重綿密で、それについてはまた後に詳しく述べる。
白石は「太古朴陋の俗」による言葉の使い方を正そうとするが、太古の人の素朴な意のうちに素直に入っていく宣長には、「太古朴陋の俗」というような白石の言い方とは全く無縁なのである。言葉の使い方と物の見方、「見る」「知る」「語る」という働きは、意識して離そうとしない限りは、一体となしている。だから、特に神の物語である古記が扱われたために、二人の歩いた道に大変際立った対照が現れることになった。
「古史伝」は、白石の説明によれば、将軍家宣の甲府宰相綱豊時代、下命によって書いたものだ。白石は「それにて本朝開国以来、おおよそ文字に載せ置き候ほどの事においては、掌を見るが如くに事済むべく候か」と言っており、非常な自信を持っていたが、神典を実録に引き下ろした研究であったから、公表は難しかった。綱豊も愛読して秘蔵していたが、死後焚き捨てられた。少し注目したいのは、「古史通」は水戸藩の文庫に収まっているということだ。すると、彰考館総裁安積澹泊も、これを読んでいたかもしれない(水戸黄門で格さんとして描かれる)。
光圀が「大日本史」を神武から始めたのも、「実に寄って事を記す」という歴史家の立場からだった。実とは人の世の実であり、神の世は切り捨てられた。この思考は白石も同様なのである。逆に「大日本史」にしても、「神とは人也」という白石の考えに無縁だったわけではないのであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
