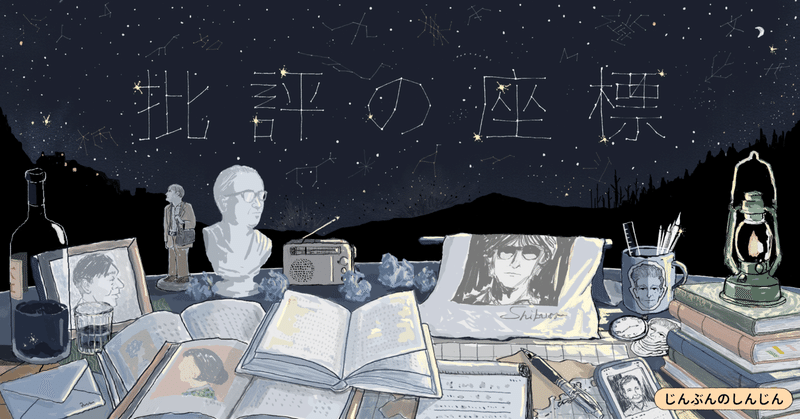
【批評の座標 第17回】失われた世界への旅先案内人——山口昌男と出会い直す(古木獠)
中沢新一や上野千鶴子の師に当たり、その後ニューアカとしてデビューしてゆく論客たちの影響源であった山口昌男。文化人類学者の山口は何を「批評」のシーンにもたらし、どのような知の「場所」を模索しようとしていたのか。『近代体操』創刊号にて、山口昌男と親密な交際を有した大江健三郎の作品を参照しながら、「悪場所」の政治思想を論じた近代体操同人であり、憲法学を専門とする古木獠が論じます。
――批評の地勢図を引き直す
失われた世界への旅先案内人
——山口昌男と出会い直す
古木獠
1 知の集団旅行
旅、何処へ?自分が属する日常生活的現実のルールが通用しない世界へ、自ら一つ一つ道標を打ち樹てて地図を作成しつつ進まなければ迷いのうちに果ててしまう知の未踏の地へ、書の世界へ?自らを隠すことに知の技術の大半を投じている秘教の世界へ、己れが継承した知的技術を破産させるような知識で満ちているような知の領域へ、である。
このまえ、熊野は新宮へ行った。批評のための運動体『近代体操』の同人である松田樹、森脇透青、そして哲学、文学、芸術、政治にかかわる人らとの、中上健次の足跡を辿る旅だった。中上が描いてきた故郷の土地をめぐり、いまや「消えた」被差別部落の「路地」という場所について考え、また市民グループ「『大逆事件』の犠牲者を顕彰する会」が運営する「熊野・新宮『大逆事件』資料室」で話を伺い、中上も関心を寄せそれを中心に据えて小説を書いてみたいと言っていた「大逆事件」について考えたのであった。「〈裏〉熊野大学」と呼ばれることになったこの旅については、『近代体操』創刊号でテーマにした空間・場所の問題と中上健次の文学との結びつきなどを述べつつ、松田がまとめている。熊野の地や文壇の状況などにも言及されており、本稿の問題意識と共通するところも多く、ぜひ参照してほしい。
むかし知識人はよく旅へ出た。それも狭いサークルに閉じず、こうした哲学、文学、演劇、音楽、映画、建築などさまざまな分野の者たちが集まって旅をしていたのである。
80年代には、学際的で自由なスタイルで、既存のアカデミズムの枠を越えマス・メディアでも展開された思想的なムーブメントとして、ニュー・アカデミズムのブームがあった。それより前に、その「ニューアカ」期を準備したとされる「プレ・ニューアカ期」の世代がいた[1]。ニューアカ・ブームは、浅田彰の『構造と力』(勁草書房、1983)や中沢新一『チベットのモーツァルト』(せりか書房、1984)がベストセラーになったところから始まり、その後多くのスター知識人が出てきた。先行世代の人々もニューアカ・ブームで注目を浴びるのであるが、その一人が山口昌男(1931-2013)である。
その当時に活躍した人たちは、今も思想界・論壇でよく知られた名であり続けているとは思う。多くの人に大きな影響を与えた、これらの人のこれこれという著作があると。しかし、そんなことよりも重要であるのは、知のムーブメントが高まりつつあった先行世代のプレ・ニューアカ期にはシーンがあったということだ。真に問題意識を共有する「集団」があった。そして、その中心に山口はいた。考えてみたいのは、今は失われた知のシーンについてである。そして、それをいかに取り戻すことができるかだ。
岩波書店の雑誌『世界』での鼎談をきっかけに、月一でのさまざまな分野の知識人の会合「例の会」が1976年に始まり、それと前後してスタートしていた「都市の会」から、叢書「文化の現在」という論集が編まれ、その延長上でプレ・ニューアカ期の代表的な雑誌『へるめす』が創刊されることになる[2]。よく知られていることであるが、「例の会」のメンバーの有志は、1979年にともにバリ島へ行っている。バリ島へ旅行した山口をはじめ、作家の井上ひさし、大江健三郎、文学者の清水徹、高橋康也、渡辺守章、哲学者の中村雄二郎、建築家の原広司、映画監督の吉田喜重らは、作曲家の武満徹を加えて、『世界』誌上でジャカルタを経てバリへというインドネシア旅行を振り返りつつ、その地の文化と芸能についての座談会を行なっている[3]。
ジャワやバリ島の地理的環境と寺院や遺跡などの関係についてや、影絵芝居、民族芝居、ガムラン音楽、踊りなどについて語り合われるのだが、それらのなべて観光化されていても観光化し切ることのできない深い文化的な次元から、あるいはその土地の生活全体から考察がなされている。このような議論は、地理や建築だけであったり、また演劇だけ、音楽だけ、踊りだけを見ていては汲み尽くせないものだ。こうしたことが可能であったのは、彼らがそれぞれの分野での第一人者であるだけではなく、普段からの日常感覚と地続きでバリにひとっ飛びし消費的に観光するのではなく、古都ジョグジャカルタを経て長い時間をかけてその土地、その文化を、それぞれの知識を交わしながら総体的に理解しようと試みていたからであろう。
論壇雑誌では毎回「現代的」なテーマで特集が組まれており、果てはSNSでも日々そうしたトピックが湧き上がっては消えているわけであるが、それぞれのトピックがたしかに重要で取り組むべきものであっても、それらは私たちの暮らす世界の中で適切な場所を与えられていない。それらと私たちの生活全体とのつながりが見えづらくなっている。同じ雑誌を読んでいて、前の号と現在の号、次の号とのつながりがまったくないように思えるのは、そうした問題の誌面への反映だろう。
次々に出されるトピックに対してその都度「正解」を見つけていく知的潮流は、あたかもチャート式で政治家ないし政党を選ぶトレンドに似たところがある。改憲、安全保障、平和、入管法改正、環境問題、婚姻制度、ジェンダー問題、天皇制、政治資金問題、増税、労働問題——これには賛成か?反対か?と答えていくと、○○党があなたの意見に最も近いです、と教えてもらえる。そこには個々の問題の間の有機的なつながりが存在しない。こうした個々の問題のそれぞれを、私たちの暮らす世界の中で総合的に捉えるのでなければ、提起された問題は次々に流れていくばかりである。このような趨勢に抗して、ばらばらにある事象を私たちにとって有意味に紡ぎ直すための舞台が必要なのだ。
バリ島の文化を総体的に理解しようとした山口らの専門分化されない豊かな集まりは、そのようなシーンとして見ることができるだろう。この「失われた知のシーン」を取り戻すことが必要ではないだろうか。
山口は、その歴史人類学三部作の掉尾を飾る『内田魯庵山脈』において、内田魯庵というもはや世間から忘れ去られた明治大正の文学者を拾い上げて、彼とその周辺の人々のネットワーク、知の水脈を掘り起こすことで意図したのは、「教科書的な意味での日本の近代とやや外れたところに存在した知の原郷というものを訪ねあてること」であった。山口は魯庵が生きた世界に「我々の時代には全く見失われてしまっているもう一つの世界」を見たのである[4]。
いま私たちは、山口昌男とその周辺を読み直すことでもきっと、失われてしまったもう一つの世界を見ることができるだろう。このように失われた世界を発見すること自体が、それを取り戻す方法であると思われるのだが、後で述べるようにそうした営為をも私は批評と呼びたい。失われた世界、知のシーンをいかに取り戻すことができるか、それを考えるに当たり、彼らの旅の続きを行くつもりで、まずは山口昌男の周辺から出発することにしよう。
2 失われた場所
「例の会」メンバーのなかでも中村雄二郎は、このバリ島旅行に大きな影響を受けた。彼は「都市の会」のメンバーとともに、半年ほどのちに再びバリ島へ訪れている。そして、これをきっかけに中村は、叢書「文化の現在」の第6巻『生と死の弁証法』(岩波書店、1980)に「魔女ランダ考 バリ島の〈パトスの知〉」を初めに書き、「演劇的知とは何か」などの論稿とともに『魔女ランダ考——演劇的知』(岩波書店、1983)を刊行する。そのなかで中村は、ヒンドゥの叙事詩『マハーバーラタ』を下敷きにするバリ島のバロン劇などに登場する魔女ランダに魅了され、そこからその存在がバリ島のコスモロジーに深く根差したものであり、また舞台装置となる寺院のあり方がトポロジカルに機能していることを分析していく。
中村の主著でもある本書についても詳しく紹介したいところであるが[5]、ここでは雑誌『へるめす』の創刊号に掲載された、中村の文章「場所・通底・遊行——トポス論の展開のために」を見てみよう――この文章は、『魔女ランダ考』、したがってバリ島旅行の延長にあるといえる。奇しくも、その中で中村は中上健次について論じている。
そこで問題とされるのは、リアリズムを約束事として多くが写実的な描写から成るというきわめて〈自由な形式〉をとる、特に近代小説と近代絵画に代表される近代諸芸術が、かえってその〈自由な形式〉ゆえに「現実の重層性に対して十分に対処できないもの、不自由なものになってきた」というアポリアである[6]。
この問題に対して、中村は画家バルテュスに注目する。その作品群は、トポス(場所、主題、記憶)[7]——「部屋とくに子供部屋、路地や街という、ふつうの意味での場所」や「大人に成りかけの少女、とくに裸の、鏡をもった少女や長椅子に寝そべる子供といった、過去の、人々に親しまれた主題=記憶」——とかかわることによって、何世紀もの時間を超えて「通底」するものを表現しえており、日常性を超えた神秘的な深層を「浮上」させることに成功していると評するのである。
このトポスというものが、近代諸芸術のアポリアを乗り越える鍵ということになる。そして、中世絵画の絵画的主題が、熊野比丘尼の用いていた比丘尼曼荼羅に通底しているということから、話は熊野という場所に移り、ここでトポスと旅との関係に焦点が合わされることになる。
場所は、その喚起するイメージから旅ないし遊行(遊牧、ノマド)と対立するものと誤解されがちだが、それは遊行によってかえって活性化される。というのも、熊野比丘尼が、絵巻や掛軸に描かれた曼荼羅の絵解きをしながら、関東・中部地方に止まらず東北地方にも西日本地方にも遊行したことで、熊野信仰が広まり、日本各地に多数の熊野神社が建立された。これはつまり、「比丘尼たちの遊行によってかえって地理的・文化的なトポスとして熊野の地が大きな意味をもっ」たということである[8]。
中上健次は、熊野というトポス、なかんずく被差別部落である〈路地〉にこだわって書いてきた。中上の諸作品の中で、地理的・歴史的事情に加えて共同体の記憶が積層する〈路地〉は、「ほとんど意味発生の根源として現われて」さえいる。しかし、開発によって「路地」は消え去ってしまう——そうした事態は、資本のフローのために、人類学者マルク・オジェが「非-場所」と呼ぶ「アイデンティティを構築するとも、関係を結ぶとも、歴史をそなえるとも定義することのできない空間」が溢れている現代都市空間として、一層問題になっている[9]。
中上の作品『日輪の翼』において、若い衆が〈オバ〉と呼ばれる「現代の〈熊野比丘尼=老婆たち〉」を大型冷凍トレーラーに乗せて日本各地のいろいろな聖地に廻遊する。熊野を出発し、やがて「天子様のおられる東京」に着いたとき、「老婆らは突然、今まで眠っていた天子様と路地のかかわりを思い出す」[10]。中村は、この仕掛けが〈移動する路地〉という「生き生きとしたトポスを再生させる」方法たりえないか期待をかけつつ、文章を結んでいる[11]。
たとえある場所が消えたとしても、その記憶を持つ者が旅をし、別の場所とつながれば、消えた場所の記憶は生き続けるのではないか。この意味でやはり場所は、旅と対立するものでもなく、固定的で閉鎖的なものでもない。そしてまた、旅によってトポス相互のネットワークが形成されると、それらの影響関係の中から新たな意味が生まれてくる。
中心的なトポスがあらゆる意味を規定するのではなく、その外部がつねに存在し、その外部との接触によってネットワークが組み変われば、意味体系は変容する。そのことを、1984年に中上健次と再びバリ島を訪れた山口昌男はよく理解していた。
路地によって、言葉=物語=制度=法=国家から排除され、歴史的時空から締め出された被差別の空間が、逆に制度=物語=文化を異化し詩的言語を発生させる特権的な地点になることを中上氏は作品〔『千年の愉楽』〕という形で示してしまった。
差別され排除され消え去った世界にこそ、現在の秩序を変革する可能性が埋もれているのである。ではこの失われた世界をいかに取り戻すことができるだろうか。その方法が山口昌男の歴史人類学である。
3 周縁性の歴史学あるいは歴史人類学という方法
山口自身がいうには、自らの文章が人にいくらかなりとも気にとめて読まれるようになったのは、精神史家・林達夫に抜擢されて編者を担当した平凡社の「現代人の思想」シリーズの一冊『未開と文明』(1969)の解説として書かれた「失われた世界の復権」からである。そこで山口は、「未開」という始源世界に回帰する希求に、ある種のユートピア思想を見出す。
「世界のなかにおけるおのれの全的な統一」が失われ、生が断片化した西洋近代において、ルソーの自然状態の賛美など、ロマン主義と名づけられてきたさまざまな思想はいずれも、「散文化した世界に抗いつつ、自己のアイデンティティを現実を超えた世界(過去・自然)を範型とする事によって再建しようとする試みであった。これらの思想家たちによって描かれた古代の像は、日常生活において実現されえない願望を色濃く投影しているという点において、すなわち日常的世界を裏返したものであるという点においてユートピア思想の延長にあったとも言える」[12]。この「はみ出し部分としての「未開」は、これらの運動のなかで、絶えず、失われているものは何であるかということを「現代」に自覚せしめるためのモデルを提供して来た」[13]。
過去とは当然、客観的時間においては戻ることのできない過ぎ去ったものであるが、今も私たちの生きる時間のなかに常に根底にあって時に顔を出す、神話的といえるような始源的なものは、「自然的時間を遡った果てにあるものでなく」、内的時間における未来に立ち現れてくるものである[14]。したがって、失われた世界とは過去のものというよりも、来たるべき世界の謂であるのだ。このような時間性において歴史人類学の可能性は認識される。
その歴史人類学は、山口の代名詞ともいえる、その著作の中でも最も有名な『文化と両義性』(岩波書店、1975)で論じられた「中心と周縁」理論を前提にすると理解しやすい。
安定した日常の秩序のために社会の「中心」は、記号を一元的な意味作用に収斂させていくが、あらゆる記号はつねに多義的な意味を担う可能性を秘めている。「中心」は自らのアイデンティティを安定させ、固定化しようと「周縁」をつくり出し他者を排除するが、閉鎖的な社会はやがて停滞する。文化が固定せず流動的に生成されるように活性化する仕掛けがうまく組み込まれている社会では、中心的秩序によって抑圧された「周縁」部分が、反秩序的な混乱を伴いながら「中心」に入り込んでくる機会が儀礼的に組み込まれていたり、現実の出来事として生じたりしてきた。このような理解をベースとして、「中心」と「周縁」を自由に往き来する両儀的な存在である、神話論における「トリックスター(いたずら者)」が、また文化における「道化」が、注目され分析された。
中心は自らを権威づけ安定させるために「正統」をつくり出す権力である。しかし、あらゆる人、あらゆる事物はつねに多義的に存在しているのであり、その存在の意味をそのような権力が一元的に決定することはできない。したがって、中心において一元的に組織される秩序とは異なる秩序、秩序に対して攪乱的な別のつながりが中心、正統とされるところからは不可視化される形で存在し、こうした「見えない」つながりに光を当てることそれ自体が反秩序的な破壊力をもつのである。
そして、山口は90年代を通じて、「日本の近代史の見えない部分」を描く歴史人類学三部作——『「挫折」の昭和史』『「敗者」の精神史』『内田魯庵山脈』——に、60代にして精力的に取り組んだ。その歴史人類学とは、公的な政治史・経済史のみを扱う狭義の歴史学に対して、資料としては文書に限定せず、また必ずしも表層の現実には現れてこない深層において歴史を捉え、現実の様々なレヴェルを扱うものである。それゆえ、それは全体史を志向し、「既成のディスクールの網の目に入って来ない」「周縁的なもの」に目を向けた歴史となる[15]。
私はこうした歴史を記すことも批評であると言いたい。唐突だろうか。山口の歴史人類学ないし「周縁性の歴史学」は収集家による歴史とも言い換えられるが、「収集」という概念によって歴史と批評は結びつくのである。
4 収集家としての批評家
批評には一種の飛躍、決断することが付きものだ。それはよく言われるように、批評(Kritik)という言葉が「決定する」ことを意味するギリシア語krineinに由来するということに関連している。同じくそこから危機(Krise)という言葉も派生しているのであるが、これは従来の判断基準(Kriterium)では対処できないような混乱状況においては何らかの決断が必要となるからである。krineinには「決定」や「判断」の前に「選択する」という意味も含まれている。したがって、そこには境界確定をし、なにものかを排除することが含意されている。
しかし、批評とはむしろ危機をもたらすものではないだろうか。そして、それは選択したり決定するよりもその前に立ち止まること、さらにこう言ってよければ立ち止まりつづけることではないか。危機において人は正しい判断を求め、自信をもって決断を下してくれるリーダーについていくことを望んでしまいがちである。真に正しい判断など誰にわかるものだろうか。決断のあとにも世界は続いていく。その決断が正しいのか思考しつづけることのほうが、決断よりも重要であるはずだ。あり得た別の可能性がつねに存在している。その可能性を考えつづけること、それは過去に止まろうとすることである。そのような人物をこそ批評家と呼ぶならば、批評家は過去をすべて保存しようという情熱をもつ者だといってよいだろう。この情熱はベンヤミンが「収集家の情熱」と言ったものである。
収集家の情熱はアナーキーで破壊的だという。なぜだろうか。ハンナ・アーレントも語っているように、収集というのは子どもっぽい情熱である[16]。子どもは、どんな事物も有用性で判断しない。生活のために役に立つとか経済的に価値があるとかは関係なく、収集はその物それ自体の固有の価値を救い出す行為である。
このように日常世界における有用性から事物を解放する収集家は、よりよい世界への道をも夢想する者であり、その情熱は革命家のそれに重なりさえする。収集家の情熱は、「現状に対する不満から生まれたものであり」、したがってそれは、硬直化した旧態依然の社会と、つまりは伝統というものと対立することになるのだ。
伝統は過去を単に年代順に秩序づけるだけでなく、何よりもまず体系的に秩序づける。そこで伝統は肯定的なものを否定的なものから、正統を異端から区別するのであり、さらに無関係なものの巨大な集合や、あるいは単に面白い意見やデータであるにすぎないものから義務を負わせる存在や適切な関係を持つ存在を区別する。一方収集家の情熱は体系的でないだけではなく、無秩序と境を接している。その理由はそれが情熱だからというよりは、それがまず分類されうるものとしての対象の質によって燃えあがるのではなく、その「純粋性」とかその独自性とか、いかなる体系的分類をも許さないものによって燃えさかるものだからである。
山口がこのような情熱をもっていたことは明らかだ。先に述べた彼の歴史人類学ないし周縁性の歴史学という方法は、伝統=正史に対抗するような収集家によるアナーキーな歴史と呼べるものであった。
歴史も一種のネットワークである。別の項が新たに加わればネットワーク全体が組み変わり、今までとは別様に位置づけられた項は、その持つ意味を変容させる。歴史は絶えず読み直される。それまで排除されていた周縁によって読み直されるのである。
大江健三郎は、1977年に文庫化された『本の神話学』(中公文庫)の解説に山口との出会いを書いている。それは林達夫を囲む会でのことで、大江は「そこで山口昌男から、いかにもかれの好みの小新聞に、いまとなってはかれの厖大な収集から提供されたものだとすぐにわかる、パンチとジュディ劇の漫画を挿画にした切りぬきをもらった」と。そのとき、山口はパンチとジュディ劇の流れを遡って、その生涯の主題であるコメディア・デラルテやアルレッキーノ型道化など、本書や他の著作で語られるさまざまなものに話を引き出し、展開することができなかったことを大江は歎く——「ああ、僕がかれの仕事の総体について、あのように無知でなかったとしたら」。ただし、大江は本書を読むことで山口と出会い直す。そしてその時、「自分のなかになにものか蘇生する喜び」を覚えるのである[17]。
出会う相手が著作家である場合、あらためて恥の思いを克服しつつ、かれの著作を読み直せば、すくなくとも一方的には、あやまりであった現実の出会いをつくりなおすことができる。僕が書物を愛する人間であることの、根柢の切実な理由としてそれがある。
山口は、「中心と周縁」理論などといって図式的であるとか、あるいは海外のさまざまな議論を輸入しているだけであるとか、思想界・論壇で人気を得て注目を得た分だけ不当な評価を受けてきた。しかし、彼があまり多くの人の関心を集めていなかった時期の地味な歴史人類学の仕事は、山口において周縁的な著作であるが、それを読み直してみると、また違った相貌を呈した山口昌男が現われてくる。そして、そこからまた彼が言及するたくさんの人、物など、あらゆるものに向かいたくなってくるはずで、すると山口の生きた知のネットワークが取り戻すべき知のシーンとして浮かび上がってくる。
〈旅〉を知のメタファーだとすれば、それは空間的なものに限られない。山口は実際、本を読むことも一種の旅だと考えていたし、すると歴史も時間的な旅だということができる。私たちはあらゆるところへ旅をすることができる。
私たちは旅しつづけることで、私たちの知の場所を確保することができるのだろう。
この〔形骸化してしまった世界のモデルをなおも押しつけ、弾力性を失った神話を強制することに異議を申し立てる〕精神が平俗な日常生活を相対化するために踏み出す第一歩は〈旅〉に出かけることである。己れをまだ汲み尽くされていない価値の源泉に一歩近づけるために旅装を整えることである。
[1] 大澤聡「批評とメディア」東浩紀ほか『現代日本の批評 1975―2001』(講談社、2017)24-25頁。
[2] 「例の会」のメンバーは、山口のほか、磯崎新、一柳慧、大岡信、鈴木忠志、武満徹、東野芳明、塙嘉彦、大塚信一で始まり、その後、中村雄二郎、清水徹、原広司が加わる。「都市の会」のメンバーは、中村雄二郎、多木浩二、前田愛、市川浩、河合隼雄。叢書「文化の現在」(大江健三郎、中村雄二郎、山口昌男 編集代表、岩波書店、全13巻、1980.11〜1982.7)。『へるめす』(大塚信一編集長、磯崎新、大江健三郎、大岡信、武満徹、中村雄二郎、山口昌男 編集同人、岩波書店、1984.12〜1997.7)。
[3] 「神々の島バリ——インドネシアの文化と芸能をたずねて——」世界408号(1979)268-301頁。
[4] 山口昌男『内田魯庵山脈(上)——〈失われた日本人〉発掘』(岩波現代文庫、2010)6頁。
[5] 中村雄二郎の著作と活動のかかわり合いについては、大塚信一『哲学者・中村雄二郎の仕事』(トランスビュー、2008)が詳しい。本論考との関係では、特に第六章を参照。
[6] 中村雄二郎「場所・通底・遊行——トポス論の展開のために」へるめす創刊号(1984)194-195頁。
[7] 通常「トポス」は「場所」と訳されるが、「ものごとを場所と関連づけることによって覚える記憶術」が存在し、それによって「論点および議論の根拠」=主題を記憶していたことから、トポスは記憶と主題をも意味するようになったと考えられる(山口義久「『トポス論』解説」『アリストテレス全集3 トポス論 ソフィスト的論駁について』(岩波書店、2014)479-502頁参照)。
[8] 中村、前掲論文、204頁。
[9] マルク・オジェ(中川真知子訳)『非-場所 スーパーモダニティの人類学に向けて』(水声社、2017)104頁。これは『近代体操』創刊号(2022)で私たちが共通の問題意識としていたことである。
[10] 中上健次『日輪の翼』(河出文庫、2012)356頁。「特にサンノオバは、本宮の血を受けていたから、代々天子様の毒味役で、宮中に召されたのが明治の頃まであったのを知っていて、頭の中で畏れ多いと分かっているしそんな事は決してしないと思っていたのに、育つのか育たないのか分からなかった赤子のツヨシに豆や芋を口で噛んで擂りつぶして食べさせたように、天子様にも毒味役としてそうしてきた気がしているので、天子様の為ならいつでも矢盾になって犠牲をいとわない誇りがむくむくと湧き出てくる」(同書、256-257頁)。
[11] 中村、前掲論文、207頁。
[12] 山口昌男「失われた世界の復権」同『人類学的思考』(筑摩書房、1990)431頁。
[13] 同上482頁。
[14] 同上参照。
[15] 山口昌男「歴史人類学或いは人類学的歴史学へ」『知の遠近法』(岩波現代文庫、2004)340頁。同論文および同書所収の「周縁性の歴史学に向かって」287-319頁参照。
[16] ハンナ・アレント『暗い時代の人々』(阿部齊訳、ちくま学芸文庫、2005)303-304頁参照。
[17] 大江健三郎「“知の世界の涯を旅する者”」山口昌男『本の神話学』(中公文庫、1977)254-255頁
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
古木獠(ふるき・りょう) 1996年生まれ。大学院生、法学研究科博士後期課程在籍。憲法学を専攻し、国民投票・発案について研究している。批評のための運動体『近代体操』同人。X(Twitter):@decaultr
次回は1月前半更新予定です。石橋直樹さんが柳田國男を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
