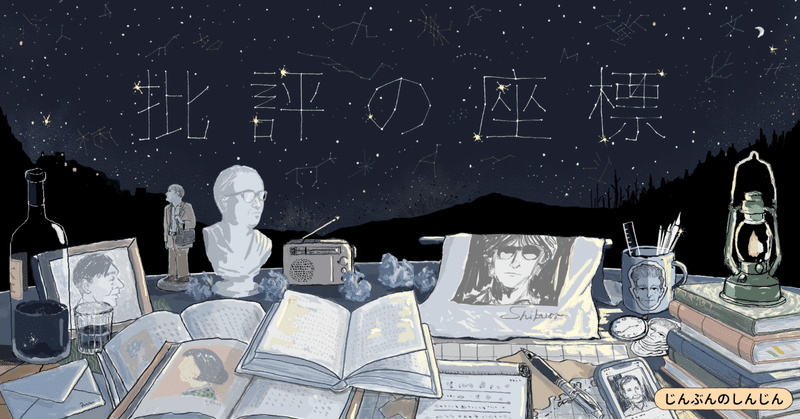
【批評の座標 第6回】東浩紀の批評的アクティヴィズムについて(森脇透青)
批評のみならず書籍出版や人文系のイベントスペースの運営等を通じて、ゼロ年代以降の批評界を牽引し続けている東浩紀。東が「再発明」した「ポスト・モダン」「誤配」等の概念を文脈に即して読解し直し、その活動全体から東の批評的視座を見いだします。執筆者は気鋭のデリダ研究者であり、批評誌『近代体操』を主宰・運営する森脇透青です。
――批評の地勢図を引き直す
東浩紀の批評的アクティヴィズムについて
森脇透青
1. 終わってくれないポスト・モダン
東浩紀(1971-)は批評家にして活動家である。このテーゼは揶揄でもアイロニーでもない。私たちは本稿を通じて、東の「批評活動」の系譜を記し、このテーゼを証明することになるだろう。
東浩紀は一般に「ポスト・モダン」の擁護者として理解されている。それも相対主義者の左翼嫌い、運動嫌いとして理解されている。しかし、東の活動について記述するうえでまず次の点を確認する必要があるだろう。東は一般的な意味では「ポスト・モダン」を擁護してなどいない。
そもそも「ポスト・モダン」は何を指しているのか曖昧な語であり、その曖昧さによってしばしば恣意的なレッテルとして運用される(そのようなレッテルはしばしば、「ソーカル事件」という雑な隠喩を伴う)。だから当然だが、多少の誠実さと知性を持ちあわせる人間は、定義もなしに「ポスト・モダン」などという語を濫用しはしない。東はすでにその活動の初期においてその事情に自覚的であった。
彼は2000年の論考「ポストモダン再考」で、「ポスト・モダニズム」と「ポスト・モダン」の区別を提案し、その語を明確に定義している[1]。東によれば、前者(「ポスト・モダニズム」)は、〈六八年五月〉と同期した哲学・運動・文化、日本では(日本でのみ)「現代思想」と呼ばれる一連の思潮を指している。それはフランスの思想家たちの固有名(フーコー、ドゥルーズ、デリダ、ラカンその他)によって想起される思想の傾向であり、それに連動した文化、種々の新たな政治運動や批判的理論(エコロジー、フェミニズム、マイノリティ運動、カルチュラル・スタディーズ……)を指している。
それに対し、後者(「ポスト・モダン」)は、社会的・政治経済的な状況を指している。つまり〈六八年五月〉以後、消費社会の大規模な拡大、グローバリゼーションの加速、反体制運動の失速と連動して生じた一連の社会的な状況を指している。この状況を象徴するのは、リオタールが『ポスト・モダンの条件』(1979年)にいう「大きな物語」の失効である。世界全体を説明しうる大文字の理論(たとえばマルクス主義)が失墜したとき、さまざまな知と実践は交流するための共通の基盤を失い、バラバラに分裂したそれぞれの経験的世界を生きることになる。このとき、個々の専門知と「趣味」の差異はかぎりなく小さくなる。
ここで認識しておかなくてはならないのは、東浩紀が批評家として活動し始めた九〇年代後半、「ポスト・モダニズム」はすでにその批判性を失った、とされていた点である。たとえば柄谷行人は、一方で自身と同時代の「ポスト・モダニズム」思想家たちにシンパシーを抱きつつも、他方でその潮流が消費文化と融合してしまった点について、批判的であった(『批評とポスト・モダン』1985年)。つまり東の分類を手引きとして言えば、柄谷は思想としての「ポスト・モダニズム」を一部肯定的に受け入れたとしても、社会状況としての「ポスト・モダン」を受け入れることはなかった。このことは、柄谷が大江や中上以後の文学(村上春樹や吉本ばなな)を拒絶したこととも並行的である。だからこそ柄谷は八〇年代の終わりに「近代文学の終焉」を宣告したのであって、それは「ポスト・モダン」化の加速によって、文学が表象=代行の能力を失ったことを意味する。
「ポスト・モダニズム」と「ポスト・モダン」が連動していた時期はたしかにある。だが、「ポスト・モダニズム」が終わっても「ポスト・モダン」は終わってくれない。冷戦以後、「ポスト・モダン」的社会状況はますます加速している。つまり消費社会の拡大を通じて、「多様性」に満ち溢れた趣味的消費が覇権を握っている。誰も「ポスト・モダン」をことさらに言いつのらなくなったのは、「大きな物語」の失脚がもはや言うまでもなく当然になったからである。それはたんにベタな現実にすぎない。
「ポスト・モダニズム」はたしかにあらゆる大文字の権威を解体あるいは「脱構築」した。しかし「ポスト・モダン」化がより進行し当たり前となった状況においては、「ポスト・モダニズム」は個別の趣味的言説でしかなくなり、そのラディカルさと普遍性を失う。しかもこのタコツボ化は、当時の「ポスト・モダニズム」そのものと無関係ではない。東によれば、九〇年代、「ポスト・モダニズム」は、各業界の棲み分けと共犯によってかろうじて生き延びていたのである[2]。
東の批評の背後には、つねにこうした状況認識が潜んでいる。それは権力論でさえある。東浩紀はいつも、自身の概念を提出する前に、状況整理と課題の発見を先に行なっている。私が強調したいのは、この実践の全体において東の活動は「批評」たりうる、さらには「活動」たりうる、という点である。介入のための有効な戦略を練らない者は、アクティヴィストたりえない。東の用いる種々の概念——「誤配」や「データベース消費」や「観光客」や「訂正可能性」——は、この状況認識と分かち難く結びつき、状況介入としてもっとも有効なものとして(そう見えるように)提出される。この時期の場合、東は死語であった「ポスト・モダン」を再発明することで、その認識を提出した。
古名(paléonymie)の再発明は、現状認識を主張し、現在の理論的布置を整理し、批評の課題を再確認するための一種の戦略[3]である。だから、東浩紀の概念をたんに一般的で抽象的な含意においてのみ理解する場合、それは東浩紀の半分しか読めていない。そのとき手元に残るのは、何にでも適応可能な、空白のマジック・ワードだけである。たとえば『動物化するポスト・モダン』(2001年)が基づくのは、すでに東によって改造された「ポスト・モダン」であって、それに基づいて東を「ポスト・モダン擁護派」として批判するなら、そのような批判は一種の遠近法的な盲点にふい撃ちされている。言い換えれば、東の戦略の内部で抗っているにすぎないのだ。
2. 郵便から動物たちの公共性へ
この時期の東にとって克服すべき課題は、「ポスト・モダン」の「棲み分け」であった。東が「横断」や「横向きの超越」や「誤配」といった語を特権化するに至るのは、この状況認識においてである。「ポスト・モダニズム」は制度への閉じ込め・囲い込みによって、かつて持っていたような新鮮な知的役割、種々の知を横断させるフレキシブルさを失い、骨抜きにされている(同様の状況は、たとえばイェール学派においても起こっていた)。ここで東は、かつて「ポスト・モダニズム」が持っていた知的役割を肯定するが、しかし今日その場所を占めるべきなのはもはや制度化された「ポスト・モダニズム」ではない、と考えるのである。
しかしそれにしても、柄谷のように「カントとマルクス」に先祖帰りすることによって「ポスト・モダン」の棲み分け状況を打破することがもはや不可能であると東が考えていたとすれば、彼は何を出発点とするのだろうか。
東浩紀のデリダ論『存在論的、郵便的』(1998年)の図式に基づくなら、たとえば近代主義(「形而上学」)の徹底によって近代主義を打破するという柄谷の議論は、「否定神学的脱構築」に対応する。それに東は「郵便的脱構築」を対置する。このふたつの脱構築は本来デリダの読解から導き出された抽象的で思弁的な概念である。しかしその読解の成果はその後の東の仕事のなかで状況論化され、肉づけされ、実体化されることになる。私は先に東浩紀の「再発明」の戦略——最近の東はそれを「訂正可能性」と呼んでいる——を確認したが、それは彼自身の概念についても例外ではない。状況から思考へ、思考から状況へと反復横跳びしつつ概念を再発明しつづけるこの運動において、東は批評活動家たりうる。ここで私はその功罪については触れずに、その「実体化」されたモデルの系譜を記述しよう[4]。
形而上学を一言で言えば、「話せばわかる」である。形而上学において手紙は必ず宛先に届けられる。形而上学は意識あるいは理性のレヴェルで他者と「わかりあえる」こと、理解の可能性を前提とする。
否定神学はそれを批判し、「わかる」ことの徹底的な不可能性を暴露する。それはあらゆるコミュニケーションを、「わかる」ことの不可能性によって基礎づける。しかしその基礎づけの手口において否定神学は隠されたひとつの審級(「わかりあえない」)を特権化している。したがって否定神学は形而上学と表裏一体である。一言で言えば、「話してもわかりあえないが「わかりあえない」ということはわかる」。否定神学において手紙は宛先に「届かない」ことで逆に確実に届けられる。否定神学的脱構築においては近代形而上学あるいは近代資本制の批判それ自体が目的化され、ひたすらそのひとつの「亀裂」が強調・反復される。
郵便的脱構築が問題にするのは、コミュニケーションの主体ではなく、むしろその流通経路である。誤配において手紙は届かないことがありうるし、別の宛先に届いてしまいすらする(誤配)。人々が「わかりあえない」としても、それは根源的に隠蔽された超越論的な理解不可能性に由来するのではない。単純に、そのつどの送受信において流通のミスが生じうるからである。意識の水準から見れば、それは送受信の失敗でしかない。しかしこのとき、ひとは何かしら知らないあいだに勝手にわかって「しまう」(「転移」)。そのつどの送受信において、私が意図したことが別の形で届いてしまう可能性は、払拭できない仕方でつねにつきまとっている。類比的にいえば、それは言説の内容ではなく、語る仕草や口調や言葉選び(文体)の問題、そしてメディアの問題である。イメージは次々と無意識間を飛び交い、複数的な仕方で分散し、別の届け先に漂着し、意識せずとも感染していく。
ネットワークの機能不全において、私たちは勝手に何かを送受信して「しまって」いる。「ポスト・モダニズム」の思想のうちに東が見るのは、否定神学の徹底(否定神学的脱構築)と否定神学からの逃走(郵便的脱構築)の絡み合いである。「ポスト・モダニズム」は、ただひたすらに近代主義を批判し自閉してしまう方向と、それとはまったく異なる新たな哲学の開始に区分される。東は後者の可能性に賭けを投じる——その可能性は、『批評空間』派ではなく、大塚英志や、宮台真司の議論に見出されるだろう。ここからゼロ年代の東の批評は、サブカルチャー論、情報環境論(メディア論)、社会学へと伸張していくことになる。
『存在論的、郵便的』直後、その可能性は、当時の情報環境(インターネットの普及)に、さらに「オタク」の消費行動のうちに見出される。オタクたちはその消費行動において、個々には閉じていたとしても、奇妙に記号的な関わり合いを見せる(データベース消費)。このモチーフ、すなわち複数の「閉じたコミュニティ」が「閉じた」ままに交流している、という「横向きの超越」のモチーフは、現在に至るまで、東浩紀の議論で繰り返し現れる。
それぞれの共同体は、あるいは各個人は、「大きな物語」のような共通の地盤や理念なしに、実は無意識に、そしてさらに「動物的に」交流している。このとき「誤配」は、動物的な消費への欲望において起きているものとしてまた「再発明」されることになる。ここでいう欲望は、精神的「欲望」(desireあるいはdésir)ではなく、むしろもっと即物的に満たされるような「欲求」(needあるいはbesoin)である。欲望/欲求のこの区別は、ヘーゲルからコジェーヴを経由して戦後フランス思想に流入してくる重要な論点のひとつである(以下では便宜的に人間的欲望/動物的欲望と表記する)。
東はコジェーヴからヒントを得て、他者へ向かう人間的欲望ではなく、自閉的で利己的な動物的欲望の時代として「ポスト・モダン」を再規定する。そして東はそれを否定も肯定もしない(『動ポモ』はオタク批判の本でもオタク肯定の本でもない)。必要なのは、消費社会を駆動させるエンジンとしての欲望を所与の条件として認め、それをテコとして閉塞した共同体間に新たなコミュニケーションを作り出すことである。
このようにして「誤配」は消費社会における動物的欲望を介した「新たな公共性」の可能性に結びつくのだが、ここでもっとも重要になるのは、『一般意志2.0』(2011年)である。このテクストでは、「熟議」(話し合い)を通じて形作られる公共性に対して、「熟議」なしに、孤独な「私」たちがそれぞれ孤独であるがままに交流する公共性という対立軸が打ち出される(アーレント/ハーバーマスに対するルソー/フロイト/グーグル)。
この図式がここまでに論じてきた対立軸に対応しているのは言うまでもないが、重要なのは『一般意志2.0』において、そのモデルがこれまでになく具体化されることである。ここで欲望を通じたコミュニケーションは、現実のアーキテクチャ(ニコニコ生放送や一部のSNS)を通じてある程度「実装」可能なものとみなされる。私たちは日々無意識に小さな動物的欲望を満たしながら生きている。情報環境は、その行動を記録し、蓄積し、データベース化する。しかし東の主張はそのような集積・可視化を通じて、大衆の欲望を直接的に政治的意志決定に反映させるということではない。東が主張するのは、アーキテクチャを通じて大衆の言葉を政治家たちの「無意識」の次元に反映させることだ。
この奇妙な提案は、具体的にはニコニコ生放送から着想を得ている。ニコニコ生放送の番組において、カメラの前に座った政治家なり知識人なりは、あくまで自身の意志で語る。だが彼らの眼前にはつねに大衆たちの大量のコメントが表示されている。そのひとつずつは取るに足らないものであって、知識人たちはそれを直接に採用・実現しようとするのではない。しかし、彼らは無意識下にそれを意識し、自身の意見を調整せざるをえない。言い換えれば、その「雰囲気」に感染せざるをえない。たとえば国会でニコニコ生放送のコメントをリアルタイムに表示すればどうか。
ここで大衆の欲望と政治的意志決定(熟議)、大衆と選良はそれぞれ独立・分離されたままに、アーキテクチャの集積技術を通じて、無意識下で通じ合う。東はこのようにして新たな公共性(民主主義2.0)が実現可能だと考えた。このゼロ年代を通じた変化は、東と協働した建築家の藤村龍至の批判的工学主義(グーグル的建築)や、濱野智や鈴木健のアーキテクチャ論と連動するものでもある。東は意識レヴェルの交流(熟議)の限界を指摘し、人々が勝手に交流してしまうようなシステムの構築に「夢」を託した。したがって「ゼロ年代批評」の可能性の中心はオタク論でもサブカル論でもなくアーキテクチャ論である。
3. 人間的な、あまりに人間的な
いずれにしても公共性の原動力になるのは、意識的(理性的)なコミュニケーションや熟議に向かう人間的努力ではない。身体性であり、情動であり、「憐れみ」(ルソー)であり、消費へ向かう動物的欲望である。そもそも「ポスト・モダン」状況において、啓蒙や熟議に基づく公共性を全面的に実現することは端的に不可能である。だとすればむしろ大衆(消費する動物たち)同士の無意識のコミュニケーションが、強い理性ではなく弱い情念が、新たな公共——「ひきこもりの民主主義」——の可能性を開く。だが、かといって東はポピュリズムの直接民主主義に与しているわけではない。彼にとって大衆社会はそれ自体として肯定すべきものなのではなく、リベラルな理念を達成するために、あるいは公共性を作り直すために避けては通れない不可避の条件であり、同時にそのためのリソースなのだ。
必要なのは、大衆を肯定することでも批判することでもない。大衆の意志を反映する制度(システム)そのものを、民主主義そのものを作り替えることである。ところで、東が『一般意志2.0』を書いていた2009年から2011年は、様々な意味で豊かな時期だった。もちろん政治状況や経済状況は理想からは程遠かっただろう。しかし一応は(「悪夢の」?)民主党政権があり、オタク・カルチャーがその全盛を迎え、ニコニコ動画や新たなSNSの登場によって、「ネットで世界が変わる」という幻想を抱きやすい時期だった。しかし東日本大震災、自民党政権復活、トランプ政権登場、ブレグジットといった出来事によって、「ゼロ年代」が夢見たインターネットは壊れた。それは「ゼロ年代」の当事者たちにも痛感されている事態である[5]。
東は『一般意志2.0』でmixi型の「閉じた」SNSに対し、つねにリツイートで「他者」に触れなければならないTwitterのシステムを評価している。Twitterでは、趣味に閉じたオタクであれ、他者からのリツイートという形でその「外部」に触れてしまう。そして場合によっては「動物的な」反射速度によって、それに「いいね」したりリツイートしたりし、そのツイートの続きを、そのアカウントの他のツイートを追ってしまう。それは、ひきこもり的な個人が否応なく——動物的に、そして偶然的に——他の世界に触れ、開かれてしまう構造である。この「公共性」を東は評価した。
しかし、Twitter的公共性は今や、二重の意味での苦難に遭遇している。一方では、私たちは「開かれすぎて」いて、「閉じたタコツボ」を形成すること自体が不可能である。にもかかわらず他方で、そうしたプラットフォームそのものは、過去に持っていたかもしれない多様さを殺しつつ、巨大な「閉じた」世界を作り出している。
いかなる発言も「誤配」されることが前提であるとき、特定の閉じた「クラスタ」(=タコツボ)の中でのみ通用する言葉を想定すること自体が困難である。「タコツボ」を閉じることはできない。だが、人々の摩擦あるいはアレルギー反応は起きつづける。それが、私たちが毎日「炎上」として観測しているものである。
誰もが「誤配」を予測しているような時、もはや「誤配」は「炎上」の同義語でしかない。同じく私たちはもはや、自分の「手紙」が自分の望まない相手に配達されることを、いつもすでに予期している。どんなときもつねに「敵の共同体」の影を想定する神経過敏。このとき私たちがSNS上で共犯的に「シェア」(=分有)しているのはひとつの「現実」であって、その単数性は、複数性と偶然性に基づくあらゆる「誤配」を、予測可能で必然的な帰結に変えてしまう。
たとえ何度「多様性」が叫ばれようと、プラットフォーム資本主義という中央集権の内部では、偶然も複数性も存在しない。それはあらゆる「誤配」を殺し、予測可能な「炎上」に変換していくシステムだからである。Twitterはもはや巨大なmixiでしかない。しかしここで私は、東がSNSや動画メディアの未来予測について見誤った、と言い、糾弾するつもりはない。むしろ指摘したいのは、かつて東が設定した人間/動物の区別が、もはや通用しなくなっていることである。
東の議論は、政治嫌い・人間嫌いの個人(そのモデルがルソーである)が、その動物的欲望の次元においてひそかに他人と通じあうという二層構造を前提としてきた。しかし、2010年代に明らかになったのは、東の想定以上に人間が政治好きだということ、人間が自身の政治的立場を意識していることである。2010年代以降に全面化する「承認の政治」あるいは「承認をめぐる闘争」(アクセル・ホネット)は、人間が政治的無関心に埋没することの難しさを示している。少なくとも近代以降、人間はつねに自己と他者をつねに意識しており、承認欲求を持っており、同時に敵対勢力への攻撃の機会をうかがっているのである。
人間は、動物的なまでに自らの動物性を否認し、他者ないし社会からの承認を要求し、「人間」たろうとしている。この人間たろうとする奇妙な動物は、熟議を通じて公共性をうちたてる「人間」にはなりえないが、かといって欲望に開き直って埋没できるほど「動物」になれるわけでもない。その者は「人間」と「動物」の極を不気味に行き来する。ヘーゲルであれば「自己意識」と呼ぶ人間の宿命的性向の回帰によって、言い換えればその人間たろうとするもう一つの破壊不可能な「欲望」によって、「ゼロ年代」の二元論は突き崩される。人間は、「孤独であるがままに/(動物として)システムを介して他者と通じ合う」という二層構造を生きることができない。私たちは「動物に−なる」(ドゥルーズ)ことができるだろうか?
4. 「ビューティフル・ドリーマー」のあとで
「ポスト・モダン」の「棲み分け」状況は、インターネットの登場によって、むしろ「接続過剰」(千葉雅也)の方向に進んだ。そのとき問題になるのは「島宇宙」の自閉ではなく、すべてが一体になった「生物都市」的ホラーである(図:諸星大二郎「生物都市」)。むろん現在の東はそのことに鈍感ではない。『観光客の哲学』(2017年)や「訂正可能性の哲学」(『ゲンロン12』2021年)はそのような問題意識から書かれている。現代社会は、各ネーションが、政治的には自身を独立したものと宣言しつつ(ナショナリズム)、身体あるいは経済の次元ではごちゃごちゃに混じり合い(グローバリズム)、もはや一つになっている共犯関係から見られることになるだろう。

「観光客」は、そうした共犯関係をすり抜け、無意識のうちに「他者」に触れる新たな主体のイメージから構想されてる。公/私のあいだに位置する「家族」もまたそのようなものとして読み返される。
しかし、このとき東は、『一般意志2.0』に見られたようなアーキテクチャ論をもはや捨てている。たしかに、意識的に他者に触れようとする努力ではなく、あえて「軽薄」な消費への欲望において他者との関係を考えなおすという点では東の議論は一貫している。ところが現在の東浩紀は、具体的なアーキテクチャのなかには夢を見ることができない。それゆえ、「哲学者」を自称しはじめた彼の仕事は、かつてなく思弁的で隠喩的に見える。
だが2011年以降の東について見るべきは、著作だけではない。この十年、東浩紀の中年期[6]は「実践の時期」だった。つまりイベントスペース「ゲンロンカフェ」(2010-)や放送プラットフォーム「シラス」(2019-)の運営である(『ゲンロン戦記』2020年)。こうしたプラットフォームは、従来から東が掲げてきた「横断的」な知を理念として持つだろう。しかし現在では東の努力はそれ以上に、外部のメディアから自立した知の空間を維持することに注がれているように見える。この局面に至って東に見え隠れするのは、動物的欲望によって人々が勝手にコミュニケーションしあうというあの「夢」のようなセカイ系的楽観ではない。いま東が挑んでいるのは、「売る」立場に立った者の「命がけの跳躍」であり、「行為action」を支える「制作work」(アーレント)の次元なのである。
諸権力から自立した「知の空間」は、古代より思想家たちが夢見てきたものでもあった。しかし、たとえば近代以降の大学は——いくら「象牙の塔」などと揶揄されようとも——国家権力や資本主義から独立したことが一度もない。「諸学部の争い」をみれば明らかなように、カントでさえ「哲学部」の自立性を守ろうとして、奇妙なロジックとレトリックを駆使せざるをえなかった。
かつて出版メディアと大学、ジャーナリズムとアカデミズムの制度的「棲み分け」を批判していたこの批評活動家は、その結託を前にして別の場所、こう言ってよければ自治空間を作らざるをえなかった。
自治空間、という語に、左翼アレルギーを持つ読者は反発するかもしれない。だが東によれば、「開かれていること」がそれ自体として賞賛すべきものであった時代も「閉じていること」がそれ自体として批判すべきものであった時代も終わっている(「訂正可能性の哲学」)。だとすればそのとき、まず必要なのは承認を求めて攻撃しあうような他者たちから遠ざかり、相対的に閉じた場所を、信頼しうる友人たちを作ることでなければならない。しかし他方で、またそれが自閉や自愛や他者排斥やホモソーシャルに陥らないためには、それをさらに相対的に外部に開き、さらに次の世代へと引き継いでいく必要もある。針の穴を通すような、それでいて柔軟体操のような「戦略」がなければ、そのような場所を持続させることはできない。言ってしまえば開きつつ閉じ、閉じつつ開くこと、これである。
袋小路に入りつつある「公共」を鋳直すチャンスがあるとすれば、おそらくそこにある。私たちはリベラルな理念としての「公共性」に期待し続けることも、消費への動物的欲望の集積が作り出す「公共性」に期待することもできない。むしろ、新たな「公共」をめざす私たちの批評活動が出発すべきなのは、具体的な「場所」である。
私たちは、思想家や批評家を読むとき、そのテクストを読むだけではなく、彼が何をなしたか・何をなすかを見なければならない。理論と実践、解釈と変革の緊張を欠いたあらゆる活動は、たんなる観念の遊戯か、党派的なアジビラのどちらか(いずれにせよ「趣味」)である。東の批評を駆動しているのは、『批評空間』を批判した九〇年代からずっと、既存の制度空間を批判しつつその外に自分の領域を作り、それを広げていくという活動家の実践だった[7]。だが現在、批評を標榜する者は、はたしてそのアクティヴィズムを引き継いでいるだろうか。政治活動の最大の弱点はいつでも後継者がいないことであり、あるいはノウハウを継承する意志の希薄さである。東浩紀以後、批評は制度を批判しつつ制度を創るような、そのような運動体でなければならない。
[1]東浩紀「ポストモダン再考——棲み分ける批評II」(『郵便的不安たちβ』所収、河出文庫、2011年)。
[2]東は「ポストモダン再考」で「現代思想」を「美学系」(蓮實重彦:東大表象文化論)、「批評系」(柄谷行人、浅田彰:『批評空間』)、「政治系」(高橋哲哉、鵜飼哲、石田英敬、小森陽一)の三領域に分割する。附言しておけば、これはきわめて「東大ローカル」な問題である。逆に言えば、東大周りについて語ることが知的状況を語ることとイコールになるような一種の集権性が存在した——おそらく今も存在する——のだろう。だが、権力や制度を論ずる「現代思想」の研究者がこうした権力性に敏感であるようには、少なくとも私には思えない。灯台下暗し!
[3]私はジャック・デリダのテクストを解読した著書で、デリダの「戦略」について述べている。森脇透青ほか『ジャック・デリダ 「差延」を読む』、読書人、2023年
[4]だから私は以下でデリダにもラカンにもジジェクにもクリプキにもハイデガーにもフロイトにも言及せずに記述を進めている。しかし実際に東浩紀に対して有効な論評を行おうと思うなら、その抽象的な概念装置と「実体化」の双方、さらにはその「再発明」の前後のずれに気を配る必要がある。そうした批判的考察は私の今後の課題となるだろう。
[5]以前私は『近代体操』創刊号で松田樹とともに藤村龍至にインタビューを行ったが、藤村はまさにそのような実感を抱き自身の方針を転換しつつあった。私は、宇野常寛がトーク・イベントで同様の総括を行うのも聞いたことがある。
[6]ところで、東浩紀の出発点にいる二人の思想家——ジャック・デリダと柄谷行人——が、同じく中年期に「実践」へと向かったのは、偶然だろうか。デリダは1974年、従来の大学制度を批判しつつ、あるべき知の制度を模索する活動団体(GREPH)を設立した(当時デリダ44歳)。それは現在まで続く「国際哲学コレージュ」の設立に至っている(1983年)。また柄谷は1991年、悪名高い(?)「湾岸戦争に反対する文学者声明」に発起人として関与したし(当時柄谷50歳)、また2000年にはNAMの活動を始動させている。ゲンロンカフェのオープンは2013年である(当時東43歳)。デリダは2004年に74歳で死に、柄谷は81歳にしていまだ好調(?)だが、東浩紀の「晩年様式(レイト・スタイル)」はいかなるものになるのだろうか。
[7] 私はしばしば、東の実践を、外山恒一が行っている教養合宿のような試みと比較したい欲求に駆られる。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
著者プロフィール
森脇透青(もりわき・とうせい)一九九五年大阪生、京都大学文学研究科博士課程所属。批評家。専門はジャック・デリダを中心とした哲学および美学(学術振興会特別研究員DC2)。批評のための運動体「近代体操」主催。著書(共著)に『ジャック・デリダ「差延」を読む』(読書人、2023年)。『週刊読書人』にて月一論壇時評「論潮」を連載中。Twitter : @satodex
次回は7月26日(水)更新予定。住本麻子さんが斎藤美奈子を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
