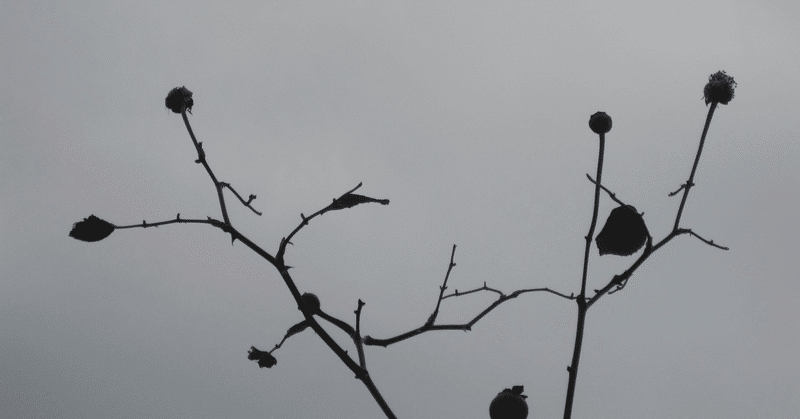
私の人生における「グレー」の苦しみ
グレー(gray)
《「グレイ」とも》
1 灰色。ねずみ色。
2 白髪交じりの髪。グレーヘア。
3 どちらでもない中間的な状態や態度。
記事を開いていただき
ありがとうございます!
私は
「人生迷子を一人でも減らす」ために
日々、情報発信等の活動をしております。
「人生迷子」とは、
「この先どう生きたらいいかわからない」と
人生の大きな方向性を見失った状態です。
なぜ、そのような活動をしているか
というと
私自身が人生に迷い苦しんだからです。
今回は、私が直面した
「グレー」の苦しみについて
お話しいたします。
ご共感いただける方が
いらっしゃいましたら、
スキ、コメントいただけますと嬉しいです。
私が直面した3つのグレー
グレー、というのは
冒頭にも引用した通り
灰色のことです。
この言葉は、白でも黒でもない
「どっちつかず」「曖昧」
という意味でもよく使われます。
この
「どっちつかず」の状態が苦しみを生む、
ということを想像できますか?
もし、思い浮かぶ方がいましたら
私の経験と共通する部分が
あるかもしれません。
私が直面した「グレー」とは、
以下の3つです。
①適応障害というグレー
②発達障害グレー
③人生へのグレーな不安
では、
それぞれ見ていきましょう。
適応障害というグレー
新卒から公立高校の教員となった私は、
6年間勤めた後に、転職をしました。
希望を持ってベンチャー企業に就職するも
環境の変化についていけなかったこと、
自分を追い詰めすぎたことで心身を崩しました。
心療内科にかかって
医師からいただいた診断は、
「適応障害」というものでした。
「適応障害」って何?
という方は、
以下の図がわかりやすいかと思います。

心療内科医の森下先生によれば、
適応障害は、ごく普通に働いていた人が何らかのストレスにさらされ、最初はうまく対処できていたのにやがてできなくなり、(略)心と身体に支障をきたしていく。そういう疾患です。
と解説しています。
この説明、とてもシンプルですが
一度でも経験したことがある身からすると
「自分のこと見てた?」
と思うくらい
実感を持って読むことができます。
私も転職後2ヶ月くらいは特に、
やる気に満ちていましたし、
普通に楽しく働いていたのです。
しかし、3ヶ月あたりから
「あれ、うまくいかないな」
ということが増えていきました。
結局、転職4ヶ月目の終わりに
起き上がれなくなるなどの症状が出て、
休職、そして最終的に退職となりました。
さて、この「適応障害」
上の図でもわかる通り、
グレーな立ち位置の疾患です。
人によって症状はさまざまなのですが、
ストレスの要因である職場を離れると
症状が良くなる人もいます。
そうすると
「え、ただのサボりじゃん」
という声も世の中から聞こえてきそうです。
「うつ病とか、パニック障害とかより
楽なんでしょ?」
そうした扱いもされやすい疾患です。
こうしたことは、
自分自身でも思うのです。
「自分が苦しんでいるのは、
ただ自分が弱くて怠けているだけ?」
「もっと苦しんでいる人に比べたら、
こんなの我慢できるはずなのに」
「いっそうつ病と診断された方が、
社会的には言いやすいのに」
「ストレス以上うつ病未満」
そうした意識が、
適応障害当事者を苦しめます。
これは人から聞いた話ですが、
医療機関にかかった時に、
まずは「適応障害」で診断されて、
職場から離れて時間が経っても
症状が良くならない場合は、
「うつ病」と診断されることが
あるのだとか。
もちろん、お医者さんにも
よるところかとは思いますが、
症状は同じでも
「まだうつ病とは言い切れない」
というパターンがあるのです。
ということは、
「適応障害だから、うつ病より苦しくない」
とは一概には言い切れないのです。
もし、かつての私のように
そのグレーさに苦しんでいる人がいたら
そう伝えたいなと思います。
そもそも重要なのは、
当人が今苦しいという事実だけです。
「あの人より楽だ」とか
「私の方が苦しい」とか言うのは
何の意味もありません。
ちなみに、この疾患について
雅子皇后のニュースで聞いたことがある
という方も多いのでは。
あれだけのエリートが、
皇室に入ったことの環境の変化で
心の調子を崩してしまうのです。
「ごく普通に働いていた人」も
誰でもなる可能性がある疾患である、
ということは強調したいところです。
適応障害という疾患
これが1つ目のグレーです。
発達障害グレー
私は先に書いた適応障害の関連で
休職中に発達障害の検査を受けました。
新しい環境で、気をつけても起こるミス
これに発達障害もかかわっているかもしれない
そう考えたのです。
心療内科にかかる方で、
同時に発達障害の検査を受ける方は
多いのだそうです。
親類にADHDなどの傾向があるのも
検査を受けた理由です。
発達障害は、遺伝の関係が大きいです。
結果は、
発達障害グレーゾーンとの診断でした。
「やっぱりな」という落胆と
「傾向が強いわけではないのか」という安堵
どちらの気持ちもありました。
心のどこかで、「発達障害」と診断されることに
少しばかり救いを求めていた気持ちも
あったと思います。
はっきり「発達障害」だと診断されれば、
開き直って、「発達障害だからできること」
それを探していけるような気がしていました。
でも、現実はグレーです。
「あなたの努力不足ですよ」
そう突きつけられているような
気持ちにもなりました。
もちろん、クリニックの方が
そんなことは言いません。
ただ、診断がグレーということは
「努力でなんとかできる範囲」です。
これは、
「努力でなんとかなる」という希望でもあり、
「努力しないとなんとかならない」という責苦
でもあります。
もちろん、もっと顕著な症状がある方は、
社会において苦しんでいます。
そうした方の書いた書籍は、
とても参考になります。
(借金玉さんの本など)
でも、これも
先の適応障害と同じです。
発達障害の傾向が弱いからといって
その苦しみが軽いとは限らない。
必要なのは、誰かと比べることではなく
そうした条件にある自分がどう生きていくか
そこにフォーカスすることなのです。
今、私は、
自分に言い聞かせる気持ちで書いています。
発達障害は、条件の一つでしかなくて、
その上でどう生きるかは選べるのです。
この発達障害グレーゾーンが、
私の2つ目のグレーです。
人生へのグレーな不安
3つ目のグレーは何かというと
人生へのグレーな不安、です。
「なんだそれは」
と思われるかもしれません。
これは、冒頭にも書いた
「人生迷子」による不安のことです。
私が「人生迷子」と表現している状態には、
なりやすい2つの時期があります。
それは、
(1) 社会に出て数年経ち、今後の人生に不安を覚える20代半ば〜30代
(2) 人生の節目を迎え、セカンドライフに迷いがある40代半ば〜50代
です。
心理学では、
(1)を「クォーター・ライフ・クライシス」
(2)を「ミッド・ライフ・クライシス」
と呼んでいます。
このうち
「クォーター・ライフ・クライシス」での
「人生迷子」に、私はまさになっていました。
20代半ば〜30代の「人生迷子」の特徴として、
「人生全体への漠然とした不安」
があります。
社会に出て数年経つと、
仕事のこともわかって先が見えてくる、
自分の結婚や出産で生活が変わる、
そうした人生の局面に直面します。
社会に出て
いろんなことが見えてきただけに
「自分の人生、このままでいいのか?」
と迷い悩むのです。
私の場合、第一子が生まれたこと、
教員を続けることのへの違和感などがあり、
人生の方向性を見直し始めました。
私は、授業の時間は好きでしたが
部活動や雑務でプライベートの時間を
奪われることは好みませんでした。
私は、家事も育児も好きですし、
子どもや妻との時間を
もっと大切にしたい。
また、教員として出会った人に
正直なところ「この人みたいになりたい!」
と思える人がいなかったこともあります。
「先が見えてしまった」感覚です。
教員という職業ではなくても、
同じように仕事に慣れたことや
ライフスタイルが変化したことで、
漠然とした不安にさいなまれる方は、
多いと思います。
もしかしたら、
この記事を読まれているあなたにも
当てはまるかもしれません。
こうして、私の
「自分の人生、このままでいいのか」
という漠然とした不安は強くなり、
転職という具体的な行動に至ります。
結果、上に書いた通り
適応障害となることで、
さらに迷いを深めることとなりました。
「漠然とした不安」と言葉にすると
ふわっとしていて
あまりつらいように思えませんね。
しかし、
「漠然としているからこそ」
苦しい面があるのです。
例えば、
「明日、重役の前でプレゼンをするから
とても不安だ」
という場合、とてもはっきりしていますね。
プレゼンが終われば、結果はさておき
「プレゼンをすること」への不安は
消えてしまいます。
しかし、
人生への漠然とした不安は、
「これをすれば終わる」
ということが不明確です。
だから、自己啓発に手を出してみたり、
自分探しの旅に出たり、と
いろんなことをするのです。
でもやはり解決をできず、
ジリジリと焦りと不安を募らせてしまう。
そうなりがちです。
私の場合は、
「人生の指針となるテツガクを明確にすること」
それにより、
漠然とした不安から抜け出すことができました。
(人生迷子について、
詳しくはこちらの記事をお読みください)
これが、
私の3つ目のグレー
人生へのグレーな不安です。
グレーから色彩の世界へ
さて、ここまでで
私が直面した3つのグレー
その苦しみについて書いてきました。
私の場合、
人生へのグレーな不安は解決できました。
適応障害についても寛解し、
セルフケアのスキルを身につけています。
とはいえ、油断はなりませんが。
しかし、
発達障害グレーについては、
一生付き合っていくものです。
だから、そのグレーに伴う苦しみとも
一生うまく付き合っていく
必要があります。
苦悩と死は人生の一部である。従って、苦悩と死を拒否するということは、すなわち人生そのものを拒絶するということに繋がるのである。
私たちが目指すべきは、
そうした苦しみが悩みが
一切ない世界ではありません。
それを手に入れようとすれば、
薬物や過度のアルコール摂取など
長期的に自分の人生を損なうものに
囚われてしまうかもしれません。
大事なのは
苦しみや悩みを一切拒絶するのではなく、
それらと出会いながらも価値のある人生を歩むことです。
発達障害がグレーでも、
私の人生全体を見れば
1つの要素でしかありません。
私が人生において大切にしたいこと、
自由や尊重、成長、愛、知性
そうしたものは、私たちの人生に彩りを加えます。
一つがグレーであることにこだわり過ぎず、
人生全体を色彩で満たせばいいのです。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございます!
冒頭でも書きましたが、
私は、「人生迷子を1人でも減らす」ために
日々活動をしております。
「人生迷子」を減らすために
運営している具体的なプログラムが
こちらです!
また、
「人生迷子」についてもう少し知りたい
という方は、こちらの記事をお読みください。
よろしければ、
自己紹介も兼ねたこちらの記事も
ご覧ください。
スキ、コメント、シェアいただけましたら、
とっても嬉しいです!!
よろしければサポートをお願いします!いただいたサポートは活動費に使わせていただきます。

