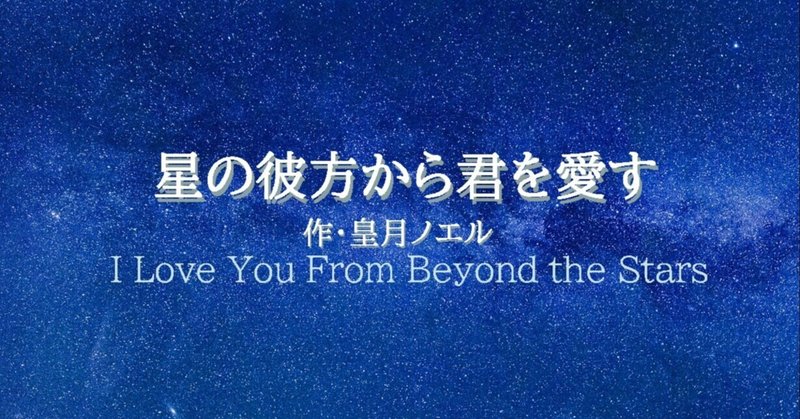
3 星の彼方から君を愛す
前の話を振り返る
https://note.com/noel_story/n/n5d005a9b05ca?magazine_key=m11e92888e5c2
あれがたった8ヶ月前のことなんて、まだ信じられない。
もし何もなければ、私たちは婚約するところのはずだった。
君から連絡がきたのは、もうすぐ定時という頃のこと。
「入院することになった」
「え!?」
自分のデスクで大声を上げてしまい、周りから何事だという目が集まる。
とっさに身を縮めた。
なんで。どうして。詳しく聞きたいのに、動揺に震える手では、返事を打つのにさえ苦労する。
「どうして。どこの病院?」
何度も間違えて消してを繰り返し、ようやく返事を送る。
君の返信は早くて、教えてくれた病院は通勤電車の沿線だった。
「終わったらすぐ行く」
私は実際にそうした。
職場と駅のざわめきを駆け抜けて病院に入ると、開いた静寂が私を包みこむ。
清潔すぎる静けさが、速まった鼓動を強調して落ち着かない。
案内された3階の病室に、君はいた。
「ああ。来てくれたんだ」
君は窓の外を見ていた。
私と看護師さんが近づく気配で振り返り、いつもの、目じりをきゅっと細める笑い方をする。
今は、それが痛々しい。
いつもの笑顔。
見慣れない入院着。
白い腕に刺さった点滴の針。
君のいつもが周りの非日常を際立たせるから、私は一緒に笑えない。
君は努めて明るく、決して楽観できない病名を告げた。大丈夫、何も心配することはないよと言いながら。
私には何の効果もなかった。むしろ、君の明るさがただの空元気に見えて、私の方が虚しくなる。
どうしていつも通りでいられるの? 怖くないの? 怖がってる私の方が不自然なの……?
とっさに、何も言えなかった。
いつも何か言い残したことがあるような気がして、私は毎日見舞いに訪れた。
君は元気な日もあれば、検査や処置で疲れきっていることもあった。
そして毎日顔を合わせていても分かるくらい、急速に痩せていった。
「……私の他に、誰かお見舞いに来たりはしたの? 職場の人とか……。ご家族、とか」
あるとき、つい気になって尋ねてしまった。
私が来る時、いつも君はひとりで窓の外を見ている。それがたまらなく孤独に見えて、不安にも似た思いに駆られてしまったのだ。
一方の君はこれが当然であるかのような口調だった。
「職場の人が1回来ただけだよ。儀礼的にね。家族は、きっと来ないよ。連絡は、いってるのかもしれないけど」
君が家族と距離を置いているのは、今まで一緒にいて知っていた。
計画しようとしていた実家への挨拶や両家顔合わせも、君はどことなく気乗りしない雰囲気だったから。
「どうして……。子どもが入院してるのにね」
それも、とても深刻な症状で。
私は君が家族を避けていることを尊重していた。否定も批判もなかった。
ただ本当の意味では、君が距離をおいている理由を理解していなかったのだ。
君は遠い目をする。
「彼らにとって、僕はどうでもいい存在なんだよ。馴染み方が分からなかったんだ。失ってきた友達と同じでね。少し上手くなった時には、もう僕たちは決定的に違っていた」
私に目を戻す。いつか話題にした時と同じように、君は困ったように笑った。
手を伸ばして、そっと私の袖を撫でる。
「今日は検査つづきで、疲れてて。……眠くなってきちゃった。
少し寝かせてもらっても良いかな」
言外に、今日の面会はこれで終わりにしようと言っている。
私は素直に席を立った。
「こちらこそ。気づかなくてごめんね。ゆっくり休んで」
忘れ物がないか確かめる私を、君はいつになくじっくりと見つめている。
今思えば、私の姿を脳裏に焼きつけようとしているみたいに。
「今日は、来てくれてありがとう」
「やだな改まって。
そうだ、明日は新刊の発売日だよ。買って持ってくるから」
「楽しみにしてるね」
私は病室を後にした。
結局、君が新刊を読むことはなかった。
病院から電話がかかってきたのは、よりにもよって、本屋でまさにレジに並ぼうとしていた時。
私は本を台に戻して、慌てて電車に飛び乗った。
それでも間に合わなかったのだ。
君がいた病室の前で、看護師さんと女性が立ち話をしている。
近づいていくと、この2ヶ月間で顔見知りになっていた看護師さんが私に気づいてくれた。
「あっ。この方が、いつもお見舞いに」
言葉を受けて、立ち話の相手が私の方を振り向いた。
眉が気が強そうにつり上がった、50代後半くらいの女性。くすんだ赤い口紅を引いた唇が、不快そうに歪んだ。
「あなたが、あの子と付き合っていたっていう子?」
投げかけられた問いで私は悟る。
この人が、きっと君のお母さんだ。
無意識に目が泳いで、君の顔立ちと似ているところを探してしまう。
一方、社会人としての私は礼儀正しく頭を下げていた。
「初めまして」
名前を名乗ると、その人はますます不快そうに鼻を鳴らす。
「あなた、人を見る目がないのね」
「え?」
予想もしなかった言葉を投げつけられた。
驚いて顔を上げる。刺すような言葉。
ぶつかった視線は、私を透かして君に投げかけられているようにも見えた。
吐き捨てるようだった。
「あんな変な子のどこがいいのよ。死んでくれてせいせいしたわ。
いつも人の心を読むようなことを言って、気味が悪い。
家を出て行ってせいせいしたと思っていたら、こういう時の手続きには親が駆り出されるんだもの。面倒ったらありゃしない」
理解できなかった。
「……それ、本当に言っているんですか?」
「は? そうだけど」
脳が追いついていかない。
どうして、この人は君のことをこんなに悪く言うの?
本質を見抜くのは、君の良いところだと思うのに。
気味が悪いなんて、考えたこともなかった。
私が驚きで声を失っている間にも、その人の目はますますすがめられていく。まるで私も「変な子の同類」であるかのように。
「じゃ、そういうことだから」
「……ちょっと待ってください!」
食い下がって、せめてお葬式とお通夜の日付と場所を尋ねようとする。
まだ決めていないと言うので、半ば押し付けるように私の連絡先を渡した。
最後に君とお別れがしたかった。
連絡は、来なかった。
つづきを読む
読んでくださりありがとうございます。良い記事だな、役に立ったなと思ったら、ぜひサポートしていただけると喜びます。 いただいたサポートは書き続けていくための軍資金等として大切に使わせていただきます。
