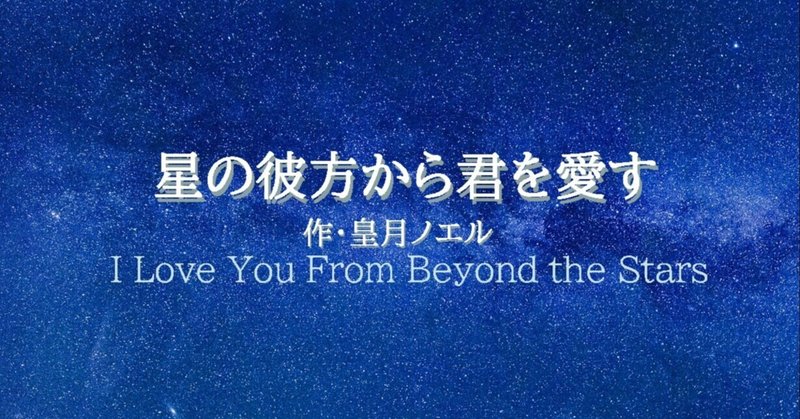
2 星の彼方から君を愛す
前の話を振り返る
「――ねえ、時間制限ってある?」
「この電話かい? 特にはないよ。どうしたの?」
「それなら、今の君がどんな風に暮らしているのか教えてよ」
未知の世界への関心も、もちろんあった。
でもそれ以上に、君の声を聞いていられるなら、なにについてでもいい。
私にまだ謝る勇気はない。
「いいよ」
君は語った。
「まず、目が覚めたら、僕は背の高い本棚が並ぶ空間に倒れていた。まるで図書館みたいなところ――いや、実際に図書館だった。通路は奥深くて、薄暗いもやの中に消えていた。見上げると、書棚もずっと高いんだ。梯子もなくて、どうやって本を取るんだろう? って思ったのを覚えてる」
君は図書館を強調した。
それは無論、図書館という場所が私たちふたりにとって思い出深い場所だからだ。
私たちは図書館で出会った。というより、私が行った図書館に、君がいた。
君に気づいたのは、図書館に通い始めて3回目のこと。
文芸書のコーナーに、いつも同じ人がいることに、急に思い至ったのだ。
文芸書のコーナーは奥まっていて、気軽に見て回るだけの人はなかなかやってこない。
君は相当な読書好きなのかな、というのが私の勝手な印象だった。
私たちは好きな作家の傾向が似ているらしく、隣り合った棚を眺めることが多かった。
そのうち君も時々やってくる私を認識したようで、目が合うと会釈を交わす間柄になった。
ある時、いつものように本を眺めていた君が、ふとその中から一冊を抜き出した。
「あっ」
思わず声を上げてしまう。目が合って、気づいたら私は話しかけていた。
「それ。私前に読んだですけど。すごく良い話で」
「あっ。そうなんですか」
「はい。おすすめです。あの、よく文芸書コーナーにおられますよね。小説が好きなんですか?」
来るたび見かけるものだから、勝手な親近感を抱いてしまっていた。
好意的な反応が重なるうちに、どうやら君もそうかもしれないと思えてくる。
私たちはその場で少し立ち話をして別れた。
次に会った時は館内のカフェでおしゃべりをして、その時間がどんどん長くなって――どちらからともなく、お付き合いが始まっていた。
そんな君がシリウス星にある図書館で目覚めたというのは、なんだかありそうな話だ。
「僕が初めて見る図書館を見回していると、気づいたらそばに男の人が立っていて、僕を待っていたと言った。
彼は僕の兄で、シリウスから、地球で暮らす僕を見守っていたそうなんだ。
その言葉を聞いた時、僕はすべてを思い出した――病院、地球で生きていた僕の死、そして何より、残してきてしまった君のことを。
同時に分かったんだ。僕の本当のルーツはここにあったんだって。
この碧い、星空を固めたような世界にね」
君の口から語られるシリウスは魅力的だった。
1日中頭上に広がる碧い星空。
地球人より背が高く、ほっそりしているシリウスの人々。
果てしない世界に広がる、想像もつかないほど広大で幻想的な風景――夜空を流し固めたような大都市、見渡すかぎりの草原、空との境界も分からないような海。
君の言葉が、私の想像力をかき立てる。
まるで私も、君と同じように星空の中を飛んで、じかに未知の世界を体験しているような気がした。
「水に触れても体が濡れることはなくて、まさに星空の中を泳いでいるみたいなんだ。
星をかきわけて進むんだよ。
それから僕の部屋はマンションの高層にあってね、すごく見晴らしがいいんだ。
友達を招いて一緒に遊んだり、思い浮かべるだけで遠くに移動することもできる。
そう、友達もできたんだ。
ここではみんなお互いの考えていることが分かるんだけど、ひとつのことについて深く考えたり、互いの意見を話し合ったりすることが、楽しみのひとつになっててね……」
私は君の熱っぽい口調に安堵する。
君は、ようやく自分の居場所を見つけたんだね。
時々さ、自分がまったく違う世界の住人だって思うことない? 僕はあるな。
いつか夜道を送ってくれながら、君が呟いていた言葉が思い出される。あれは付き合い始めたばかりの頃だった。
私は君のすべてを肯定していた。
むしろ批判したり、否定したりする必要のあるところなんて何ひとつ見つからないと思っていた。
その思いは今も変わらない。だから君も心を許して、思ったことをそのまま私に話してくれていたのかな。
君は私に出会うまでを振り返って、ずっと周りに馴染めなかった、誰からも理解されなかったと言った。
それは君自身の深い視点や、鋭い指摘を口に出してしまう欠点のせいなんだと。
けれど私は、まさに君のそういうところが好きだった。
誰とも違うところを見ている、静謐な雰囲気が。
「そうだ。こっちの本はすごく不思議だよ。もちろん、ページには文字が書いてあるんだけど、文字を目で追わない読み方もできるんだ。見開きのページをざっと眺めて、そこに込められたエネルギーから物語を『読む』やり方。目で文字を読むよりずっと臨場感があって、まるで自分も本の中に入りこんでしまった感じがする。
きっと君も気に入るんじゃないかな。
誰でも物語を書いて、図書館に収めておくことができるんだ。
町にひとつある大図書館に、すべての本が収められている。僕が目覚めたのもここなんだ。すべての本が集まっていれば、誰でも借りて読むことができるでしょう。
図書館の真ん中には特別な端末があって、他の惑星の芸術にも触れられるんだ。
地球の小説を読み直したりとか。
ここでは芸術がすごく大事にされていてね。
僕は本が好きだから特に本にフォーカスしているけど、絵画でも、音楽でも、彫刻でも……何かを作ることに関しては、全部に同じことが言えるんじゃないかな」
「うん」
相槌を打つ声が震えそうになって、全身がぎゅっとこわばる。相反する感情が一気に押し寄せてきて、どうすれば良いか分からなくなった。
君の声から伝わってくる。
君は今、健康で幸せだ。
もうなじめない感覚に悩むこともなく、好きな本を読み続けている。
君の幸せが、私にとってもすごく嬉しい。
同時に、寂しい。
何光年かも私には分からないほど、君は遠く離れてしまった。
私はもう元気な君の隣を歩くことができない。
一緒に笑うことも、肩を寄せ合う感覚も、未来を一緒に生きていくことも。
この電話だって、切れてしまったら次にいつ繋がるか。
それとも、この一度きりで終わりなんだろうか。
思い至ると、寂しさばかりが大きくなる。
――謝らなきゃ。
唐突に使命感にも似た感覚が湧いた。
「それで、そっちはどう? 最近はなにしてた?」
君は無邪気に問いかけてくる。私は答えに窮してしまった。
謝らなきゃ。その気持ちに嘘はない。
でも、怖い。
もしも、「実はまだ怒ってる」と言われたら?
「あの時は傷ついた」と言われたら……。
私はどうしたら良いか分からなくなりそうだ。
いっそ何もなかったことにして、他愛ない話だけでこの電話を終わらせてしまおうか。
「……」
迷っている間にも、刻々と無言の時間が過ぎていく。
「あれ、どうしたの?」
君の不思議そうな問いかけ。
迷っているのが苦しくなって、私は詰めた息を吐き出すように口を開いた。
「ごめんね。最後に嫌な思いをさせるようなことを言って」
「……」
唐突な言葉に、さすがの君も黙りこむ。
私はさらに言い募った。
「本当はあの時、あんな話題を出されて嫌だったんじゃない。
だから私を帰したんでしょう。
私は私のせいで、君にお別れも言えなくて……。
申し訳なかったと思ってるのに、どう伝えたら良いか分からなくなっちゃった。
君に謝れなかった。
それがすごく、すごく気がかりで、自分が許せなくて」
「そんなこと……」
「ごめんね。ごめんなさい」
涙が出て止まらない。
思い出すだけで、息が詰まりそうな記憶。
ひとつ蘇ると止め方も分からなくて、私は吞まれるように過去へと運ばれていった。
つづきを読む
読んでくださりありがとうございます。良い記事だな、役に立ったなと思ったら、ぜひサポートしていただけると喜びます。 いただいたサポートは書き続けていくための軍資金等として大切に使わせていただきます。
