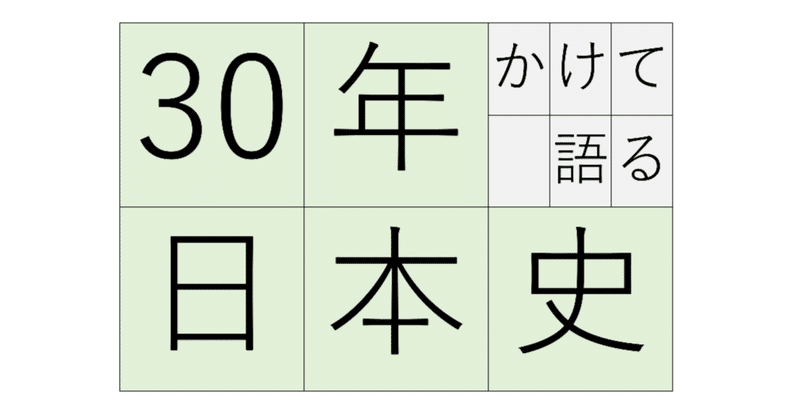
30年日本史00563【鎌倉前期】曽我兄弟の仇討ち 兄弟の決意
河津祐泰が非業の死を遂げたとき、二人の息子がいました。数え年で5歳の十郎と3歳の五郎です。
その兄弟の母親・満江御前(まんこうごぜん)は、夫を失った悲しみに打ちひしがれ、子を育てる気力をも失ってしまいました。子を他家に養子に出して自らは出家しようとしますが、伊東祐親は孫たちの将来を気遣い、満江御前に再婚をしきりに薦めました。こうして、満江御前は二人の息子を連れて曽我祐信(そがすけのぶ)に嫁ぐこととなりました。これ以後、兄弟は曽我十郎・五郎と名乗るようになります。
「曽我物語」は、この兄弟の哀れなエピソードを数多く記しています。9歳と7歳になった兄弟は、名月の夜に庭に出て空を飛ぶ鴈を眺めていました。兄の十郎が
「あの5羽連れだって飛ぶ鳥を見ろ。2羽は両親で、3羽は子たちだろう。物言わぬ動物ですら父母がいるというのに、我々はどうだ。曽我殿は誠の父ではない。我らの父は河津殿というのだ。父が生きていれば一緒に狩りに行くこともできただろうに」
と述べ、兄弟で額を合わせて泣いたというのです。
さらに、このようなエピソードもあります。幼い兄弟は、いつか父の仇を討ちたいと考え、竹とススキで作った弓矢で仇討ちの練習をするようになります。それを知った満江御前は驚いて二人を呼び寄せ、泣きながら
「二人は鎌倉殿(頼朝)に敵対した伊東祐親の孫であることを忘れてはなりません。仇討ちをしようなどという思いは捨てなさい」
と戒めます。
確かに、伊東家の人間は鎌倉幕府から見ると言わば逆賊ですから、既に危険分子扱いされていても不思議ではありません。母親としては、息子たちにこれ以上の危険を冒してほしくないというのが人情でしょう。
母の思いを知った兄弟は、父への思慕の思いを断念せざるを得ないのかと涙に暮れました。
その後兄の十郎は13歳で元服し、「曽我十郎祐成」と名乗ることとなりますが、弟の五郎は寺に入って僧侶を目指すよう、母から説得を受けます。義父の曽我祐信にとって二人の男子を養う余裕がなかったということもあるのでしょうが、おそらく兄弟を引き離すことによって仇討ちを諦めさせようという意図もあったのでしょう。五郎はやむなく、元暦2(1185)年11月に箱根権現(現在の箱根神社)に入室することとなりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
