読書メモ:M・ミッチェル・ワールドロップ『複雑系 生命現象から政治、経済までを統合する知の革命』第1章〜第4章
1977年のノーベル化学賞受賞者であるイリヤ・プリゴジンは、「なぜこの世には秩序と構造があるのか? それはどうして生まれるのか?」を問いとして掲げた。そして〈自己組織化〉という発想を持ち出した。後にサンタフェ研究所に参加する物理学者ブライアン・アーサーはプリゴジンの著作を読み、多大な影響を受ける。
〈自己組織化システム〉は自己強化に依存している。つまり「条件が整っていれば、小さな影響が除去されるのではなく拡大される傾向」のことをいう。工学の世界でいう〈ポジティブ・フィードバック〉。
たとえば鍋にスープが入っている。火にかけられていなければ、スープの表面の高速分子が大気中の低速分子と衝突して、エネルギーが大気に伝達されていき、スープは冷める。〈熱力学第二法則〉である。
火をごく弱火でかけ始めると、システムは平衡状態ではなくなるが、何かを乱すほどではない。さらに中火にしていくと、熱エネルギーが増加したためにスープの平衡状態は不安定になる。スープの分子のいくつかがランダム運動を始め、成長していき、流体の一部が上昇し、また一部が下降する。こうしてスープが沸騰して、煮えていく。
こうした〈自己組織化システム〉は、自然にあまねく存在する。レーザー(光子が自己組織化し、すべての光子を同じ動きに保つ強力な単一光線へと変じたもの)、ハリケーン(太陽エネルギーが風を起こし、雨になる水を海から吸い上げる)、細胞(食糧からエネルギーを取り込み、熱と老廃物によってエネルギーを排出する)、そして遺伝子の発現調節(ジャコブとモノーの研究によるオペロン説)……
新古典派の経済学では、〈ネガティブ・フィードバック〉によって経済が支配され、調和と安定、均衡状態の中にあると仮定されていた。〈収穫逓減の法則〉つまり「小さな効果は消え去る傾向にある」、と考えられていた。肥料を二倍にしても生産は二倍にならない、なにかに関してすればするほど後のものが役立たなくなったり益が少なくなる、と。
しかし〈収穫逓増の法則〉こそが、経済を動かしているのではないかとアーサーは考えた。安定しない市場で、変動的な動きを考慮すると、「持てる者はさらに与えられる」という秩序と構造が生まれてくる。
〈ポジティブ・フィードバック〉と〈ネガティブ・フィードバック〉が結合するとき、〈パターン〉が生まれる。歴史においても、些細な偶然が〈収穫逓増〉によって歴史的に逆戻りできないものに拡大していく。
* * *
コンピュータ・キーボードはQWERTYの配列(上段の列の左寄り6文字を並べた名称)をしており、実質的に西洋圏のすべてでこのパターンが使われている。これはかつてのタイプライターがあまり速くタイピングされると動かなくなることから、1873年にクリストファー・ショールズという技師がタイピストの手を遅くするために考案した。
しかし、その後レミントン・ソーイング・マシン・カンパニーがこの配列のキーボードを大量生産し、多くのタイピストがこのシステムを学んでタイピングし始めたため、他の会社もQWERTYの配列でキーボードを作るようになった。
〈予測不可能性〉をもつ偶然性が、〈収穫逓増〉によって〈ロック・イン〉された例である。
ちいさな偶然の重なりによって〈ポジティブ・フィードバック〉を受けたことで、いくつもある可能性のうちの一つが〈ロック・イン〉されたのだとしたら、その結果は必ずしも最上のものではないかもしれない。
* * *
経済が複雑なものになっていくプロセスには、可能な技術のネットワークが存在する。相互に結びつき、可能なものが増えるにつれて成長していくものだ。このネットワーク下では、生物学的なエコシステムと同様に、進化的創造と大量絶滅という出来事が起こり得る。
たとえば自動車のような新技術が発明され、馬という古い技術に取って代わる。すると、馬とともに鍛冶屋、ポニー速達便、水飲み場、納屋、馬の手入れをする人間が消えていく。馬に依存していた技術のサブ・ネットワーク全体が突如として崩壊する。一方で、自動車のための舗装道路やガソリンスタンド、ファーストフード店、交通信号などが生まれ、物やサービスの新しいネットワークが成長を開始する。
このプロセスが〈収穫逓増〉の典型例であり、〈ロック・イン〉という現象を動かしている。特定の技術へのニッチの依存度合いが大きければ大きいほど、その技術を変えることは難しくなる。
* * *
生物学者スチュアート・カウフマンは、〈秩序〉と〈自己組織化〉の概念を研究していた。ジャコブとモノーがノーベル賞を受賞した遺伝子回路に関する研究に彼は注目した。「どんな細胞にも、いくつかの調節的な遺伝子が含まれ、それらの遺伝子はスイッチの役割をもっており、互いに他の機能をオンやオフにできる」という研究だった。
しかし遺伝子が互いにでたらめにスイッチをオン・オフしあっていたら、細胞は無秩序に激しく揺れ動いてしまう。「ゲノム全体が安定した、一貫性のある、活動遺伝子の〈パターン〉に落ち着くのはなぜか」を考えなければならない、とカウフマンは推論した。ゲノムは逐次処理方式ではなく、遺伝子の指令のほとんどもしくはすべてを並行処理で同時に実行しているのだろう、と。そう考えると、遺伝子の調節システムの秩序は自然なものであるはずだった。
ダーウィンが述べたように、遺伝子の精緻さはランダムな変異と自然淘汰によってもたらされたものだろうが、生命の組織化それ自体は遺伝子のネットワーク構造から生まれるものなのではないか。生命の物語は、「偶然の物語」であると同時に「秩序の物語」でもあると、カウフマンには思えた。そして複雑なシステムについての自然法則がどのように見つけられるか、どこから秩序が生まれるのかを考えていった。
* * *
カウフマンのいう〈秩序〉とは、アーサーのいう〈混乱〉を意味していた。経済的均衡という市場法則のネガティブ・フィードバックから自己組織化してパターンを形成しようとする複雑系の絶えざる作用、つまり〈創発〉を経済学者であるアーサーは見つけた。そして生物学者であるカウフマンは、法則などないダーウィンの偶然と自然淘汰の世界においてポジティブ・フィードバックを扱い続けてきた。二人は正反対の方向からアプローチして、本質的に同じ概念に達していたのだ。
カウフマンは自己触媒作用の実験によって、複雑さはある閾値を超えると、一種の相転移を見せることを明らかにした。化学反応が単純で相互作用の複雑さのレベルが低いと、何も起きない。システムが〈亜臨海〉だから。だが、もし相互作用の複雑さが十分なら、システムは〈超臨界〉になり、自己触媒作用が必然的に生じて、無から秩序が生まれる。
五億七千万年前、海藻と浮きかすで覆われていた世界が突如として複雑な多細胞生物を生み出していった。カンブリア紀のことである。これにはおそらく、まず多様性を引き起こす臨界点に達してから爆発する必要があった。海藻よりもすこし複雑な何かが生じ、それがプロセスに作用してまた新しいプロセスを生み出していく爆発的プロセスを起こしたのだろう。
これを経済学に当てはめると、こうなる。複雑さが閾値より下にあるとき、国家はごく少数の主産業に依存し、国の経済は脆弱で不活発なものになる。もしバナナを生産することがすべてであれば、バナナが増える以外、何も起こらない。だが、国が経済の複雑さを限界点以上にもっていけば、経済成長とイノベーションの爆発的増加が見込める。
この相転移の存在によって、貿易が繁栄に繋がることも説明できる。一国では閾値に達しなくとも、両国が貿易を開始することで、二国の経済が相互に結びつき、より高いレベルの複雑さを備える。そして一体化したシステムが閾値を超え、外に向かって爆発するようになる。
* * *
「サンタフェ研究所」は、ジョージ・コーワンが構想し、ノーベル賞受賞者の物理学者マレー・ゲルマン、物理学者フィル・アンダーソン、経済学者ケネス・アローらが賛同し、1984年に設立に至る。
コーワンは、原子爆弾の開発を目的として創設されたロス・アラモス研究所の研究部長だった。戦後には、コーワンを含めマンハッタン計画に参加した多くの科学者が政治的な活動グループを作り、軍ではなく文民管理によって核兵器を管理するよう圧力をかけた。
その後、ホワイトハウスの科学委員会の席を受けて、より広範囲の専門知識を求められた。化学、政治、経済、環境、さらに宗教や道徳までもが相互に関係する情況での問題がそこにはあった。委員会のメンバーはスペシャリストとして過ごしてきた者たちだった。
当時の科学は、還元主義手法(この世界を可能な限り小さく単純な断片に刻んで、理想化した問題設計に対する解を求める方法)だった。しかし、現実の世界はホリスティックにすべてが互いに影響しあって存在している。関係の網を理解するためのアプローチをする必要がある。
ニュートン以来の三百年、物理学は線形システムに依存してきた。「全体はその部分の総和に等しい」とすることで、各要素は他の部分で何が起きていようとそれ自身のことをしていてよいとされてきた。きわめて単純な物理的システムは、確かに線形システムで動いている。
だが物理学者たちは〈非線形力学〉によって複雑なシステムを解くことができるのではないかと考え始めた。「全体はほとんどいつも、その部分の総和よりかなり大きい」。この世のすべてのものごと、すべての人間が、誘引と制約と結合の大きな非線形の網のなかに捕らわれている。ある場所のわずかな変化が、他のすべての場所に振動を引き起こす。
こうした非線形の研究にロス・アラモス研究所のメンバーが取り組んでいく。この研究所では高エネルギー粒子物理学、流体力学、核融合エネルギー研究、熱核衝撃波などなんでもやっていたからだ。そうした非線形問題の大多数は同一の数学的構造を有し、本質的に同一の問題といえた。そしてその問題は、物理学と化学に限らず、生物学、情報処理、経済学、政治化学、人間世界の諸事すべてを包含するような根源的統合を果たすための知の手法になりえると、コーワンは考えた。
複雑性のシステムを調べてみると、大抵の場合、基本構成物と基本法則はきわめて単純である。つまり単純な多数の構成物が同時に相互作用することで、無数の可能な状態が組織化して、複雑性が生まれる。
そうした単純な構成物を〈エージェント〉という。〈エージェント〉から一つのシステムが成り立つ。分子は細胞を、ニューロンは脳を、種はエコシステム(生態系)を、消費者や企業は経済を形成する。〈エージェント〉同士が相互の調整と拮抗をとおして、たえずより大きな構造へと自己組織化していく。それぞれのレベルで新しい創発的な構造を形成し、また新しい創発的な挙動を示していく。複雑性とは創発の科学であり、創発の基本的な法則を見いだすことがサンタフェ研究所の仕事であった。
* * *
* * *
M・ミッチェル・ワールドロップ『複雑系 生命現象から政治、経済までを統合する知の革命』田中三彦・遠山峻征訳、新潮社、1996年。
第1章〜第4章
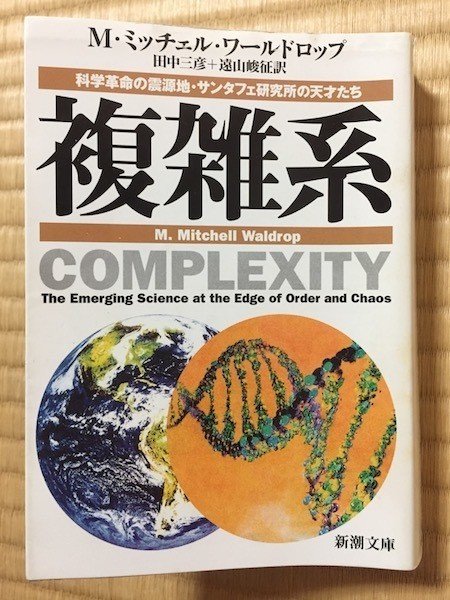
M・ミッチェル・ワールドロップ
サイエンス・ジャーナリスト。ウィスコンシン大学で素粒子物理学の博士号を取得。十年間にわたり、「Science」誌のシニア・ライターとして活動。
