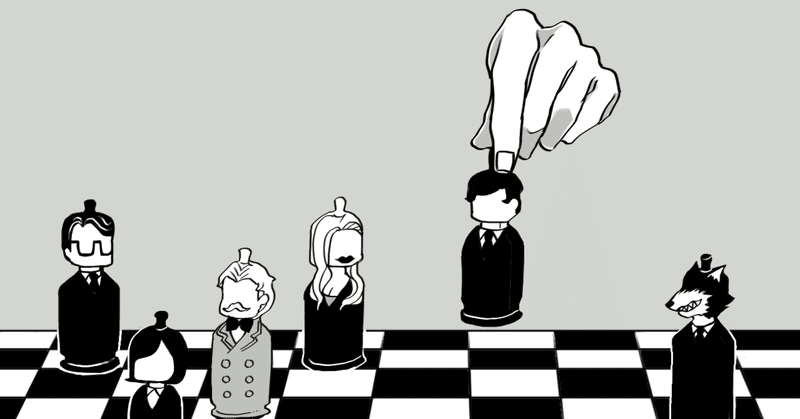
断片小説集 5
私はパン職人になりたかったんです。母もパン職人に憧れてましたから、私が会社を辞めてパン職人に弟子入りしたいと言っても、反対はしませんでした。
パン職人は体力勝負です。運動音痴で、体育の成績はいつも1か2だった私ですから、5年ぐらいは修行を積まなきゃと思ってました。どうせ修行するなら長い間パン屋さんを続けている職人さんの下で修行したいと思ったんです。
私はあちこちの町を歩き回って、パン屋さんを探しました。そして3ヶ月目にようやく私の理想に近いパン屋さんを発見したんです。商品棚に並んだパンはどれも美味しそうで、下見だけのつもりがパンを10個も買ってしまったほどです。家に帰って一口齧ってみたら、もう夢のような美味しさでした。
パン屋さんは店主の人がひとりでやっているようでした。
パンも焼き、棚に並べ、お客さんの相手もして。とっても忙しそうでした。髭面で、腕もすごく太くて、パン作りには厳しい職人さんなんだろうなと思ったけれど、私みたいな素人が修行するには厳しいくらいでちょうどいいはずだと思っていました。
次の日、私はもう一度パン屋さんに行って、雇ってもらえるようにお願いをしたんです。修行をしたいことも、パン職人になりたいことも、全部伝えました。
パン屋さんは「じゃあ明日の昼前に面接しよう」と言ってくれました。
私は履歴書を持って面接をしてもらいました。
「君がいちばん好きなパンって何?」
「焼きたてのクロワッサンです。表面は輝いていて、歯が当たるだけでパリッと音を立てて、でも中はバターでしっとりしてるようなクロワッサンを想像するだけでよだれが出そうです」
「じゃあサンドイッチに限ったらいちばん好きなのは?」
なんて答えるのが最適なのかを考えました。
何より記憶に残っているサンドイッチときたらお母さんがお弁当に作ってくれたタマゴサンドとまい泉のカツサンド、駅前のフルーツパーラーのフルーツサンドぐらいしかなかったから、なんて答えるかを迷ってしまったんです。そうしたらパン屋さんに「プリントーストサンド食べたことある?」と聞かれたんです。一瞬、フレンチトーストが頭に浮かびましたが、答えとは違っている予感がしました。変に知ったかぶりせずに、知らないものは知らないと言おうと覚悟を決めました。
「すみません、食べたことありません」
「はちみつ漬けの梅干しサンドは? 板ずりウドのサンドイッチは? 生牡蠣とコーヒークリームのサンドイッチは? 雪締めウサギのローストサンドは? 松葉漬けの落ち鮎のエビ殻ソース和えサンドは? カエルの吊るしローストサンドは?」
私が食べたことのあるサンドイッチは一つもありませんでした。
正直に言えば、どれひとつとして食べてみたいと一瞬でも思ったものはなかったです。
パン屋さんは少しだけ悲しい顔をして、小さくため息をつきました。
でも、私は少しだけ腹が立ってきたんです。ウドだのはちみつ漬けの梅干しだの、そんなのがパンに挟まれてるのなんて見たことがありませんから。
「じゃあ、これまでに食べたサンドイッチで印象的だったのある?」と投げやりに聞かれて、ますます腹が立ってきました。
だから嘘をついたんです。
「蒸したアルマジロの舌とドラゴンフルーツのサンドイッチは印象に残ってます」
ドラゴンフルーツは見た目がもう食べたいものじゃないし、アルマジロなんて生で見たこともありません。
でもパン職人さんの目が急に輝き出して「アレがわかるってすごいよ! どこで食べたの? エクアドル?グアテマラ? コスタリカかもなあ。いちばん美味しいのは実はグアテマラなんだけどね!」って、いきなり。
嘘なのに。
で、最後に、本当にオマケみたいに、そんなことどうだっていいでしょみたいな感じで「あ、そうそう。君、合格ね。明日からよろしく」とおっしゃって、それが私のパン職人への道の第一歩でした。
その後ですか? いつかアガペシロップ漬けのアルマジロのレバーのサンドイッチを食べて欲しいなあって、何度もおっしゃるんですけど、アルマジロなんて食べたくないですよね、やっぱり。当然、私も作ろうとは思いません。
(「プリントースト」)
* * *
「閑話休題」と書いて「それはさておき」とルビを降るのを癖にしている作家がいた。もちろん意図的にやっていたのだと思う。だって「閑話休題」と、こんな見た目になるのだ。意図的でなければ目立ちたがり屋だ。
連載している週刊誌の原稿の最後に、「閑話九題」と思わせぶりにわざとらしい間違いをしたら、担当の編集者からすぐに電話が来た。
「先生、いくら週刊誌でも連載小説の途中で9週も本筋と関係ない話を入れたら、読者がいなくなっちゃいます」
と、泣きそうな声で懇願してきた。
冗談は通じてないし、わざとらしい間違いにも気がついてないのかもしれない。なにせあの編集者は膝の半月板も「そもそも満月板なのが、トップ選手は摩耗して半月板になるのだ」と嘘つかれても間に受けていた。三半規管も「3.5器官」だとずっと思い込んでいたのだ。閑話九題ぐらい楽勝で勘違いしてもおかしくない。
(「満月板と3.5器官」)
* * *
田舎に引っ込もうと決心した理由ははっきりしている。
決心してすぐに引っ越し先を探し始め、10日後には東京から少々離れた里山のふもとに見つけた農家の空き家に移り住んだ。
生活はいくらか不便になった。だが代わりに手に入れた静かさは不便さより上だった。
俺の仕事は、世間的に言えば文筆家ということになる。
文筆業を専業とする前、私は客商売をしていた。5人も入れば満員になる小さな店を作り、ありがたいことにその店は繁盛していた。
文筆専業になるにあたって俺は店を畳み、自宅に引っ込んだ。すると店の常連だった連中が我が家に土産をぶら下げてやってくるようになった。追い返せるわけがない。
店のメニューなど諳んじているほど足繁く通っていた連中だ。俺に何が作れて、何ができないかまで熟知している。俺はかつてと同じようにコーヒーを淹れたり、ミルクをホイップしたり、チャイを作る羽目になった。
そうして俺はかつての店と変わらない自分の家から逃げ出した。
ともあれ引っ越した後の半年ほどはのんびりとした毎日だった。
早朝に目覚め、コーヒーを淹れ、原稿を書き、早く眠る。
健康的な生活の模範のような毎日だった。
執筆の依頼を受けて原稿を書き、依頼主にメールで送れば済む。誰かに会う必要は最小限で済ませられる。静かであるのはなんら不思議なことではなかった。
半年経ったある週末、東京の我が家に入り浸っていた常連の一人が里山の家にやってきた。事前の連絡などなかった。半年ぶりに俺は料理を作り、コーヒーを淹れた。久しぶりに誰かのためにキッチンに立つのは意外に楽しかった。翌朝、そいつは満足そうに帰っていった。
それからである。週末には必ず誰かがやってきた。どうやら申し合わせをして、里山の家を訪れる順番を決めているようだった。
我が家への出入りを田舎の住人たちが見逃すわけがない。
近所に住む農家の一人が「コーヒーが美味しいんだって?」とやってきてしまった。新参者の俺がそいつを追い返せるはずもない。いつものようにコーヒーを淹れ、仕方なく当たり障りのない世間話に付き合う羽目になった。
その後は予想した通りの展開で、午後の3時になると我が家の縁側は近くに畑や田圃を持つ農家の住人たちの休憩所と化した。
二週間もすると「タダで飲ませてもらっちゃ悪いから」と畑で採れた野菜やら米やらを持ってきては、帰り際に置いて行くようになった。中には百円玉を数枚残して行く者もあった。
貰い物の野菜でキッチンはすぐに埋まりはじめ、俺は野菜を使った料理を「お礼です」と近隣の連中に食わせて消費することを目論んだ。だがそれは失敗だった。料理を出してしまったことで、キッチンに積まれる野菜はさらに増えてしまった。
余ってしまう大量の野菜は、東京からやってくる客たちに配り、どうにかキッチンが侵食されるのを食い止めていた。
彼らは彼らで「タダというわけには」と幾ばくかの金をおいていくようになった。
俺は野菜の仲介業者ではない。農家の奥さん連中に頼んで、週末だけ庭で野菜の即売をしてもらうことにした。その結果、東京からの来客は倍増し、縁側に座りきれない人が庭で順番待ちをするほどになってしまった。
仕方なく俺は庭に椅子と小さなテーブルを用意して、雨の日には屋根代わりなるようにシートを張った。
そのうち「テーブルが小さい」と、誰かがどこからか樫の木の大きなテーブルを持ってきた。席数は8席増え、縁側と合わせると14人が座れるようになってしまった。
俺は今、この里山の家から逃げ出すことを考えはじめている。
(「満員御礼」)
ぜひサポートにご協力ください。 サポートは評価の一つですので多寡に関わらず本当に嬉しいです。サポートは創作のアイデア探しの際の交通費に充てさせていただきます。
