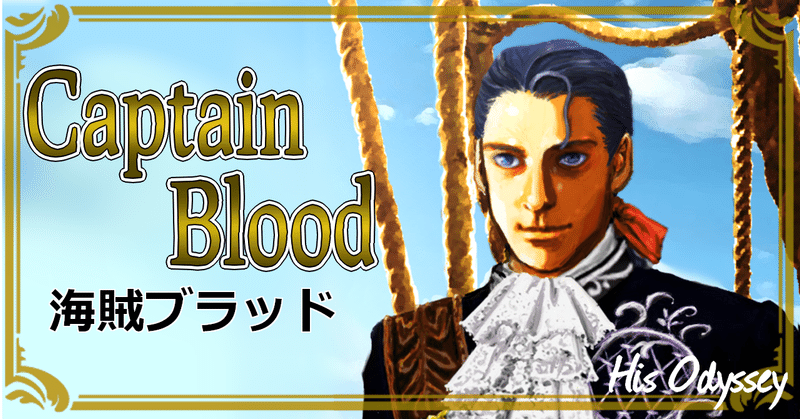
海賊ブラッド (10)ドン・ディエゴ
ドン・ディエゴ・デ・エスピノーサ・イ・バルデスは目を覚まし、痛む頭とけだるい目で、背後にある正方形の窓から陽の光が差し込んでいる船室を見回した。それから彼はうめき声を上げて、頭部の猛烈な痛みに思わずまた目を閉じた。横たわり、彼は考えようと試みた。今はいつで、自分はどこにいるのか。しかし頭の痛みと混乱した思考では、筋が通った考えは不可能であるとわかった。
漠然とした不安から再び目を開き、彼はもう一度、自分の置かれた状況を確かめるように己を鼓舞した。
彼が自分の船であるシンコ・ラガス号内のグレートキャビン(船長室)で横になっていた事に疑いの余地はなく、漠とした不安には根拠などないはずだった。だがしかし、湧き上る記憶が省察を助け、それが落ち着かぬ感覚と共に、この場の何かが決定的に間違っているという認識を強いた。低い位置にきている太陽が、正方形の船尾舷窓から船室に黄金の光を溢れさせており、彼は当初、船が西に向かっているという仮定の下で、今は早朝であると判断した。それから別の可能性が心に浮かんだ。船が東に向かっているのなら、時刻は遅い午後のはずだ。足元の船体の穏やかなうねりから、船が航行しているのは感じ取れた。しかし彼等はどのような成り行きで船を出したのだろうか?そしてマスター(航海長)である彼は、航路が東か西かも知らないのか、あるいは目的地を思い出せないのか?
彼の思考は昨日の冒険を想起していた。それが実際に昨日であれば、なのだが。バルバドス島に上陸し、容易に成功した襲撃については、はっきりしていた。船に帰還する為に再び甲板に踏み出した瞬間までの記憶は、あらゆる細部までが全て鮮明に存在していた。記憶はそこで突然に、そして不可解に途切れていた。
煩悶しつつ懸命に答えを導きだそうとしていた時、ドアが開き、ドン・ディエゴにとって不可解な謎が更に増えた。彼の最も上等な衣装を着た男が船室に入ってくるのを目撃したのである。それは一年前にカディスで彼の為に仕立てられた、銀糸のレース飾りがあしらわれた黒いタフタの極めて優雅で個性的なスペイン様式の衣装であり、その服の細部まで熟知していた彼には見間違えようがなかった。
その衣装を着た男は扉を閉める為に足を止め、それからドン・ディエゴが横になっているソファーに向かって歩を進めた。その服を着て船室に入ってきたのは、ドン・ディエゴ自身の身長体格と大差のない痩せた長身の紳士であった。驚愕で大きく見開かれたスペイン人の目が自分に向けられているのに気づくと、その紳士は歩幅を大きくした。
「お目覚めかな?」スペイン語で彼は言った。
横たわったままの男は、黒い巻き毛の房に縁取られた黄褐色の皮肉っぽい顔から彼を見つめている、一対のライトブルーの瞳を当惑しつつ見上げた。しかし彼は如何なる答えであれ、言葉を返すにはあまりにも当惑していた。
見知らぬ男の指がドン・ディエゴの頭頂に触れ、痛みにたじろいだドン・ディエゴは悲鳴を上げた。
「圧痛有り、か?」見知らぬ男は言った。彼はドン・ディエゴの手首を親指と人差し指で掴んだ。そして遂に困惑に耐え切れなくなったスペイン人は言葉を発した。
「君は医者か?」
「でもある」浅黒い紳士は患者の脈をとり続けた。「安定かつ平常」ようやく彼はそう宣言し、手首を放した。「深刻な傷害は負わなかったようだ」
ドン・ディエゴは赤いベルベットのソファーから懸命に起き上がり、居ずまいを正そうとした。
「貴様、何者だ?」彼は尋ねた。「私の服を着て、私の船に乗って、一体何をしている?」
平行だった黒い眉が上がり、かすかな微笑が唇に曲線を描いた。
「未だうわごとを言っているのか、困った事だ。これは貴方の船ではない。これは私の船であり、そしてこれは私の服だ」
「貴様の船、だと?」驚愕したように相手の言葉を繰り返し、更なる驚愕のままに言葉を継いだ。「貴様の服?しかし……それは……」彼の目は懸命にその男を凝視した。その視線は再び船室内をめぐり、馴染み深い調度の一つひとつを綿密に確かめた。「私はおかしくなったのか?」彼はようやく尋ねた。「この船は確かにシンコ・ラガス号か?」
「シンコ・ラガスだ」
「それなら…」スペイン人は突然、口をつぐんだ。彼のまなざしは苦悩を深めた。「バルガ・ミ・ディオス!(神よ、お助けあれ!)」彼は苦悶しつつ叫んだ。「では、貴様は自分がドン・ディエゴ・デ・エスピノーサだとでも言うつもりか?」
「いや、違う。私の名はブラッド――キャプテン・ピーター・ブラッド。この船は、この洒落た衣装と同じように、勝者の権利によって私のものとなった。ドン・ディエゴ、貴方が私の捕虜となったのと同じようにね」
その説明に仰天させられつつも、しかしそれは同時にドン・ディエゴの心を落ち着かせるものでもあった。それは彼が思い描き始めていた事態よりは、まだ有り得る範囲のものであった。
「だが……では、貴様はスペイン人ではないのか?」
「私のカスティリャ語をお褒めいただけて光栄だ。私はアイルランド人に生まれた事を誇りに思っている。貴方は奇跡が起きたと思っていたようだが。そう、これは――私の才覚によって引き起こされた奇跡だ、類いまれなる能力によってね」
手短かに真相を語る事によって、キャプテン・ブラッドは謎を晴らした。スペイン人の顔を朱と白の交互に染めたのは、その顛末であった。彼は自分の後頭部を探り、そこにその話を裏付けるような鳩の卵程度の大きさの瘤があるのを確かめた。最後に彼は冷笑を浮かべたキャプテン・ブラッドを、動揺を露にした目付きでにらんだ。
「では私の息子は?息子はどうしている?」彼は叫んだ。「息子は私のボートに同乗していた」
「御子息は無事だ。彼とボートの乗組員は、貴方のガンナー(砲手)とその部下達と共にハッチ(船倉口)の下で大人しく拘束中だ」
ドン・ディエゴは再びソファーに沈み込んだが、ぎらついた黒い目は、彼を見下ろしている黄褐色の顔に定めたままだった。彼は気を落ち着かせた。ともあれ、彼はこの絶望的な交渉に必要とされる冷静さを取り戻した。この博打では、既に賽は負けの目を出していた。大勝ちしたと思った瞬間に、大逆転されたのである。彼は宿命論者の堅忍をもって状況を受け入れた。
最大限の冷静さを保ちつつ、彼は問うた。
「それで、現状は?セニョール・キャピタン(船長殿)」
「それで、現状は」キャプテン・ブラッドは――ドン・ディエゴが彼を呼んだ称号を当然のように受け止め――答えた。「慈悲を知る者として、貴方が我々の加えた軽打で死に至らなかった事を気の毒に思う。何故ならば、それはつまり、貴方が再び振り出しに戻って死の不安に向き合わねばならない事を意味するのだから」
「ああ!」ドン・ディエゴは深く息をした。「だが、そんな必要はあるのか?」そう尋ねた彼は内心の動揺を表には出さなかった。
キャプテン・ブラッドの青い目は、彼の態度に満足を示した。「自分の胸に訊きたまえ」彼は言った。「経験豊かな、そして血にまみれたパイレート(海賊)として、貴方自身が私の立場にあれば何をする?」
「ああ、だが相違もあるぞ」ドン・ディエゴはこの問題を議論する為に姿勢を正した。「君は慈悲深い男と自負しているのだろう」
キャプテン・ブラッドは長い樫テーブルの縁に腰を下ろした。「だが私は愚か者ではない」彼は言った。「そして私の身に備わったアイルランド人的な感傷癖をもってしても、必要かつ適切な行為を妨げはしないだろう。貴方自身と、貴方の部下である凶賊の生き残り達は、この船にとっての脅威だ。それ以上に、当船は水と食料を無駄にできない。幸いにも我々は少数だが、しかし貴方と貴方の部下達は食い扶持を増やしてしまう。よろしいか、思慮分別に従えば、あらゆる点から見て貴方達には謹んで御退場いただくべきであり、我々の慈悲深い心を鬼にせざるを得ず、かなうならば自主的に舷側から板をまたいで海原に消えて欲しいものなのだが」
「わかった」物思いに沈みつつスペイン人は言った。彼はソファーから身を起こし、その端に座ると膝上に肘をついた。ドン・ディエゴは相対した男を見定めた上で、表面的な上品さと人当たりの良い超然とした態度で調子を合わせた。「白状するが」と彼は認めた。「君の意見はもっとも過ぎて、反論の余地が見つけられないな」
「お陰でこちらも気が楽になった」キャプテン・ブラッドは言った。「私は不必要に剣呑な振舞いはしない。ましてや私と我が友人達は、貴方に大きな借りがあるのだから。他の者達にとってはどうあれ、我々にとって貴方のバルバドスへの襲撃は実に好都合だった。従って私は、私に選択の余地がない事を貴方に御理解いただけて非常にうれしいのですよ」
「しかし我が良き友よ、私は受け入れられんぞ」
「貴方に代替案がおありなら、それを検討できれば幸甚」
ドン・ディエゴは鋭く黒い顎鬚を撫でた。
「朝までの猶予をもらえるか?頭がひどく痛んでな、考えがまとまらん。それにこれは、君も認めるだろうが、重大な問題なのだから」
キャプテン・ブラッドは立ち上がった。彼は棚から三十分の砂時計をとると、赤い砂の満ちた側が上になるように逆さまにしてテーブルの上に置いた。
「ドン・ディエゴ、このような問題を押しつけて、まことに遺憾に思うが、しかしこの砂一杯が貴方に与えられる猶予だ。この砂が落ち切るまでに受容可能な選択肢を提案できないならば、私は断腸の思いで貴方と貴方の友人達に、揃って舷側の向こうに消えていただくようにお願いしなければならないだろう」
キャプテン・ブラッドはお辞儀をし、部屋を出ると扉に錠を下ろした。膝上に肘をつき、掌に顔を乗せて座ると、ドン・ディエゴは赤い砂が上の球から下の球へと少しづつ落ちてゆく様を見つめた。それを見る彼の褐色の顔にはしわが深くなった。時間通りに最後の砂粒が落ち切った時、ドアは再び開いた。
スペイン人は溜息をつき、彼の答えを聞く為に戻ったキャプテン・ブラッドに向かい合う為に背を伸ばして座った。
「私は代替案を考えた、サー・キャプテン。だが、それは君の寛容に依存する。君がこの厄介な群島の一つに我々を上陸させ、後の事は我々自身にゆだねるという選択肢だ」
キャプテン・ブラッドは唇をすぼめた。「それは難しいな」ゆっくりと彼は言った。
「で、あろう事を恐れていた」ドン・ディエゴは再び溜息をつき、立ち上がった。「ならばもう言うまい」
彼に向けられたライトブルーの目は剣の切っ先のようにひらめいた。
「貴方は死を恐ないのか、ドン・ディエゴ?」
スペイン人は眉間にしわを寄せ、頭をめぐらせた。
「その質問は愉快なものではないな」
「では、私から一つ提案をさせていただきたい――恐らくは、もう少し愉快なものだ。貴方は生きる事を望まないか?」
「ああ、こうは言えるな。私は生きる事を望む。更に言えば、私の息子の生存も望む。とはいえ、君の楽しみの為にへつらう事は望まんがな、冷笑家殿」彼がわずかであれ昂ぶりの、もしくは憤慨の兆候を見せたのは、これが初めてであった。
キャプテン・ブラッドは、すぐには答えなかった。先程と同じように、彼はテーブルの角に腰掛けた。
「貴方は生命と自由を――貴方御自身、貴方の御子息、そして船内にいる他のスペイン人達の生命と自由を獲得する事をお望みだろうか?」
「獲得する事?」ドン・ディエゴはそう言い、そして用心深い青い目は、彼に走った震えを見逃さなかった。「それを獲得する事を、と言うのか?君の提示する条件が私の名誉を傷つけるようなものならば……」
「私がその配慮をしないとでも?」ブラッドは断言した。「海賊にも名誉がある事は承知している」そして直ちに彼は申し出を明らかにした。「その窓から外を見れば、ドン・ディエゴ、水平線に姿を現している雲のようなものが見えるだろう。あれは遠ざかりつつあるバルバドス島だ。我々は終日、追風を受けてひたすら東に航行してきた。ただ一つの目的――可能な限りバルバドスと我々との間の距離を広げるという目的の為に。しかし陸地がほとんど視界から消えた今、我々は困難に直面している。航法を習得している唯一の乗組員は、高熱で臥せってうわごとを言っている。実をいえば、我々が彼をここに運び入れるより前に、陸でいささか惨い仕打ちに遭った結果そうなったのだが。私は操舵ができるし、私の助手を務められる者も一、二人搭乗している。しかし高度な船舶操縦術や、目印のない大海を行く道を見つける術に関してはお手上げだ。岸に沿って航行し、貴方が適切にも厄介な群島と呼んだ海域に紛れ込んだ時、我々が自ら大変な厄介事を招くであろうと想像するのは容易だろう。それで、結論はこういう事だ。我々は可能な限り真っ直ぐに、キュラソー島のネーデルラント植民地に向かいたい。貴方は御自分の名誉にかけて誓えますか。もしも私が貴方に執行猶予の待遇を与えたならば、貴方はその為の航路を教えると?貴方にそれが誓えるのなら、我々はその地に到着次第、貴方と貴方の生き残った部下達を解放しましょう」
ドン・ディエゴは深くうなだれると、物思いにふけりつつ船尾舷窓に向けて大股で歩き去った。そこで彼は明るい光の当たる海と、大型船の航跡のよどんだ水とを見つめて立ち尽くした――彼の船、このイングランドの犬どもが彼から奪い取った船。彼の船、それを安全に港につけるよう求められたが、その港に入れば完全に彼から取り上げられ、恐らくは彼の同胞と戦う為に改装されてしまう船。それが天秤の片側に乗せられており、もう一方の側には十六人の命が乗っていた。そのうちの十四人は、彼にとってさして重要ではなかったが、しかし残る二人は、彼自身と彼の息子の命であった。
彼はようやく振り返ったが、逆光になっている彼の顔がどれほど青ざめているかを、ブラッドは見る事ができなかった。
「承諾しよう」彼は言った。
ここから先は

ラファエル・サバチニの『海賊ブラッド』
1685年イングランド。アイルランド人医師ピーター・ブラッドは、叛乱に参加し負傷した患者を治療した責めを負い、自らも謀反の罪でバルバドス島…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
