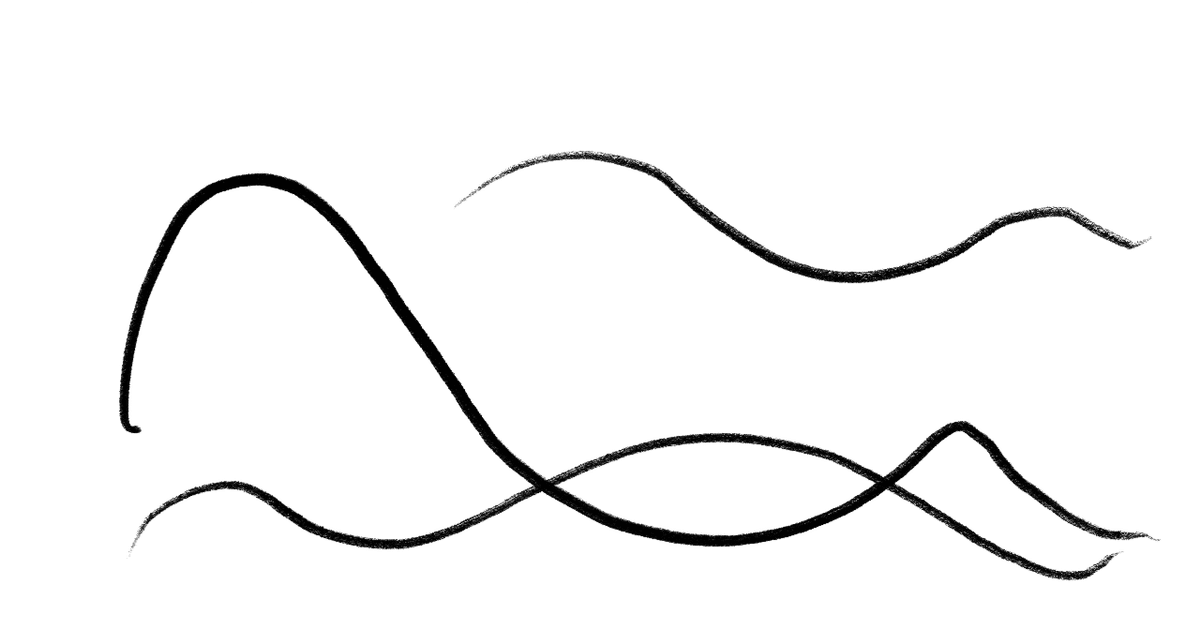
サミュエル・ベケット『名づけえぬもの』
小説、とくに長編小説とか読んでると、これってひとつのでっかい独り語り、モノローグなんじゃないかって感じることがある。
誰か知らんけど語り手が全部を語ってるのかもなあ~と覚めてみることがあるというか、そうして見たほうが楽しいこともある。
サミュエル・ベケットの『名づけえぬもの』だとそのメカニズムを露わにしてみせて、なおかつ生成と衰弱と消滅と継続の過程を示しているという、かゆいところに手が届くというか、いや読んでる感じはもどかしいんだけど、でも普段、小説を読んでいる過程で見えず意識できないところを、他ならぬ小説によって見せて意識させてくれるような小説だなあと思っている。読んでわかるのは、ここに封じられているのはすんごい冷めた覚めたメタさだし、読む陶酔みたいなものも同時にある。
そして、言葉という「精妙でいて大胆なもの」の不可思議さを思わされる。
『名づけえぬもの』は、一見、壊滅的で再帰不可能なスタイルでいて、意識だか声だか言葉だかわからないが「何か」の持続は途切れずに続いており、その持続に沿うようにひょろひょろした一本の線を音楽を聴いているようにつたっていけばいいように読んでいる。
音楽、という言葉を出したのは、この小説は一種、究極の小説なんじゃないかという気もするから。ひたすら意味やら文脈やら論理ですらないコトバの筋をたどっていくことで、読者に地獄や煉獄やそれに類するもの、あるいはどんづまりや昂揚を体験させられるのは、これは徹底的な「ミニマル文学」というものなんじゃないかと。
どうかすると、もうちょっとで、言葉の物体化、モノ化、逆に言葉の音符化、音楽化にまで達しそうなところを、あるいは空中分解寸前で、そこをぎりぎり散文にしているのは、「何か」、自体の、に対する、状態、持続で、誰かにこれが小説のエッセンスそのものなんだと言われたら、もう、へへー、おっしゃる通りです、というしかない。でも語り手もベケットも、もっともっと遠くを深みを凝視している気もして、実際この後も文学を続けるし、『名づけられないもの』はなんかドエライ達成をしてるなと思うと同時に、まさに「おれ」「私」たちは現にここから続けなくちゃなあ、って感じもして。
読むたびに、そこに書かれているもの、あるいは見事に書くことに失敗していること、書かれることを拒絶しているもののバイブレーションに瞬間、のっとられて、その「何か」に、ゆりうごかされる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
