
【笹久保伸】コロナ禍だからこそ時空を超えて繋がった、秩父とブラジルの仲間たち
6/20発刊号intoxicateにて、秩父在住のギタリストである笹久保伸さんに取材しました。本誌には収まらなかったロングヴァージョンのインタヴュー記事をnote限定公開します!
**********************************

©Itaru Hirama
コロナ禍だからこそ時空を超えて繋がった、秩父とブラジルの仲間たち
interview&text:佐藤英輔
我が道を行くギタリスト、笹久保伸が新作『CHICHIBU』を出す。これまで、ソロ演奏のアルバムが多かった彼だが、なんと今作は6人の個性派たちと1曲ずつコラボレーションした曲を収めた内容となる。その協調者は、アントニオ・ロウレイロとジョアナ・ケイロスとフレデリコ・エリオドロというブラジルの新ミナス派の精鋭、さらにはサンパウロ在住の逸材シンガーであるモニカ・サルマーゾ、ノンサッチ発のスタンダード曲を素材に置く音響作『Satin Dall』他で評判の高い米国人サックス奏者のサム・ゲンデル、そして感覚派シンガー・ソングライターここに極まれりと言いたくなる日本人のmarucoporoporo(彼女は前作『PERSPECTIVISM』でも1曲関与している)。笹久保は何を求めて、この面々を選び、協調はどのように進められたのか。これまでの、独立独歩の彼のキャリアも振り返りつつ、そのジャイアント・ステップ作の真価を図る。
——新作『CHICHIBU』は、30作めになるんですか?
「なるんです。最初は(ギターを学びに行った)ペルーでリリースし、13枚出しました。たまたま売れたからというので、レコード会社が出してくれました。ありがたいですよね、2、3年で13枚も出してくれるわけですから」
——4年ほど、ペルーにはいたんですよね。
「はい、でも最初の1年は出してないですから」
——それだけレコードを出せたわけですから、シン・ササクボはペルーで結構有名だったんですよね。
「当時、知られていましたよね。今でも知っている人はいっぱいいますけど。ペルーでは(海外から来た)そういう人はあまりいなかったので、可愛がってもらいました」
——その際は、フォルクローレの曲をやっていたんですか。
「はい。とともに、ペルー時代から自分の曲もやっていました」
——それで、日本に戻ってきてからも勢力的にアルバムをリリースしています。
「日本で最初に録ったのが、2013年かな。15枚目からは、自主レーベルの“Chichibu”から出しています」
——一応、30作めとなることで、節目であるとは考えました?
「一応、節目だなとは思いました。今回LP(アナログ)も作ろうと思ったのは、だからですね」
——節目ということもあり、どういう内容のものにしようと思ったのでしょう。
「もともとペルーの音楽をやってきて、アンデスの演奏家とかフォルクローレの演奏家とか思われるのが癪だったんですよ。それで、即興とかいろんなことをやってきて、アルバムを出しているんですけど、今回は30枚めにあたり違うものを出したいなと思いがありました」
——そう考えたときに、旬のブラジル人をはじめとする今を清新に出すことができる音楽家とコラボレーションしようというアイデアが出てきたわけですね。
「そうですね。最初の段階では誰とやるかというのは全然決めていませんでした。ここ(インタヴューをやった、秩父の<喫茶 カルネ>)でお茶を飲んでいたりすると、僕と全然合わなさそうな音楽家の情報を教えてくれるんですよ。サム・ゲンデルはここで教えてもらい、彼とやりたくなりました。ここ、秩父での会話の中からミュージシャンを選んでいったという部分もありますね」
——6人の協調者を見て、ぼくが一番驚いたというか、膝を打ったのがサム・ゲンデルです。
「サムはいいですよね。不思議ですよね、どうしてあんなに日本好きなのか(PVをわざわざ日本で撮っていたりする)。彼はロサンゼルスに住んでいるじゃないですか。彼とやりとりがうまく行った理由は、メキシコ移民とか多かったりするせいかもしれませんが、彼がスペイン語を喋れたからです。僕、英語ができないんです」
————サムはアメリカ人ですが、ブラジルの人たちともスペイン語でやりとりしたんですか。
「スペイン語ですね。ブラジルはポルトガル語ですけど、みんなスペイン語が分かりますね。アントニオ・ロウレイロとは面識がありました。同じ年の“スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド”で一緒になったんです。それで、いつかできることはないかなと思っていました。でも、最大のポイントは、何人にせよ、海外のミュージシャンとやるときに相手の土俵でやることが多いなか、そういうのはやめようと思ったことです。彼らの流儀に乗るといい音楽にはなると思うんですが、それはちょっとダサいと思った。それで、あえてアルバム表題も『CHICHIBU』にしたんですけど、思いはそれしかなかった。彼らを秩父に引き込み、自分の土俵でやりたかったんです」
——相手の個性を出させつつ、みんなを秩父に連れてくる……。
「もちろん、ブラジル感とか出ているんですが、でもブラジルのリズムを使ってはいません。だから、“ミナス風”とか書かれるとそれはちょっと違うかな、と。モニカ・サルマーゾはサンパウロで、ミナスに住んでいませんし。だから、僕は“秩父”と言い切っています。自分の世界観の中で、自分の音楽を作るために、彼らを呼んでいるわけですから。やっているのは、やっぱり秩父の音楽なんです」
——はい。だから、秩父に来て、話を聞かなきゃと思いました。ところで、ブラジル音楽はもともと聞いているんですか。
「聞いていないです。モニカとかは有名だから、名前は知っていましたが」
——それぞれのアーティストって、日本に来ていたり、レコードを出していたりしているんですよね。
「そうなんですよね。でも、モニカのライヴも見ていないですから」
——モニカ・サルマーゾは渡辺貞夫さんやギンガと来ていますね。サムはライ・クーダーと一緒にツアーをやったりとか、アントニオ・ロウレイロとフレデリコ・エリオドロはジャズ・ギタリストのカート・ローゼンウィンケルのカイピ・バンドに関わったりとか、ギタリストと一緒にやっている人も多いですよね。
「そうですね、多いですね」
——とにかく、気になった人に声をかけてみたわけですね。
「コロナ禍であったのは大きいです。コロナ禍にならないと、こんなにブラジル人たちとやろうという気は起きなかったかもしれない。やっぱり、ギャラ払ったりするのも大変じゃないですか。でも、コロナ禍だからみんな家にいて暇で、チャンスだと思いました。あまり海外の人とこういうアルバムを出している人はいないようなのも幸いでした」
——あと、みんなシンガー・ソングライター的な資質を持つ人たちということができるかもしれない。
「そうですね。みんなマルチですよね。marucoporoporoもマルチで、ギターだけじゃなくピアノも弾きますし。Marucoporoporoはアルゼンチンのフローレンシア・ルイスから影響を受けていたりもしますね」
——アルゼンチンの話が出たんですが、今アルゼンチンのシーンも面白いじゃないですか?
「面白いですよね。アルゼンチン人とやる選択もあったんですけど、言葉もスペイン語だし、なんかすぐできそうじゃないですか。ブラジル人はあまり友達がいないので、逆にできないかなと思ったんです」
——ブラジルのほうがインパクトがあると思います。アルゼンチンだと言葉つながりで、という感じが出てしまうし。
「なんとなくやったんだなって、思われてしまいますもんね。ブラジルのほうが違和感はありますよね。今回たまたまうまく行ったというのはあります。なかなかできないような相手でも、すぐにレスポンスしてくれました」
——どういうものを、相手に最初送ったんですか?
「アイフォンで録った音源をメールに添付して、送りました」
——過去の音源とかは? ぼくだったら、こういうことをしていますみたいな感じで付けそうな気がしますが。
「ああ、確かにそうですね。でも、しなかったです。携帯で録ったやつをつけて、こういうのがあるんだけど、なんかできないかな、と。そしたら、みんな全然いいよみたいな答えを返してきてくれました」
——他にあたった人はいました?
「最初、ミルトン(・ナシメント)にメールしたんですよ。だけど、高齢だし、返信が来ませんでした。メールも見てないんじゃないかな。ミルトンのようなレジェンドとやりたかったんです。あと、クリス・デイヴ(R&Bバンドのミント・コンディションやロバート・グラスパーのバンドから巣立った、現代ジャズ/ヒップホップのドラマー)にもメールしたんですけど、それもしかとされました。彼には、2回メールしたんですけどね」
——おお。どうして、クリス・デイヴ?
「彼とやりたいんですよ。なんかあのジャズが広がっていってヒップホップと一体化しているという感じが面白い。ロバート・グラスパーなんかもそうですよね」
——笹久保さんがきっちり今のビート、ドラマーと折り合ったアルバムを聞いてみたいです。
「だから、フォルクローレのギタリストというところから逸脱したものを作りたかったわけです。僕はいろんな要素を持っていると思うし、そういうところを見せたいと思いました。カテゴライズされる中でフォルクローレのギタリストと言っても多くの人にはピンとこないと思うので、違うところでやっていきたいと思うんです」
——お願いメールの際に、こんな曲あるんだけどと出した曲をみんなやっているんですか?
「そうです。ぼくが作った曲をこれはロウレイロだなと思ったら、ロウレイロにやってもらいました」
——ちなみに、クリス・デイヴに送った曲はどういうものだったんですか?
「ギターの即興的なやつですね」
——相手に曲を提示した段階では、曲名は決まっていないですよね。曲の背景とか、説明はしていないんですか?
「伝えていないです。僕が秩父でちゃんとレコーディングしたものを送って、そうすると3日後ぐらいにハイって返してきました」
——では、アルバムで聴ける音は帰ってきた音そのままで、手を加えたりしていないんですか?
「はい、ほんとみんなスキルがすごいんです」
——サム・ゲンデルとの曲って、18分を超える長い曲じゃないですか。
「あの尺のものを、彼に送りました」
——そうなんですか。彼の場合もそうなんですけど、即興がある一方、ちゃんと絶妙に構成させているというか、重なりに起承転結のようなものがあるじゃないですか。共演者の美点を誘発させる最初のマテリアルを出した笹久保さんもすごいけど、それを返してきた彼らものすごいと思います。
「ほんと、すごいスキルだなと思いました。もう、3日とか、2日かとかで返してきていますから。サムだけは1週間ぐらいかかりましたね」
——彼の曲は長いですからね。
「サムは本当によくやってくれましたよ」
——本当にそうですよね。ぼくは周到なやりとりのもと音を送り、場合によってはポスト・プロダクションを施しているものもあるのかと思いました。
「ないです。もう丸任せで、そのままです」
——データーの交換でやっているので、一緒にせえのでやっているというのはないと思いましたが、そう言われたらそう思えてしまうようなものにもなっています。
「そう思いますよね。でも、編集も全然していないです。削ったりとかも。もう一度ここを入れてくれといった要求もしていません」
——楽譜は送っていないですよね。
「音だけです。歌が入る曲は、僕が歌ったデモを送っているんです。ヘタな鼻歌なんですけどね。鼻歌でもぼくの作るメロディが難しすぎてすごい期間がかかっているのに、モニカたちはいきなり返してくるので驚きました。曲自体はインスピレーションで作っているのですぐにできるんですが、それを覚えるのに時間がかかるんです。歌いにくいフレーズもあるので」
——なるほど。まずは、相手のことを想起しての曲であるわけですね。
「曲を作ってから相手を選んだというのはありますけど」
——そういえば、英国在住の作曲家である藤倉大さんとの『マナヤチャナ』(ソニー。2014年)はデーターの交換で作ったアルバムですよね。その時の経験が、今作に生かされている部分はありますか?
「それは、あります。あの時の作業がとても役に立っていると思います」
——今回協調している人は散っていますが、どういう部分は共通していると思いますか?
「秩父の哀愁が出ているところでしょうか」
——協調者を選んだ際の、共通する観点は何かあったりしたのでしょうか。
「特にないですね。その相手が好きで依頼したわけじゃないですか。だから、心配とかはなかったです。でも、僕の想像を超えたものがみんなやってくれました」
——とにかく、返してもらったものをそのまま出している、というのには驚きました。
「今回は他者に紹介してもらわずに、直接交渉するという手法を取りました。サムは久保田(麻琴)さんと交流があるんですけど、久保田さんを通していませんし。モニカもジョアナも、みんな直接やりました。それのやり方は、功を奏したかなと思っています」
——それで、サムとかジョアナやmarucoporoporoやフレデリコ・エリオドロは、音や声を重ねているじゃないですか。それについても指示は出していないんですか。
「出していないです。ロウレイロはピアノを弾いてもらおうかなとも思ったんですけどね」
——あの人のピアノはいいですよね。ぼくは、彼にソロ・ピアノのアルバムを出して欲しいと思っていますから。
「ほんと、素晴らしいですよね。もともとは打楽器で、ドラムやマリンバとかですよね。しかし、サムとか一緒にやりたいと思う人がもっと出てこないのが不思議ですね」
——彼の真価を知る人だったら、太刀打ちできないと思うんじゃないですか。
「それはそうでしょうね。今更こんな音楽が出てきて、これまでと全く異なる質感を持っていて。誰もがエフェクターを持っているのに、彼は違うじゃないですか。すごいセンスですよね。彼に声をかけて良かったです。これをやることによって、彼らからたくさんのことも得ましたし」
——どうして、サム・ゲンデルだけあんなに長い曲になったんですか?
「たまたま僕が弾いた曲が、即興なんですけど長くなってしまったんです。それでこれはサムかなと思って送ったら、長いので1週間ぐらいかかるかなと返事が来ました」
——そして、曲の流れに沿うように見事な音を入れてきたというわけですね。
「素晴らしいですよ。すごい感覚とスキルがある。みんなそうですけど」
——そのサム・ゲンデルとの曲は、《Cielo People》と名付けられていますね。
「“Cielo”はスペイン語で空。“People”は英語で、人々ですね。これは武甲山、秩父の民間的なコスモヴィジョンで、死んだ人間の魂は山に登っていくというものがあるんです。まあ、日本全国そういう風習はあるんじゃないかと思いますが、山に祈るとか、お祭りで山から神が降りて来るとか、そういう秩父にある世界観に基づいた曲ですね」
——あの曲、サムはどのぐらい重ねているんでしょうね?
「あれ、サックス2本だけなんですよ。あと、エフェクター使いですね。意外とシンプルなんです」
——長い曲ですし、あれを1曲めにするしかないですよね。
「そうですね。1曲目ですよね。曲順はかなり気を使いました。今回はLP も出すので、どの順序で何を入れるかには気を使いました」
——今回は、なぜアナログを出そうと思ったんですか。
「なんとなく、出したいな、と。話題にもなるし。それにここ(喫茶 カルネ)もそうなんですが、最近秩父のお店がLP づいているんですよ。同時期に(アナログ・プレイヤーを)導入しているんです」
——2曲めは、「Arorkisne, una cancion de febrero」と題されています。
「これ(Arorkisne)、アイヌ語なんですよ。ちょっとアイヌ文化にもはまっていて、秩父という名前の由来がアイヌ語らしいんです。フップという場所が秩父にあるんですが、それもアイヌ語だと研究者が言っています。Arorkisneって、こっそりという意味。2本の川があって凍っていて、でも気温が上がってくると中では水が流れていて、そのことをArorkisneと言うらしくて、それいいなと。20代のアイヌの人がつけてくれた。それに続くスペイン語は“2月の歌”という意味です」
——これは、ジョアナが歌う曲ですが、途中から入る彼女が吹くクラリネットもいいですよねえ。
「いいですね。勝手にやってと渡したら、これが戻ってきてわあラッキーと思いました。途中からギターがなくなってクラリネットの演奏だけになるんですが、ギターはなしでソロでやってくれとお願いしました」
——3曲めは、モニカ・サルマーゾが歌う《Luz ambar》。これも聞くと、歌がすごいなあと思わずにはいられません。
「すごいですよねえ。僕の中ではレジェンド的な存在で、これはモニカしかいないかなと思いました。音を送ったら、いい曲じゃないとすぐに返事をくれて、本当にいい人でした」
——彼女はサンパウロですし、そんなにミナス、ミナスと書かない方がいいような気もします。
「そうですね、書かない方がいいかもしれない。ミナスってスペイン語では鉱山という意味なんです。そして、秩父で僕は武甲山という鉱山をずっと追ってきたわけじゃないですか。それが、僕の中のコンセプトとしてあるんです」
——ブラジルのミナスも鉱山の街だったりして。
「そうです。やっぱり、スペイン語とポルトガル語は近いですね。ここで僕はブラジルの音楽家とやっているわけですが、そこがブラジル音楽のファンにどう聞かれるのか、興味があります」
——とはいえ、タイトルも『CHICHIBU』だし、ブラジルの音楽じゃない、俺の音楽だと打ち出しています。
「それしかない。向こうの土俵に乗ったら、向こうの音楽にまぜてもらっている感じになってしまうので。あと、全然別な話ですけど、昔ミルトンが70年代に『ミナス』(EMI、1975年)というレコードを出していて、それって格好いいなと思ったんですよ。日本で言ったら、これは『秩父』になるなと思ったことがあったんです。でも、まっすぐにそうしてしまうと、なんかダサいじゃないですか。そこをなんとか、『秩父』って格好良くなったらいいな、と」
——続く《Rioella》はアントニオ・ロウレイロが入った曲です。
「先ほども言いましたが、ロウレイロは面識があって、いつかやりたいなと思っていました。とはいえ、接点を見出すのはなかなか大変でした。僕はジャズを通過していないんですが、どちらかというとみんなジャズの人ですから。これは、造語のタイトルです。“Rio”は川という意味で、“ella”は彼女とかいう意味で、秩父の川を歩いているときに作った曲。川の中州につけた名前なんです。冬になると中州が現れて、夏になると消えてしまう儚い感じを表現した曲ですね」
——この曲は、彼のどういう面を引き出したかったのでしょう。
「彼には、あのファルセットで歌ってもらえれば、と。でも、ピアノも弾いてもらおうかと最後まで悩みました」
——次回に、ピアノを弾いてもらえばいいじゃないですか。笹久保さんとピアノを連弾しちゃう曲にするとか(笑い)。
「(爆笑)」
——笹久保さんは、ソロ・ピアノ作『Music Of Bukohsophy』(Chichibu、2019年)を出しています。あれは、即興ですよね。
「即興です。ピアノは弾けませんから。いい会場で、いいピアノを借りて、まったく弾けない楽器を弾くという、滅茶苦茶なコンセプトのアルバムでした。僕の精神はパンク、中にあるものはそうなんです。今でこそ、なんか音楽家っぽい感じにしてますけど、元々は不良でしたから」
——でも、それでよくクラシックのギターを習いましたよね。
「それは、(秩父が)田舎だから、周りに人がいなかった。ロックをやっている奴もいなかったし。ギターは小学校の4年生から、近くの幼稚園の放課後に教えている先生がいて、そこに行っていました。そこで中学生まで習い、高校からは東京の立川で先生に習っていました」
——結構、将来を嘱望される存在だったんですか。
「先生はちゃんとクラシックの奏者になってほしいと思っていたみたいです。コンクールで高校生の時に優勝したりもしましたし」
——じゃ、音大という選択肢もあったんですか?
「それもありましたけど、人間性がダメだったので。大学に行けるようなキャラじゃなかったです」
——その一方、ペルーのフォルクローレにも興味を持ったわけですよね。
「そうですね。独学ですけど、CDを聴いて」
——それはどうして?
「親が医療関係でペルーに1年住んだので、ぼくも0歳から1歳までペルーにいたんです。それで、父親が音楽好きだから、カセットとか日本に帰ってきてからも聴いていたんですね」
——ベルーのギター表現って、かなり即興的な部分、自由がありますよね。
「ありますね。その点、クラシックは譜面に縛られる音楽ですから、性に合わなかったですね」
——それで、再びペルーに渡ったのは?
「21歳です。17歳から人前で演奏するようにもなり、それまでは本当にクラシックのギタリストになろうかという感じもありました。同世代で有名になっている人もいますね」
——では、小綺麗な格好して、かしこまって演奏していた可能性もあります?
「なくはないですね」
——人生って、面白いですねえ。
「僕はグレていたので、やっぱりクラシックの奏者はなかったと思いますね。とにかく、海外で勉強したいというのがあったんですよ。たとえば、フランスとかに留学して帰ってきた奴を見て、ダサいなという印象を持っていた。ヨーロッパに行くとこういう感じになって戻ってくるのかと。僕はロックやジャズを通過していません。ポップスも。もちろん、Jポップは流れているものは、子供の頃から耳にしていますけど」
——そういえば、ライヴのときに周到にチューニングするじゃないですか。それは、クラシックから来ているんですか。
「そうですね」
——フォルクローレの人は、そこまで神経質にはならないですよね。
「ならないですね。ギターはやっぱり一番チューニングが大切ですね」
——その様に触れると、道を極めるミュージシャンは厳しいなあと思ってしまいます。それって、曲ごとにチューニングを代えているからでもありますよね。
「このアルバムでも代えています。訳がわからないチューニングばかりですね。ロウレイロの曲だけノーマルで、あとは全部異なるチューニングを使っています。ベルーのフォルクローレっていろんなチューニングがあって、それを少しづつ代えていっていますね」
——ギターでいろんなチューニングを使うというのは、とくにペルーの場合は顕著なんですか?
「ペルーは多いですね。アルゼンチンはそんなでもないですし。ペルーだけかもしれないですね。あとは、(アメリカの)ブルースもそうですよね。もしかして、ブルースの影響もあるかもしれない」
——ブルースはオープン・チューニングを使いますからね。昔のカントリー・ブルースの時代なんて、まっとうな弦を張ったギターなんてなかったろうし、バラバラなチューニングでやっていたと思います。
「南米は、ブルースの影響もあると思いますね。もともと、ペルーで使われるギターは鉄弦だったんです。僕はガットを使っていますけど。1950~60年代の奏者は鉄弦で弾く人もいた。だから、そこにもブルースの影響もあるかもしれない。やはり、アメリカからレコードが持ち込まれるじゃないですか」
——オーセンティックなブルース・マンはやはりピックを使わず、指で弾きますよね。
「そうですよね。調弦の概念でも繋がるところはありように思いますね。調弦を代えると、世界観が変わるんですよ」
——ですよね。レギュラー・チューニングだと定められた道しか行けないですけど、変則チューニングにするといろんな道を行くことができます。ジョニ・ミッチェルの楽曲がいまだ新鮮なのは、彼女がいろんなチューニングを使っているからでもありますから。
「そうですよね。やっぱり独特の世界観を作るには必要ですね。marucoporoporoもものすごい特殊調弦を使うんですよ」
——ジョイント・ライヴをこの1月に見ましたが、彼女もすごいですよね。いくつぐらいですか?
「25、6ですね。3年前ぐらいですね、知り合ったのは。彼女は秩父でフィールド・レコーディングしたりしていて、僕のライヴに来てくれ、知り合いになりました。縁ですよね。彼女が秩父でレコーディングしなかったら、僕は興味を持たなかったと思うんですよ」
——ライヴでは、彼女の曲を演奏していたりもするじゃないですか。
「はい、良き音楽友達であり共演者であるmarucoporoporoとの出会いは、この3年の僕の音楽に大きな影響を与えていますね。僕は今37歳ですが、20代でああいうことをする彼女を見てビビッたんですよ。この感性は僕にはないと。その存在は僕にとって尊敬の対象を超えて、ほぼ「神話的」なものになってもいます。友達ですが、あのセンスはおそるべきもの。アルバムの2曲目、3曲目、6曲目はmarucoporoporoの曲をギター・ソロに編曲している途中、そこから演奏アイデアが生まれた音楽でもあります」
——彼女はエフェクターも効果的に用いた弾き語り表現をしますよね。
「ええ。やっぱり、新しいですよね。僕はこれまでずっと先輩たちの影響を受けてきましたが、ここに来て初めて年下の影響を受け、学んだことは、僕にとっては大きなことでした。ここでも、モニカ以外はみんな僕より若いんじゃないかな。世界はどんどん変わってきていて、若い人たちから学ぶことの偉大さに気づいています。彼らは全く違う世界観で音を鳴らしてきますから。marucoporoporoはまだアルバムは1枚しか出していないんだけど、カセットも出しているので、次は3枚目になるのかな。それがどんなものになるのかとても興味があります」
——そんな彼女が歌を載せた《Lilium》に続く、最後の曲は《Chichibu》。これは、フレデリコ・エリオドロが歌とエレクトリック・ギターをスライド・バーで弾いたような音で協調しています。
「(ベーシストである)彼のことはロウレイロのバンドにいて、存在を知りました。音を送ったら僕が特殊調弦で弾いているため、ベースの役割もギターでやってしまっているので、いわゆる普通のベースを弾いてもしょうがないので、リード・ベース的な浮遊感のあるものを弾いています。ベースの役割を担わないベースというは面白いですよね」
——ジャズを知らないと言いつつ、ジャコ・パストリアスは好きですよね。前に彼の《ポートレイト・オブ・トレイシー》をカヴァーしたアルバムもありましたし(2013年作、『Quince』)。
「ジャコは好きです。僕、彼のソロのベース演奏が好きなんです。アンサンブルとか聴いてもよく分からなくて、とにかくソロの演奏に魅力を感じますね。ウェザー・リポートなんかも好きじゃないんですが、これからジャズを聴きたいとは思います」
——でも、知らないからこそ、俺のジャズができるという面もあるかと思います。
「僕、ジャズの人になりたいんですよ」
——笹久保さんの表現って、すごく研ぎ澄まされた即興感覚があると思います。ライヴでチューニングしている様を見ても、その場の空気や響きと対話している感じをぼくは得ますし、演奏も繊細かつ大胆に相乗表現〜インプロヴィゼイションしていると感じてしまいます。
「クラシックや現代音楽や秩父やアンデスやいろいろな影響が僕の中でミクスチャーされたものが、『CHICHIBU』でもあります。これまで転機はいろいろあったんですが、今回のアルバムは一つの転機といえば、転機かもしれないです。あとは、もっと海外に出たいですね」

『CHICHIBU』
笹久保伸(g)
[CHICHIBU LABEL CHICHIBU-010 (CD)]6/7発売
[CHICHIBU LABEL CHICHIBU-010LP (LP)]7/11発売
【LIVE INFO.】
笹久保伸 Live & Talk 会場ライヴ/生配信
〇7/10(土)17:00 開場/18:00開演 【会場】晴れたら空に豆まいて
haremame.com/
【掲載号】
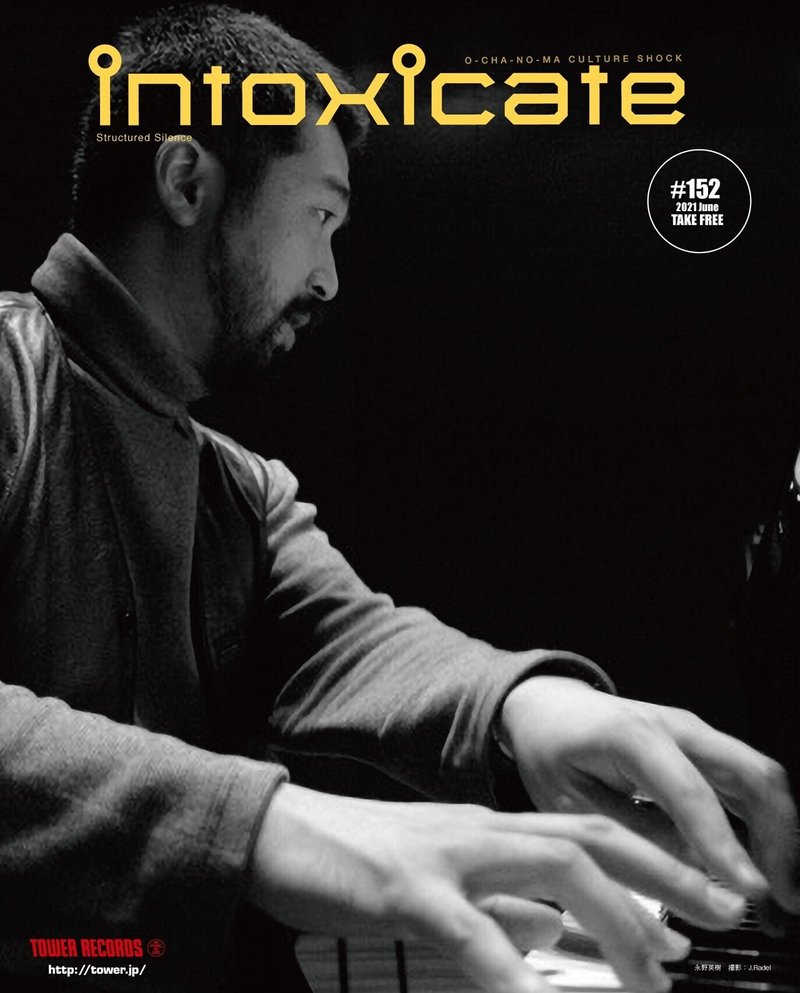
2021.6.20号
タワーレコード店舗以外の配布スポットはこちら!
▼配布一覧
https://tower.jp/mag/intoxicate/specialthanks
タワーオンラインでも購入できます!
▼タワーオンライン
https://tower.jp/article/campaign/2013/12/25/03/01
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
