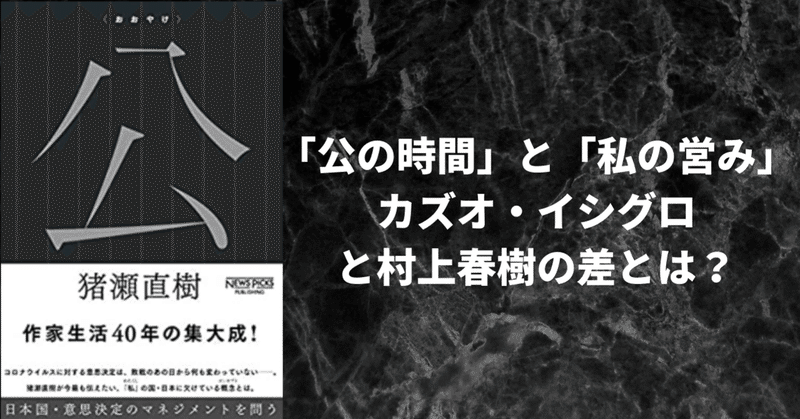
「公の時間」と「私の営み」 カズオ・イシグロと村上春樹の差とは?
『公〈おおやけ〉 日本国・意思決定のマネジメントを問う』第Ⅱ部「作家とマーケット」の冒頭「カズオ・イシグロと「公」の時間」を公開します。
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
三島由紀夫の自決を考える
三島由紀夫の評伝『ペルソナ』(文春文庫)を執筆したのは1995年(平成7年)、三島由紀夫が1970年(昭和45年)に自決してから25年後のことである。僕は40代最後の年だった。
1970年11月25日をできるだけ正確に再現するために、テレビ局に保存されている三島事件を報じたニュース番組の素材テープを繰り返しチェックした。
バルコニーで演説する姿は、いまもしばしば戦後史特集のハイライトとして使われる。
僕はふっと、ある画面で手を止めた。それは勇ましい三島の映像ではなく、ただ自衛隊市ヶ谷駐屯地の正門が映っているだけのありふれた光景だった。
看板の墨文字が「市ヶ谷駐とん地」となっている。「屯」は、たむろするという意味である。平仮名の「とん」の間の抜けた印象がたまらない。
とたんにすべてが滑稽に見えてきて、やがて悲壮感ただよわせた三島の顔と重なり、殊れみを覚えた。そうだ、あんたのせいしゃないんだよ。
こういう醜いぐずぐずこそが日常性であって、その日常性にとんな嫌悪感を抱こうか、あの戦争で300万人以上の自国民が犠牲になった結果、日本人は形而上の世界は考えないことにしたのだ。
それでよいわけがない。日本にはリアルなど何もなくて、「ディズニーランド」のような歴史の存在しない世界がただあるだけなのだ。
自衛隊は憲法上どう書かれていようと暴力装置=軍隊であることに変わりない。1960年代の日本では「非武装中立」が論壇の主流であったから、軍隊というものの存在を、そこにあるにもかかわらす「ない」ということにしていた。
いまも自衛隊は災害出動などで存在感が増してはいるが憲法改正をしていないから、正式には「ない」ままだ。軍隊ではないから軍法会議(軍事法廷)というものがない。
軍隊でない実力部隊、それも世界第8位の軍事予算(ドイツより多い)をもっている、そういう存在であっても一般の法廷で裁かれるのだ。闇夜で敵と遭遇して撃ち合いになった際に、敵かテロリストか一般人かはわからない。一般人と判定されたら、自衛隊の武器使用基準は、警察官職務執行法第7条の「正当防衛、緊急避難」なので、刑事事件の殺人罪が適用される可能性がある。これでは自衛隊員は戦えない。躊躇している間に殺されるかもしれない。
自衛隊は非嫡出子として誕生したので偏見をもって見られてきたが、品行方正に育って成人したのだから認知しなければいけない。憲法改正で「軍隊である」と書き込めばよいだけだが、それを怠ってきた。右翼とか左翼という問題ではない。戦争をするとかしないとかの問題ではない。存在している事実を認めるか否かにすぎない。そうでなければシビリアンコントロールが成立しない。制度の誤魔化しは、心の偽りである。
「公の時間」のなかの「私の営み」
そういう何もない虚しい平和という環境を、後に描くことになる僕と同世代の作家が村上春樹で、虚しさを描いてもただ甘さと苦さの入り交じった感傷が残るだけだが、村上作品はつぎつぎとベストセラーになったので僕の味覚は少数派なのかもしれない。日本人は自分が「ディズニーランド」の中にいることに無自覚なのだと思う。
カズオ・イシグロが2017年にノーベル賞をとった折、村上春樹ファンのがっかりする声が聞こえてきたが、それは仕方のないことであった。なぜならカズオ・イシグロの作品には、時間が停止した「ディズニーランド」とは異なる、歴史のなかに生きる人物が描かれているからである。
代表作の『日の名残り』は貴族の館の執事長と女中頭と、仕事を切り盛りするマネジャー同士の切ない恋心がテーマになっているのだが、第一次大戦から第二次大戦へと向かう戦間期が時代背景として丹念に書き込まれている。そこには現実の政治や国際情勢に接続している「公の時間」が連綿と流れているのである。
『日の名残り』には「公の時間」のなかに「私の営み」が叙情的に描き込まれている。
「公の時間」とは、家の土台のような確固たる事実が堆積した世界であり、個人の苦悩や葛藤という「私の営み」はその土台の上に構築されるはずだ。個別・具体的な「私の営み」を、普遍的な「公の時間」につなげるのがクリエイティブな作家の仕事である。
『日の名残り』の舞台となる貴族の館には、チャーチルも訪れればナチスドイツの高官も訪れる。そこで繰り広げられる密議は、ヨーロッパの正史そのものであった。戦後のEU体制や最近のブレグジットと地続きの世界が「私の営み」の背景として語られている。
2017年の映画『ウィンストン・チャーチル』や同年の映画『ダンケルク』とも、『日の名残り』のテーマは重なり合っている。
第二次大戦の始まりは1939年9月にドインがポーランドにいきなり宣戦布告もなく侵攻、スターリンとの密約がありソ連も同時に東から攻め、ポーランドは分割された。
東側を固めたヒトラーは翌1940年4月にデンマークへ侵攻、さらに5月にいきなりオランダを電撃空爆、ベルギー、ルクセンブルクもたちまち降伏する。フランス軍は大部隊を出動させたが防御が手薄になった背後からフランス領に入ったドイツ軍に惨敗、フランス軍と援軍のイギリス軍30万人がドーバー海峡に面したダンケルクの崖っぷちに追い詰められた。「ダンケルクの悲劇」として知られている。
映画『ダンケルク』は、イギリスの無数の漁船が兵士を助けに行く史実に即した美談仕立ての物語になっている。このときイギリスの政権はナチスに押され接近し、有和策に呑み込まれる瀬戸際にあった。いきおいを増すドイツと接近したほうが得策だとする親ナチス派の閣僚が優勢になりかけた。首相になったばかりのチャーチルと親ナチス派の閣僚との政争と、その過程でのチャーチルの決断がリアルに描かれた映画が『ウィンストン・チャーチル』だ。
『日の名残り』の主人公である執事長は、貴族の館を訪れるナチス高官と親ナチス派の閣僚の外交会議を裏方として取り仕切る姿が描かれている。
第二次大戦はナチスドイツの敗北で終わるが、勝利したイギリスも疲弊していた。売りに出された貴族の館はアメリカ人の資産家の手に渡った。戦後の国際社会は、ヨーロッパからパックスアメリカーナの時代へと移り変わる。『日の名残り』には、そのあたりの情景が淡々と描かれている。七つの海を支配した大英帝国にはかつての栄光はなく「斜陽」の時代を迎える。
第一次大戦と第二次大戦、どちらも勝者のいない戦争とヨーロッパでは認識された。勝っても得るものが失うものより少ないとわかったのだ。その認識が現在のEU体制へとつながっているのである。
そのEU体制にいま綻びが生じている。イギリスはEU離脱で国論を二分した。『日の名残り』を読み『ダンケルク』や『ウィンストン・チャーチル』を観ることで、ヨーロッパの現在を考えることができる。現在の自分たちが過去に連続するかたちで存在していることを理解する。
ところが日本では第二次大戦そのものを置き去りにしている。アメリカの「属国」として「戦前」を切り離し、「ディズニーランド」の世界にいる。カズオ・イシグロと村上春樹の読者層の違いはそこにある。「戦前」は存在しないし、いまの自分とのつながりを考えようとしない。
カズオ・イシグロの作品に較べると、日本の文学はひたすら「私の営み」だけを追い求めている。歴史から切断された「私」の虚しさを追い求めても、辿り着く地平は陽炎のようにただ遠ざかるばかりだ。
ヨーロッパ文学であるカズオ・イシグロの作品は、「公の時間」と「私の時間」がバランスよく拮抗している。「私」というものが「公」と結んでいき「私」の葛藤はそのなかで現れるのだ。
ところが、1970年に三島由紀夫が自決し、それ以降の日本の文学は、「私だけの空間」になってきた。
日本の文学というのは、私的な空疎さ、自分のなかの空疎なものを探しあぐねているだけで、「公の時間」が見えない。近年の日本文学は、虚しい「私」の空回りである。
(公開はここまで。続きは書籍をお買い求めください)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
オンラインサロン「猪瀬直樹の近現代を読む」、会員限定追加募集中です!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
