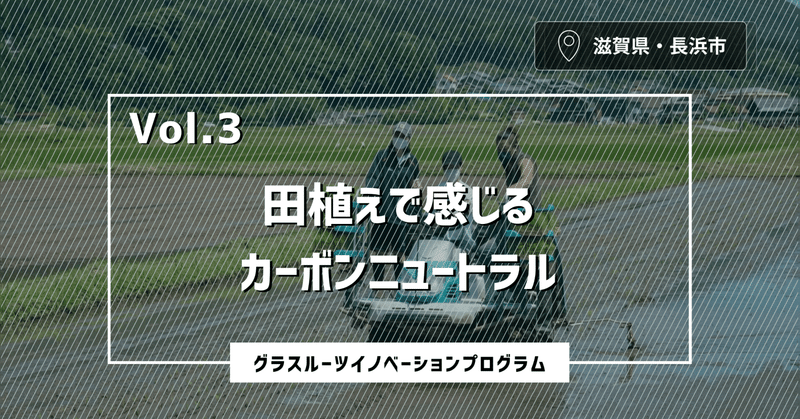
【GRIP.3】田植えで感じるカーボンニュートラル
こんにちは。
インパクトラボの佐藤です。
今回は、6月12日(日)に実施した虎姫高校新聞部、立命館大学生を対象とした長浜市西浅井町での田植え体験の様子をお届けします。
この取り組みは、2022年度立命館大学グラスルーツ・イノベーションプログラム(GRIP)に採択された「カーボンニュートラルを軸とした新たな教育パラダイムの創出・実践・量的評価指標の開発」(代表者:山中 司・立命館大学教授)の研究の一環で実施しています。(注)
田植えにチャレンジ
田植えを始める前に、西浅井町庄地区で活動しているONE SLASHの清水さんより、米作りの現状や新しいチャレンジとしてライスレジンについてお話を伺いました。

ライスレジンは、バイオマスレジンホールディングスが提供する日本初の非食用のお米を原料とするバイオマスプラスチックです。脱炭素、カーボンニュートラル、脱プラへの機運の高まりにより注目されています。ライスレジンを活用することで、CO2を大幅に削減することができます。

清水さんは、西浅井でつくったお米をライスレジンに使用する新たな挑戦ができるのはないかと考えているそうです。
説明後は、実際に田植えを行いました。田んぼ入ると、蛭(ひる)がいてみんな驚いていました。蛭がいるということは、蛭が食べるエサが豊富にあり、そのエサのエサも豊富にあり、という食物連鎖が成り立っていて、栄養分が豊富な土壌であることを示します。また、蛭は人間の古い血液を吸うとのことです。

今回は、田植え体験で一般的な手植え体験と機械での田植え体験のどちらも行いました。
今までは、田植えというと手植えのイメージがあったと思います。しかし、現代では機械で作業する方が主流です。そのため、実際の農家が田植えをしているように、田植え機に乗って、田植えをしました。田植え機に乗る機会が今までほとんどなかったので苦戦しましたが、楽しみながら田植えを体験が出来ました。

田んぼを管理する最新のシステムを見学
田植えのあとは、周辺の田んぼで最新の技術を取り入れた取り組みについて見学しました。
まずは、ソーラー基地局から水位を管理し、スマホから水門の開閉を操作できる仕組みを見学しました。今までは、手作業で田んぼに入る水門を調整していましたが、この仕組みが導入されたことで、電波が届く範囲であれば、どこからでも農業に参加することができます。そのため、現地にいなくても農業に関わることができ、多くの関わりしろをつくることができます。

そのあと、たんぼアートを見学しました。田んぼに描いているのは、「コメコイン」。最近注目されているNFTの仮想コインとして価値を生み出すことで、一次産業のあらたな収入源になるのではないかと取り組みを始めています。これから、稲の収穫時期になるときれいに形が浮き出てくるのが楽しみです。
散策をしていると、水路が多いのが印象的でした。地域のみんなが利用する水路であるため、どのように水が行き届くようにしていくのか、きれいな水を守り続けることはとても大切です。
川や水路でコアユなど遡上している魚を見ることができました。このような景観・自然を守っていくためにも、農業のあり方を考えていく必要があるのだと感じました。
最後はみんなで炊き出しご飯
ツアーの最後には、ONESLASHの皆さんが釜でご飯を炊いてくださいました。今回は「コシヒカリ」と「いのちの壱」の2種類を用意してくださり、食べ比べをしながらいただきました。いのちの壱は粒が大きく、香りや粘りがすぐれているのが特徴です。食べ比べていましたが、炊き立てのご飯はどちらも本当においしかったです。

今回は、若い世代が田植えで感じるカーボンニュートラルの様子をお届けしました。田植えだけでなく、それを支える自然の営み、ひとのちから、新しい技術を見ることができたことで、より食のありがたみや食料生産の現場を深く感じることができたのではないかと思います。
脱炭素やカーボンニュートラルの取り組みとして、ゼロカーボンビレッジと呼ばれる取り組みが注目されています。今回の遠隔管理システムを太陽光パネルでエネルギーを生み出したり、用水路を利用した小水力発電により、エネルギーを地産地消をすることができる可能性があります。そのようなモデル地域に今回訪問した長浜市西浅井町は可能性があると感じました。さらに、これらの取り組みを若い世代が学ぶことで脱炭素を意識したまちづくりをイメージしやすいと思います。
(注)立命館大学グラスルーツ・イノベーションプログラム(GRIP)
R2030チャレンジ・デザインでは「次世代研究大学の実現」と「イノベーション・創発性人材の育成」を目標に掲げ、研究・教育を通じて社会課題を発見・解決し、社会と共有される知的価値である「社会共生価値」を創造していくことを目指しています。
グラスルーツ・イノベーションとは、社会共生価値の創造に向けてビジョンを共有する内外の関係者が、課題解決を必要とする地域・場所に赴き、その場で知の循環を図りながら研究成果を実装し、システムとして根付かせる「草の根型」の研究・地域連携の実践を意味しています。
本プログラムは、グラスルーツ・イノベーションの理念に共感し、地域の課題解決に取り組む草の根型の研究プロジェクトを支援することを目的としており、人文社会科学や自然科学といった研究分野を問わず、本大学の研究成果を利用した、地域での実証実験や、地域課題の発見・抽出のためのワークショップ・調査等により「総合知・実践知」の蓄積に資する活動を広く支援の対象としております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
