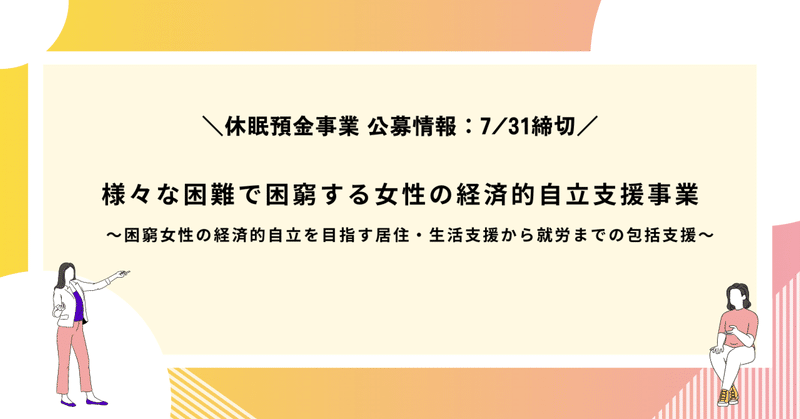
【休眠預金事業 公募情報:7/31締切】様々な困難で困窮する女性の経済的自立支援事業~困窮女性の経済的自立を目指す居住・生活支援から就労までの包括支援~
公益財団法人パブリックリソース財団が資金分配をする、通年枠(3年)の休眠預金事業が2023年7月31日まで公募されています。

2023/6/6時点の画像
本事業で行う「包括支援」は、ハード(住まい)とソフト(居住支援、就労に向けた自立支援まで)と幅広いので、助成金額が3年間で1団体あたり5000万円上限と金額が大きめです。
女性包括支援の全体像のなかでどの部分を行うのかの整理が必要
包括支援と副題にあるように、経済的困窮・虐待や DV 等様々な困難を抱える若年女性、生活困窮下にあるシングルマザー、不安定雇用下の低収入で困窮する単身女性等を対象として、居住支援・生活支援・回復支援・就労支援の各支援を、当事者の状況に応じて包括的に支援を提供することがもとめられます。

「こうした広範囲な事業を1団体がすべてを担うのでなく、地域資源を繋げることに重点を置いた包括的な支援モデルの構築を目指す」と書かれている通り、全てをカバーする必要はありません。が、ここで示されている各支援が、地域のどの組織が担っているのかや、どこが空白なのかを把握した上でで事業計画をする必要はあります。
経済的困窮等を抱える女性支援において3年以上の活動実績がある、非営利組織の団体(企業や非営利型ではない一般社団はNG)で、有給職員が1名以上いることが要件に含まれていることから、当事者に対して影響のある活動をしていることや、地域の自治体・NPO・企業などとのネットワークの中で一定の存在感があることが求められています。
3年後の短期アウトカム実現に向けた3つの事業設計の必要性
本事業の成果目標として3年後の短期アウトカムとして以下3つがあげられています。
1.実行団体における変化
困窮女性の経済的自立を目指した切れ目のない包括支援のモデル事業となり、他地域への波及が促進されている。
「経済的自立を目指した」包括支援の事業のモデル化が求められているので、特に出口戦略に比重が置かれているような印象を持ちました。「企業連携の広がり」を事業設計として入れておく必要性を感じます。
つまり、この事業では当事者に対して、福祉的な支援もしつつ地域で理解してくださる企業数を増やしていき、協働事業を複数実施する道筋がいるのではないかということです。
2.受益者における変化
かつて困窮していた女性が、本事業を通じて支援を受けたことにより、継続的に働き、経済的自立を果たし、自己決定できる状態となっている。
経済的困窮を抱えている女性への支援は、一部の企業が主導して行っているケースはありますが、その企業の業種や職種にどうしても限定されてしまう現状がありました。
継続的に働くとなると、個々人の特性にあった職業選択が必要になります。自分の得意なこと、自分の特性、今の生活における制約等を考慮して、職業を支援者と相談しながら「職業選択」をしたり、何らかの「意思決定」をしていくには、中長期のかかわりがあったり、関連する支援機関や組織との連携体制がないと当事者との信頼関係が構築できません。人ひとりの人生に関われる体制がある団体であることが、求められている受益者の変化のためには必要そうです。
3.社会における変化
困窮女性の存在と彼女らが必要とする経済的自立のための支援の理解が進み、法制度の整備が進み公的資金の充実化が図られ、民間資金も呼び込みながら、セクターを越えて、支援に必要となる機関、団体、企業等が連携し協働する仕組みが各地でうまれている。
休眠預金事業では3年間の短期アウトカムについて指標化と目標設定を行い事前・中間・事後評価をしていきます。今回のように要項に成果が明示されている場合は、ロジックモデルの短期アウトカムにそれを含めておく必要があります。
つまり、「関係者への理解」をどのように拡げていくのか、「セクターを超えた協働」をどのように生み出していくのか、「公的資金の充実と民間資金の呼び込み」をどうするのか、この3つが問われています。
これを行うには、団体の広報力、事業開発力、行政との調整力、企業への提案力、まとめていく事務力、等が必要です。こうした当事者支援の周縁に関わる力を持っている団体は少ないので、この部分が少し足りない場合は組織体制強化の計画も盛り込んでいく必要があります。
申請をするところから第三者の関わりが必要
休眠預金事業のような複数のセクターをまたいだ協働が必要だったり、社会的インパクトを見ていかないといけない事業の場合は、「第三者の関わり」がとても重要です。
それは、どうしても事業を推進する立場では、評価をするために指標を設定するとか、情報を収集する、現状を価値判断をする等の作業は受益者のための活動とは直結していないためモチベーションがわきにくいのと、主観的な視点でみてしまいがちだからです。
指定活用団体のJANPIAが発行する評価のハンドブックにおいても、折に触れて第三者の関与の必要性が書かれているのは、こうしたことがあるからです。
しかし、実行団体において評価アドバイザーを継続的につけているところはあまり見たことがありません。
地域にそうした人材はいるとは思うのですが、業務委託として何をお願いしたらいいのか切り出しにくいことが一因にあると思います。団体側がよく理解している業務は切り出しやすいですが、これまでやったことのない業務を契約書に明記するのは難しい作業です。
しかし、こうした休眠預金事業の通常枠をとりにいくのであれば、事業設計・申請書作成・事前評価・中間評価・事後評価と継続的に関わってもらえる第三者の存在が必要だと思います。
このnoteを読んで申請をしたいと思った団体さんは、是非申請書作成の段階から第三者に関わってもらってください。
ここから先は
記事を読んでくださいましてありがとうございます。少しでもお役に立てれば幸いです。おかげさまで毎回楽しく制作しております。皆さんからの応援があるとさらに励みになりますので、サポートお願いいたします!!
