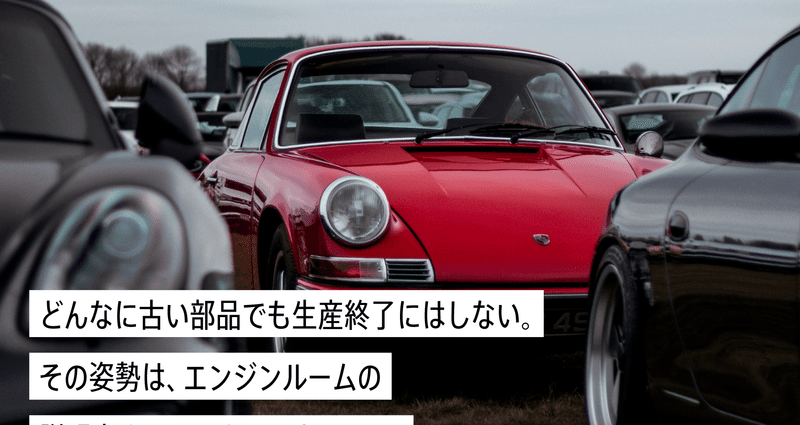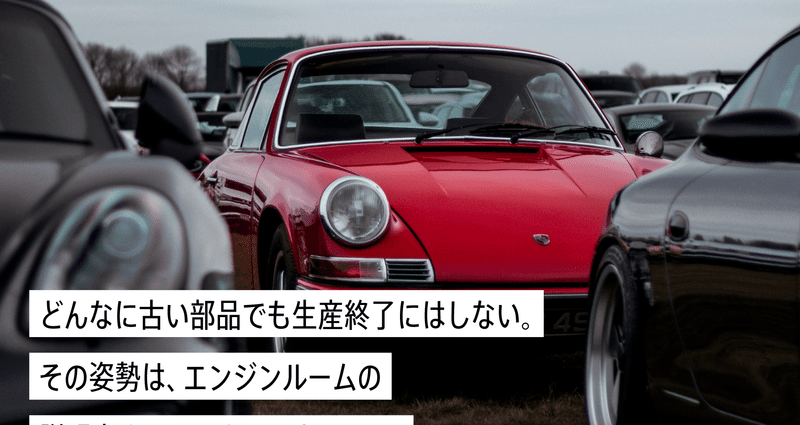固形シャンプー:液体を固体にすることで容器が不要に (CASE: 34/100)
▲「固形シャンプー」とサステナビリティ
シャンプーは液体である、という常識は覆されつつあります。
固形シャンプーとは、その名の通り、固形石鹸と同じ見た目をしたシャンプーです。髪を濡らし、直接シャンプーを頭皮につけたのち、手で泡立てて使います。
私の住むドイツでは、写真のようにすでに多様なブランドから異なる髪質・頭皮向けに商品が開発されており、紙のパッケージに入れられて、ごく普通にドラッグストアの棚に並んでいます。
消費者のエコ意識の高まりからこの数年で普及が進みましたが、日