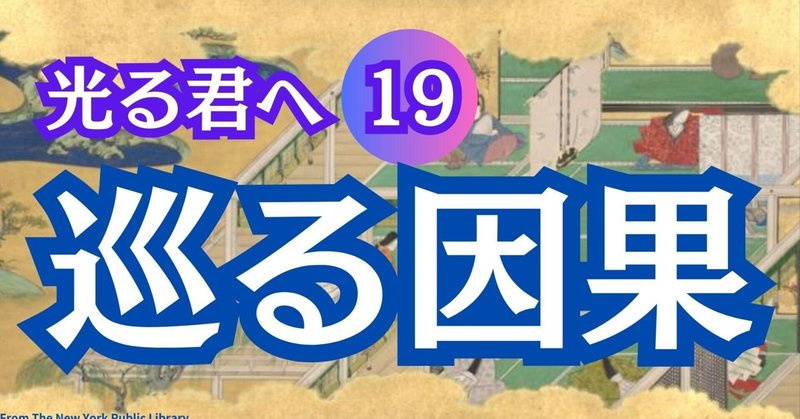
光る君へ(19)道長が為時を推挙するための脚本的な手続き・大河ドラマで学ぶ脚本テクニック
大河ドラマ「光る君へ」が面白い。ということで、「「光る君へ」で学ぶ脚本テクニック」と題した動画を作っていくことにしました。動画といっても内容はスライドとテキストなので、noteにも載せていきます。今回は第19回の学びポイントです。
歴史の知識や「源氏物語」については一切触れませんので、予めご了承ください。
今回の学び

今回のテーマは「巡る因果」です。
巡る因果
ここまでの構成

今回道長は右大臣になり、政の頂に立ちました。第3部の始まりといった感じですね。
ここまでの構成を俯瞰すると、道長一家のストーリーで3つに区切ることができます
第1部は、第1回の詮子の入内から、第10回の寛和の変(かんなのへん)まで。兼家が権力を掌握するまでのストーリーですね。
第2部は、第11回の一条天皇即位から、第18回の七日関白まで。棚ぼた式に道長に権力の座が回ってくるストーリーですね。
で 今回の道長右大臣就任から始まるのが第3部。おそらく長徳の変中心のストーリーが展開するのでしょう。
こうやって構成を俯瞰してみると、道長一家のストーリーが、為時の就職と失業という形でまひろ一家に大きな影響を及ぼし、そのふたつがうまく絡み合って全体のプロットを形作っているということがよくわかります。
見事だと思うのは、その絡ませ方です。
細かい因果関係を何段階も重ねることで ご都合主義に陥らないよう工夫しています。
どういうことか、具体的に説明します。
因果のすごろく

今回、右大臣になった道長が、まひろの父・為時を従五位に推挙します。
道長には、為時の就職を世話する動機がありますし、今回そうする権力を得たわけですが、そこを短絡してしまったのでは道長のキャラに合いませんし、ドラマとして面白くありませんよね
だから、あえてすごく回り道をして、細かい因果関係をすごろくみたいに繋いで描いています。
まずは道長が、若狭に来た宋人について陣定を行おこないます。
ききょうがその話をすると、まひろは宋の政について熱く語ります。
ちょうど新楽府を学んだところだったからです。
ききょうは面白がってまひろを中宮に紹介します。
すると突然そこに帝が現れます。
この帝の登場がご都合主義にならないのは、帝が中宮にぞっこんであるというこれまでのプロットが生きているからです。
話はそれますが、この「大人の」シーン、目配せだけですべてを語らせるのがとても面白いですよね。
まひろは目だけで「エッ真っ昼間ですけど!」って言ってます。
その目に「お上と中宮様は重いご使命を担っておられますので」と、すまして答えるききょうも最高です。
話を元に戻すと、その後まひろと帝は新楽府の話で意気投合し、帝からそれを聞いた道長は申文を探して為時を従五位に推挙します。
エピソードとしては地味ですが、脚本のテクニックが感じられて とても面白いと思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
背景画像:
From The New York Public Library https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e3-fe62-a3d9-e040-e00a18064a99
動画
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
