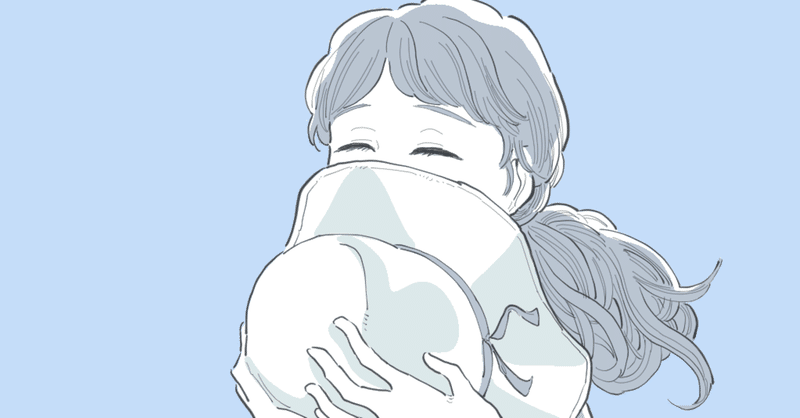
ものがたりの途中
誰もが、ものがたりを抱えて生きている。でも、それは落丁・乱丁だらけのもので……大切な部分に限って抜け落ちているような気がしてならない。
人はいつか死んでしまうということを、初めて知ったのはいつだったか。そのとき、どう感じた? ……そんなことも忘れて生きてるなんて、気持ち悪い。もし、言葉にできないような、しちゃいけないような思いを、全てとっておく術があったなら……よかった?
「産んでくれなんて頼んでない」
そんな言葉が喉元まで来るたびに呑み込んだ頃のことなら、よく覚えている。使い古された定型文だけど、中身はあった。重すぎるぐらいに。切実に、本気で、生まれたくなかったって思った。あれは「反抗期」特有の感情なんかじゃない。今だって別に、なくなったわけじゃない。ちゃんと、忘れてない。
わけもわからず生まれてきた子に、言っていいことと悪いことを教える。「普通」と「異常」のイメージを植え付ける。生まれる前からある決まりに背いたら正す。そんなの、ずるいじゃんか……って、なんで誰も言ってくれないんだ。そんで、なんでまた、同じこと繰り返すんだ。新しい誰かを、喜び悲しみ苦痛とか、善と悪、とか、そんなのが中途半端に混ざってて偏りっぱなしの世の中に晒すなんてこと、なんで、何百万年も続けてこれたんだ――。もうこのへんでやめましょうって、誰かが言ってくれていれば。……無理か、普通に考えて。
「ねえ」
彼女の声に、ふっと顔を上げた。……目をまっすぐ見ることはできなかった。彼女が他愛のない話を始める。相槌を打つ。彼女の腕には、痛々しい傷跡がある。……いったい、どんなものがたりが刻まれているのか。そんなことも知らずに一緒にいていいんだろうか?
いや……、でも……背負える? 彼女の分まで。自分の中の痛みと後悔だって、どう扱ったらいいかわからないくせに。
「今の私だけを見てくれないかなあ」
彼女の声はずいぶんとのんきな調子だったけれど、心を見透かされたような気がしてどきっとした。
「それでいいの?」
「それが、いい」
「でも」
「無理?」
「かも、しれない、だって」
「なに?」
「平気なの?」
「……わたし?」
「だって、そういうのってさ、見るたびに、その……」
「……まあ」
「痛みとか、後悔とか」
「思い出すよ」
「……なんで生きてこれたの」
「死ねなかったから」
「……それ、苦しくない?」
「今は、平気。たぶん」
「なんで?」
「死ななくてよかったって思えるから」
「それは……」
「んー……あなたがいるから?」
「……まじ?」
「……とか、言ってみたかった」
「……言われてみたかった、かも」
「そっか、よかったね」
彼女が、笑った。きれいに。それは、彼女自身の物語を、一瞬だけ、漂白するような笑顔だった。
つられて、自分のものがたりも……というわけにはいかなかった。もう解放してくれって心が悲鳴上げてるのに、なんでか、どこかで、どうしても忘れたくないって抵抗しちゃってる、そんな厄介な記憶が、こんな時でさえ顔を出す。
ほんとは、ふたり一緒にものがたりを捨てられたらよかったのにって、それができないなら、誰かを好きになるって、絶対、そのひとのものがたりごと好きになるってことじゃなきゃ駄目なんだって思ってたけど、そんなことないのかなって、だって……。
今この瞬間の彼女が好きだ。
唯一確かな気持ちが今ここにあって、この先のものがたりも、そんなものの積み重なりで続いていく。
なんか、たぶん、これでいいんだろうなあ。
――何生きちゃってんだよ、馬鹿。どうせ死んじゃうくせに。
……うん、ほんと、そうなんだよ。わかってるんだけどさ。
馬鹿でもいいや、と開き直ってみる心地は、案外悪くないなと思えた。
高校3年生のときに書いたものがたりです。10代にしか書けない文章を書きたい、と強く思っていた頃。
ある時、友達の腕に、明らかに自分でつけたような傷跡があるのを見てしまいました。いくつも。私は見て見ぬふりをして、何も言えなくて、それで、すごく……言葉にできない気持ちになりました。
何も言わなくてよかったんだと思います。共感できるわけじゃない。気の利いた言葉もかけられない。そもそも私にそんなことは求められていない。わかった気になるべきじゃない。私はただ、一緒に遊びに行って、おしゃべりして、それで、あの子も楽しいって思ってくれたなら。
痛かったね、とか、大丈夫だよ、とか。無条件に安心させてくれるような誰かが、あの子のそばにいてくれたらいいんだけど。どうかな。そんなことも全然、わからない。
モヤモヤが消えなかったから、開き直るために書きました。わからないことだらけでも大丈夫だって。傷があっても、死なずにいれば、別に恋愛に限らず、誰かと、何かとつながって、これでいいんだろうなあって思える瞬間があれば、生きていけるんだって。
目に見えない痛みとか後悔だってたくさんあるけど、純粋にきれいじゃないものがたりを背負ってるけど。私だって、誰かに全部を語る気なんてない。どんなに親しい相手でも。じゃあ、そんなものでしょ。そういうもので、いいんじゃないの? あの傷は、目に焼きついて離れてくれないけど。本当は、そういうの、話したいって思ってもらえて、ちゃんと受け止められる人になりたいんだけど。まず自分の心に余裕がないと無理だろうな。
あの頃は余裕なんてなかった。自分のことばっかり。10代、ってことにやたらとこだわっていた。執着。どうしても若いうちに好きなことで認められたいって本気で思っていた。中学生の頃から目指していた小説新人賞も、高校生になって新しく見つけた目標の脚本賞も、たまたま、私が一番必死で夢中になって書いていたときに、私よりも年下の10代の子が最年少受賞した。何者でもないくせに馬鹿みたいだけど悔しくて、羨ましくて、焦った。焦燥、後悔、羨望、不安。そういうもので構成された、ぐちゃぐちゃした重たい創作意欲に突き動かされていた。
「もう10代は半分過ぎたんだよなぁ」、そんなことを友達と話したのが、本当に、つい最近のことのように思える。私はあと3か月とちょっとで10代じゃなくなる。でも、あの頃とはまた何か違う。あんな焦り方はしていない。余裕があるかどうかは微妙だけど、とりあえず、さすがに、10代じゃなくなったからってその瞬間何かを失うわけじゃないってわかるから。価値が、とか思ってたなら、ちょっと悲しい。もっと大事なことがある。私は私、って、当たり前なんだけど。
開き直った。もう別に認められなくてもいい。才能とか、年齢とか、もうどうだっていい。ただ、私はやっぱり、ものがたりを書きたい。10代にしか書けない作品、じゃなくて、私が書きたいのは、痛みとつながりを大切にする、そういうものがたりだ。
やっと、認められたい、よりも書きたい、が先行してくれた。最初はそうだったはずだから、お帰りって感じなのかな。わからないことだらけだけど、この気持ちは確かで、なんだかワクワクしてきた。書きたい。今の私なら、何をどう書くんだろう。わからない。とにかく、書きたい。
認められなきゃ、私が死んでも生き続けるような作品じゃなきゃ意味がないんだよ、とかってあの頃の私は言いそうだけど。別にいいやって開き直ってみる心地は、確かに、案外悪くないなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
