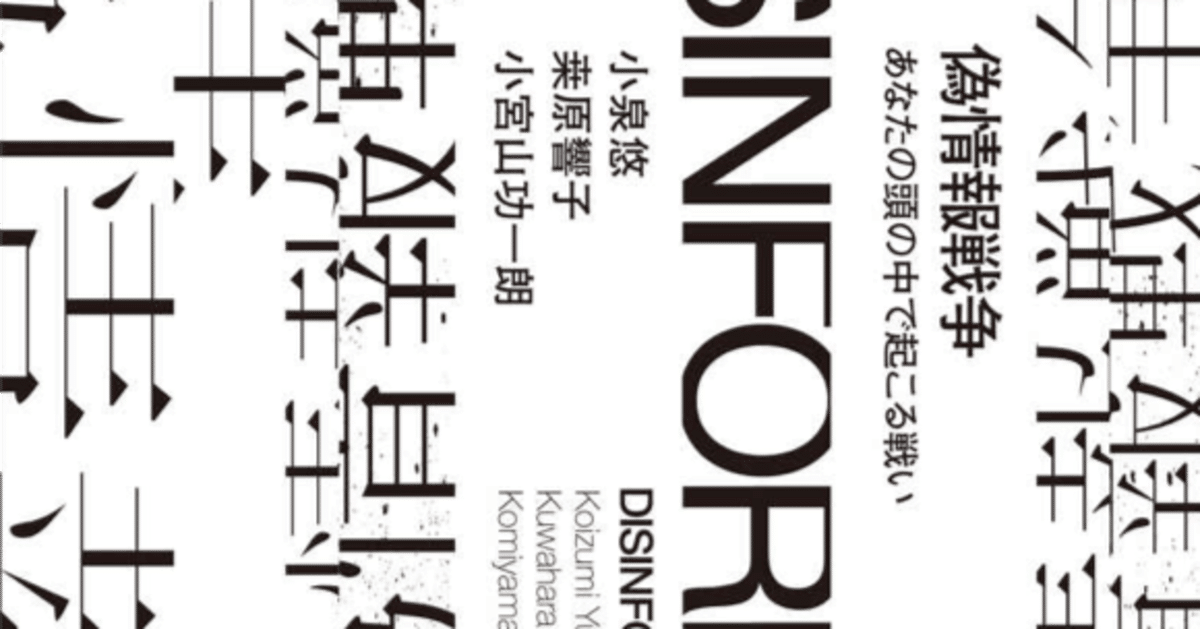
注目の3人=小泉悠、桒原響子、小宮山功一朗の『偽情報戦争』を読んだ
『偽情報戦争 あなたの頭の中で起こる戦い』(ウェッジ、2023年1月19日)は、中国やロシア、サイバー関係で著名な3人=小泉悠、桒原響子、小宮山功一朗が集って、偽情報=ディスインフォメーションについて書いた本である。
●本書の内容
全部で7章あり、最後に3人の著者の鼎談がある。
・第1章外交と偽情報 ディスインフォメーションについての概要
本書で扱う内容の概要と、言葉の定義をおこなっている。ディスインフォメーションをめぐる世界の状況と日本との対比などが描かれている。定義はかなりくわしく書かれており、パブリック・ディプロマシー、プロパガンダ、影響工作、戦略的コミュニケーションなど類似の言葉との違いまでくわしく解説されており、重宝する。
ディスインフォメーションに関する世界と日本の現状がわかりやすくコンパクトにまとめられている。
・第2章中国の情報戦 中国の情報戦を具体的な例をあげて解説
中国の情報戦について、全体的な流れを説明し、次に日本における実態を駐大阪中国領事館を例にあげて解説している。余談であるが、薛剣総領事の着任時期が本文とグラフで異なっているので、どちらかが間違っているのだろう(おそらくグラフ)。
世界および日本で中国の戦狼外交的な情報戦が必ずしも成果をあげていないと分析し、今後台湾有事をみすえた活動が活発になるだろうと予測している。
・第3章ロシアの情報作戦 ロシアの情報作戦の理論を執心に解説
最初にプーチンの世界観について解説があり、続いて情報戦理論の系譜の解説がある。情報戦理論の解説は初めて知ることも多く、とても参考になった。
国内向けの情報戦争、ウクライナに対する情報戦、アメリカに対する情報戦と解説が続く。
・第4章ポスト「2016」の世界 アメリカ大統領選でのロシアの介入後からウクライナまでを解説
まず、2020年アメリカ大統領選と2022年のウクライナ戦でロシアの情報戦がうまくいっていないことを解説。
続いてゼレンスキーの活躍の紹介と、情報の非対称性について整理されている。ここでの情報の非対称性とは、ゼレンスキーの活躍は報道される一方で負の部分が報道されないことや、西側のストーリーが主として報道されている現状の指摘である。
・第5章情報操作とそのインフラ 物理インフラとしてのケーブルと論理インフラとしてのSNSを解説
サイバー空間のインフラを物理インフラ、論理インフラ、情報の3つに分けている。物理インフラとは海底ケーブルやデータセンター、通信衛星など。論理インフラとは情報通信に必要だが、物理的な制約のないもの=メッセージングサービス、SNSなど。そしてこれらのうえで情報がやりとりされる。
まず、物理インフラとしての海底ケーブルをめぐる戦いを紹介し、ついで論理インフラをめぐる問題を紹介している。
・第6章民主主義の危機をもたらすサイバー空間 民主主義の危機とサイバー空間あるいはテクノロジーがどのように関係しているかを解説
民主主義という政治形態全般に、サイバー空間が及ぼす影響を検討している。当初期待を持って迎えられたサイバー空間が、民主主義を脅かすものとなった原因について、3つの誤算があったと指摘する。
1.ディスインフォメーションの危険性
2.民主主義というシステムの持つ問題
3.サイバー空間のガバナンスの問題
それぞれについて考察し、テクノロジーによる民主主義の可能性を示している。
・終章 日本の情報安全保障はどうあるべきか
日本も脅威にさらされていることを指摘し、情報安全保障について整理している。この章はとても短い。
・巻末鼎談
3人の鼎談が記録されていて、きれいにまとまってはいないが、前述の情報の非対称性やSNSプラットフォームなどさまざまな問題について、それぞれの視点で語っていて、興味深い。
三人三様の問題意識と視点で参加しており、きれいに噛み合っているわけではないが、類書にない情報や切り口があった。知らなかったことや読んだことのない資料も紹介されていて参考になった。ただ、ディスインフォメーションについて少し知識のある人が読むとすごく役に立ちそうな気がした。わかりやすく書かれているので、ほとんど知らない人が読んでも問題ないと思うが、戸惑うこともありそうな気がする。
●感想 気のついた点
本書はこの問題に関心のある方にはおすすめできる1冊であり、他にはない視点と情報が掲載されていてとてもよい本だと思う。大きな瑕疵はないと思う。……ということを前提に、いくつか気になったことを書いておきたい。
・西側大手メディアによるアジェンダ・セッテイング
何度も書いてきた国際世論についての話が、「アジェンダ・セッテイング」と呼ばれていることを知った。知らないことが多すぎて恥ずかしい。
なお、ウクライナ国内は自国の負の部分を報道してはいけないという自粛が広がっており、軍隊の不祥事が闇に葬られている。この風潮に対する告発記事が出ている。
Kyiv Independent紙が告発 ウクライナのメディアの自己検閲
https://note.com/ichi_twnovel/n/n44e1b7e9829a

・国内向けデジタル影響工作については触れていない
デジタル影響工作では国外向けよりも国内向けの方が多いことはいくつかのレポートでわかっている。特に選挙において用いられることが多く、世論を歪め、民主主義を毀損している。本書では第一章の定義でも国内向けに当てはまるものがなく、唯一近いのはプロパガンダくらいである。日本が国内のフェイクニュース対策にとどまっているという解説も国内向けと言えなくもないかな。また、他の章でも2章でロシアがおこなった情報戦争の解説があるくらいだ。
国内向けと国外向けは異なる点が多いので、分けてもよいと思うのだが、その場合は分けていることとその理由を明示してあった方が親切だと思った。
どんな形であれ、デジタル影響工作をおこなう場合は国内向けの体制を整える必要がある。
・日本でのディスインフォメーションについて
本書で、日本は深刻なディスインフォメーションにさらされていないということが何度か書かれているが、個人的にはアメリカおよび政権から発信されるディスインフォメーションを許容してきたことが背景にあるように思える。アメリカと時の日本の政権はどちらも国内と言っても差し支えないだろう。これらのディスインフォメーションを浸透させるためには対策はない方がよいという判断もあったかもしれない(誤った判断だが)。
アメリカの施策を円滑に日本で実施するための工作はもとより、比較的最近では「江戸しぐさ」という偽史を文科省認定教科書や教材でも使われ、新聞にも多数登場した事件もあった。もっともこれはいまだに「事件」と認識されていないようだ。余命三年時事ブログによる大量懲戒請求事件などもあった。細かく見ていくと、国内でさまざまなアクターが人々を扇動していることが起きている。これらは日本人がディスインフォメーションによる扇動へのガードが甘いことに起因し、そうなった原因はアメリカと政権の扇動を受け入れやすくしてきたことせいのような気がする。
その是非はおくとして、こうした背景が仮にほんとうにあったとすると改善はかなりやっかいだ。
・SNSプラットフォームについて
プラットフォームの役割や影響が大きいことは本書でも何度も触れられているが、プラットフォームがほぼ意図的に反ワクチン、極右、差別主義、陰謀論を支援していることには触れていない。
フェイスブックがこうしたコミュニティを優遇していたことはフェイスブックペーパーで明らかにされ、大スキャンダルとなった。グーグルは多額の広告費用をこれらに支払い続けているだけでなく、こっそりと中国やイスラエルに対して検閲機能つきのサーチエンジン、クラウドサービスを提供しようとしている。
彼らは結果的にこうした問題のあるコミュニティの温床となる道を選んでいる。こうした問題もとりあげてほしかった。
●こまごま気になったこと
・BLMにロシアが介入していたことは
当時SNS監視システムを全米に売り込んでいたZeroFOX社がボルチモア市に送りつけた提案書(“危機管理(Crisis Management)” と題する二十二ページのレポート)の中ですでに暴かれていた。BLMはSNS監視システムが全米に普及するきっかけにもなった事件だった。くわしくは『犯罪「事前」捜査』(角川新書)。
・中国がロシアが使っている「サイバー主権」
という言葉を使わなかったのはなにか意図があったのだろうか? あと、この話題ならWCIT2012年は入れてほしかった。
民主主義とサイバー空間だとフランシス・フクヤマの論考などもあったことを思い出した。
民主主義以外の選択肢というと、『Against Democracy』くらいしか読んだことがなかったので勉強になった。
ビッグテックの影響について若江さんとほぼ同種の主張をイアン・ブレマーもおこなっていて、最近公開された中国の新しい方針を予言した内容になっていたので参照してほしかった。
・ゼレンスキーの負の部分
については、下記のような話もある。出典は末尾を参照。拙著『ウクライナ侵攻と情報戦』でもいろいろ紹介しています。
ウクライナの4分の1以上がSNSを主なニュース源としており、その3分の2は主にFacebookを利用している。アクティブなボットが確認されており、最も多くのボットがフォローしていた政治家は、ゼレンスキー(27,926)だった。次いでポロシェンコ(20,065)で、それ以外はかなり少なかった。ボットが投稿したコメントのほとんどはネガティブなものだった。
Erase This If You Can. What Ukrainian Bots Are Doing on Ukrainian Politicians’ Pageshttps://voxukraine.org/en/erase-this-if-you-can-what-ukrainian-bots-are-doing-on-ukrainian-politicians-pages/
ゼレンスキーは当選すると臨時総選挙を仕掛けた。この時、組織犯罪と汚職の告発を行っている団体OCCRPのジャーナリストが潜入捜査を行っている。トロール工場は2つあり、DopingとPRagmaticoで、潜入したのはDopingである。潜入した記者は月給365ドルで働き始めた。これはウクライナのマクドナルドのレジ係と同じだそうだ。稼働は朝8時から夜11時までの3交代制だった。使用するSNSはフェイスブックのみ。1日に数回仕事の指示があり、たいていは人気の記事にコメントすることで、1日あたり300コメントしていた。そのオフィスには潜入記者以外に10人ほどの男女が勤務していた。主に進歩的で当選可能性のありそうな候補者を支援していた。当選可能性がなくなると、すぐに他の候補者の支援に変更された。このトロール工場のマネージャーによると、月1万件の書き込みで5千ドルから7千ドルがかかるという。記事では進歩的な候補者を当選させるよう依頼した人物は特定されていない。
また、JENSAと呼ばれる手法も多様していた。くわしくは『ウクライナ侵攻と情報戦』(扶桑社新書)。
・アゾフなど
国連人権高等弁務官事務所(OCHA)は2016年の報告書でアゾフが国際人道法に違反していると非難している。報告書には民間人からの財産の略奪や強姦、拷問が指摘されている。アムネスティ・インターナショナルは、Kolomoiskyが資金を提供したエイダル大隊が、不法な拉致、不法な拘留、強盗、恐喝、さらには処刑の可能性など、戦争犯罪を犯したと報告している。
2015年6月、カナダとアメリカの両国は、ネオナチとのつながりを理由に、自国軍がアゾフ連隊を支援・訓練しないことを発表した。しかし、翌年、米国は国防総省の圧力で禁止を解除した。
2016年、フェイスブックはアゾフを危険な組織として排除した。Tier 1指定下に置かれた。Tier 1グループの称賛、支援、表現に従事するユーザーも禁止される。2016年10月、Biletskyは極右政党「国民軍団」を設立し、その中核はアゾフの退役軍人たちだ。
2018年1月、アゾフは首都キエフの秩序を回復するため、街頭パトロール部隊を展開し、ロマ人コミュニティやLGBTQコミュニティのメンバーを襲った。
2019年10月、アメリカ議会議員40人が、国務省にアゾフを「外国テロ組織」(FTO)に指定するよう求める書簡に署名し、不成立に終わった。
2022年2月24日、ロシアの侵攻に伴い、フェイスブック措置を撤回し、アゾフへの条件付きで賞賛を認めることにした。
●ゼレンスキー関連の出典
・オリガリヒKolomoisky一族が、資金および傘下のメディアを使ってゼレンスキーを支援
How to Mainstream Neo-Nazis: A Lesson from Ukraine’s New Government、October 21, 2019
・ウクライナのオリガリヒの支援する民兵組織(現在は軍など公的機関の一部になっている)
How to Mainstream Neo-Nazis: A Lesson from Ukraine’s New Government、October 21, 2019
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/10/21/how-to-mainstream-neo-nazis-a-lesson-from-ukraines-new-government/
・メディアへの圧力
好評発売中!
『ウクライナ侵攻と情報戦』(扶桑社新書)
『フェイクニュース 戦略的戦争兵器』(角川新書)
『犯罪「事前」捜査』(角川新書)<政府機関が利用する民間企業製のスパイウェアについて解説。
本noteではサポートを受け付けております。よろしくお願いいたします。
