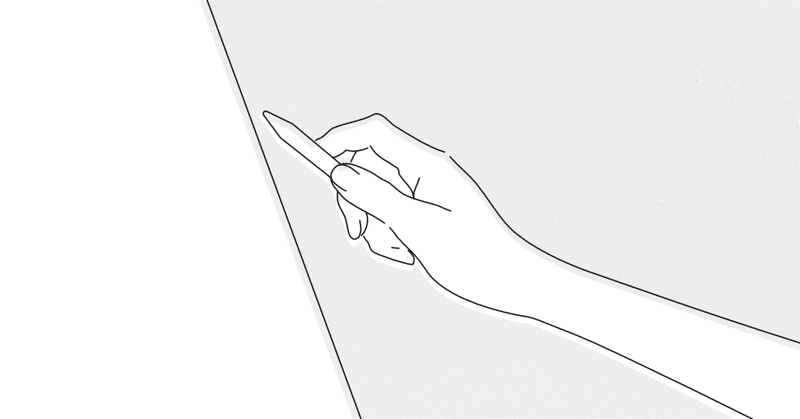
【5000字】あれから僕はキャンデーを舐めるのをやめた【短編小説】
初恋はレモンの味、というのは本当だと思う。
その証拠に、僕の場合はレモンキャンデーの味だった。生の果実よりもずっと甘くて、無機質な後味が尾を引くもの。
その味を想起するたび、僕は今でも思い出す。
教室の片隅、後ろから3番目の窓際の席に座って本を読む黒髪の女、
長嶋由希子の後ろ姿を。
*
「考えてばっかじゃ、何も描けないままなんじゃない」
その言葉とともに、僕の目の前にコロリと転がった黄色いキャンデー。
思えばあれが、僕の後の人生に長く爪痕を残すことになる女との最初の出会いであったのだ。
耳にかけられていた腰までのロングヘアが、白い長袖のブラウスにこぼれ落ちる。
窓の桟に腰掛けた女のそれは風を含んでふわりと広がり、僕は「カーテンみたいだな」という思いを抱いた。
その彫刻みたいに白い顔の口角の片側が持ち上がる。僕がその表情の意味を考えるに至る前に、奴は踵を返して去っていった。
風で鉛筆が落ちる乾いた音で、僕は我に返った。
机に置いてあった白紙のスケッチブックがパラパラとめくれる。
慌てて手元の画材一式を直しながら、冷静になった頭に少しずつ血が上るのを感じた。
僕の有意義な昼休みが乱された。
もしその妨害がチョコレートや温かい興味と励ましの言葉だったのなら、こんなに憤慨することもなかっただろう。
奴の鼻持ちならない態度とレモンキャンデーは、どちらかというと冷笑の意味合いを含んでいる。そう僕は判断した。
教室の隅で独りで絵を描く僕への嘲りだ。
奴ーー長嶋由希子は僕と違い、どちらかというと人当たりが良いタイプの人間だった。
誰とでも話すし、よく笑っている。誰が言ったことに対しても、どんなことに対しても。
だが、あまり人と群れているところは見ない。気がつくと自分の席にいて本を開いている、そんな奴だ。
その夜、僕は悩んだ挙句にそのキャンデーを舐めた。食べ物に罪はないと判断したからだ。
口の中に、レモンと思しき甘やかな香りが広がる。飴の固体が溶けて消えても、その香りは消えない。
その日僕は、スケッチブックに向かいながらペン回しをすることしか出来なかった。
その後も、僕のスランプは続いた。今までで最長記録だった。
目の端に長嶋が映るたびに、自分の中に沸々と苦いものが湧いてくるのを感じた。その雑念が筆から僕を遠ざけるせいで、レモンの苦味がもっと濃くなる。そんな悪循環が身体の中で繰り返されているのを、僕はなすすべなく眺めていた。
ある昼下がり、僕が例によってスケッチブックを前に鉛筆を握りしめていると、黒髪がさらりと視界に下りてきた。
「スランプなの?最近描いてないよね」
僕は反射的にスケッチブックを胸にかき抱いた。心臓がいつもより早く脈打つのが聞こえる。
机に手をついた長嶋は僕をちらりと見やると、僕の挙動を特段気にした風でもなく前の席に腰を下ろした。
「ねぇ、いつも何描いてるの」
『誰がお前なんかに』という言葉は喉元でシュウと消えた。実際に口に出た言葉はもっと覇気のないものだった。
「…デッサンとかだよ」
「へぇ、じゃあ教室とか外とかの風景ってこと?」
『なんでそこまで言わなきゃいけないんだ』とは僕の口は言えない。
「そうだね」
「鉛筆で描いてるの?」
『うるさい』「デッサンだからね」
「鉛筆って色んな濃さあるんだよね?」
『邪魔するな、帰れ』「…時と場合によって使い分けるかな、今持ってるのは2Bだけど」
「ふぅん。…じゃあさ」
長嶋はそこで一旦言葉を区切った。
「人って、描くの?」
長嶋の薄いブラウンの瞳が僕を覗き込む。
その吸い込まれそうな瞳孔の暗さに、僕は硬直した。
話そうとしても掠れた吐息しか出てこない。その時に出来る最大限のことは、徐に長嶋の視線から目を逸らすことだった。
「あ、そういえばさ」
長嶋はまた僕の態度を気にする様子もなく、明るい声を出した。
「美味しかったでしょ、あのキャンデー」
俯いたままの僕の前に、ぽとりとキャンデーが置かれる。
「頭使うと糖分、欲しくなるもんね」
僕が面を上げた時には、既に長嶋はいなかった。嵐が去った後のように虚ろな頭のまま、僕は残されたキャンデーをぼんやりと見つめた。
今度のものは、桃味だった。
次の日、僕は長嶋を描いた。
今まで人をデッサンしたことは何回もあったから、作業自体は造作もないものだった。
ただ、脳内を独占して絵から遠ざけるものがあるならばそいつを題材にしてしまえばいい。初めはそれくらいのつもりだった。
いや、そのつもりだと、自分に言い聞かせていただけなのかもしれない。
僕は長嶋が気に障る限り、長嶋を描いた。
クラスメイトと話す横顔、一人で読書に耽る後ろ姿、ぼんやりと黒板を眺める5時間目の猫背。
真っ白だったスケッチブックが、あいつの痕跡でどんどん黒く染まっていく。
あのレモンと桃以来、長嶋はふとしたときに僕に話しかけ、キャンデーを落としていくようになった。ご丁寧にいつも違う種類で。
りんご、ぶどう、マスカット、オレンジ、メロン…。
僕の口腔内を、色とりどりの味が染め上げていく。
僕には生きた長嶋が描けなかった。
写実的ではある。彼女の外見的な特徴を正確に捉えてはいる。
でも、何かが抜け落ちていた。
描くうちに、長嶋という人間がわからなくなる。
あいつはどこを見ているんだろう?
談笑する時も本を読む時も、長嶋は綺麗だ。手本のような笑顔を浮かべ、女子高生の典型のような頬杖のつき方をする。
だから、わからなかった。だからこそ、知りたかった。
長嶋を知りたくて、僕はいつまでも彼女を描き続けた。
千切れたスケッチブックのページの山に、キャンデーの包み紙が重なっていく。白黒の硬質な紙に、カラフルな皺だらけの紙。
息を吹きかければ一面に飛散してしまいそうなほどに、それらは層を成して積もっていった。
*
思い返せば、長嶋はいつだって唐突だった。僕が奴を気に入らない理由の一つだ。
その日も、僕はいつもと変わらず長嶋をデッサンしようとしていただけだった。勿論、見ながら描くとバレてしまう恐れがあるから、まずは奴の姿を記憶に収めようとした。
周辺の情報が排除されて黒く塗りつぶされたフレームの中、歓談中の長嶋の横顔だけが切り取られる。
誰かがウケ狙いのことでも言ったのだろう、ケラケラと無邪気そうに笑うその白い顔の、整った鼻先と口端のえくぼ。僕の視界はまるでカメラのように奴の顔にズームインしていく。
と、長嶋がこちらを向いた。
被写体と目が合ったカメラは固まり、咄嗟に視線を下に逸らす。視界一杯に広がる机の木目模様が歪んで見える。
コツコツコツ、と、靴音が僕に近づいてくるのがわかった。
「ねぇ」
促されるままに上げた目に、ズームの必要がない倍率の長嶋の顔が映る。僕に合わせられた目線、奴の吐息もかかるくらいの距離。
「あたしがいなくなったら、何描くの」
その時初めて、僕は長嶋の瞳を観察した。
抜けるように透明なブラウンの瞳、一点だけ墨を落としたような黒い瞳孔。
僕が映っているのがはっきりと見える、その目はどこまでも透けていた。
鏡は僕らを映し出すが、それ以上の何も見せてはくれない。ただ正確に、僕たちの在る姿を、時には最も望ましい形で映し出す。
鏡に「何を思っているの」と聞く人間はいない。答えは返ってこないとわかっているのだから。
コロン、という聞き馴染みのある音がして僕はふと意識を取り戻した。
周囲の景色やざわめきが、また五感に帰ってくる。
目の前に長嶋はもういない。
机に転がされた水色のキャンデーを見つめながら、僕は耳が赤くなるのを感じた。長嶋の言葉が脳内に反芻している。
奴を描いていると気づかれていたらしい。
最善の注意を払っていたが、やはり描く頻度が高すぎたか。
僕は包み紙を雑に剥がしてキャンデーを口に放り込んだ。
「あたしがいなくなったら」と、長嶋は言った。
ソーダの弾ける炭酸の味とともに、その一言が頭を巡る。
僕は包み紙をくしゃりと握りつぶした。
次の日、長嶋は学校を休んだ。
その次の日も、そのまた次の日も。
クラスメイトにその理由を知る人間はいないようだった。担任だけが、「えー、今日も長嶋は休みです」と言うときに、眼鏡の下の眉間を少し掻いた。
ただし数日休んだと思うと何事もなかったかのように顔を出すから、「長嶋は何日かに一回来る」という奇妙な状況がクラスの日常になりつつあるのが感じられた。
数日に一度の長嶋を、僕は毎回絵に収めた。
前よりも筆圧が濃くなった。だが、それに反して絵の中のあいつからは、段々と何かが抜け落ちていくみたいだった。少しずつあいつが痩せていって、より白くなっていくのを僕は感じていた。
教室の窓際、後ろから3番目の席は今日も空いている。
一週間、長嶋が学校を休んだ時があった。
クラスの人間たちがその長さの異常さに気付いたのかはわからない。
ただ僕は、今までの平均であった3日を過ぎたあたりから、朝礼時の出席確認で脈拍が速くなるのを感じるようになった。
だから、教室に入って久しぶりに3番目の窓際の席が埋まっているのを見たときについ吐息が漏れてしまったのだろう。
長嶋はいつもと変わらない様子で本を開いている。その目の下には、うっすらと隈が出来ていた。
その日の昼休み、僕は図書室へ行った。
本棚の森を抜けた部屋の奥の片隅、いつも開け放たれた窓のそばの机。僕の特等席へと、本を数冊手に取ってから向かう。
だがそこには先客がいた。
長嶋だった。
机に伏せていて顔は見えなかったが、造形物みたいに綺麗な頭のフォルムと風になびく黒髪は間違いなくあいつだった。その背中が呼吸に合わせて上下している。
僕は黙って、一つ間を空けた席に本を置いた。
その物音に気づいたのだろうか、長嶋が目を開けた。
「…ごめん、ここ座ろうとしてた?」
立ちあがろうとした長嶋の肩を僕は手で制した。
「いいよ、寝てなよ」ブラウスのさらさらした感触越しに伝わる、長嶋の体温。「寝れてないんだろ」
そのとき、僕は長嶋の涙を見た。
つぅっと、頬を伝う透明な雫。長嶋の瞳と同じくらいに、どこまでも透きとおった色。
風が吹き抜ける。
疾風にさらわれてはためく、長嶋のボタンの取れた袖口から、ちらりと肌が覗く。
そして、何本もの細い傷痕。
もうかさぶたになっているもの、今しがた付けられたかのように生々しいもの。それらは真っ白な肌の上で、異様なくらいの赤黒さを誇っていた。
その夜、僕は狂ったように鉛筆を走らせた。
芯は何度も折れて、その度にカッターで削り直される。デッサンが完成する頃には、鉛筆は半分くらいの長さになっていた。
自分の描いた絵を、僕は初めて心の底から美しいと思った。
絵の中の長嶋は、泣いている。
黒髪に縁取られた白い顔に、驚愕か安堵か、もしくはその他の感情かが複雑に折り重なった表情。
その頬に、ひとすじの涙が走っている。薄い色の瞳は、真珠のような涙を湛えて一層透けるような光を放つ。
あいつの透明な瞳の向こう側に何があったのかを、僕はこのとき知った。
見せたい。僕はそう思ってしまった。
この絵を、長嶋に見てほしい。
だが、その日は一生来ることはなかった。
欠席が続いた後、長嶋の席は教室から消えた。
いつあいつが去ったのか、僕にはわからなかった。
ただ、朝礼で担任がいつしか眉間を掻くことをしなくなって、やがて出席簿からあいつの名前が消えていた。
それから、僕はまた、何枚も何枚も長嶋を描いた。
だが、一枚たりとてあの絵に敵うものはなかった。何か一つ切り込んだものを描こうとすると、どこかが嘘っぽいような虚ろなような、そんなものが出来上がるだけだった。
*
以来僕は、キャンデーを食べるのをやめた。
年月が経ち絵を描くことが生業になった今でも、一度たりとて手に取ったことはない。
長嶋が消えてしまったのは、あの涙の絵のせいだったのかもしれない。そんな取り止めのないことも考えた。
何度あいつの笑顔を見た奴らも、何度あいつと言葉を交わした奴らも、決して触れたことのないもの。
それを僕が描いてしまったから、陸上に上がったら泡沫と化してしまう人魚姫のように、長嶋はもうこの世界にはいられなくなったのではないだろうか。
だから、僕はキャンデーに思い出を重ねるのを止めた。
僕しか知らないあいつがいるのなら、あいつしか辿り着くことの出来ない僕の何かがあるべきだ。
あの色とりどりの包み紙たちは、もはや白黒のデッサン紙なしでは存在し得なかった。
スケッチブックの奥に眠る、長嶋は変わらない。
今もどこかで生きているのだろうか。あの傷がもうあいつを蝕んでしまったのだろうか。
一生の間、街ですれ違える一瞬があるのだろうか。もしくは、僕の人生が終わってあの世に行ったとき、初めてあいつに会えるのだろうか。
もしもそんな時が来たのなら、
長嶋、
僕にまた、キャンデーをくれないか。
ー終ー
あとがきはこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
