
ロシア内戦③余波・フィクション作品
こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。
今回はロシア内戦の英語版Wikipediaの翻訳をします。
翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれません。正確さよりも一般の日本語ネイティブがあまり知られていない海外情報などの全体の流れを掴めるようになること、これを第一の優先課題としていますのでこの点ご理解いただけますと幸いです。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。
翻訳において、思想や宗教について扱っている場合がありますが、私自身の思想信条とは全く関係がないということは予め述べておきます。あくまで資料としての価値を優先して翻訳しているだけです。
ロシア内戦
余波
⬛その後の反乱
中央アジアでは、赤軍部隊は1923年まで抵抗に直面し続けた。バスマチ(イスラム系ゲリラの武装集団)は、ボルシェヴィキの占領と戦うために結成された。ソヴィエトは、ドゥンガン騎兵連隊長マガザ・マサンチのような中央アジアの非ロシア系民族をバスマチとの戦いに従事させた。共産党がこのグループを完全に解体したのは1934年のことだった。

マガザ・マサンチ(馬三奇)
アナトリー・ペペリャーエフ将軍は、1923年6月までアヤノ=メイスキー地区で武装抵抗を続けた。カムチャツカと北サハリンの地域は、1925年にソヴィエト連邦と条約を結ぶまで日本の占領下に置かれ、最終的に日本軍は撤退した。

白軍の将軍アントリー・ペペリャーエフ
⬛死傷者
内戦の結果は重大だった。ソ連の人口学者ボリス・ウルラニスは、内戦とポーランド・ソ連戦争の戦死者は30万人(赤軍12万5000人、白軍とポーランド人17万5500人)、病死した両軍の軍人の総数は45万人と推定した。ボリス・センニコフは、戦争、処刑、強制収容所への投獄による1920年から1922年のタンボフ地方の人口の損失総数を約24万人と推定した。
ロシア内戦の結果、1000万人もの命が失われたが、その圧倒的多数は市民の犠牲であった。赤色テロによる死者の数については、西側の歴史家の間でコンセンサスは得られていない。ある資料では、1917年12月から1922年2月まで、年間2万8000人が処刑されたと推定している。赤色テロの初期に射殺された人数は、少なくとも1万人と推定されている。全期間についての推定は、最低5万人から最高14万人、20万人まである。処刑総数については、ほとんどの推定が約10万人である。ヴァディム・エルリクマンの調査によれば、赤色テロの犠牲者の数は少なくとも120万人である。ロバート・コンクエストによれば、1917年から1922年にかけて、合計14万人が銃殺されたが、ジョナサン・D・スメールは、「おそらくその半分以下」と、かなり少なかったと見積もっている。歴史科学専攻のニコライ・ザヤツは、1918-1922年にチェーカーが射殺した人数は約3万7300人、1918-1921年に裁判の判決によって射殺された人数は1万4200人、すなわち合計で約5万~5万5000人であると述べている。1924年、反ボルシェヴィキの人民社会主義者セルゲイ・メルグノフ(1879-1956)は、ロシアの赤色テロに関する詳細な記述を発表し、ボルシェヴィキの政策による死者176万6188人というシャルル・サロレア教授の推定を引用した。彼はその数字の正確さには疑問を呈したが、サロレアの「ロシアにおける恐怖の定型化」を支持し、それが現実に合致していると述べた。現代の歴史家セルゲイ・ヴォルコフは、赤色テロを内戦期(1917-1922年)のボリシェヴィキの抑圧政策全体として評価し、赤色テロによる直接的な死者を200万人と見積もっている。しかし、ヴォルコフの計算は、他の主要な学者によって確認されていないようである。
およそ300万人の人口のうち、1万人から50万人のコサックがコサック弾圧政策で殺害されるか追放された。推定10万人のユダヤ人がウクライナで殺された。1918年5月から1919年1月までの間に、全大ドン・コサックホストの懲罰機関が2万5000人に死刑を宣告した。コルチャークの政府は、エカテリンブルク州だけで2万5000人を射殺した。後に知られるようになる「白色テロ」は、合計で約30万人を殺害した。
内戦が終わると、ロシア連邦は疲弊し、破滅に近づいた。1920年と1921年の干ばつと1921年の飢饉は災害をさらに悪化させ、およそ500万人が死亡した。病気は大流行し、戦争を通じて300万人がチフスで死亡した。さらに何百万人もの人々が、広範な飢餓、両陣営による大規模な虐殺、ウクライナやロシア南部でのユダヤ人に対するポグロムによって命を落とした。第一次世界大戦と内戦による10年近い荒廃の結果、1922年までにロシアには少なくとも700万人のストリートチルドレンがいた。

白軍の移民として知られる別の100万人から200万人がロシアを脱出し、その多くはヴーランゲリ将軍とともに、ある者は極東を、またある者は西の新しく独立したバルト諸国へと向かった。移住者の中には、ロシアで教育を受け熟練した技能を持つ人々の大部分も含まれていた。


内戦はロシア経済に壊滅的な打撃を与えた。戒厳令が敷かれ、利益追求が禁止されたにもかかわらず、ロシアでは闇市場が出現した。ルーブルは暴落し、物々交換がますます貨幣に取って代わり、1921年までに重工業の生産高は1913年の20%にまで落ち込んだ。賃金の90%は貨幣ではなく商品で支払われた。機関車の70%は修理が必要であり、食糧徴発は、7年間の戦争の影響と深刻な干ばつと相まって、300万人から1000万人の死者を出す飢饉を引き起こした。石炭生産量は2750万トン(1913年)から700万トン(1920年)に減少し、工場全体の生産量も100億ルーブルから10億ルーブルに減少した。著名な歴史家デイヴィッド・クリスチャンによれば、穀物の収穫量も8010万トン(1913年)から4650万トン(1920年)に削減された。
戦争共産主義は内戦中のソ連政府を救ったが、ロシア経済の大部分は行き詰まっていた。一部の農民は、土地を耕すことを拒否することで、食糧徴発に応じた。1921年までに、耕作地は戦前の62%にまで縮小し、収穫量は通常の37%にとどまった。馬は1916年の3500万頭から1920年には2400万頭に、牛は5800万頭から3700万頭に減少した。対米ドル為替レートは1914年の2ルーブルから1920年には1200ルーブルに下落した。
戦争が終結したことで、共産党はその存在と権力に対する深刻な軍事的脅威に直面しなくなった。しかし、民衆の不満が続くという脅威は、ドイツ革命を筆頭とする他国での社会主義革命の失敗と相まって、ソヴィエト社会の軍国主義化を継続させる要因となった。ロシアは1930年代に極めて急速な経済成長を遂げたが、第一次世界大戦と内戦の複合的な影響はロシア社会に永続的な傷跡を残し、ソヴィエト連邦の発展に恒久的な影響を及ぼした。
フィクション作品
⬛文学
『カルバリーへの道』(1922-41年)トルストイ
『チャパーエフ』(1923年)ドミトリー・フルマーノフ
『鉄の洪水』(1924年)アレクサンドル・セラフィモヴィチ著
『赤い騎兵隊』(1926年)アイザック・バベル
『ルウト』(1927年)アレクサンドル・ファデーエフ
『征服された都市』(1932年)ヴィクトル・セルジュ
『無益』(1922年)ウィリアム・ゲルハルディ作
『鋼鉄はいかにして鍛えられたか』(1934年)ニコライ・オストロフスキー
『楽観的悲劇』(1934年)ヴセヴォロド・ヴィシュネフスキー
『静かなるドン』(1928-1940)ミハイル・ショーロホフ
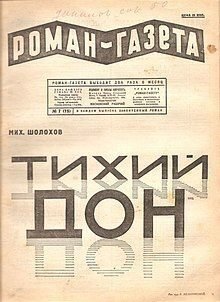
『ドンは海へ流れる』(1940年)ミハイル・ショーロホフ
『ドクトル・ジバゴ』(1957年)ボリス・パステルナーク
『白衛兵』(1966年)ミハイル・ブルガーコフ
『ビザンチウムは耐えている』(1981年)マイケル・ムアコック
『チェヴェングール』(1927年執筆、1988年ソ連で初版発行)アンドレイ・プラトーノフ
『巨人の落日』(2010年)ケン・フォレット
『華麗なる小さな戦争』(2012年)デレク・ロビンソン
⬛映画
『アーセナル』(1928年)
『アジアの嵐』(1928年)
『チャパーエフ』(1934年)
『十三』(1936)監督:ミハイル・ローム監督
『われはクロンシュタットから』(1936)(イェフィム・ジガン監督
『鎧なき騎士』(1937年)
『1919年』(1938年)監督:イリヤ・トラウベルク
『バルト海兵隊』(1939)監督:A・ファインツィマー
『シュチョルス』(1939年)監督:ドフジェンコ
『パヴェル・コルチャギン』(1956)監督:A・アロフ、V・ナウモフ
『四十一』(1956)監督:グリゴリ・チュクライ
『共産主義者』(1957)監督:ユリ・ライズマン
『静かなるドン』(1958)監督:セルゲイ・ゲラシモフ
『ドクトル・ジバゴ』(1965)監督:デヴィッド・リーン
『とらえどころのない復讐者たち』(1966年)
『赤と白』(1967年)
『砂漠の白い太陽』(1970年)
『飛翔』(1970)監督:A・アロフ、V・ナウモフ
『レッズ』(1981)監督:ウォーレン・ベイティ

『シベリアのコルト・マルテーゼ』(2002年)
『ネストル・マフノの9つの人生』(2005/2007年)
『提督』(2008年)
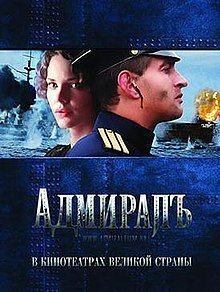
『日射病』(2014年)監督:ニキータ・ミハルコフ

関連記事
最後に
最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。
今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。
Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。https://twitter.com/Fant_Mch
筆者の大まかな思想信条は以下のリンクにまとめています。https://note.com/ia_wake/menu/117366
今回はここまでになります。またのご訪問をお待ちしております。
それでは良い一日をお過ごしください。
今後の活動のためにご支援いただけますと助かります。 もし一連の活動にご関心がありましたらサポートのご協力お願いします。
