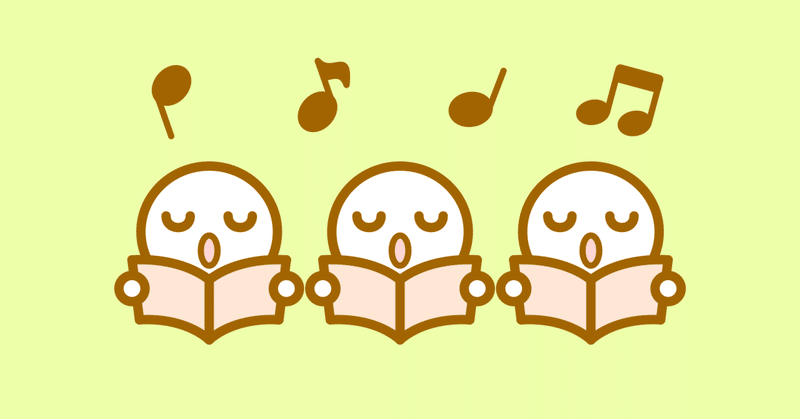
俺にとっての詩を考える
自分にとっての詩とは何か。
最近「詩」について色々考える事が多く、一度思い切って書いてみる事にした。その記録をする理由を言語化するためには、自分が歩んできた人生について描く必要があったため、かなり長い内容になってしまった。
俺にとっての詩とは何か。
その答えは「感覚」というキーワードに詰まっている。のだが、誰の感覚であるのか、なぜ「感覚」がキーワードになるのか。といった事を体験してもらうために、自分の人生を描く事で、追体験とまではいかないが、読んでくださる皆さんに伝えようと思った。
そのために、この3万字が必要なのか、というのは自分でも分からないが、でも、最後まで読んでくれたら嬉しいと思う。
詩に初めて触れたのは、高校一年生の春だった。
合唱部の開いた新入生を歓迎するコンサートで披露された曲の詩の一節に心が揺さぶられた時だった。
自分が合唱部に入った理由は、合唱部が披露してくれた校歌がかっこよかったからだった。(本当であれば、YouTubeにアップロードされている校歌の音源でも張り付けた方がいいと思っているのだが、自分の出身高校がばれてしまう上に、それから、自分の過去の行いによって傷つけてしまった人達に対して、何かしらの感情を逆なでしてしまう可能性があることから、やめた。また、基本的にこれから登場する他者については、当事者の方は分かるとは思うが、それ以外の方が読んだとしても、何かしらのプロフィールが連想されるような内容はなるべく書かないようにした。これは自分の為に書いた文章であることもそうだが、検索エンジンの結果に引っかかる事は避けたいと思った。当事者の方に読んで頂けたら嬉しいとは思っているが、逆に言うと、そのために人の名前を書く事はどうしてもできなかった。)
体育館で開かれた新入生オリエンテーションの時間に、部活動紹介のコーナーがあった。
自分が入った高校というのは地元の伝統校という事もあってか、他の高校にはない種々様々が部活動があった。とはいえ、殆どの部活動のアピール内容は、ただ事前に書き上げた原稿を読み上げる、といった内容で基本的につまらなかった。
そんな中で、急に上級生の群れがステージの上に上がってきたのだった。合唱部のアピールは、校歌の合唱だった。校歌というと長調のなめらかなスローテンポな旋律が続く、穏やかなだけの音楽という印象があった。且つ詩の内容も特に面白みのない、昔の人の書いた、熟語だけやたらかっこいい、学び舎を称え、友と同じ青春の時間を歩めることに対する喜びを羅列したものだと思っていた。
だから、演奏が始まるまでは何も期待していなかった。
なんの刺激もない音楽がただ流れて終わり。
それで済めばよかったのだが、実際は違った。
合唱部の演奏する校歌は今まで聞いた事がないかっこいい校歌だった。
普通、合唱と言えばピアノの伴奏がついていると思うのだが、この校歌には伴奏がなかった。いきなりアカペラの女声のユニゾンから始まったのだ。歌詞の内容は聞いた事もない熟語によって構成された、端的な風景描写から始まる、シンプルかつ荘厳さを感じさせるものだった。
アカペラ且つユニゾンの歌というのは、音色が一つしかないことから、詩が真っすぐ耳に入ってきやすい。その歌のスタイルと、歌詞の荘厳さがマッチしていた。無論、歌詞の内容は難しすぎて、意味は分からなかった。だが、雰囲気がけた違いにかっこよかったのだ。
校歌が2番に入ると同時に、男声のユニゾンに切り替わった。男性合唱を生まれて初めて生で聞いた。重い響きの声がびりびりと体育館の空間に広がって行った。鼓膜が痺れた。胸の中にある肺の空間まで侵食してくるような音の重たさ・響きによって、全身が震えた。
ラストの三番は混声合唱だった。今までのユニゾンとは異なる、重厚なハーモニーの連打、連打だった。
雷に打たれたような気分なんだ。
なんてかっこいい校歌なんだろうと、心が惹かれた。
中学三年生の夏休みの学校見学の際に体験した、友達と入るつもりだった地学研究部への興味は完全に消え失せてしまった。学校の授業が終わった後、真っ先に音楽室に向かった。新入生のために開かれるコンサートが開催されるからだ。校歌以外の歌も聞きたかった。無論、一緒に音楽室へ見学しに行ってくれる男友達など一人もいなかった。そして、同じ中学出身の生徒は3人しかいなかったから、完全に一人だった。とても不安な気持ちになりながらも、音楽室の戸を開いた。その先にいる人達は、今まで全くあった事のない人達だらけだった。ピアノをじゃんじゃか暗譜で弾いていたり、オペラ歌手みたいな歌声で歌曲を諳んじている人がいたり、新入生の中には、既にスカウトされている人がいたりした。
自分はまるで邪魔者みたいで、ただ音楽室にいるだけで怖かった。
だが、それでもなお、合唱曲の魅力に導かれて、この世界に飛び込んでしまったのだった。
新入生のために合唱部が開いてくれたイベントは二つあった。一つは、先ほども述べた通り、音楽室で小さなコンサートを開き、これから部活動で練習していく合唱曲を新入生に聞いてもらうという内容だった。
そこで、合唱部が新入生のために用意してくれた曲は、JPOPのカバーみたいな、中学生でも聞いた事のあるような曲の合唱バージョンみたいな話ではなく、ゴリゴリの合唱曲だった。この曲を聴いて音楽室を去った子もいて、合唱部員が苦い顔をしていたのは今でも心に残っている。
そんな一番最初に歌われた曲は谷川俊太郎の「私が歌う理由(わけ)」であった。と、同時に、それが自分が初めて出会った「詩」でもあった訳だ。始まりのフレーズを引用する。宜しければ、曲も聞いてみて欲しい。
私が歌うわけは
いっぴきの仔猫
ずぶぬれで死んでゆく
いっぴきの仔猫
自分が合唱部に入ろうと思った理由とは全く違うなと思った。その強烈な違和感に、逆に惹かれた。でも、なぜその違和感を覚えたのか当時は全く考えなかった。この曲は校歌と同じようなアカペラ曲だ。ただ、校歌とは違い、メロディーだけを歌う訳ではなく、複雑なリズムのボーカリーズ(声のみの発声)によって、ピアノの伴奏を声によって代用している曲である。わかりやすい例で言えば、ハモネプにおけるビートボクサーみたいな役割、つまりドラムみたいなイメージでいいと思う。(本当は違うと思うけど‥‥)
とにかく、ボーカーリーズから始まるこの曲のイントロは楽しそうなのである。だから、タイトルの「私が歌う理由」から来る連想を踏まえても、楽しそうな曲だなと勘違いしてしまうのだ。と思っていたら詩の始まりは、深刻そうな内容を描いているのだ。そのギャップが心に槍を突き付けてくる。
結局、この曲から得た違和感について、当時は振り返る事も深く考える事もなかったと思う。ただ、自分が歌に対して感じていた「感覚」とは全く以て異なる歌う理由があるということに驚いてしまった。今思えば、この時から「詩」に対する「自分には理解できない物」という苦手意識が芽生え始めたのだと思う。当時の自分の得意科目が国語であったこともあり、自分が想定した事のない感情があるという事実を受け入れる事ができなかったのだ。
「何が書かれているのか分からない・理解できない物」=詩という思いは、これから先ずっと自分の詩について回る呪いみたいな価値観となって定着した。
コンサートが終わった次の日、もう一つのイベントが開催された。今度は、スピッツの「チェリー」を合唱部のメンバーと一緒に歌おうという内容だった。
少しだけ混声合唱のパートの説明する。混声合唱団というは、基本的に男性・女性それぞれに高音・低音パート、つまり4部パートによって構成されている。メンバーは団に入ると、いずれかのパートに所属することになる。4部パートに分かれている理由は、単純に4部構成の合唱曲が多いからということもあるが、それぞれのパート毎に発声方法や、音色の出し方が異なるためだ。男性の低い声の出し方と、高い声の出し方は実は異なるのだ。
これは上級生になって気づいた事なのだが、このイベントの目的は新入生に合唱の楽しさを知ってもらうこと以上に、新入生のポテンシャルを図る場所でもあった。具体的な話は後述するが、合唱はある程度訓練すれば歌を歌うことは出来るようになる。が、うまれ持った声帯の大きさだけは変えることはできないし、鍛える事もできない。
体験に来た新入生は、音楽スキルをもった上級生による、「声域の診断」の結果の応じて、ハリーポッターの組分け帽子のように、所属パートを便宜的に振り分けられる。(その中で他の人もよりも音域が広い子は目を付けられ、上級生が全力で接待し、絶対に合唱部に入って貰うように誘導する)
パートが分かれた後にたいのは、音取りという作業だった。これは、上級生から手渡された初めての楽譜を手に持ち、自分の担当するパートの音を、パートリーダーが奏でるピアノの音を頼りに歌っていく…という一見簡単な作業なのだが、やってみるとかなり難しかった。
理由はいくつかあるが、まず、スピッツのメロディーを歌えるのは基本的にソプラノだけであり、他のパートはハモリ部分を担当する事になるということだ。頭に残っているチェリーのメロディに引きずられないよう、気を付けながらハモリ部分を覚えないといけない。
そのイベント自体は楽しかったと思う。自分は高校生になるまで、カラオケに行ったことがなかったのだが、歌を歌う事は好きだった。一人でよく風呂の中で歌を歌っていたし、中学校や小学校の時にあった合唱コンクールで歌を歌う事が好きだった。そういった歌に対する欲求を全面に押し出しても、誰にも何も言われないという快感は言葉にできなかったと思う。(特に上京してからは、大声を好きにだせる。無料でピアノを弾けるでかいスタジオが使い放題という事の意味を痛感する事になるのだが)
また、みんなで1つの曲を作り上げていくという経験が楽しすぎた。「みんな」の部分についてより細かく書くとすれば、上級生達の合唱に対する思いが濃かったのが良かった。「合唱」というと女子だけが熱中して男子は歌よりも部活・遊びに夢中という印象が強い行事だと思うが、自分が入った高校が元男子校ということもあって、この合唱部は元々男声合唱の部活「グリークラブ」という歴史を持っていて、男声合唱をするために入学してきた先輩が沢山いた。ピアノをバンバン弾いて、短時間で1つの曲の音を取り終え、ハーモニーを構成していくその巧みさに惹かれた。あっという間にスピッツが合唱になってしまったのだ。その中に自分が混ざっているという高揚感は、自分が惹かれたあの校歌の一員として参加できたような錯覚を与えてくれた。
更に強いていうのであれば、合唱部に入部するのは、基本的に女子が多く、男は本当に少なかった。だから、体験入部に参加するだけで、かなりもてはやされたのだ。自分が最初に恐れていた、混じれないのではないかという不安が一気に払拭され、コミュニティに受け入れられた気がした。
この二つの経験が決めてとなり、合唱部に入る事に決めたのだった。
とはいえ、合唱部に入ってからは散々だった。
自分はとにかく歌がへたくそだったのである。
そして、いくら練習しても歌が上手くならなかった。
これは高校生活3年間を経て思う自分に対する評価としては、揺るがない。
合唱コンクールなどの大会に出場すると、自分の団体の演奏というのを録音している業者からCDを買う事ができたりするのだが、自分の手元にはそれが一切ない。ない理由は明白だった。自分の演奏が聞くに堪えないからである。怖くて聞きなおす事ができないのだ。
合唱における「歌が上手い」というのは大きく三つの要素がある。
➀発声が綺麗であること
②ピッチが正確であること
③楽譜の指示を理解しその通りに歌えること
この場合の「発声」というのは、西洋音楽における合唱という文化の中で良しとされている発声ができることである。例えば、フォークソングにおけるだみ声だとか、能楽のような、日本式の反響しない木造建造物による、開けた音を吸う空間であっても、声を届かせるような、地を這うような横の響きを持つ声とは異なる。
端的に言ってしまうと、音楽ホールという空間全体響かせる縦の発声の事を指す。少しだけそのメカニズムについて解説すると、口腔という人間内部に広がる空間に対して、腹式呼吸という横隔膜の上下運動に基づく呼吸法によって練り上げた空気を、一気にぶつける事で声帯から発せられる声を、空間へ効率よく伝達する発声方法である。
腹から脳天に向かって突き抜けた、上向き声がそのまま音楽ホール一杯に広がって行くことによって、普段の日常生活でしゃべっているような喉だけを使った声(喉だけを使って発声するというのは日本人の生活空間に適しているので、自然とそうなることが多い)では達成できないくらいまで遠くに、人一人の声を響かせる事ができる。
この発声を極めると、例えば、バックにオーケストラを迎えて歌曲を歌ったとしても声が埋もれる事はない。マイクのような機械によって声量を拡張せずとも、小さな声を詩の発音を生活に伝えながら、観客席の隅っこまで届けることが出来たりする。
無論、その発声獲得するためには、ある程度の訓練が必要ではある。先ほど、括弧書きで注釈を入れたように、日本式と西洋式の発声方法がそもそも異なるし、西洋人とアジア人の頭の骨格がそもそも違うことから、西洋人が日常的に発話するときのような口腔状態を無理矢理形作る必要があったりする。(オペラ歌手の口の形が凄い形相に見える事が変に感じた人もいるだろうが、それは日本人の顔の骨格では達成できない口腔の広がりを形成するための工夫だったりするわけだ)
そういった問題も含めて、特に自分の場合は、腹式呼吸ができても、そこからはじき出される「声」がいつもくぐもった響きを伴う発声になってしまった。最初から西洋式の発声が出来るメンバーがいるなかで、自分には全く以てできなかった。特に、自分の場合は生まれつき舌が大きく、巻き舌ができなかった。舌が大きいという事は、その分口腔内の空間が圧迫されており、舌を使った口腔内のコントロールをしにくいという致命的な問題を抱えているという事だった。
結局、いくら訓練をしても、色々な勉強会に参加して技術を仕入れて練習しても、友達や先生に指導してもらっても、自分の理想とする発声をすることは叶わなかった。
ピッチが正確であるということは、ただ、楽譜に書いてある音符の音を正確に出せるという事だけではない。勿論、まずは楽譜に書かれた音符通りの音階を再現できることが重要だ。正確に言うのであれば、音取りの段階で、ピアノの鍵を叩いて出した音と同じ周波数で出せる事が重要である。その音を常に出せる状態になってようやくハーモニーの練習ができるからだ。合唱というのは、基本的に「声」のみによって作り出された和音=ハーモニーをひたすら連ね続けていく音楽である。
人間は基本的に単音しか出すことができない。(声帯が一つしかないからだ。弦楽器のように声帯が3本あればできるかもしれないし、最近では機械上で合成して一人合唱をする猛者もいるが)という誓約の中で、声のみによって和音を奏でるという事は、必然的に他の人が発声した「音」とかみ合うような周波数の音を出さねばならない。
体感した方が早いと思うので、携帯のピアノアプリをインストールして、適当に「ドミソ」の鍵を同時に弾いてみる事をお勧めする。最初は「ド」だけ強く、次に「ミ」だけ強く、最後に「ソ」だけ強く弾いてみよう。聞こえ方が変わるはずである。また、その聞こえ方というのは、ピアノ上で奏でた音の響きであることは忘れてはいけない。また、その「ドミソ」が高音階か低音階か、あるいは音階をまたいで構成されているのかによって、音の聞こえ方が変わる。その中で、どの響きが一番好みだったか考えてみて欲しい。
ともかく、それら和音を構成する音素の内一つを、声として表出する事が求められる訳だが、当然、その和音が一番きれいに聞こえる周波数や声量の組み合わせというのを常に意識しながら、音を出さなければならないという発想に行き着くはずである。
また、ちょっとだけ専門的な話をするならば、ただ、ハーモニーに求められる「音」を出せばいい訳ではない。厄介なのが周波数の問題だ。例えば先ほど例に出した「ドミソ」の和音の内、「ミ」の音はピアノで出す「ミ」よりも「100分の1」程度音程を下げた方が良いとされている(うろ覚えというか、物理的な話)。ピアノの音色は曲の最中に調弦することができない、音程の裁断された楽器という事もあって、実はピアノ上で引いた和音の音色=理想的なハーモニーの音色ではないという問題があったりする。
人の声はどちらかというと、弦楽器の音色に近いと言われている。その訳は発声のメカニズムに近いというのもあるだろうが、バイオリンに明確な鍵盤が刻まれていないように、人間の持っている一本の弦=「声帯」も同じように、微細な調整が可能であるということだ。その弦を調整することで、極微細な音程=ピッチの調整をきかせることができるのが、人間の声の特徴であり、逆に言えばその繊細な音程の出力を常に求められる訳でもある。
自分の周りには、絶対音感を持っている人や、後天的に獲得した相対音感を持っている人が沢山いて、軽々と、楽譜に書かれた音程通りの声を出していった。
自分の場合は、そもそもピアノの音と同じ音すら出せなかった。それが出来ないという事は、ハーモニーも当然合わせる事ができなかった。また、自分が発声できる音域が少なかった。特に、男性に求められる低い声が出なかった。自分の所属していた混声合唱団は深刻な低音男性不足に陥っていて、最終的に部員が抜けた3年生の夏の大会では、ほぼ一人で声の出ない音域を担当する羽目になったのだが、手の施しようがなかった。出ないものは出ないのである。だが、自分が出すしかないのだ。
低音部は基本的に生まれ持った喉の大きさに左右される音域である(能楽では低音部を拡張させることもできるらしいが、文字通り喉を壊し、血を吐きながら10年くらい修行する必要があるらしい)。喉を開くと声帯の弦が広がり、低い音を出すことが出来る。喉を閉じれば声帯の弦は小さくなり、高い音が出せるようになる。イメージが出来ない方は、弦楽器を思い浮かべよう。バイオリンがなぜ小さく、コントラバスが大きいのか。それは弦の長さ・太さ・身体の大きさ(身体の空間を目いっぱい使える)によって出る音域が異なるからだ。基本的に小さな楽器は、高い音が出る。大きな楽器は低い音が出るという想像がつけば、その原理を人間に当てはめることができるはずだ。
努力しても音程が良くならない。自分が求められる低音は生まれ持った声帯としてそもそも出すことができない。という事は、自分が求められている仕事を達成することはできないということだった。
楽譜の指示を理解できるということは、まずは、曲に設定されたテンポ通りに歌える事、それから、音符のリズム(拍)や音楽記号の指示の意味を理解できていることである。(実は歌が上手い人程、楽譜から外れた自分の表現をしてしまい、怒られる事があったりする。自己流のアレンジを加えるのは実は最後の段階に加えるスパイスとして程度だったりする)しかし、楽譜に書かれていることをただ再現することを競うだけでは、正直つまらない演奏になってしまう。楽譜の指示は、形からその曲を知る為に必要な目印でしかない。大事なのは、その導を頼りに、作曲家が表現したいと思っている、音楽的な効果や、表現したい詩のニュアンスを掴む事なのだ。
基本的に合唱曲というのは、詩が先にあることが多い。作曲家は、実は現代詩のマニアだったりして、その詩だけではなく、詩人の著作を読みこんだうえで、詩からもたらされるインスパイアを楽譜上に現象化させていく。作曲家ががその詩から受けたインスパイアを最大限表現するための、伝えるためのメロディーであり、ハーモニーであり、声の大小の指示(ダイナミクスの演出)、独自の音楽記号の提示であり、ブレスの位置の指示であり、休符なのだ。楽譜に込められた情報量を汲み取るだけでかなり大変である。音楽的な素養があった上で、更にそれらを駆使した上で、楽譜に込められた指示がどう詩と対応しているのかつかみ取っていく。それらの結果として、作曲家が曲に込めたサウンドを現出することができるのだ。これが出来る状態というのが、楽譜の指示を理解しているということになる。
自分はそれまったくできなかった。テンポは周りとずれる、詩の文節を考えずにブレスを吸ってしまう。詩が伝わらない程に滑舌が悪く。楽譜の指示だけしか見えず、曲の中におけるその指示の対応関係がつかめなかった。とりあえず、歌う事だけが必死だった
特に極めつけだったのは、詩の意味が分からないということだった。分からないということは、なぜ、その音楽記号による指示を作曲家が提示したのか分からないということでもあった。多少音楽的な素養を高めるために、和音の構造分析だとか、音楽的なアプローチでも取ればよかったのだろうと、今では思うが、それもせずに、ただただ、楽譜にかいてある記号の意味だけを調べ、それを自分の感覚で再現することに必死になった。なぜなら、詩に何が書いてあるのか分からなかったからだ。ただただ、単語の意味を覚えて、英語の文章が読めないような、効率の悪い勉強をしていた。
無論、詩の解釈を考える時間というのはなくはなかった。というのは練習が極まってくると、基礎的な音を合わせる練習から、表現を極める練習の比重が高まってくるのだが、その中で歌詞に対する共通認識を持つための会議が定期的に行われるのだ。その中で、それぞれが詩のテキストをどう解釈しているのか、みたいな話し合いが行われるのだが、正直腑の落ちるような気持ちになったことは無かったと思う。そういう時間の沈黙というのは、割と耐えがたい空気感を纏っていて、最終的には、詩を理解するというよりは、詩の言葉の単語や文節のニュアンスを声で表現する方向に躍起になっていった。そこでぶつかるのが、「自分なりの解釈」という問題だった。
「一つの詩」「一つの歌」という文脈を無視した、詩の単語のニュアンスだけを表現することに躍起になり始めると、今度は楽譜の指示から外れていくことになる。そういった練習を特に自分はしていたので、「お前は楽譜を読んでいない」と言われることが多かった。事実その通りであったし、最近まで気が付かなかったくらいに、自分なりのニュアンスに拘泥してしまったのだった。
➀~③の要素がまるで達成できていない人は、合唱部に沢山いた。合唱部に入った理由を尋ねると、「歌が好きだ」という子と、「歌を歌うのが下手くそだけどみんなと一緒なら歌えるかもしれない」という願いを持って参加した子が半数半数だった。そして、だいたい歌が下手くそだと自称していた人達は2年半の部活動の中でどんどん歌がうまくなっていった。逆に、歌が上手い人の方が求められる責任が重かったのもあるが、自由に自分が思うように歌えないストレスを抱えていたと思う。
自分は歌の素人であり、何もかも人と比べてできなかった。だから、自分もいつか歌がうまくなれると信じて、毎日練習した。だが、自分は部活動を卒業するまでに➀~③の要素を一つも達成することはできなかった。
声が変。身体を動かして歌うな。なんでそこで息を吸うのか。音程合わせる気がある? 舌をひっこめろ。楽譜の指示をなぜ守らない。あんまり声出さなくていいよ。お前の声は他の奴らに比べてゴミ。色々な形で、自分の歌声は毎日批判された。
ただ、その批判を見返したくて、毎日始発に乗って音楽室で練習した、土日は一番乗りで音楽室に向かい、歌の練習をした。音楽室にあるCDは全て借りて聞いた。なんなら自分でCDや楽譜を購入し音楽室に寄付したぐらいだ。誰よりも合唱曲に対する知識や合唱曲に対する耳が肥えている自負があった。歌う事になった合唱曲は調べて一冊のノートにまとめて、徹底的に研究した。誰よりもその歌う曲を愛している自信があった。だから、みんなが詩の解釈会議で沈黙している中、自分なりに詩の見解を積極的に述べまくった。自分が2年生の時に挑戦したコンクールの曲は日本語の現代詩が採用されていたので、その詩を収録した詩集を図書館から探し出し、原典を読み込んだ。
しかし、自分は歌がへたくそだった。そして詩の解釈についての熱弁はいつもから回していた。「かっこいいフレーズなんだよ!」という印象以外何も言えなかったと思う。楽譜の指示と詩の内容と自分の妄想が混濁した汚物を喜々として発表していた。
そのせいか、「自分がいいと思った曲」=「百均の感性が評価しているのだから基本的に変な曲」という評価がついてしまった。部活内における、合唱曲の風評被害を巻き散らかしてしまった。コンクールや演奏会で歌う曲を自分がいくら提案しても感覚で却下された時は、部員を本気で恨んだ。というか、今でも若干恨んでいるし、なんなら「百均が好きだから変な曲かと思ってたけど、案外良かった」みたいな形で後からこっそり演奏会の曲として採用された時は本気で殴ろうと思った。しかし、そんんなことはどうでもいい。それよりも自分が傷ついたのは、自分の中にある感覚を徹底的に破壊されたということだったと思う。
今思えば、「自分の声が他者にどう聞こえているのか」「他者は自分の声をどう聞いているのか」「他者はどのように声を出しているのか」「自分はどのように声を出しているのか」そこに大して思考を巡らせ、「声」という感覚を徹底的に見つめるべきだったし、それを言語化すべきだった…そう思うのだが、当時は自分の中にある声の感覚を見つめることができなかった。徹底的に目を背けていた。逆にいえばそれ以外の事はがむしゃらにやっていた。自分は必至に頑張っている。頑張っているのに、歌はいつまでもうまくならない。誰よりも合唱曲で耳を肥やしているのに、自分より合唱曲を聞いていない奴が馬鹿にしてくる。なんでそいつの方が歌が上手いんだろう。なんでそいつの、「この合唱曲はださい」っていう感覚は共有されて、自分が推す曲はダメなんだろう。一体何が悪いんだろう。なんで伝わらないんだろう。自分の中に常に響く声は誰よりもうまかったと本気で思っていた。本当にCDから聞こえてくる音と同じ音が、低いベース音が鳴っていたのだった。
それを再現するために毎日練習していた。なのに、他の奴の声はなんで、綺麗だと評価されるんだろう。おかしい。絶対におかしいはずだ。
自分が合唱に捧げた努力を先輩が評価してくれて、低音部のパートリーダーに任命された。それは、3年生の引退した2年生の秋の始まりのことだった。だが、パートリーダーとして自分に出来る事は何もなかった。
まず、楽譜通りにピアノを弾く事ができなかった。
練習をしていなかった訳ではないが、楽譜に書かれている音を拾って、1音ずつ指で弾く事が手一杯だった。ということは、合唱の基礎として必要な音取りの作業ができない。
みんなの声が、CDの声と比較したら未熟なの事だけは分かった。
でも、その声をどうしたら成長させることができるか、分からなかった。
毎日、先生や絶対音感を持つ学生指揮者(先生が不在の際や、基礎連のハーモニー練習の際に指揮する、音楽的なスキル・指揮能力の高い生徒が担当する役職、部長とは違う)に毎日罵倒された。
後輩を見習えと言われ、後輩から向けられた蔑むような眼は今でも忘れられなかった。
パートリーダーであるのに、自分が一番歌がへたくそだった。
だが、へたくそから抜け出す事ができなった。
自分のどこがへたくそなのか分からなかったからだ。
それを最大限自覚した時があった、自分の声の録音を聞いた時だ。
部活の中で誰よりもへたくそな歌だと思った。
びっくりした。
あの、脳みその中で聞こえる美しい声はなんだったのか?
何も信じられなくなった。
だったら、と、歌の解釈を誰よりも極めようと思った。
だが、自分がパートリーダーになった年に歌ったコンクールの曲は、ダンテの神曲がテキストになっている、ラテン語の曲だった。正確な発音をする所からつまずいた。まず、巻き舌ができなかった。巻き舌ができないということはRの発音がのっぺりしてしまうことに繋がり、ラテン語の持つ音の響きが、片言の英語発音のようになってしまう。ラテン語の正式な発音をコンクールの審査員が完全に把握している訳ではないが、外国人が日本語の曲を歌うときに、片言の英語的なアクセントの発音で日本語を歌う時に感じる違和感が曲の中に生まれてしまうのは致命的だった。
また、曲の解釈をするためにダンテの神曲を読もうとして挫折した。ダンテの神曲の本の太さ。書いてある言葉の意味が最初から分からず、投げ出した。ある時、後輩の楽譜を覗いてみたら、ダンテの神曲を読みこんだうえで、詩の中に引用されている文章に対して自分なりに注釈を加えていた。それを見てしまった。また更にそれを学生指揮者の友人が取り上げて絶賛した。先生も拍手していた。負けだ、もう負けだ。パートリーダーの立場が辛くなって逃げだした。メンバーには毎日愚痴を吐いた。自分が奪った、自分よりも音楽的資質を持った友人に対して愚痴を吐いてしまった。当時彼は何を思っていただろう。
そして、歌の練習をやめた。あんなにただ歌う事が好きだったのに、歌う事が毎日苦痛になった。毎日遅刻ギリギリで登校するようになった。昼休みに音楽室に行くことはなくなった。放課後は掃除を理由に発声練習から逃げ出した。
何が正解なのか、何を求められているのか、何をすればどうすれば皆の期待に応えられるのか。全てを見失っていた。先輩からパートリーダーの責務を引き継ぐする際に宣言した「絶対に全国に行きます」という約束から逃げ出した。自分が2年生の時の大会で、我が合唱部は30年ぶりに地方大会で金賞を獲得し、あと順位が2つ上であれば全国大会にいけるレベルにあった。歴代最高峰レベルの合唱団の、男声低音部のリーダーの責任を背負う事が怖かった。それが、自分のせいで全て崩れてしまう日々におびえた。
高校最後の大会が終わった時、最初に思った感想は、「やっと終わった」だった。負けたのに、悔しくなかった。地獄からやっと抜け出した事に満足していた。大会の練習を進める中で、一時的に自分を取り戻した事もあったが、結局➀~③の課題は解決できないまま、地方大会銀賞という結果で終わってしまった。そこからの日々は燃え尽き症候群のように何のやる気も起きなかった。受験は想定通りに失敗し、浪人生活に突入したのだが、そのさなかで出会ったのがネット詩だった。
音楽の才能はないと自分に決めつけていた自分の最後の砦はおそらく詩だったのだと思う。自分にとって中学生の頃にあった、学業という砦は部活動に熱中するあまり無くなっていた。…というのは言い訳で、正直入った高校のレベルが高すぎて、自分には学力がない事を思い知らされたというのがある。1年生の最初の学内テストの結果がほぼ最下位だったのだ。授業の内容は何を言っているのか殆ど分からなかった。分からないから、部活動に逃げるしかなかったのだ。また、部活動が終わった野球部がその後一気に勉強して志望大学に入る。みたいなストーリーを死んでいた事もあって、自分も部活を引退したら勉強を頑張るだろうと思っていた。
だが、実際にそんなことはなく、勉強する気は全く起きなかった。さぼってきた3年分の勉強をゼロから追いかける事も億劫だったが、なにより、勉強していきたい大学がなかった。要は人生の目的というものがなかった。自分にとって唯一大切だった「合唱」は当時自分が思っていた感覚としては「合唱」側から見切りを付けられた存在だった。
自分には何があるのか…という自問自答の果てに、見つけたのは詩だった。
そうだ。詩だ。詩である。
詩は、特に日本語で書かれた詩なら、自分はまだ戦える…気がする。ダンテが分からなくても、日本語の詩に書いてあることを理解し表現することが得意だと思っていた。楽譜通りに歌う事ができないならば、自分が指揮者になればいいのだ、指揮者として振る舞う理想的な環境は、自分で作った曲を振るう事にあるんじゃないか。俺には歌の才能がなかった。ならば、作曲の才能があるかもしれない。作曲の才能がなくとも、詩の才能があれば、どうにかなるかもしれない。
という考えに至った結果、詩を市立図書館で探して読んでる事に決めたのだ。みんなが勉強している合間、詩をあさり続けた。だが、正直、面白いと思える詩は見つからなかった。詩の蔵書が思ったより少なかったということもあるが(現代詩文庫は最新の20巻くらいしかなかったというのもあるし、市で最大の図書館だというのに、現代詩手帖は講読していなかった)
今思えば、そもそも詩に何が書かれているのか分からなかったのだと思う。日本語に書いてある現代文の文章すら分からず、国語の点数が悪かった自分には詩は呪文みたいな意味の分からない日本語として見えていたと思う
。合唱曲という作曲家がインスパイアされたイメージがあっても分からなかったのに、詩単体から何かしらを受け取ることなど出来るはずのなかった。一番最悪なのは、詩を読む目的が、もはや受験期の不安を紛らわすための暇つぶしや逃避であることに気が付いていなかったという事だろ思う。
そんな状態で、図書館にある詩はつまらないと見切りをつけてしまった。でも自分には、もう詩しかない。正確には、曲を作る為には、インスパイア元となる詩がどうしても必要だった。(合唱曲は特に、現代詩から詩を採用するという文化ということもあったが。偶に曲の後に詞を付けた作品や、作詞・作曲が同じ人もいるが極まれだ)
最終的に行き着いたのは「自分で詩を作るしかない」ということだった。そのために詩の修行場を探し始めた。ライトノベルの賞が、ネットから簡単に応募できることを知っていたので、「詩」もネット上に投稿できる賞があると思っていて調べた結果であったのがネット詩の投稿サイトだった。市の図書館においてあるパソコンからネットに接続し、「詩」「プロ」で検索した結果、今は亡き、ネット詩の投稿サイトに辿りついた。
ここから自分はネット詩に夢中になっていく。
自分がネット詩に嵌った理由は大きく三つある。
➀詩について真剣に語る人が沢山いる
②他の人の詩の感想がいくらでも参照できるし、自分も混ざることが出来る
③自分の詩を投稿でき、感想が貰える
合唱に惹かれた時と対して変わらない動機だったのではないか。と、こう並べてみて思う。
合唱部には、音楽のエキスパートは沢山いた。だが、詩のエキスパートはいなかった。(漢詩・短歌はいた)詩の解釈会議を部活で開けば、誰もしゃべらない事が殆どで、というか自分以外は「よく分からない」というのが口癖だった。そして、自分は自分で熱弁しておきながら、結局何を言っているのか分からなくなってしまっていた。そういった状況に対するフラストレーションが溜まっていたこともあり、詩について語る相手が当時は切実に欲しかったのだ。解釈の交換が出来るような人を求めていた。自分の読みを確かめあえるような存在が欲しかった。その相手が、ネットの掲示板に沢山いるという事実は衝撃的だった。
さっそく、自分の周りの友達にネット詩を紹介して回った。一度でいいから見てほしかった。当時流行り出したスマートフォンを友達に開かせ、ネットに接続させ、投稿サイトを見せた。乗っている詩や、評文を参照させて、こんなすごい世界があるのだと熱弁した。特に、当時の自分が一番呼応していた考え方は「紙媒体の詩はつまらないから、ネット上で新しい詩の文化を作り、売れる詩集を作ろう!」みたいな考えだったと思う。というかそういう事を実現する場がネット詩なんだ解釈していた。(認知の歪みがかなり出ていると思いますが、当時の僕の感覚なので、その点は留意いただきたい)だから、本当は「詩」って面白いもので、自分達高校生にとっても面白いもので、読める物であって、図書館においてある詩がつまらないのは、その価値が分からないからではない、詩が悪いのだと錯覚してしまった。読まれるための詩を追求している人達がいて、詩を滅茶苦茶書いているという事実を曲解して、自分が詩が読めなかった理由は、自分の感覚が間違っていたのではない、詩の方が間違えていたのだということにした。
調べると、ネットの掲示板に参加している人たちの年齢は自分とそこまで離れていない事に気がついた。自分より3、4個年が上の世代の人達がガラケーからネットにアクセスして作品を発表している。その事実を知って、勇気が出た。自分もこの世界の飛び込んでみたいと思った。
受験勉強そっちのけでネット詩にのめりこんでいった。
その結果は…もうお分かりであろうが、合唱と同じ過ちを犯すことになった。合唱に嵌ったと同じ手法で勉強した。まず、誰よりもネット詩を読んだ。過去ログをさかのぼり、最初から最後までなんども読んだ。誰よりも長いレスを書いて作品を読み込む姿勢を見せた。誰よりも長い作品を書く事で気合を見せようとした。詩がかけるようになれば、詩が読めるようになると本気で思っていた。
ネット詩の掲示板へはいきなり参加しなかった。まずはROM専から始めて、掲示板の流れを掴んだ。次に、段階的に自分が参加する場を変える作戦をとる事で、徐々に自分の憧れの人へ近づいていくことにした。目標は自分の憧れの方の作品にレスを付ける事。そして、憧れの人達から自分の作品を褒められる事。そのためだけに、参加しつづけた。大学に行く目的は出来たのはこの時だった。とりあえず文学部に入ろうと思った。文学部に入れば詩を学術的に読めようになるに違いないと思った。何も考えていない場当たり的な他人任せの発想だった。実際に、大学選びには失敗して、自分が入った文学部には、詩を担当している教授がいなかった。また、合唱サークルはとなりのトトロを歌っているような、女声合唱団の小さなサークルだったし、大学生活では何も得ることが出来なかった。
結局、中身が変化しないのであれば、場所が変わったって結果は同じなのである。詩を紹介しても碌な紹介はできないから見せることしかできない。それを友達に「詩は分からないからなぁ」と否定されたら切れるしかなかった。「お前にはもう紹介しない」と逆切れした。この良さが分からない奴はセンスが遅れていると本気で思っていた。実際には遅れているのは自分の方だった。読んでいる俺は誰よりも分かっていると思い込んでいたが、実際には誰よりも本を読んでいなかった。誰よりも詩を読んでいなかった。読んでいたのはサイトトップにある檄文と、そこでなされる正直しょうもない人間関係のいざこざのログと、作品に寄せられた書かれた感想だけだった。感想を読んでわかった気になっていた。だから、作者と作品名だけやたら覚えた。誰よりも中身のないレスを書いた。レスを書けば書くほど、色々と整合性が取れなくなっていく自分の感覚の矛盾が首を絞めてきた。自分の妄想を押し付けて、罵倒した所で的外れになることが多かった。この表現が分からない。なぜ分からないのかというと、書いてあることが分からないからです。という事をいうために、長ったらしいレスを書いては、その返答で、お前は何も読んでいないと否定された。悔しかった。でも、その通りだと思った。最終的に、自分の乏しい読書体験と投稿された作品を比較して、つまらないみたいなレスを書き始めたが、それは結局、自分の中にストックされた認識と作品を比較して「俺の知っているものの方が凄い!」とドヤ顔をする行為に過ぎなかった。詩と関係のない漫画を引用して酷評していたこともあったが、今思うとなんで漫画の表現と詩の言葉の表現を比較できるんだろうと思う。
こういった意味の無い批判を書くために、大学生活の殆どの時間を費やした。
自分にとっての詩とは何か。
自分が合唱で叶える事のできなかった、自己表現欲求を満たすための、道具にすぎなかった。歌う事を諦めて、曲を書くために、詩が必要だった。でも、自分の琴線に触れる詩が、多分なかった。あったものは既に歌になっていたからどうしようもなかった。だから、自分で詩を書くために、ネット詩という新しいプラットホームを探し出したのだ。そして、「詩」への興味よりも、ネット詩に居る人達や場所に惹かれた。
「詩」はいつも自分の外側にあって大事なのは詩の存在する「場所」だった。
いつしか、詩を読むために詩を書き始めていた。
作曲という目的はとうの昔に忘れ去られていた。
詩に書きたい内容なんてなかった。読むために書いていたのだから。作者の視点を手に入れる事で、技術的な素養を身に付ければ、詩が読めると信じていたのだ。だから、自分が書く作品というのは、誤字脱字だらけだった。どんなに内容が酷かろうが、詩を書くのは歌を練習するようなものと一緒だった。最初はへたくそであったとしても、手本となる作品を読みながら書いて行くことで、うまくなるはず。そしたら詩が読めるようになるはず。という狙いから始めた行為が、いつしか自分の首を絞めていった。書けるものというのは、結局「自分」が全てだった。描きたい幻想も思想もイメージも比喩も表現技本も物語も何も持ち合わせていない、そんな自分のちっぽけさだけが日に日に自覚させられただけだった。
また、その全てが自分が罵倒してきた多くの作品達と比べて、貧弱だった。自分が描くことが出来るのは、自分が切り捨ててきたような、自己憐憫・自分語りによって構成された感傷だけだった。そんなものに愛着など湧く訳がなかった。逆に自作をこう考えていた。「自分の作品を評価する人間の目は絶対に信じない。なぜなら、こんな世にありふれている、読まれるための努力や伝えるものがない作品を評価している人というのは、排泄物を評価する人間であると考える。そういった人達を見抜くチェッカーとして徹底的に活用しよう」その発想が極めて人を馬鹿している事は分かっていたが、自分にはもうネット詩しかないのだ。自分に詩の才能がなく、何を信じればいいのかわからなくなっていくなかで、詩を書く事をやめられなかった。
そして、合唱から逃げ出した時のように、詩から逃げ出した。数年前の事だ。その時、自分は詩の掲示板の管理人を担当していた。パートリーダーに選出された時のように、詩のサイトを新しく作るからその管理人にならないかと今までの努力を認められてサイトの主催者に声をかけられたのだ。最初は、自分には無理だと思っていたので断ろうと思った。でも、同じミスを詩で繰り返す訳にはいないと思っていた詩、このままでは自分を救ってくれたネット詩という場所がなくなってしまうと当時は本気で考えていた。
また、なんだかんだ言って、自分に声を掛けてくれたことが嬉しかった。できないと思いながら、惹かれて始めた事だらけの人生で、初めて詩の世界で声を掛けられた事は恐れ多いと思う自分がいつつ、しかし嬉しかったのだ。また、運営に参加することで、今までのネット詩の歴史を追体験が出来るとおもった。最初は同じ轍を踏んで、色々とトラブルが起きるかもしれない。運営をするのは大変ということは過去のログを見れば明らかだったし、トラブルは絶対に起きるだろうと思っていた。だが、でもそういった経験を積んでいくことで、その先にいくことができたら、何か変わるかもしれない。そう考えた。自分には詩を作る才能も、読む才能もなかった。でも、運営はできるかもしれない。詩で金を稼ぐことが出来るかもしれない。
そういう思いで、参加した。
他にもいろいろな理由があるにはあったが、ともかく、詩から逃げる訳にはいかなったのだ。逃げたら自分がどこで生きればいいのか分からなくなってしまう。
だが、結果的に逃走することになった。
逃亡直前に「詩の賞」の開催を発表したのを覚えている。
確か、賞金10,000円の個人賞だった。
その賞を開催する事を宣言した次の日に被害者面した運営を退任し、ネット詩から足を洗う事を宣言するようなtweetを連投した。
当時毎月担当していた、詩の選考は自分で担当しておきながら苦しんでいた。その時の管理人のメンバーに言われた「お前には詩が読めない」という言葉は、かなりきつかった。当時は、頑張って言い返していたが、その理屈をひねり出す裏側で、泣いていた。
自分は詩が読めない。そして、運営能力がない。無能だろいうこと。
それだけは絶対に認める訳にはいかないのだ。
次の逃げ場所は必然的に仕事になった。詩のサイト運営から逃げ出した要員の1つが大学を卒業して、社会人になってしまい、日々の仕事に忙殺されて、趣味である詩に割く事のできる時間が減ってしまったという理由があった。だから、趣味の世界に浸るのではなく、現実を生きる事にした。
とはいえ、仕事は全く以て上手くいかなかった。求められた仕事を期限までこなす事は出来なかった。チームプレイが常に求められるのが辛かった。仕事場で、飲み屋で。議事録を書くのが苦痛だった。何を書けばいいのかわからなかった。会議の内容を全部書けばいいのかどれくらいカットすればいいのか何も分からない。メールの書き方が分からなかった。仕事の専門用語が分からなかった。上司の言っている事が分からなかった。仕事でミスをした時になぜなぜ分析を受けた。5時間に渡り本社の会議室で上司に分析された。自分の仕事のミスを分析された。それでも、自分が確認を怠ったというミスを認められなかった。確認しろと言われても何を確認すればいいのか分からなかったから無理だと思っていた。
そして、仕事から逃げるように詩の世界に戻った。だが、現状は何も変わらなかった。中身が変わらないのだから。また、仕事に戻った。仕事が辛くなって詩に戻った。それを繰り返した。片方に夢中になれば片方がおざなりになる事の連続の中で、毎日の出社が苦しくなってしまった。朝は常に苦しみの中にあった。相変わらず詩は全くよめなかったし、読んでいて楽しくなかった。自分が過去心酔していた思想は社会人になってから、どんどん色あせていった。ある意味現実が見えるようになったのかもしれない。詩の世界がネット以外にも沢山あることを知った。知った事により、自分の中のネット詩を守らねばという使命感が消えてしまった。紙の世界の方が詩は案外しっかりしている事に気が付いた。また、自分の知らない人達が沢山自分の去った場所にいて、それぞれ活動していることを知った。詩は何度読んでも過去の感動を利用して無理矢理泣いているようなものになっていった。自分の果たす事のできなかった沢山の後悔だけが時折急に襲ってくるのが怖かった。「かなえる事のできなかった気持ち」救ってくれる詩がたまにあって、自分を繋ぎとめてくれた。そんな自分が詩を読む意味は当時これしかなかった。「救ってくれる作品」それ以外になんの価値があるだろう。それに応えてくれない詩になんの価値があるだろう。逆に、それ以外の価値を自分は見つける事がなんでできないんだろう。自分が詩を読んで泣いている意味がわからなかった。
自分にとって大事な感情「救われたい」という気持ちは、他者と共有することができなかった。どんなに救われたと思ったところで、ちゃんと作品を読んでいくと別の感想にたどり着いてしまう事が殆どだった。
偶に自分が感動した作品を紹介しようとしたこともあった。だが、その度に失敗していた。なんで、こんなに言語化できないんだろう。自分がマイクの前で話す感想には疑問符がついて回った。自分が発した言葉が常に間違っているように思えた。自分の感動は何も信じられなかった。
相変わらず、本は一切読んでいなかった。正確には読めなくなっていた。常に何かを疑うかのように文を読み、書くようになってしまった結果、散文なんかまともに読んでいられなかった。そういった理由から詩だけは読んでいた。詩は短いから、まだ読むことが出来た。表面的な読書量の話だ。
自分の詩に対する姿勢というのは、仕事に影響を及ぼした。例えば、メールを書く時は、いつも結果ではなく、その結果を導き足した検討プロセスに重点を置いた。だから、1通のメールを書くために2時間かけていた。まるで、その結論自体の是非を問うのではなく、自分なりにここまで検討したのだから、この結論が正しいはずだ。という事を、叫んでいるようだった。自分が否定されることが怖かった。
ある時、ツイキャスで誰かに自分の事をこう評価された「常に何かにおびえている」怖かった。自分よりも自分を知っている他者が怖かった。それを自分よりも先に、繕っている自我を暴かれた気がした。誰か自分の事を殺してくれないかと願った。しかし、自分で死ぬ勇気なんてものはなかった。自分より苦しみを負って生きている家族がいたということもあるが、ネット上には自分よりも辛い境遇の人達が沢山いた事を知っていた。
自分はまだましだ。
だって、詩に救われたんだから。
生きて行けるはずだ。
大丈夫。
今年、表面的なやる気が認められて会社でリーダー任命された。上司になったという事は部下を導く立場になったという事であるし、目標を自分で設定して達成しなければならなくなった。しかし、いつまで経っても目標を決めることはできなかった。リーダーの依頼を受ける事にしたのは、人が足りなかったという事もあるが、自分がパートリーダーのや、ネット詩の運営を引き受けた時と同じ理由だったと思う。「やる気があることを評価された」それだけだ。ビジョンはでっち上げることにした。自分のチームが欲しい。そのために顧客から信頼を集める。部下の面倒は見る。今度は誰も見放さない。同じ轍は踏まない。そういう事にした。
(本当に?)
(同じ轍は踏まないの?)
というささやき声は常に聞こえていた。自分の何が正しいのか、生きる目的は、相手の気持ちとはなんだ、そういった事が、何も分からないままコロナ禍に突入した。家の中で仕事を続けることができなかった。やがて発狂ししてしまった。心療内科に駆け込み、発達障害の診断を受けることにした。診断結果は注意欠陥多動性障害だった。これが全ての現況であってほしいと思った。全部こいつが悪いんだろ思ったら楽になった。医者に処方されたストラテラを飲んだ。効果は得られなかった。結局、かかりつけの病院を変えて、薬をコンサータに替えて飲み始めた。いくらか症状はましになったのだが、それでも、日々生きていく中で薬ではカバーできないことが沢山あった。
自分の発達障害を治すために必要な要素は多分生きる目的だった。合唱に夢中になった時のように、ただ一つの目的に向かって全力を注ぐことが出来たら、そういった夢に向かって全力を出すことが出来たら、日々が楽しくなるはずだったのだ。そのためだったらなんでもできるはずだと信じていた。それが見つからない限り、どんな目先の目標を持っても、誰かの役に立ちたいとか、恩を返したいと思っても、あるいは経験するうちに目的が見つかるかもしれないというような一縷の望みに身を託したとしても、どんなに自分の感情を一時的に偽っても、どんなに作品に感動して一時的に気持ちが楽になっても、今の状況から抜け出せるとは思わなかった。
常に心の中は不安だった。「何かをした所で意味なんてないよね」というささやき声が常に胸の中に響いていた。
そして、また、詩に戻ってきてしまった。
その時、自分の思いをTwitterにぶちまけまくった。
Twitterにはなるべく書かないようにしてきたことも全て。
でも、中途半端に終わった。やっぱり、Twitterに自分の思いをそのまま描く事なんかできなかったのだ。自分のイメージを下げる事が怖かったのもあるが、書けば書くほど苦しくなってしまったというのが実情だ。自分がメンヘラにしか見えなかった。自分の事しか見えてないガキであることを認めてしまうのが嫌だった。
詩の感想は一切かけなくなっていた。
感想を抱いた瞬間に疑念が心をつついた。それを言葉として固めて発露するのが怖かった。感想を口に開いて言おうとすれば、何か違うような気がした。実際に他者から「何を言っているのか分からない」と指摘されると、苦しくなった。でも、それはやっぱり自分の主催するラジオの録音を聞き返したりすると、自分でも何を言っているのか分からなかったから、正し感想だと認めるしかなかった。また更にそれが、自分の一番嫌いな声で再生される事がきつかった。
詩は、偶に発表していた。切れ切れの限界的な状態から、話材を見つけてだした。それらを縫合して、膿を吐くように掲示板に投下した。いったい、なんのために詩を書いているのか分からかった。溢れてくる苦しみを言語化できなかった。また、言語化した所で伝わらないと思っていた。また、言語化して伝えた所でよくある感傷に過ぎないのが嫌だった。それを他者に伝える気なんか起きるはずがなかった。他者に読ませる価値なんてものはない。ただのゴミでしかない事を自覚しているのに、気が付いたら投稿ボタンを押していた。最低限の作法として、それまで培ってきた詩のテクニックらしきものをふんだんにまぶしたり、自分が使う事のできる最低限の日本語、言葉遊び、記号、改行、体裁、タイトルの含み、そういったものを詰め込んだ。全ては繕う為だった。自分が去った場所に、自分が捨てた場所に。だが、感想が付けば軒並み嬉しかった。自分がゴミだと思っているからこそ、自分の感覚を信じられないからこそ、他者に読まれる事によって、自分がどういう苦しみの中にいるのか、理解できたからだ。それが正に救いになっていた。
そういった「矛盾」に揉まれる中で、気がふれそうになりながら、投稿ボタンを押してしまった日はいつも寝れなかった、そのまま徹夜して朝を迎えてた日は、二度寝して遅刻した。遅刻の回数は日に日に増えていった。
……というここまでが、長い前座の話である。(こういったどうしようもない状況から、今ようやく抜け出そうとしていて、そのために、この記事を書いていると言ってもいいくらいだ。)ここからが本番なのであるが、それを描くためには過去の自分がしてきた行いや、自己評価を書く必要があった。過去の自分の認識の全てが間違っていたことを認め、自分が犯してしまった罪と受けるべき罰の話をするために必要なプロセスだった。これでも、自分にとって都合が悪い部分は省略したので、許してくれるとありがたい。
自分が詩に求めていたのは、詩ではなくそこにいる人だった。というのは先ほど書いた通りだ。言ってしまえば、友達が欲しかったのだのだと思う。自分の価値観を尊重してくれて、自分の好奇心を刺激してくれるようなそんな友達が。
詩をやめてしまうと友達がいなくなってしまった。
(大学・高校以前の友達とはほぼ連絡を取っていなかったし、そもそも自分の近くに住んでいなかったというのもあるが。)
だから、詩の世界に何度も戻ってきたのだと思う。友達がいるから、詩が嫌いでも戻ってくるしかなかったのだ。詩でつながっている限り、友達は友達でいてくれた。逆にいうと、友人が自分の事を手放さなかったお陰で自分は今ここにいて、この記事を書いている。振替ると沢山失礼を働いてきたののに、なんで友達でいてくれるんだろうと不思議ではある。
そんな友達が最近2つの詩を紹介してくれた。
その後、こんな質問を投げてかけてくれたのだった。
「今のあなたにとって、(〇〇をやる・するときに)何を大切だと感じてますか?」その〇〇に「詩」を入れたとしたら。
詩の感想は色々考えた結果、別の記事で書く事にした。この記事の中に入れてしまうと、「自分の人生」という文脈の中と、その作品を比較して、如何に自分がその作品によって救われたのか。という話になってしまいそうだからだ。それは本位でないし、今の僕がしたいことではないからだ。
ただ、重要なのは、その紹介してもらった作品を読んだ結果、出された質問について真剣に考えたという事だ。今までは、分かった風に適当に答えていた。反射的に、「言葉」が大事だとか「大切なものはない」「読まれる事によって自分が分かる」とかそういった質問自体を拒否する答えや浅はかな詩に対するイメージを頼りにした適用な回答しかしなかっただろう。
そしてこの質問に対するアンサーとしてこの記事を書く事はなかっただろう。
……最近、自分は人を傷つけてしまった。何をどう傷つけたのか。それは、詩を自分の感覚を徹底的に押し付けるように読んでしまったという事だった。自分は「読めない」という免罪符を使って、詩を単語レベルで八つ裂きに分解したのだ。その八つ裂きに分解している様子を、あろうことか作品を書いた人に向けて喜々として話してしまったのである。
傷つけてしまった人は、自分が詩に思っていた事を思い出させてくれた方だった。辛抱強く、自分の中にたまっていた詩に対する思いを吐き出させてくれた。覆っていた偽りの感情と諦めをはがしてくれたのだ。自分にとっての詩は「救い」だけだったのか。そうじゃないだろうということを思い出させてくれた。
一番最初に引用した、「私が歌う理由は」の最初の歌詞に感じた「違和感」正にそれこそが自分が詩に感じていたものだったはずだ。ネット詩に惹かれたのは現場に惹かれただけじゃない。投稿された作品が、図書館で読んだ作品よりも魅力的に、当時見えたからじゃないのか。それは合唱と出会ったときもそうだったはずじゃないのか。その感覚に身を焼かれるくらいまではまってしまった理由は、自分が出会ったあの時のインパクトを自分で表現できるようになりたいからじゃないのか?
全ての出発点となる気持ちを気が付かせてくれた方の作品を、俺は徹底的に裁断して、その人の考えを自分の中に取り込もうとしていた。その過程を、見せつけてしまった。3時間かけてメールを書いていた、結果のないプロセスの検討だけしかないあのメールみたいな内容だった。自分が何を受け取ったのかではなく、必死こいて無理矢理受け取ろうとしていたのだ。そういう解体現場を、見せつけた。自分の中にあるエゴしかない読解の現場を。延々とその人にぶちまけてしまった。それが、自分の中にある「感覚」で他者の感覚を凌辱する行為だと気が付いた時、友人の質問の答えが出てきた。
「今のあなたにとって、(〇〇をやる・するときに)何を大切だと感じてますか?」その〇〇に「詩」を入れたとしたら。
俺は詩を書く時、読むとき「感覚」を大切にしているのではないだろうか。
どんな?
自分の感覚を知る為に書いていた。
他者の持っている感覚と自分の持っている感覚が一致してほしかった。
そのために、俺は自分の作品が排泄物だと知りながら、しかし、掲示板に出して、自分の感覚を他者に教えて欲しがったのではないか?
わざわざ、感想のかける掲示板に出して、確かめていたのではないか?
他者の感覚と自分の感覚がズレている事におびえていた。
常に自分の感覚が他者と重なりあっていて欲しかった。そのために、自分の感覚で他者の作品を上塗りするように読んでいたのではないだろうか。
「自分の感覚」のために詩を読み、書いてきた。という事に気が付いてしまったとき、そこには、「他者」という要素がどこにもない事に気が付いた。自分は誰かの感覚を尊重したことがあったのだろうか?
全く以てない事にきがついてしまった。
そのことに気が付いた途端、自分が今まで語ってきた全ての作品に対する言葉が、相手の感覚を否定し、自分が絶対であることを押し付ける行為であることを自覚してしまったのだ。自分の感覚全ては正義であって、その感覚を点検しようとすらしなかったのは、他者とすり合わる気がなかっただった。なんだかんだ排泄物といいながら、自分の奥底では、自分の感覚が正義であってほしいと願っていた。否定されたくない物は、自分の感覚だったのだ。だから、自分の感覚を守る為に、他者の感覚を馬鹿にしていた。その理由は「自分は他者より努力しているから」という理屈だったのではないだろうか。友達ができなかったのは、友達と縁を切ったのか、友達の事が信じられず、友達の事をただ自分の感覚に対して共感してくれる存在としか見なさなかったからではないのか。部活動で、自分の歌声に対して毎日指摘してくれた友人の思いを考えたことがあっただろうか。自分の声の録音から感じた嫌悪感からなぜ逃げたのか。才能という言葉や、発達障害という言葉で逃げたのはなぜか。仕事から逃げたのはなぜか。いつも、自分から誘ったという形式を持つことから避けたのはなぜだろう。責任を負う事から逃げるためだ。誘われたから始めただけであって、自分から始めた訳ではないという、「逃げ道」がないと人と関われなくなったのは、人の事を人とみていないからだ。その人のせいにする事しか考えていなかった。誘ってくれた人の気持ちなんか考えた事もなかった。考えたふりはしていても、心の底にあるのは、自分の気持ちが第一だった。
人の気持ちがずっと分からないと思っていた。特に怒られる時に強く思っていた。なんで怒られるのか分からなかったのは。自分の感覚で耳をふさいでいたからだ。相手がどういう思いで、どういう感覚で、自分に語り掛けているのか知ろうとも考えようともしなかった。ただ、突き付けられる激しい言葉や感情が怖くて、逃げる事しか考えられなかった。でもそれは、心の奥底で他者を馬鹿にしていたからではないのだろうか。
ここに書いただけでは収まらない、過去の一つ一つの出来事が、全ての人生で自分が目を背けてきた、自分の感覚と他者の感覚と向き合うという行為が、文字通りの罪と罰として一気に去来した。
歌が上手くなる近道というのは、実は分かっていた。
自分の録音を聞く事だった。
次の日はその声よりも綺麗な声を出せばいい。
ただ、それを只管繰り返せばいいのだ。
脳みそに谺す音が他者から聞こえる音と違うのであれば、自分の声を録音して聞けばいいだけだった。
目指すべき目標は、沢山聞いたCDで得た知識の中にあったし、後は、自分の感覚と他者の感覚を相対的に比較しながら、自分の声を聞いて、理想的な発声に向けて修正すればいいだけだった。
色々と御託をならべて自分にはできない理由を沢山並べていたが、所詮高校生の素人が導き出した、結論に過ぎなかった。また、その結論を出す前に、自分の声を聞くべきだった。自分の弱さを客観的に捉え、修正していけばよかったのだ。
それが、なぜできなかったのか?
自分の感覚が、脳内に響き渡る声が、自分のしてきた努力が、まやかしであり、無駄であることを否定されたくなかった。
それだけの話なのだ。
自分の感覚を冷静に受け止め、検討し、言語化してフィードバックすればよかった。
「私が歌う理由」に感じたあの違和感の正体をちゃんと言語化すべきだったのだ。まずは、しかし、当時は自分の心に響き渡る価値観が正しいものであって他者の感覚は自分の想定内の感覚に基づく価値観しか認められなかったのだと思う。自分のプライドを保つために、それを脅かすものは受けられなかった。受け付けられる訳がない。だから、谷川俊太郎の「私が歌う理由」の始まりの一節におびえたのだ。自分の価値観を浸食してくるような詩を許容する訳にはいかなかった。
自分が詩に救われた理由もよくよく考えれば、「自分の感覚を言語化してくれたから」という事になるが、しかしそれは、自分の都合のいいように、作品を寄り添わせて読んだだけに過ぎなかった。自分の価値観をみとめてくれたような気がしただけなのだ。自分から作品に描かれた感覚に寄り添ってなどいなかった。何も寄り添う気がないのに、他者の感覚なんかわかる訳がない。自分は救われたいのだ。でも、その作品が自分を救う為に書かれている訳がないのだ。その動機は別の所にあるはずだし、書かれた契機なんかそれぞれの作品ごとに異なって当然のはずだ。ましてや、通常の散文的な語りではない、特殊な表現方法を駆使してまで表現に拘っている口語自由詩において、自分の中にある感性だけで読み取れるものが全てな訳がないのだ。
自分が詩に救われたと思っていた時、起きていた自分の内部事情はこういうことだ。「自分の感覚」という既存の巻き尺が反応して顔を出し「これはお前の為にある作品だ」「この表現は今のお前を表している」という感想を出力したに過ぎないのだ。これで何を読んだ事になるんだろう。気持ち悪い。
「自分の感覚」でしか詩と関わっていない。いや、他者と関わってこなかった。という事実に気が付いてしまった。それは、仕事の最中のことだった。吐き気が止まらなくなり、心臓を抑えて、何度もトイレの個室に入って、項垂れた。過去全ての人生の中で犠牲にしてきたもの、自分のために時間を使ってくれた人達、それらの人達に対する裏切り、罵倒、気持ちの押し付け、正に善意と思って提供した誤読によって傷つけてしまった事、自分の気持ちを分かってくれないからと、他者の感覚を踏みにじった事、他者を傷つけてきた記憶が脳内で再生された。それらの全てから槍を刺された気分だった。それを守ってくれる、自分の盾はもうどこにもなかった。目を背けてきた自分が悪い事を認めたからだ。
もう過去は戻ってこない。
だが、気が付いたところで、取返しなどつく筈なんてないと思っていた。
この気持ちを吐き出したい。消えないだろうが、紛らわしたい。そのために、他者を使用するのは、やっぱりできない。どうしよう。もう無理だ。助けを求めている訳じゃなかった。耐え切れずに、Twitterで呟いてしまった。直ぐに消した。でも、この不安は消えてくれなかった。そういう逃げの行動をとってしまう自分が、気持ち悪くてしょうがなかった。
最終的に友人に頼る事にした。
質問を投げてくれた友人に、中途半端なチャットを送ってしまった。
よくわからんですが、とりあえず自分がキーワードだと感じたことを、一回まとめてみたら、それこそが感覚なんやないか。
ちなみに、今日、過去の記事読み返したけど、過去の自分に教わることってあるよね。
https://note.com/collaborationyou/n/n66182440187a
自分の為にまた友達を利用してしまった。という思いを抱きながら、返ってきたメッセージにすがった。引用されたnoteの記事を開いてみた。それは、自分で書いた文章だった。
書いた事は正直忘れていた。
そこには、自分が切除した汚い自分の感覚が刻まれていた。
相手に対する嫉妬心や、傷つけてきた過去の全てが勢いのまま書かれていた。なんて醜いんだろうと。しかし、そこで、ふと思ったのは、自分が捨ててきた、自分の抱いていた言語化しがたい「感覚」を今まで自分は詩として書いてきたんじゃないのか。という事だった。
忘れるということは、記憶のような情報だけではなく、感覚も忘れる事が出来るのである。この自分の言葉は醜い。書いている時も、多分醜いと思いながら書いていたと思う。でも、なんで忘れているのだろう。そして、その醜いと思ってまでも、言葉にして伝えたかったのはなぜなんだろう。
ということを考えた時に、自分にとっての詩が見えてきたのだった。
自分にとっての詩とは何か。
自分の中にある感覚を伝えるための言語表現手段だった。
自分の中にある認められない感覚を切り離すための排泄行為だった。
自分の中から切り捨て忘れようとした感覚を記録するための行為だった。
自分の中から消えてしまった感覚を思い出すための記録だった。
そして、自分の中にない感覚を教えてくれる表現方法だった。
時に違和感として、時に気持ち悪さとして、時に喜びとして、時に悲しみとして、自分では経験することも考える事もなかった他者の感覚を。
突き付けてくれるものが詩だった。
そのために、詩人はあらゆる言葉の技法駆使して、
他者に分かりにくい何が書いてあるかわからないと言われようが、
一冊の本を出すのに金が掛かろうが、
読む人がいなかろうが全力で表現しているんじゃないのか。
感覚を伝える為に。伝えたい感覚を表現するためにだ。
それが、他者から見てどんなにしょうもないものだったとしても。
自分の作品を読んで、自分が過去抱いていた感覚を教わる。という体験が、自分の犯してきたことと、取返しの付かないことに対する、後悔の気持ちで一杯な心を落ち着かせてくれた。最終的には「何言ってるんだお前は」と思ったのも事実だが、自分の事でありながら、そこに置いてきた感覚を持つ話者の語りであるかのように思えたのだった。他者の感覚をたどっているかのようだった。
なんとなく、この記事を書く前に本屋に向かった。そこで久し振りに本を読もうと思ったのだった。今までは、自分には教養がないからという理由で名前だけ聞いた事のある作家の本を買っては一切本が読めないという日々を過ごしていた。正に課題をこなすために本を買い、読もうとしていた。
だから、その発想をやめて、まずは最後まで読み通す事のできる本を探そうと思った。その目的をクリアするために必要な条件を考えた結果、自分の肌にあう「文体」を持つ作品を探そうと思った。
最近、自分を詩に戻してくれた方が、夏目漱石の三四郎を紹介してくれたのだが、とても面白かった。(といってもまだ途中ではあるのだが)なんで面白かったというと、文体が面白かった。ただそれだけだった。読んでいて没入感に浸ることができた読書は、本当に久しぶりだった。細かい技術だとか、言葉の意味や比喩だとか、そういった事を一切何も考えずに読む事に没頭した読書は楽しいという事を思い出したのだ。
文体がなにを指しているのかというのは、正直今は言語化できない。ただ、文体が面白いと思う作品は、多分最後まで集中力を保って読むことができるんじゃないだろうか。人の話を長い間聞く事ができるのは、その人のしゃべりが上手いからに他ならない。話の組み立ての構造が綺麗だから聞けるという要素もあるとは思うが、自分の場合特に重視しているのは、文の息吹、つまりフローなのだと思う。相手の話の内容ではなく、いつまでも聞いていたいと思えるようなしゃべくりがあれば、多分最後まで話を聴けるのではないか。逆にいうと、何か話を聴いていてノイズが入ってしまったとたん、自分の集中力は絶対に切れる。きっとスマートフォンの誘惑に惹かれてゲームをしてしまうだろうし、読むという行為の虚無さが顔を出してきて「読むの楽しい?」とかそういった囁き声が聞こえてくるに違いない。だから、それを防ぐためには、相手の話がいつまでも聞けるような、文体でなければだめだと思った。無論自分の肌に合わない本がダメということではない。今の自分はとにかく何か一冊の本を読みたかったのだ。
大型書店に入って、さまざまなコーナーに出向いて、50冊以上最初の一ページだけ読んで、するっと2ページ目に手が動いてしまうような、そういった感覚を与えてくれる本を探した。内容やジャンルは関係なかった。事前情報を調べて他者の評判や知っている作者や名作や売れている本みたいな外部情報は一切無視した。ただ、最初の一ページが肌にあうか会わないか。という事を徹底して検証した。そして、一冊の本を買ったのだ、これが当たりだったと思う。
『文体の舵を取れ』というルグィンの本があるが、正にその通り、文体という舵に導かれながら、その本を読み進めた。それまで、短編1つ読むだけで、床を踏み鳴らし早く終わってくれと泣きながら小説を読んでいたのに、そんな自分が200ページの本をたった2時間で読み切ってしまった。
小説の話者の過ごした濃密な小説内の時間を一緒に過ごしたような感覚だった。まるで、一緒に人生を旅したような感覚だった。本屋を出てから電車にのり、自宅に帰るまでのあいだ頁を捲る手が止まることはなかった。最後の20ページに差し掛かったところで、最寄り駅についてしまったのだが、人のいなくなったホーム棒立ちし、最後まで読んでしまった。
最後の一文がとにかく強烈で、話者の激しい痛みが苦しみが決意が全身を駆け巡るようだった。誰もいないホームの真ん中で、声を上げ、天を仰いでしまった。
話者の生きた時間が、感覚が、流れてくるようだった。誰かの人生を一身に浴びたような感覚だった。この感覚を直ぐに言葉にすることはできなかった。今までは、自分の人生を重ねることで、話者の気持ちに寄り添ったり、価値判断や比較をすることで読んできた。自分の感覚と一致するか、しないかが最重要評価項目だった。しかし、本作を読んでいても自分の過去の経験みたいな物はなかった。ただ、現代に生きる話者とシンクロしたかのような、感覚だけがあった。そこに比較もくそもなかった。一緒に同じ時を生きたという結果だけが残った。
文体という息吹は、この2時間の旅に自分引きずり込んでくれたのだった。自分はいつの間にか、話者の感覚と同化していた。それが許されたのは、話者は文体を通じて必死に話者の感覚を流し込んでくれたからだと思う。だから、自分は余計な情報で話者の価値観に対して値踏みするように接
するという発想を持たなくてよかったのだ。
読むという行為に明確な目的が生まれた瞬間だった。
他者の感覚を掴みたい。
書くという行為に明確な目的が生まれた瞬間だった。
流れ込んできた他者の感覚を共有したい。
自分はしたかったのは感動の紹介ではなく、感覚の紹介だったんだよ。
あの、感覚が広がった瞬間を、一緒に共有したいだけなんだよ。
自分の感覚をつぎ込むこと。他者の感覚を受け取ること。他者の分からない感覚に触れる事。それは、輪郭を確かめるように表現と向き合う事なのではないだろうか。それを勝手に自分の感覚で判断してはいけないのだ。上塗りしてしまったら、自分の感覚が広がって行く事等ないのだから。ただ、そこ全身全霊で描かれた感覚を一心に受け止める事だけを考えればいい。それに浸ればいい。そこから、考えればいいだけなんだ。
そうして、自分の世界が、認識が、感覚が広がって行くこと。時には広げた感覚を忘れてしまう事があっても、書いて残せば、また、他人の感覚のように読み直す事が出来るんだ。
それの究極が、詩なんじゃないのか。
この文章の中には具体的な人名は出さなかった。
実際に出した結果更に傷つける事や迷惑をかけることは申し訳ないし、
この文章を読んだ際、その当事者の方だけが分かればいいと思っているからだ。
自分がいくら反省しようが、自分がしてしまったことは取り戻せない。
その人達に自分のわがままを押し付けて更に傷つける事になるのは、加害者側の一方的な都合によるものだからだ。
自分ができることは、受け取った感覚から逃げないこと。この場を通じて言語化し、共有していくことだ。それが俺のしたいことだ。ただ、全ての感覚を受け止められるほど、自分にはキャパシティーがない。だから、自分が聞きたいと思った人や・あるいは文体の感覚に対して向き合っていくを続けていくしかないと思っている。
それ以外にできることなんかない。
そういった行動の果てで、過去傷つけてしまった作品や人の感覚に近づけたと思ったときに、こうして感想として残すことができたら、多少は誠意のある謝罪みたいな形で表現することは出来るかもしれないが、しかし、そんなものは自己満足にすぎないと思っている。自分が押し付けてきた過去の罪は消えようがないのだから。だって、みんな真剣に自分が伝えたい事を作品に込めてきたんだから。そこに興味がない人が詩に嵌る訳なんて、やっぱりないと思う。多かれ少なかれ。みんな考えて書いている。考えているから口語自由詩という世界に身を投じて、戦っている。それを一度でも、自分の感覚で否定した人間が、どの口下げてもう一度関わらせてくださいと言えるのか。そんなのは傲慢だ。
詩とは何かから、なんか広いレンジの話になってしまったかもしれないが、ご容赦いただきたい。
とはいえ、ここ一か月の中で自分が目を背けてきた感覚を言語化しなければ前に進めないと思った。だから、自分の為にこれは書いた。それが、あなたにもし届いたのであれば、それ以上に嬉しい事はない。
これからが本当の百均によっての読みの始まりであり、書く事の始まりである。この一文の意味がぺらっぺらではない、その感覚が伝わる事を願う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
