
レビューと随想◆エモすぎて傷ついたほどのクラシックコンサート『いつ明けるともしれない夜また夜を』
昨年末あたりから何となく、コロナ禍に因んだ芸術作品を選んで観に行くようになった。作品を通して、あの日々とはいったい何だったのかを自分なりに考えたい、そんな時期に来たのかもしれない。その中で最もショッキングだった作品がある。今年5月13・14日、北千住にある銭湯跡を改装した地下スペースBuoyで聴いた(観た)クラシックの企画演奏会『いつ明けるともしれない夜また夜を(布施砂丘彦・作)』だ。
圧倒された。痛かった。深く癒された。そして全てがエモかった。「ヤバイ・・・これヤバイって・・・」あの日の終演後、Buoyの地下空間からひとり北千住駅に向かう帰り道、ちょっとしたショック状態に陥り「ヤバイ」というアホっぽい感嘆符だけが脳内を駆け巡った。それは「危機」と「癒し」が同時に存在するアンビバレントな感情だった。感情がいろいろどうこうなって、むしろちょっと傷ついた。
そのせいで、考えも整理できなかったので長らく余韻を弄んでいたが、先日ついにYouTubeで配信を観た。やはりこれは、もっと多くの人たちに観てほしい作品だ。
まずは公演レビュー、次に作品全体のまとめ。最後に私の体験と公演の感想を交えつつ布施さんの掲げたステートメントより「音楽と日常」の接点、そして「音楽の力」について考えてみたい。随想に次ぐ随想で、なんか全然まとまらない感じに仕上がるかもしれないが、せめて熱量だけは感じて行ってほしい・・・ということで、とりま勇気出して、いってみよう!
実はなんと、YouTubeで無料でみられるんだぜ…
そもそも何故この作品を「推す」のか。
理由は2つ。
1つ目は「これからも、まだまだ多くの人に観てもらいたいから」
是非またどこかで再演してほしい。
おそらく(然るべき時と場所がマッチすれば)普段クラシックに親和性がない人たちにも受け入れられる作品だろう。(まず、この作品での演奏家さんたちの姿が、単純に素敵すぎたのもあるが)コロナ禍の日々は人類共通の「記憶」であり、そこにジャンルを超えた「精神的な普遍性」があるからだ。特に若い人たちへ――そう言うと、ここぞとばかりに、じゃあこの機会にクラシックに親しんでとか、クラシックファンの裾野が広ればとか。ゴメンナサイ、そういう気持ちはない。申し訳ないけれど、今回に関しては、一切無い!それよりも、まず音楽で、この作品で「自分の感情と向き合う体験をして」ほしいのだ。「いろいろあったこの2年余り――あなたは、どんな思いで過ごしましたか?」
というのは、主宰の布施砂丘彦さんは1996年生まれ。東京藝大の同級生でもある大光嘉理人さんをコンサート・マスターに、今回の演奏家さん達はとにかくみな若手だ。そんな彼らが、まず同世代の人たちへこれを届けずに、どこに届けるというのか。この作品に関しては本気でそう思う。彼らの中にはもしかしたら世間の学生たちと同じように、休校やリモート授業を経験した人もいるかもしれない。仕事ができなかった人がいるかもしれない。だからこそ、普段どんなに違うフィールドで生きていても、まったく違う音楽を聴いていても、何なら音楽は好きだけどTikTokしか見ないし…みたいな人にも。同じ世代でしか感じられないものや彼らにしか見えない景色を、それぞれのやり方で何か共有してほしい、という思いがある。
とはいえ、自分のような「若くはない」人間にも琴線に触れるものがある。内容自体は、年齢の若い若くないはあまり関係なくて、その人がどう生きているか、社会の何を見ているかの問題だと思う。「けしからん!俺がルールだ!」という怒りや「何でみんな私のようにしないの?!」という満たされない期待。「ま、私はいいけど・・・」という冷笑的態度は、精神を硬直させ思考停止させてしまうものだ。しかし常に考え続けていきたいと思う人であれば、本作のエネルギーは絶対に伝わるはずだ。(というわけで、クラシックには似つかわしくない表現が散見されますが、ご容赦ください)

けっきょく、音楽には戦争を止めることなんてできない。疫病を治すこともできない。腹を膨らせることも寒さを凌がせることもできない。音楽には、わたしたちを癒してわたしたちが見たくない現実を忘れさせること以外に、なにかできることはあるのだろうか。 (公演ステートメントより抜粋)
プログラムに書かれたこのステートメント。演奏会の冒頭にも俳優のヒビノアヤコさんによって読み上げられたが、この言葉こそ作品を貫くテーマである。そしてこれが、私がこの作品を推す2つ目の理由だ。「このステートメントに対する、みんなの答えを知りたい」のだ。行き詰まりつつある世界情勢の中で、音楽の意義や役割はどこにあるのか。あるとすれば何か。どんな力を持つのか。ステートメントは命題(問い)である。それらを「音楽だけで」問う、本作はそんな企画演奏会だといえる。
ステートメントの全文は以下のリンクから!
ここからレビュー的に公演をふり返ってみる。
といっても、私には演奏技術を語れる技量もなければそんな立場でもない。そうではなく「音楽を聴いて五感で受け止めたもの」を書き記しておく。
注)そしてこのレビューは(なるべく意図とはかけ離れないように考慮はしたが)結局は私自身の聴き方・感じ方をもとにしたものであり、これが聴き方や解釈の「答え」だとか、ネタバレ的な何かだとか、そういうものでは決してない。まず感じるべきは「聴いた人自身の内面」その点は、あらかじめ強調しておきたい。(♪ ~ ♪ までレビュー部分)
本来なら読む人のことを考え、演奏曲目ごとに箇条書きし、段落分けをして見やすいレイアウトにすべきなのかもしれない。けれど1曲1曲を区切らずに一連の流れにしたほうが演奏会の空気感に近いのではと考え、読みにくいのを承知で、あえて一気に書き切ることにする。では行きますよ!
♪
五感で受け止める公演レビュー
開演前の客入れ。
地下のほの暗い会場には、すでにある音声が流れていた。コロナウィルス蔓延第1波、各地でおこった様々な「差別」のニュースだ。
医療関係者への差別。
感染者への差別。
東京から地方へやって来た人への容赦ない攻撃。
——そうだった、あの時の混乱。
いま思うとバカげた振る舞い。
でもあの時は、
誰もがみな、おかしくなっていた。
ずっと舞台袖に佇んでいたヒビノさんが中央に歩み寄った。そしてステートメントを読み上げる。続いてモーツァルトの「再び音楽を始めよ」が、もったりとした調子で始まった。折り目正しいリズムと優雅なメロディ。
——しかし。このお行儀がいい曲には、何ともいえない嘘くささが感じられる。勘違いかな?いや、水面下で「秩序を乱す異質なもの」はすでに浸食を始め、静かに増殖していたのだ。曲が終わる頃は、すっかり悪魔的な音楽に成り代わっていた。
ひたひたと、音楽が近づいてくる。ヴィヴァルディの「冬」第1楽章だ。ここで我々は「得体の知れない夜の時代」がやって来たらしいことを感じ取る。しかしそれは、ややオーバー気味に表現された演奏のように、どこかの「大袈裟な他人事」に思えるのだった。
しかし、ショスタコーヴィチの室内交響曲が始まり、会場が重々しさと狂気を孕んだ空気で満たされると、これはもう他人事ではないことが実感としてわかってくる。寒さ、凍てついた社会の怖さみたいなものが、直接的にわが身に沁みた。精神は張り詰め、かなりのストレス下に晒される。音楽で「寒い」と錯覚するのは、はじめてのことだ。このような閉じられた空間で聴くショスタコーヴィチは、体感温度までをバグらせるほどの威力があった。
ここまで厳しい音楽下に置かれ切実に温もりを求めていたものの、続いて演奏されたバッハ「わたしです、わたしこそ償うべき者です」に、そんな安易な温もりはなかった!むしろ人間の甘さ、自分のエゴを見つめさせる厳しさしかない。不安だから、怖いから、ただ自分だけは責任を免れて安息に逃げ込みたい――社会が、みんなが、だってあの人が。そうではない。まず私から、ここから始めなければ、何事も解決しない。その覚悟を感じさせる痛すぎる音楽。祈りとは、辛いものだ。
途中、ヒビノさんが、演奏者たちの周囲に敷き詰められたメトロノームを、1台また1台と動かしてゆく。演奏者もそれに続き、メトロノームを動かしては徐々にはけてゆく。コラールが終わる頃には「そして誰もいなくなった」かわりに、100台のメトロノームが一斉に、バラバラのリズムを刻んだひとかたまりの音の集合体となって、会場を覆い尽くしていた。
(そのまま休憩)
全てのメトロノームが動きをやめた時、後半が始まった。16世紀のイタリアの作曲家カルロ・ジュズアルドの歌「ああ苦しみの中で息絶えよう」空間を捻じ曲げそうなほどのメランコリックな旋律は、自己陶酔的に飛躍して、ちょっと気持ちが悪い。あらかじめプログラムで彼の経歴を読んでしまったことも悪かったのか。この人あきらかに異常者なんだけど・・・
この曲は、悲しくも自分の考え方からどうしても外に出られない人の(それを現代では「共感性の欠如」とでもいうのだろう)いびつな愛のかたち。孤独な人間の嘆きの歌なのだ。
突如として時代が翻る。
抽象的な現代音楽がエアポケットのように挟み込まれた。
「アルファ」
「ベータ」
「ラムダ」
「オミクロン」
covid-19の変異株の名称と偶然に一致した楽曲名。何かの洒落なのか。しかし、なにぶん私は現代音楽には疎い。ならばと思い、各楽曲から想起される「形状」の違いを感じてみることにした(変異株だけに?)
自分は音に「カタチ」を感じやすいタイプなのだが、人はそれぞれみんな違うわけで、そこは聴く人の数だけ「最適解」があるのだろう。
そしてなんと、再びヴィヴァルディ「冬」より第1楽章 に帰還するという、旅のようなカタルシス。
でも、なんか違う・・・?
途中で気づいた。
ヴィヴァルディの冬に似ているが別の曲だ。(実は「25%のヴィヴァルディ Recomposed By マックス・リヒター」の「冬」だ)ということは、これは帰還ではなく前進だろう。
「冬」だけど、あの「冬」じゃない。
似ているけれど、すでに別の冬。
同じ日は2度と来ない。
同じ冬も2度とない。
時間は着実に前へ進んでいるのだ。
そして「弦楽のためのアダージョ」が、柔らかく会場を包み始めた。プログラムの終曲に来て、私はようやく薄い暖色の音を聴いた。
どこか遠くの、微かなぬくもりの予感。
けれど、どこで始まったのかもわからないほどの弱い兆候。いまだ「気配」でしかない。しかし確実に感じた、空気の緩み。
夜明けって、こんな感じだ。
早春の雪解けって、こんな感じだ。
豪雪だった郷里の春を思い出して、懐かしさが蘇る。この1時間ちょっと、実は感覚が麻痺するほど、自分も会場の空気も張り詰めていたのだ。
図らずも泣きそうになった。
人は渦中よりも安堵した時、心折れるものだ。
アンコール曲として演奏された
エドゥアルド・グリーグの「遅すぎた春」
が、少しずつ会場の空気を温かくさせてくれた。
もう少し、余韻を楽しんでもいいらしい。
グリーグの調べに、念を押された。
それでも希望を持つようにと、励まされた。
待ち望んでいた夜明けへの想いに、あまりにもマッチしたタイトル。ほんと布施さんの選曲って粋だな・・・などと一生懸命に気を逸らしていたが(私は意外と素直じゃない)結局ここで涙腺が崩壊することに。慌てて暗い会場を見やると、やはりそっとハンカチで顔を覆っている人が何人もいた。
この2年間あまりずっと堪えていた気持ち。
それを秘密の空間でそっと打ち明けたような、
会場はそんな暖かい「共振」で満たされていた。
この作品に見た景色は、ひとりひとり全く違うだろう。けれど布施さんが、最後に「置きにいった小さな希望」を、きっと会場の誰もが、確かに受け取ったに違いない。

いつ明けるともしれない夜また夜を、超えて。
もしかしたら今日、今日が夜の底かと、
そうだったらいいなと、祈る。
明日こそ平穏がやってきますように。
明日こそ・・・明日こそ・・・と思いながら、
今はそうして生きるしかない。
♪
作品全体の「まとめ」
レビューを読んでおわかりの通り、本作は、指揮者や主催者がキュレーション的にセレクトした楽曲を順に演奏していく企画演奏会ではない。時代背景や作曲家、もしくは休憩時間などの時間配分、ソロ音楽家のための見せ場などの「諸事情により決まったプログラム編成」ではない。この順番で並べられた楽曲には、それなりに決まった意味や役割がある。各楽曲はある意図をもったストーリーの一部となり、見事につながっているのだ。これは音楽だけで紡がれた物語、映画のようだ。本作の場合はどちらかというと、社会派のドキュメンタリー作品に近いかもしれないが。
とにかく、音楽によるエモーショナルな流れの作り方がうまい。音楽だけで紡がれた(演劇的要素は最小限で)作品なのに、私たちの感情を「ある到達点」まで、迷わせずに連れて行ってくれる。きっと布施さんは、その音楽にはどんな感情が想起されがちで、どんなトーンや質感・温度感を持ち、どんな背景で作曲されて、何故このタイトルなのかというところまで、ものすごく熟知しているのだろう。さきほどの私のレビューは、感情の流れを際立たせるため「ちょっとボリューム大きめ」で書いてみたが、実際にはもっと繊細かつ微細なニュアンスで心が震えるはずだ。
こういう作品の場合、演奏の順序やトーンの統一感って本当に重要だ。作曲者の時代とかジャンルなどに関係なくランダムに並んでいるように見えるが、聴いてみると「必要な場所に置かれている」のがわかる。布施さんは普段、「古楽(作曲当時の楽器や奏法で演奏する)」普及のための演奏会活動もしている。今回プログラムされた楽曲の中にも、16世紀や17世紀に作曲された「古い楽器で演奏した方が味がある曲」が何曲かあった。けれど本作では、それらの古い音楽たちも現代音楽と同等に肩を並べ「いま、ここの音」として誇らしげに響いていた。
演出面では、客入れで流したコロナ差別のエピソード紹介が、この作品の前提として提示されたことで、より聴衆にステートメントを強く意識させた。それは楽曲に対する先入観(クラシックに詳しければ詳しいほど、その曲にまつわる周辺情報が頭に入っているのは致し方ないのだが)によるミスリードを防ぐ役割を果たす。また演奏会の前半部分には、進行役として演劇的要素が入ったが、これも作品への心理的導入に一役買っていた。

音楽と日常性と、その力について
~没入するか拡張するか~
ここで、最初のステートメントをふり返る。
けっきょく、音楽には戦争を止めることなんてできない。疫病を治すこともできない。腹を膨らせることも寒さを凌がせることもできない。音楽には、わたしたちを癒してわたしたちが見たくない現実を忘れさせること以外に、なにかできることはあるのだろうか。 (公演ステートメントより抜粋)
音楽には、聴いただけで実際に経験したかのような感情を作り出す作用を持っている。布施さん自身も、ステートメントの他の部分でショスタコーヴィチやベートーベンを例にとっている。
本作の中で、自分にとってかなり「痛かった」楽曲がある。前半最後、バッハの「わたしです、わたしこそ償うべき者です」だ。それは「私のコロナ体験の象徴」ともいうべきある記憶を強く呼び起こし、心をえぐった。それでいて、実は自分が直接経験した出来事ではない。どういうことかというと、私はコロナ禍で2回だけ「誰かも知らない他人のために泣いた」その時の痛みが、一気に呼び起こされたのだ。
最初の緊急事態宣言真っ只中だった。
道に、街に、人が消えた。
「とにかく外に出ないで」
「人と離れて」
「人と話さないで」
「買い物は最低限にしてひとりで」
こんなことを言われる日が来るなんて、信じられなかった。玄関を一歩外に出たら最後、全ての場所が危険地帯だという「逃げ場のない恐怖」を、生まれて初めて味わった。郷里の名士が遺した言葉に「常在戦場」というのがあるが、それのもっとタチの悪いやつになったと、苦々しく思った。私は気管支が弱い。感染が怖すぎて、どうかなりそうだった。うつされたくない。その一心だった。しかし逆をいえば、相手にだって私の存在は「人」というよりただの「脅威」でしかないのだろうと想像するのはたやすく、それも切なかった。さして混みあってもいない道をすれ違うだけで、互いが一瞬で警戒する気配を感じる。そして避け合うようにして歩く。
その日は家族が買い物に出かけ、私は家で待機していた。しばらくして帰っては来たが、店の殺伐とした雰囲気にすっかり気疲れしたようだった。
「道はどんなかんじ?」私が聞くと、
「いや全然。誰も歩いてないし」
しかし、思い出したようにこう続けたのだ。
「そういえば1人だけ、おばあちゃん歩いてたな。ほらそこの、国道の、上り坂を、買い物袋とトイレットペーパー持って絶望的な足取りで。なんか十字架でも背負わされたみたいにさ」
もうだめだ、
こんなこと聞いたが最後。
その人は一瞬で、
私の中で「生き」始めた。
戦場や震災の写真を見て「あの人は今頃・・・」と想像し、苦しくて眠れなくなるという心境に初めてなった。どうして普通のおばあちゃんが、絶望した足取りになるほど、辛い思いをしなくてはけない。だってこの人、何もしてないじゃない?
私だ
私こそがこの人に
重荷を背負わせている
まるで自分の罪のように真正面から受け止めてしまった。可哀そうだという気持ちはあった。けれどそれだけじゃなかった。今思えば、私が苦しくなったのは、私に道徳心があるからとか、いい人だからということでない。自分の中の「公共心」が痛んだのだ。元公務員魂がこんなところで発動してしまった。社会は外側にあるのではない。私もその構成員なのだ。おばあちゃんの絶望は、私にも関係がある。自分の「せい」ではないが「責任」はあるのだ。それを受け入れなければと。
そしてその日から、どうやっても「想像上のおばあちゃん」が脳裏から消えなくなった。発作的に思い出し、そのたびに涙が出た。(いま考えると、ちょっとメンタルおかしかった)だから私は、この演奏会を、あのおばあちゃんと一緒に聴いた。自分だけが救われて、自分だけが楽になって、それで済むのか。私だけが逃げたところで解決しないのが、この社会というものだ。
2度目は、純粋に腹が立ちすぎて泣いた。
はじめてのワクチン接種が始まった夏のことだ。接種の優先度が低い若者たちのために、渋谷に予約なしの接種会場ができたというニュースを見た。(予想に反して?)多くの若者が列をつくった。炎天下の中、できるかどうかの確約もないなかで列に並ばされる若者たち。案の定すぐに定員に達した。それでも接種できなかった者は、何も言わず、おとなしく三々五々散っていった。テレビの取材が1人の男の子にマイクを向ける。「打てるかなと思ったんですけど・・・仕方ないので今日は帰ります」
それから少しして、何気なくツイッターのタイムラインを追っていた時だ。(おそらく年配の)あるツイートが目に入った。めちゃくちゃ怒りが湧いた。こういう感じの内容だった。
若いやつらが集まるだけならまだしも、渋谷まで来て接種できなかったからといって、まさか腹いせに遊んで帰るつもりじゃないだろうな――
ものすごくムカついた。自分の中で、近年稀にみるほど腹が立った。もう頭に来すぎて偏頭痛が始まりそうだった。そして怒り過ぎて涙が出た。私はたまらなくなり、ついエアリプしてしまった。
「わざわざ渋谷に来て並んで、抽選に外れて大人しく帰ってくれるならまだしも、じゃあ遊んで帰ろうなんてことはしないよな?」
— 越水玲衣 (@migeneco_1756) August 28, 2021
てなツイート見かけて、その発想に泣きそうになった。
まだしも、だと?!
RT そうなんだよ。ニュースのさ、断られて帰る子たちの顔見た?
— 越水玲衣 (@migeneco_1756) August 27, 2021
Apple Storeの前で好きで並んだんじゃないんだよ。健康と安全のために並んだんだよ。絶望を我慢して、諦めて帰る彼らの様子を見て、なんか胸が張り裂けそうだった。
自分だけの発想で世の中を見ることが、どんなに気持ち悪いことか。ツイートした人は、おそらくこれ以上の感染(特に自分)を避けたい気持ちだったのだろう。けれどこの「正義」がすごく残酷なものに思えた。どんなに偉くても、どんなに「稼げて」いても、どんなにインテリでも、こういう人にはなりたくない。それからというもの(職場に若い人たちがたくさんいることもあり)若い人たちのこれから生きる世界が、いいものでありますようにと、案じることが多くなった。だからこそ本作を、もっとたくさんの人に(とくに若い人に)何としてでも観てもらいたいと思うのだ。
自分にとって本作は、ここ2年ほどの生々しい現実そのものだった。恐怖、寒さ、人への恐れ、怒り、悲しみ。そんな「リアルガチ」な現実。音楽はそれを生々しく追体験させ、再構成してくれ、そして癒してくれた。そう、音楽にはつらい現実から逃げ込むだけ、没入するだけの”VR(仮想現実)的”な「非日常体験」だけではない、もう1つの大きな力があるではないか。
宗教曲、レクイエム、失恋した時に聴きたいランキングに入る系の歌。音楽には、あえて現実を見つめさせる力がある。このところ私は、音楽のこういった側面に注目している。音楽から得られる癒しというか「現実を適切に葬る力」とでもいうべきか。私はあの日、音楽を聴いてショックを受けた。けれどショック療法みたいなもので、持て余していた2年余りのモヤモヤを刷新してくれた。音楽で「喪の仕事」をする。こういう時、音楽は”AR(拡張現実)”的になる。日常の延長上の「現実」になる。
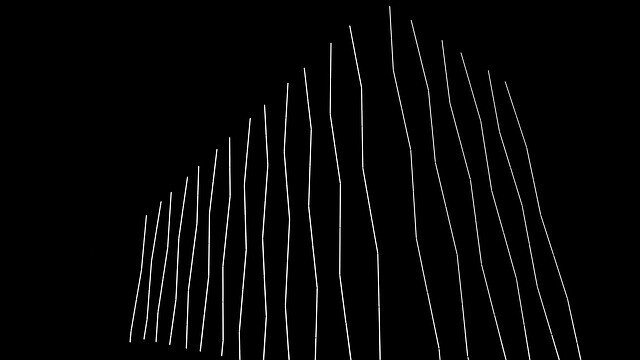
音楽をダークフォースに使わないために
最後に、このステートメントの抜粋を。
音楽は戦争を止められなくても、病気を治せなくても、せめて、わたしやあなたが誰かを傷付けないようにすることくらいできるのではないか。わたしたちは誰でも簡単に加害者になりうる。音楽はそれをわたしたちに教えてくれるのではないか。
わたしは、音楽が持つ、そんなちっぽけな可能性を信じたい。
人間関係でのコミュニケーションと同じように、音楽にも加害に相当するチカラがある。誰かを洗脳、社会を扇動、自分を悪い方向に鼓舞。これは音楽のダークサイド、ダークフォースである。
しかし音楽には、一度は負の感情に突き落とすものの、その後強い癒しを起こす場合もあるし、深い感動によって生まれ変わったような作用を及ぼす時もある。重い気持ちを軽くするためのスポンジ役になってくれたり、もう会えない人に会ったような気持ちにさせたり、行ってもいない宇宙のハム音を聴いたような神秘的な気分に襲われフリーズさせたり。仕事場での単純作業で、作業が身軽になるよう身体のリズムを整えてくれたりする。(これは某アスリートの方から直接私が「教わった」音楽の使い方だ)
音楽が何かの機能を及ぼすなんて芸術じゃない――そう思う方もいるかもしれない。芸術は役に立たないもの。立たせてはいけないもの。そこに存在するだけで、置いておくだけで完結するもの。自分も前はそう思っていた。モーツァルトが胎教にいいとか、α派を出すから聴きましょうとか。それってなんか「使われてる」ようで嫌だなと思っていた。しかし音——音楽といえど、結局はこの世に存在する事象の1つである以上、何らかの「働き」はするものではないのか。そしてそう考えたほうがnatural、自然ではないのか。最近はそう考えるようになった。ダークフォースとして使わなければ、音楽は最高の伴侶である。
そして願わくば、こんなふうにライトフォース的な加害——「エモすぎて傷つく」ほどのダメージを負うインパクトある音楽や作品に、今後も出会っていきたいなあと、変態マニアック人間である自分は常々思っている。
~演奏曲目~
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
「再び音楽を始めよ」
アントニオ・ヴィヴァルディ
「冬」より第1楽章
ショスタコーヴィチ=バルシャイ
「室内交響曲」
ヨハン・セバスティアン・バッハ
「わたしです、わたしこそ償うべき者です」
リゲティ・ジョルジュ
「100台のメトロノームのためのポエム・サンフォニック」
カルロ・ジェズアルド
「ああ苦しみの中で息絶えよう」
ブライアン・ファーニホウ
ソナタより「アルファ」「ベータ」「ラムダ」「オミクロン」
ラ・モンテ・ヤング
「コンポジション1960より第13番」
オスカル・リンドベイ
「弦楽のためのアダージョ」
(アンコール)
エドゥアルド・グリーグ
「遅すぎた春」
越水玲衣/Koshimizu Rei
書く人 兼 勤め人
エッセイ|コラム|小説|脚本|批評
16歳で県の高校生小説賞、集英社『ロードショー』シネマエッセイ受賞。以来主宰していた演劇ユニットや市民劇の脚本、エッセイ寄稿など「好きな世界を文章で表現する」活動をしている。自分の中ではブレない活動をしているつもりだが、それでも「やっぱり何者なのかよくわからないし、次に何をするかもわからない人」と思われている。元市役所職員。現在大学職員。哲学卒。バレエ経験有11年。モーツァルトと芸術語り、夜の灯りが好き。
募集)今後もたくさん「劇評」「ダンス評」「演劇的作品評」を書きたいです。☆☆☆☆☆ 思いのたけを綴ります!
毎日の労働から早く解放されて専業ライターでやっていけますように、是非サポートをお願いします。
