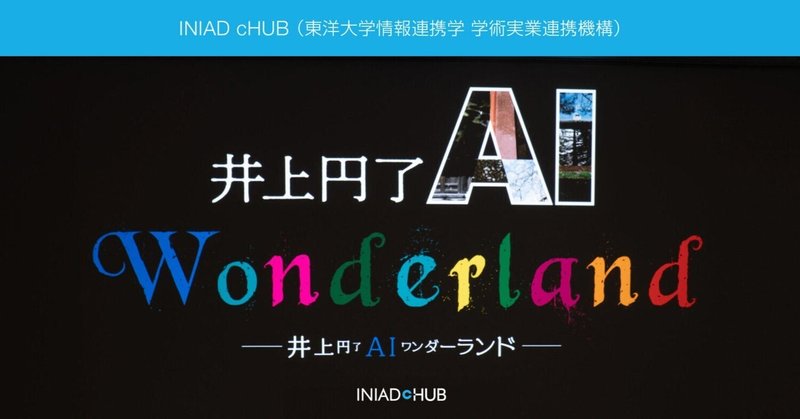
東洋大学「井上円了AIワンダーランド」から考える、大学発わからない人に寄り添うイベントの重要性
大学が発信する情報を見ていると、いろいろな大学が社会に向けて魅力的なイベントや講座を開催していることに気づきます。今回、取り上げるのも、そんな大学の社会に向けたイベントの一つ。近年話題のAIを使った、だいぶぶっとんだ取り組みなのですが、こういうものこそ大学がやるべき取り組みなのだと強く感じます。
創立者✕AIという、これまでにないユニークなイベント
取り上げるのは、東洋大学による「井上円了AIワンダーランド」。東洋大学は、全国に先駆けて大学案内を廃止し、オンラインに特化した入試広報を展開するなど、かねてより挑戦的にデジタルを活用している大学です。そういった大学なので、今回のイベントも東洋大学らしいなあと感じました。
イベントタイトルにある「井上円了」ですが、この方は東洋大学の創立者であり、幕末から明治にかけて活躍した哲学者です。AIを使って何かをやろうとしたときに、創立者を掛け合わせようという発想が出ること自体、だいぶとフリーダムです。また、この企画が学内でちゃんと通ることに、井上円了が東洋大学で愛されていることを感じました。なんというか、単に尊敬されているのではなく“愛されている”と思うんですよね、こういうのができるのって。
ではこの魅惑的なタイトルがつけられたイベントですが、何をするのでしょうか。いくつか抜粋すると、井上円了のAIがモデレーターになり、哲学の偉人たちのAIが討論する「井上円了×AI×四聖討論」。「妖怪学」の創始者とも呼ばれる井上円了がまとめた妖怪に関する記述をAIで動画化する「井上円了×AI×妖怪動画」などが挙げられます。詳しくは、下記特設サイトにまとめられているので、ぜひこちらをご覧ください。
大学は、よくわからない世界に触れる最適の場
特設サイトの説明文を読んでいただくと感じてもらえると思うのですが、どんなことが展開されるのか、ほとんどイメージがつかないんです。文章としての意味はわかる、でもよくわからない…って感じです。これって、説明文が悪いわけでも、企画内容がおかしいわけでもなく(いい意味で変ではありますが…)、AIというものが、私たちの理解の範疇にまだうまく収まりきっていないからなのだと思います。
今回のAIは最たるものの一つだと思うのですが、技術発展や社会の変化が急激に起きているいま、理解の範疇にうまく収まらないものというのは、さらに出てくるように思います。これら理解が及ばないものって、興味深い反面、基準がないため、どう判断していいかわからないんですよね。もっとネガティブに捉えるなら、わからないことに漬け込まれてだまされたり、恣意的なイメージを植え付けられたりする可能性だってあるわけです。
こういったよくわからない世界にまず触れる場として、大学はすごく理想的だと思います。というのも、大学の社会向けの取り組みは公共性が高く、何かしら自大学の利益につなげようという腹積もりがあっての活動は、ほとんどありません。時たま有料講座のプロモーションとして無料講座を開催することもありますが、その場合はちゃんと明記されています。なんとなくメアドを書いたら、あとからしつこくセールスメールが送られてきた…なんてことは、まず起きないでしょう。
さらに大学教員は、その分野の専門家として、社会的に保証されている人たちです。それゆえに信頼がおけるし、取り組みがその分野の先端を踏まえた内容になっている可能性も、とても高いわけです。
消極的で曖昧な動機をもつ人たちの受け皿として
AIは今後さらに進化のスピードを早めるでしょうし、それに引っ張られるように新たな技術や、思いもしなかった課題などが出てくることは想像に難くありません。こういった状況になると、興味があるから学ぶ、ではなく、知っておいた方が良さそうだから、とか、わからないから、といった、もっと消極的で曖昧な動機で知ろうと動く人が増えてくるはずです。
知識が乏しくて不安がっている人なんて、言い方は悪いですが、いいカモなわけです。こういった人たちをターゲットにしたイベントやコンテンツというのは、これからもっと増えていくでしょう。そういったなかで存在感を発揮すべきは大学だと強く思います。社会的に信頼されており、リソースがあり、ビジネス的な腹心もない、どう考えても適役だからです。
そのように考えていくと、今回の東洋大学のキャッチーな切り口で間口を広げ、多くの人に未知なる世界を伝えるというイベントスタイルは、まさにこれからの大学がやるべきイベントの一つの型なのではないかと感じました。イベントタイトルに惹かれて読んだプレスリリースだったのですが、いやはや奥が深いイベントですよ、これは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
