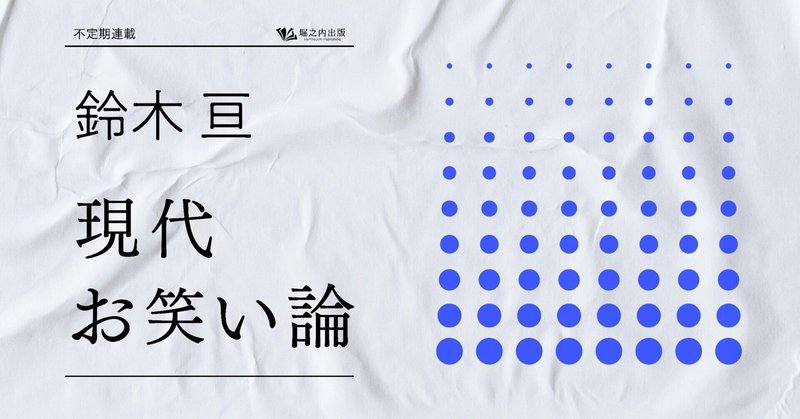
【現代お笑い論】#004 爆笑問題 太田光に見る「冗長」の美学 鈴木亘
※こちらのnoteは鈴木亘さんの不定期連載「現代お笑い論」の第四回です。他の記事はこちらから。
爆笑問題 太田光に見る「冗長」の美学
爆笑問題と神田伯山の冠番組である「爆問×伯山の刺さルール!」が9月で終了するのが悲しい。前身の「爆笑問題&霜降り明星のシンパイ賞!!」と「太田伯山」(→「太田伯山ウイカのはなつまみ」)から毎週楽しみに見ていたが、幾度ものリニューアルを経て終わってしまった。
番組はひとつ終わるとはいえ、爆笑問題の存在感はむしろ、ここ数年で間違いなく高まっている。多くの後輩芸人がファンを公言するようになったし、雑誌やイベントの特集もどんどん出てくる。それは爆笑問題世代とも言うべき私たち(筆者は91年生まれである)が大人になったこととも無関係ではないだろう。
例えば「シンパイ賞」で共演した霜降り明星や、爆笑問題への憧れを公言する空気階段の水川かたまりは私と同世代、少し上では空気階段の鈴木もぐらやハライチ岩井らが影響を語っている。私はと言えば、小学校で「爆チュー問題」に出会い、中学校では「爆笑問題のバク天!」で笑い、高校では「爆笑問題の検索ちゃん」を見ていた。「爆笑問題カーボーイ」は今でも続いている。テレビ・ラジオだけではない。『日本原論』をはじめとする漫才本やエッセイから、様々なことを学んだ。佐野元春や立川談志や黒澤明を教えてくれたのも爆笑問題だったと思う。私(たち)の成長は太田光と田中裕二とともにあった。
他方、現在の日本のお笑いは松本人志のパラダイムにあるとよく言われる。それについての詳細な検討は措くとして、今のお笑いに支配的な二つの傾向の中心に松本がいることは事実と言ってよいだろう。すなわち、短時間での効率的な笑いの獲得と、なるべく新たなシステムの発明が要求される賞レースの隆盛(「M-1グランプリ」審査員)、そして、お題に即座にボケをぶつける瞬発力と、なるべくひねったコメントをする発想力が要求される大喜利の流行(「IPPONグランプリ」大会チェアマン)である。
事実、お笑いにおける「新しいもの至上主義」については連載第一回で触れたとおりだし、月曜から金曜の朝2時間を、川島明(麒麟)を中心とする芸人による大喜利的な〈ワードセンスの笑い〉が実質的なコアをなす、生放送情報番組「ラヴィット!」が占めているのだ。
それを横目に見ながら、ここでは爆笑問題について語りたい。理由は二つある。
第一に、爆笑問題の芸を考えることで、メインストリームとは一歩離れたところから、現代のお笑いシーンを相対化する可能性を見出せるからだ。
第二に、私たちの日常を見つめ直すきっかけになるからだ。友人の笑い話に対して、「◯◯の部分はいらなかったな」「前にも聞いた話だけど少し変わっているな」などと感じたことはないだろうか。私たちがふだん何で笑うか、何を面白いと思うかは、テレビやラジオから流れるお笑いに深く影響されている。本記事では、世間のお笑いの基準点とオルタナティブを共に捉えることで、私たちの日常的なコミュニケーションに新たな光を当てる可能性も探りたい。
論点はいろいろあるのだが、今回は爆笑問題の、というよりとりわけ太田光の話芸にテーマを限定して論じたい。
***
太田光の話芸:長さ
太田のイメージを語る語彙として、「はちゃめちゃ」「破壊的」というものがある。番組進行などお構いなしに喋り続ける、スタジオを所狭しと暴れ回る、アナーキーでベタでナンセンスなギャグを連発する......。実際、舞台やテレビでこのような光景にしばしば遭遇するのだから、そのイメージはたしかに正しい。だが彼の話芸に着目したとき、見えてくるのは「はちゃめちゃ」とは別の、対極とも言える特徴である。以下ではそれを二つ指摘したい。
第一の特徴は語りの長さである。爆笑問題の出演番組では随所で太田の長尺トークを聞くことができる。オープニングに毎回40分ほどのフリートークがある「カーボーイ」だけでなく、テレビ番組のふとした機会にもその話芸は披露される(カットされることもあるが)。近年ではYoutubeもそうだ。話芸といっても、例えば『男はつらいよ』で車寅次郎がよくやる売り口上のような、切れのいい啖呵、流暢な語り口というわけではない。むしろどちらかと言えばレトリカルではない、フレーズごとに区切りのある、一言一言を確かめるような語り方である。「要するにさ」とか「言ってみりゃ」といったつなぎ言葉も多用する。また、例えば「すべらない話」に典型的なように、クライマックス(オチで爆笑)に向けて全体が構築されたエピソードトークというわけでもない。クライマックスの笑いにどれだけ寄与するか、という観点から見れば無駄に思われる部分も多く、しばしば脱線もする。太田のトークが長いと言われる理由の多くはそこにあるのだろう。最短距離で効果的に笑いを目指すという価値観、笑いに対する効率主義とは対照的だ。それを思い切って、「冗長」という言葉で形容してみよう。
太田光の話芸:長さ─冗長
「冗長」といっても太田の芸を腐したいわけではなく、むしろポジティブに語ってみたいのだ。ではその芸の本分はどこにあるのか。それは一言でいえば、描写の芸である。太田のトークは身辺雑記から社会的トピックに対する意見表明まで多岐にわたるが、中でも特徴的なのが「描写」なのだ。すなわち、経験した出来事や観たもの・読んだものの内容を、あたかもリアルタイムで居合わせているかのように語るのである。
例えば「カーボーイ」ではかつて『金閣寺』や『エデンの東』を冒頭から結末まで語り切っていた。最近印象深かったのは、昨年8月に放送されたNHK「最後の授業」での柄本明の講義を語る回(2022年8月30日。笑いを交えつつ講義の緊張感そのものがピリピリと伝わってくる)、Dos MonosのTaiTanとの対談に触発されて、『ガープの世界』を全編語る回だ(2022年10月18日。ちょうど統一教会への見解をめぐる「炎上」のさなかで、作品を通じて大衆について考えている)。
これらは単に、作品や出来事を一言一句反復しただけのものではない。太田は描写しながら要所要所で解釈を加え、自らの思想を開陳する。というよりもその描写そのものが、彼の思想によって編集され解釈されたものなのだ。それでも、そのような作品の再構成は、あたかもそれ自体がひとつの作品のような面白さを有している。もちろん語る内容のみならず「語り口」の部分、声のトーンやテンポ、間、あるいはそれらの言葉に収まりきらない全体的な雰囲気──「フラ」とか「ニン」とか言ってもいい──もまた、そこに寄与していることは言うまでもない。
そしてこの面白さをすでに的確に言い当てているのが、講談師の神田伯山である。彼は太田の再現的な語りおろしを、マルセ太郎の「スクリーンのない映画館」になぞらえている(「問わず語りの神田伯山」2020年7月17日放送。他でも言っていたはずだ)。2001年に亡くなったマルセ太郎を知る人は現代であまり多くないかもしれないが、パントマイムや形態模写を得意とする芸人だ。「スクリーンのない映画館」とは、一本の映画の全編を漫談形式で語る舞台芸である。あらすじや解釈を説明しながら、重要なシーンは身振りやセリフで再現し、舞台装置も小道具もなくたった一人で映画を描写しきるのだ──伯山の本業ゆえに講談になぞらえることまではしないものの、いずれにせよその意味で太田の描写は話芸の伝統に通じている。
さらに言えば、このような再現描写がひとつの芸たりうることは、西洋の芸術理論からも傍証を取ってくることができる。すなわち芸術作品(とくに視覚芸術)を、言葉によって、それがあたかも目の前にそれがあるかのように描写する技法には、古代以来「エクフラシス」という名前が与えられているのである。[1]
太田光の話芸:繰り返し─冗長
第二の特徴は繰り返しである。「冗長」という語のもうひとつの意味だ。太田は同じ話を何度もする。「カーボーイ」で聞いた話を「太田上田」でも聞く、というケースは数多い。同時期に収録した色々な媒体で同じ話をするというのは芸人一般によくあることではあるが、太田の特徴は同じトークを何年にもわたって繰り返すところにある。今でもネタ番組やライブのたびに新ネタを作り続けているのとは対称的だ。
ちょうど先日、佐久間宣行のYoutubeチャンネルに爆笑問題がゲスト出演していた(前編、後編)。そこで披露された立川談志・ビートたけしとのエピソードも、明石家さんまとのエピソードも、耳にしたことのあるおなじみの話である。それでもやはり、そのトークには引き込まれる。もちろん先に触れた描写の迫真性のためでもある。だがここで、もうひとつのファクターを付け加えてみたい。
太田光の話芸:対話
それは、たとえ同じ話でも、太田は常に目の前の相手と対話している、という点だ。彼は同じ話をただ機械的に反復しているのでは決してない。むしろ相手に語りかけ、その反応を承けて次の話を重ねる、というしかたで、すでに語ったことのある内容でも新鮮に生成変化してゆく。その時・そこで・その人としかできない対話を創造しているのだ。演説的ではない地に足ついた語りも、対話者のレスポンスを前提とするからであり(その意味で、大学時代からの対話者である田中の存在は常に重要である)、先に触れた確かめるような語り口も、いまこのことをどうしても語りたい、どうしても聞いてもらいたいという懸命さの表れであり、相手への敬意と誠実さの証である。
もちろんこれはモラルやマナーの議論にとどまるものではない。重要なのは芸の部分である。同じ話をそのつど変えて話すこと。そこに太田の卓越があると指摘していたのは、伊集院光である。「カーボーイ」のライブ特番(2023年2月7日。「カーボーイ」と「伊集院光 深夜の馬鹿力」の放送枠であるTBSラジオ「JUNK」の20周年イベント)にゲスト出演した伊集院は、〈同じ出来事でもそのつど角度を変えて語ることのできる人〉として、太田を称賛していた。つまり、すでに何度も話している物事でも、相手や尺、文脈に合わせ、あたかもカメラを自在に動かすかのように、強調したい部分や膨らませたいポイントを変えて話すことができるというのだ。いわばひとつの出来事を繰り返し同じように語るのではなく、立体的に語ることができるという評である。そして付け加えておけば、この評はかつてノーベル賞作家の大江健三郎が伊集院光その人に与えたものでもある[2]──知られるように、大江の執筆スタイルは、一度書き上げたものを徹底的に推敲するというものだった。また同じテーマを別の小説で何度も取り上げたり、発表した作品を自ら再解釈し、それを新たな作品として反復することもたびたびあった。その意味で大江もまた、書き直しと繰り返しという「冗長」の思想の実践者である。太田の芸はかくのごとく、伊集院を通して大江の物語的想像力の世界にまで通じているのだ。
***
以上のように太田の「冗長な」話芸は、じっくりとした描写と立体的な語りとにおいて、マルセ太郎・大江健三郎という物語をめぐる二つの伝統に触れている。太田の系譜としては立川談志・ビートたけしのラインがよく知られている(過去を継承しつつ知性と批評眼をもって現在と切り結ぶ東京芸人としてのラインになるだろう)が、本記事で試みたのはそれとは別の系譜を取り出すことである。[3]
そしてこの系譜はまた、現在の日本お笑い界を支配する──松本人志的な、と言っていいのだろうか?──新たな笑いのシステムを発明し続けなければならないというオブセッション、そして発想力やワードセンスといった瞬発性を競うかのような評価語の流行に対する、ひそやかなアンチテーゼとして機能し続けているように思われる。
[1]余談になるが、この芸を若手で継承しうるのは、過去の記憶を再現する能力を持ち、また古今の芸能への愛情を隠さない、「シンパイ賞」で爆笑問題と共演した霜降り明星のせいやではないか。
[2]https://plaza.rakuten.co.jp/norimasa1718/diary/200803030002/
[3]なお上で紹介したYouTube動画には、太田のトークを落語など伝統芸能になぞらえるコメントがいくつも投稿されている。太田の語りは落語だ、とイコールで結びつけるのは拙速な単純化であるけれども、少なくとも長尺のトークをじっくりと聞かせ、同じ話を繰り返し練り上げる、という点に関して言えば、太田の話芸を落語的と形容することは正しい。そのようになぞらえる時、コメント主たちはおそらく、太田の話芸がテレビ的な瞬発力の笑いに対するオルタナティブを提供していることに気づいているのだ。

著者プロフィール
1991年生まれ。現在、東京大学大学総合教育研究センター特任助教。専門は美学。主な論文に、「ランシエールの政治的テクスト読解の諸相──フロベール論に基づいて」(『表象』第15号、2021年)、「ランシエール美学におけるマラルメの地位変化──『マラルメ』から『アイステーシス』まで 」(『美学』第256号、2020年)。他に、「おしゃべりな小三治──柳家の美学について 」(『ユリイカ』2022年1月号、特集:柳家小三治)など。訳書に、ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『受肉した絵画』(水声社、2021年、共訳)など。
Twitter:@s_waterloo
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
