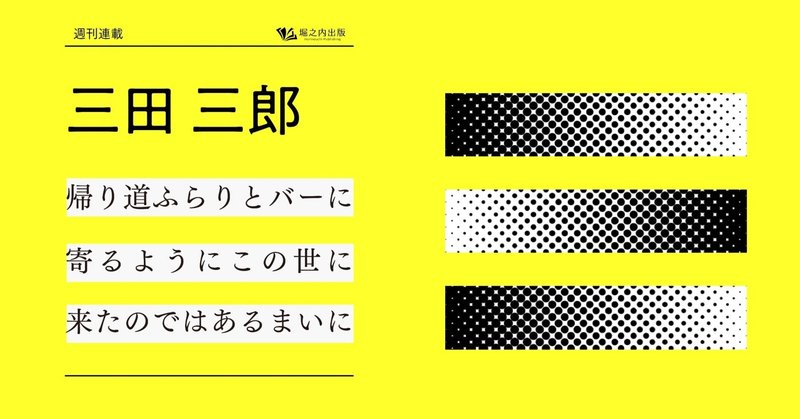
【三田三郎連載】#001:泥酔の経験は人間を謙虚にする
※こちらのnoteは三田三郎さんの週刊連載「帰り道ふらりとバーに寄るようにこの世に来たのではあるまいに」の第一回です。
他の記事はこちらから。
泥酔の経験は人間を謙虚にする
今の時代、酒を飲み過ぎて泥酔しようものなら、「だらしない」「社会人失格だ」「自己管理がなっていない」「人間として本来備えるべき理性が欠如している」などといった印象を周囲に与え、場合によっては厳しい非難を受けることも覚悟しなければならない。コンプライアンスが声高に叫ばれるこの現代日本社会にあって、泥酔することはもはや倫理的に問題のある振る舞いと看做されかねないのである。
しかしながら私は、この時勢に抗して、泥酔には人間を倫理的に望ましい方向へと導くような効用もあるという説を唱えたい。その効用とは、「泥酔の経験は人間を謙虚にする」というものである。こんな風に書くと、「いい加減なことを言うな、人間は酔っ払うとみな気が大きくなるではないか」というお叱りの声が聞こえてきそうである。確かに、誰しも酔っ払っている最中は気が大きくなり、謙虚とは縁遠い状態になっていることだろう。だが、私が言わんとしているのは、「泥酔を経験した人間は、平常時にはかえって謙虚になる」ということである。一見すると逆説的にも思えるこの命題について、私の個人的な経験も交えながら説明していきたい。
まず、泥酔が人間を謙虚にする第一の理由として、「内なる他者の存在に気付くことができるから」というものが挙げられる。
人間は泥酔すると、素面のときには考えられないような奇行に及ぶことが多々ある。同席者に後日その事実を指摘されるものの、自分では全く覚えていないといったことは、酒飲みであれば日常茶飯事だろう。
例えば私は、泥酔すると急に誰彼構わず土下座をすることがあるらしい。何か粗相をして、それに対して謝っているわけではない。何の脈絡もなく、突如として捨て身の先制攻撃でも仕掛けるかのように土下座を始めるのである。もちろん、私はそれについて全く記憶がなく、よく一緒に飲む友人に指摘されて初めて知ったことである(なぜそんな奇行に走るのかについては、一応は思い当たるふしがあって、私は過去に仕事上で土下座を強いられたことがあり、その屈辱が素面の状態では無意識の領域に抑圧されているものの、泥酔するとそれが噴出してくるものだから、土下座を自発的に行うことによって、以前の土下座もまた自発的なものであったと記憶を改竄し、トラウマを克服しようという心理的機制が働くのではないかと推察される)。
このように、平常時の自分のコントロールが及ばないもう一人の自分が、泥酔時には現れるのである。このことは、一つの倫理的な教訓を与えてくれる。それは決して、「酒を飲んでもきちんと自らを律せよ」といったものではない。そんなことはそもそも無理な相談である。酒を飲みながら自己を律せよというのは、「走りながら休憩せよ」というのと同じくらい根本的に矛盾した命令だからである。では、泥酔によってもたらされる倫理的な教訓とは何か。それは、「自らの内に他者が存在することを意識し、決して自分が自分の全てをコントロールできるなどと思うな」というものである。泥酔から醒めた人間は、記憶には残っていないが確かになされたという自らの奇行を何らかの形で知る度に、自身に潜む制御不能な他者の存在を否応なしに意識させられるのである。
そもそも、理性的な人間はみな主体的に自らをコントロールできるはずだという考えそのものが、近代化によって生じた幻想であり、「近代的個人」の思い上がりでしかない。泥酔の経験は、自身を自律的な主体であると信じていい気になっている「近代的個人」に、内なる他者の存在を意識させ、自らの驕りと向き合う機会をもたらす。そして、自分が自分を制御しきれないという事実を突き付けられることで生じる無力感は、人間を幾分かは謙虚にしてくれるのである。
また、これまでに述べたものとは別の理由によって、泥酔から謙虚さへと至る道が開かれることもある。その理由とは、「自らの命のありがたみに気付くことができるから」というものである。
泥酔している人間は、絶えず事故死の危険に晒されている。ここで恐縮ながら再び私の事例を引き合いに出すと、私が人生において最も死に接近したのは、大学四年生の泥酔時である。当時失恋直後だった私は、自棄を起こしてバーでテキーラをストレートで呷り続けたために、帰り際にはまともに歩けなくなっていた。そして巡り合わせの悪いことに、飲んでいたバーはエレベーターがない雑居ビルの二階にあり、帰るためには急峻な階段を下りなければならなかった。千鳥足を通り越してコンテンポラリーダンス状態になっていた私は、当然のように階段を頭から転げ落ちた。そこからどういう経緯で病院に行ったのかは覚えていないが、頭部を負傷していたために諸々の検査を受けた。結果としては異常なしで、単なる打撲と裂傷だけだったのだが、医師からはショッキングな事実を告げられた。医師曰く、「怪我の状態を見る限り、頭を打った際に、あなたは猫背だから衝撃が逃げて助かったものの、もし姿勢が良かったら死んでいたかもしれない」と。このときほど自分が猫背でよかったと思ったことはないが、一方でその猫背の背筋が寒くなったのも確かである。このとき以来、泥酔には事故死の危険性が伴うことを強く認識するようになった。そして、「テキーラは飲まない」「猫背は治さない」という二つの掟を自らに課しつつ、飲酒には文字通り命懸けの覚悟で臨むようになったのである。
このように、泥酔というものは常に死と隣り合わせである。深い酔いから醒めた折に、ふとその危険性に思い至ったならば、誰しも自らの生命が存続していることなど偶然の結果にすぎないという事実を思い知らされるに違いない。そして、死の危険に晒されつつもたまたま生かされたという僥倖に気付いた人間は、必ずや自らの命に感謝することだろう。こうした経験もまた、人間を謙虚にしてくれるのである。
以上、泥酔の経験が人間を謙虚にする二つの理由を示した。結論を繰り返すと、泥酔を経験した人間は、第一には内なる他者の存在に気付くことによって、第二には自らの命のありがたみに気付くことによって、謙虚になる契機を与えられるのである。これを図式的に整理すれば、第一の理由は「自己の行為の制御の困難の認識」に、第二の理由は「自己の存在の制御の困難の認識」に、それぞれ対応していると言える。
ただ、ここまで説明を尽くしたところで、「個人的な経験を過度に一般化している」「泥酔すると得られるものよりも失うものの方が遥かに多い」「筆者の生活態度を考慮すると酒飲みの自己正当化にしか思えない」「そもそも他人に迷惑をかけているくせに屁理屈をこねて開き直っている時点で全く謙虚ではない」といった批判は免れないだろう。確かに、私の記述には大なり小なり常習的泥酔者のバイアスがかかっているに違いないから、そうした批判は甘んじて受け入れざるを得ない。だが、誰もがコンプライアンスで雁字搦めになっているこの時代にあって、反倫理の極北とも言えるような泥酔という経験が、逆説的にも新たな倫理の生じる契機になるかもしれないという可能性に、私はどうしても微かな光明を見出さずにはいられないのである。
自己という虚空に酒をぶち込めば涙の代わりに尿が出てくる 三田三郎
著者プロフィール
1990年、兵庫県生まれ。短歌を作ったり酒を飲んだりして暮らしています。歌集に『もうちょっと生きる』(風詠社、2018年)、『鬼と踊る』(左右社、2021年)。好きな芋焼酎は「明るい農村」、好きなウィスキーは「ジェムソン」。
X(旧Twitter):@saburo124
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
