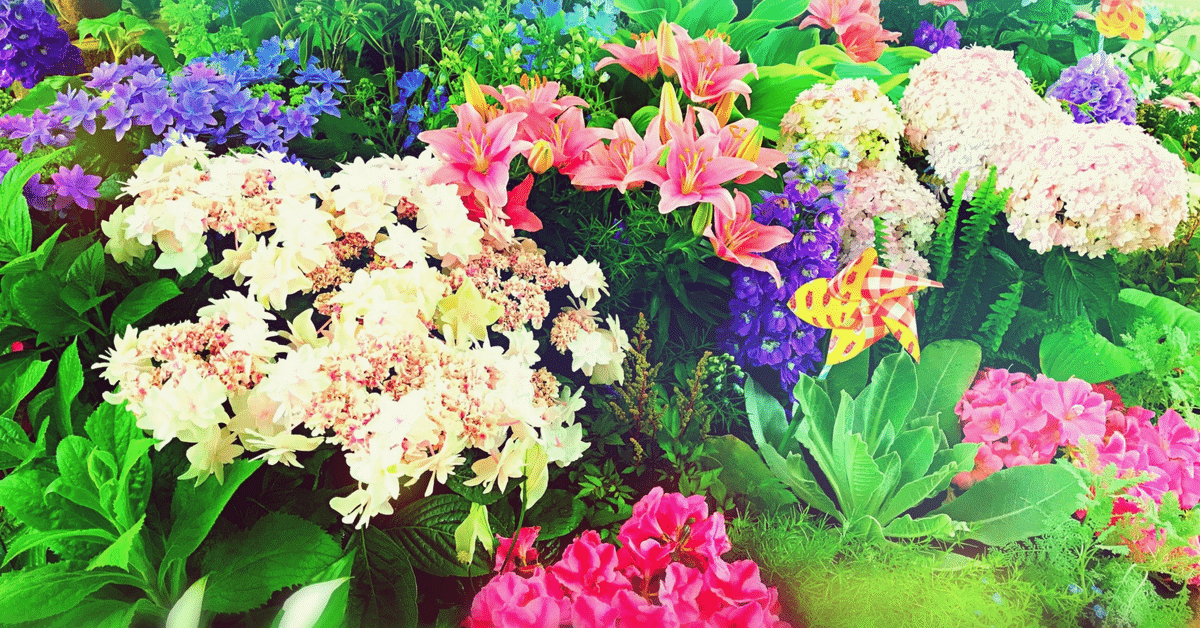
よしもとばななさんの『花のベッドでひるねして』を誤読する。
久しぶりによしもとばなさんの小説を読みました。
90年代前半の一時期、ばなな作品を読みまくった世代なんですけどね。
その後も、疲れたな~と感じたときにふと手に取ってしまう、言いようのない居心地の良さというか、そんな空気感を醸し出してくれるのが、私にとってのよしもとばなな(吉本ばなな)作品でした。
なんですけど。
『花のベッドでひるねして』は、居心地良さの裏にホラーがあるような、そんな作品でした。
注:私が感じたホラーは、作品の中でモチーフ的に取り上げられた怖さとは違う怖さなので、以後の記事は誤読と思っていただいて構いません。
また、ネタバレをやらかす確率も高いので、ご了承ください。
自己肯定感の高さ
よしもとばなな作品といえば、主人公の自己肯定感の高さですよね。
なんだかんだあっても、一生懸命に現状を受け入れて肯定しようとする。
この作品の主人公・幹は、浜辺でわかめにくるまれて捨てられていた赤ちゃんで、でも母となる大平淑子に拾われたことから、大平家の一員として成長していきます。
作品の冒頭で、幹は自分が捨て子であることに、それなりにこだわります。
大平家の家族(母、無口で芸術家の父、スピリチュアルな祖父、母の弟の章夫おじさん)は、幹が捨て子であったことを隠さず話す派で、むしろ「あなたがうちに来てくれて本当に良かった」と伝えてきた人たちなので、幹も大平家になじんでいくのですが、それでも思春期は揺れます。
揺れつつも、現状を肯定し、己のネガティブさに打ち克とうとする強さは、読者に自己啓発本を読んでいるかのような錯覚を起こさせます。
でもね。
幹がポジティブに語れば語るほど、なんか切なくなってくるんだよねえ。
気を張りすぎなくらい張ってないと、多分、不安でしようがないんだろうけど。
「ひとつでも脇道にそれたら、落ちてしまう。そういう道だったよ、私の道は。」
幹の自己肯定感の高さって、好景気を知っているバブル世代の感覚なのかと思いきや、実は衰退期の今しか知らない世代の感覚なのかもしれませんね。
「違うこと」をしないように、というスピリチュアルな祖父の呪い
大平家の祖父は、スピリチュアルおじいちゃんです。
一歩間違えたら新興宗教の教祖とかやってそうな、引き寄せの不思議な力がある人。
大平家は、なんとなくこのスピリチュアル祖父が主導権を握り、祖父の教えを刷り込まれるようにして、みなが生きていきます。
この祖父の教えとして「違うことをしないように」というのがあるのですが。
「違うこと」って何なのか、この祖父も明言しないまま亡くなってしまうんですね。
だから、残された若者たち(幹と祖父の弟子だった野村君)の中に、言葉だけが残ってしまう。
幹にとっての人生は、捨てられたところから始まるわけですから、幹を捨てた親は「違うこと」をしたという確信があるわけですよ。
実の親が捨てさえしなかったら、幹が悩んだあれこれは存在しないわけですし、どう考えても子どもを捨てるって「違うこと」でしょ?
そんなかなりの高確率で死んでいたであろう自分が、スピリチュアルな祖父の娘である母の引き寄せ力によって救われ、今までこうして生きている。
その幸運は、引き寄せ力を持っている大平家の人々のおかげなのだから、その大平家に御恩は返したいし、だからこそ「違うこと」をして迷惑をかけたくない。
そう思うのも不思議ではなく、幹は大人になっても村の外に出ることなく、家業の民宿(という理解でいいのか?)を手伝いながら、結婚も恋愛もせず、今のままの生活を続けたいと願います。
外国から野村君が戻ってきて、大平家の裏に引っ越してきて、変化が生まれる……と幹は思っているけれど、大平家の呪縛に囚われている事実は変わらない。
結局、祖父の言う「違うこと」が何なのか、人の道に反することなのか、倫理観や人権意識を基準としているのか、それとも運命に逆らう……というようなよくわからないものなのか、そこがはっきりしていないからこそ、幹たちは振り回されるのではないかと思っています。
そしてそれが、スピリチュアルな力のある者にだけわかるしるしだったりした場合、その力がない(血を分けた孫ではない)幹は、祖父の顔色をうかがうしかなくて、祖父の死後も記憶に支配されるようになります。
これ、ホラーじゃないですか?
幹が、大人になっても外の社会に飛び出すことなく、大平家にとどまり続けるのも、勿論御恩を返すことは「違うことではない」という確信(人道的に違わない)があるのでしょうけど。
とどまり続けるからこそ、大平家とつながっていられる、自分は根無し草ではないという安心感のほかに、スピリチュアルな力の余波を受け続けられる安心感もあるのかな、と思うんですね。
自分には見えない強い力を持った人たちが目の前にいて、その人たちの強い力のおかげで自分もいい目を見ることができて。
最強の祖父は亡くなってしまったけど、その娘の母はまだ健在で。
自分ひとりの力なんてたいしたことないから、今の幸せを守ることだけ考えて生きていきたい。
この発想が、祖父による支配の果ての思考停止に思えるし、祖父が築いた権威態勢にすがっているだけに見える……と言ってしまうのは酷でしょうね。
死者を弔う人生
幹には生きてる人間の友だちがいません。例外的に野村君だけ。
学生時代の友だちはほぼ村を出て人生を作り、村人からは一歩距離を置かれていることも認識しています。(嫌われているわけではないけれど)
普通の子なら、そんな環境に嫌気がさして、街の大学に行くなり就職するなりするけれど、呪縛に囚われた幹にはそれができない。
それができないけれど、幹は夢の中で死者と交信するようになり、人間は自由だという境地に至ります。
幹がつかんだ、精一杯の幸せがそこにあるんですよねえ。
これが悪いとは思わないし、多分、幹は両親が死んだあとも大平家の墓守をして生涯を終えるんだろうなあ、それが彼女の本望だろうなあ、と思うから、それはそれで幹の物語だと思います。
ただ、切ないよね。
過去はどうしようもないけれど、過去に受けた心の傷が一生を左右するってあるけど、そんなときに現状を肯定することが幸福への一番の近道だってのもわかるけど、でもやっぱり幹の人生って切なすぎる。
祖父のわけのわからない力に反発したり、たいして稼ぐ気のない親を批判したり、都会に憧れたり、夢を持ったり、憧れの人に自分を好きになってもらいたいと思ったり、そういう普通の若者みたいなことをして欲しかったんです。
おわりに
この本を読んでいて、ポジティブ思考一辺倒だとやっぱり辛いなというのを感じました。
世の中は何でもかんでもポジティブで行け! という感じだけど、それだと自ら不幸のど真ん中に突っ込んでいても気づかないじゃん! というのが、幹なので。
幸い大平家は善良な人たちばかりだからよかったけど、黒屋敷な人たちだったら、幹は宗教2世になってましたからね。
それぐらい、一辺倒というのは危うい。
また、生存の根本を否定された傷を抱えながら生きている幹の気持ちを、そうではない人間が想像する難しさというのも、今現在も感じています。
大平家は、養親一族としては理想的ともいえる家族だと思うし、幹は大事にされてたし、幸せだったと思うし、他の家庭に引きとられていてもっと苦汁をなめたかもしれない人生もあったと思う。
だから、大平家に対して不服を感じるのは、幹の境遇で育っていないもののエゴと言われればそうかもしれない。
どんな大人も、大なり小なり子どもに呪縛をかけるのでね、自分でも気づかぬうちに。
それぐらい「違うことをしない」って難しいんだよ、幹のおじいちゃん?
するなって言われても、やっちゃうの、人間は間違える生き物だから。
そこをどうリカバリーするか、でしかないんだよ。
大変だけど、それの繰り返しをやることで、成長していくしかないんだよ。
と、大平家祖父に異議申し立てをしたところで、終わりたいと思います。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
この記事が参加している募集
よろしければサポートをお願いします。いただきましたサポートは、私と二人の家族の活動費用にあてさせていただきます。
