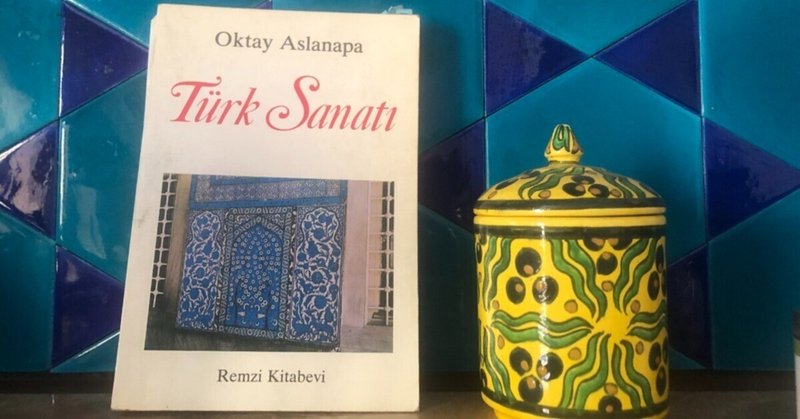
ヨルダン砂漠の遠足と美術史家という病|魅惑のオスマン美術史入門(4)|イスタンブル便り
この連載「イスタンブル便り」では、25年以上トルコを生活・仕事の拠点としてきたジラルデッリ青木美由紀さんが、専門の美術史を通して、あるいはそれを離れたふとした日常から観察したトルコの魅力を切り取ります。人との関わりのなかで実際に経験した、心温まる話、はっとする話、ほろりとする話など。見事奨学金を勝ち取った筆者。はじめてのトルコで留学生活が始まります。彼の地には、数々の出会いが待っていました。

日本の文部省(当時)から受けた奨学金の期間は二年。しかしわたしには、留学する前から密かに抱いた野望があった。
トルコ語で博士論文を書く。
トルコで博士号を取得する、というよりも、美術や建築作品を生み出した言語、それを愛でた人々が話し、考えていた言語で、作品を理解したい。そういう切実な願いを持っていた。
たとえば日本美術の専門家がいたとする。その人が日本語を少しも理解しなかったとしたら、日本人のわたしたちは、どう受け止めるだろうか? ああ、日本美術が好きなのね、と思いこそすれ、自分たちが理解するようには、この人は日本美術を捉えていない、と思うのが普通だろう。日本美術理解の前提となる、和歌や、漢詩や、仏教経典や、黄表紙本や、謡曲や、そんな素養なくして、そこから生み出された美術は、深い文脈では理解できない。
それと同じことが、オスマン美術にも言えるだろうと思ったのだ。
それにもうひとつ。いわゆる「イスラーム美術」について、アメリカやフランスの大学で勉強し、西洋の言語で博士論文を書くことは、「なにか違う」という感じが、していた。
図書館などでの文献調査は、格段に簡単だろう。博物館などのコレクションも、整備されているにちがいない。だがそれは、一旦アメリカなりフランスなり、別の国の、フィルターを通したものではないだろうか?
変な石頭である。しかしそんなわけから、わたしは「博士論文をトルコ語で書くのだ」と、当初から心に決めていた。

留学して丸一年も経たない春、イスタンブル工科大学の博士課程を受験した。当時は外国人枠などなく、条件はすべてトルコ人の他の受験者と同じである。トルコ語も満足にできなかったのに、随分と一足飛びの話だ。
外国語として英語の試験もあった。 全国統一のマークシート方式の公務員外国語試験KPDSに加え、専門文献の「英文和訳」ならぬ、 「英文トルコ語訳」の筆記試験もあった。英語→日本語→トルコ語、などとやっていては時間が間に合わぬから、英語→トルコ語を直接翻訳するのである。
だが、そんなことは序の口だった。専門の試験の出題範囲は、古今東西の美術史、特にトルコ美術については、詳細な知識が要求される。いったい何から手をつければ良いのだろうか?
わたしがやったのは、じつは単純なことだった。日本でオスマン美術史を志した時にやったのと同じだ。「トルコ美術」についての基本書、一冊のみ、を、トルコ語で読み、一行一行、ひと単語ひと単語、徹底的にわかるようにすることである。トルコ語で読めば、トルコ語の勉強にもなるから、一石二鳥である。
そして選んだのが、オクタイ・アスラナパ『Türk Sanatı』(トルコ美術)だった。
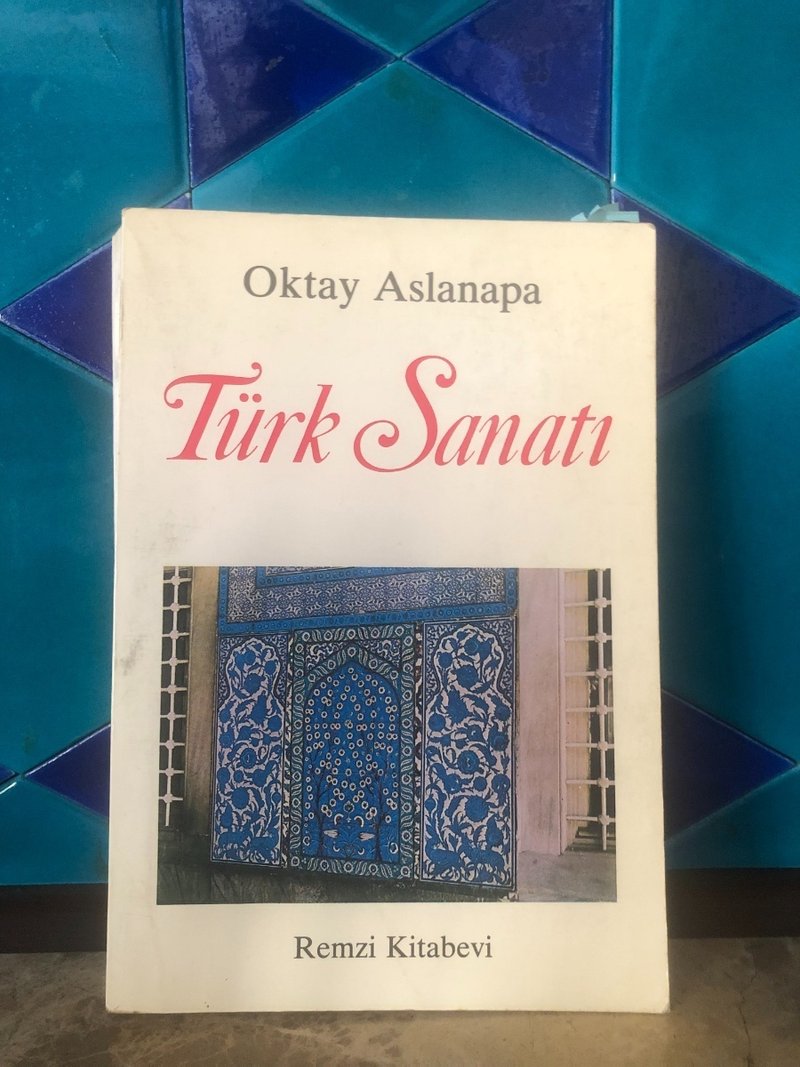
オクタイ・ベイは、トルコ美術史研究における、もうひとりの記念碑的存在である。1970年代に書かれたその本は、それまで欧米の研究者が中心だったトルコ(あるいはオスマン)美術史研究のなかで、トルコ人による、トルコ語で書かれた最初の通史のひとつである(日本人が中心の日本美術史研究と比べると、驚きだが、その話はひとまず措く)。

わたしが留学した当初、オクタイ・ベイ(ベイは男性につける敬称)は、すでにイスタンブル大学教授の職を退かれていたが、週に一度、非常勤で講義を持っていた。それをじかに受ける幸運に、わたしは間に合ったのだった。わたしはその本を最初から最後まで、トルコ語で読む、という計画を立てた。
* * *
何かを成し遂げる人物の驚異的に強靭な体力について、このトルコ美術史の碩学の、印象深い話がある。2003年のことだ。国際トルコ美術史学会が、ヨルダンのアンマンで開かれた。
オクタイ・ベイはその時、おそらく七〇代後半だったと思う。学会の遠足で、ヨルダンの有名な考古学的遺跡、ジェラシュを訪れた。しかし、過酷な試練が待っていたとは、参加者は誰も知らなかった。学会が用意したバスには、クーラーがなかったのである。
バスは、灼熱の砂漠を走る。窓を開けるとドライヤーのような熱風と砂埃が吹き込むので、閉めたままである。誰も、一滴の飲料水も持っていなかった。
全員、じっと耐えていた。偶然近くに座った学会理事のコレージュ・ド・フランス教授フランソワ氏とオスマン帝国の貨幣制度の話をしながら、わたしはしかし、暑さで死にそうになっていた。
その時、変わらなかった人物が、たったひとりだけいた。オクタイ・ベイである。ネクタイにジャケットといういつものスタイルを崩さない。不平も言わない。無駄なおしゃべりもしない。終始静かに、にこやかに、バスの後部座席に座っていた。
あの砂漠の遠足で、わたしは確信したのだった。この『トルコ美術』の著者が、若い日にどれだけこのような状況をくぐり抜けたのかを。誰も訪れぬ幾多の建造物を、文献から知り、こうやって実際に訪れたのかを(現在のトルコ共和国には砂漠はないが)。あの本は、血肉によって書かれたものだ。この忍耐と、鋼の体力によって、書かれたものにちがいなかった。
* * *
話が逸れた。とにもかくにも、試験までに、わたしはその本を通読した(つもりだった)。しかし、予想もしない展開が待っていた。結局出題されたのは、その本の中で、「難しいから後で読もう」と後回しにした(そして最後に読みきれなかった)、冒頭の部分だったのである。
――Emevi美術について述べよ。
「Emevi Sanatı 」(イスラーム以前のアラブ美術)という単語を、わたしは知らなかった。痛恨の極みだった。
だが、それ以外はできていたのだろう。不思議なことに、それ以外の出題はなんだったのか、覚えていない。
合格の知らせを受けた日、わたしはアヤソフィアのドームの上にいた。日本から筑波大学の日高健一郎先生率いる調査隊がドームの耐震調査にやってきて、運よくわたしも 参加させていただいていたのだった。
その日わたしは、アヤソフィアのドームの最頂点、アルトゥン・トプに、初めて手を触れた。

* * *
「ミユキ、今度ブルサに連れて行ってあげる。ブルサで国際学会があるから、そこで発表しなさい」。
イスタンブル工科大学での指導教授、アフィーフェ先生からそう声をかけていただいたのは、15世紀初期オスマン建築の代表作、イェシル・ジャーミ(「緑のモスク」)を19世紀に修復したフランス人について調べる、と決めてから、数年経った頃だった。

オスマン帝国の最初の首都、ブルサで開かれた国際学会に、アフィーフェ先生はトルコ建築界の重鎮として、基調講演に招かれていたのだった。会議のプログラムを見て、わたしは興奮した。ベアトリス・サン=ローラン、という名前が書かれていたのである。

トルコへ留学して最初の宿題で、テーマとして選んだブルサのイェシル・ジャーミイ。わたしの興味を強烈に掻き立てたのは、ベアトリス・サン=ローランという人物の書いた論文だった。19世紀に、オスマン建築史の最重要作品の一つブルサのイェシル・ジャーミイを修復したのがフランス人だった、という話を読み、なぜそんなことが起こったのか、疑問を持ったのだった。それは、わたしをトルコへ駆り立てたそもそもの問い、19 世紀に近代化の象徴として建造された政府の中枢、ドルマバフチェ宮殿が、なぜ伝統様式でなく西洋式なのか、という疑問に通じる。ように思える。

ベアトリスは、 意志的な顔立ちの、背の高い女性だった。当時ハーヴァード大学で講師をしていた。彼女はアメリカ人だったのである。親切にメールアドレスをくれ、ボストンに来たら訪ねていらっしゃい、と言ってくれた。
翌年の5月、私は生まれて初めてアメリカを訪れた。行き先はボストン、ニューヨーク、ワシントンDC。
その出会いから、わたしのアプローチは角度を変えた。トルコ語で博士論文を書くのはいい。だが、トルコの中だけに頑なにとどまっていてはいけないのではないか。中からも、そして外からも、両方見る。もしかしたら、重要なのは、その自在さではないのか?
最初にその視点を与えてくれたのは、指導教授のアフィーフェ先生である。
文部省(当時)の奨学金は、二年で終わる。トルコで研究を続けるためには新たな資金が必要だ。日本学術振興会特別研究員のポストに申請することにした。推薦状に、こう書いてくださったのだ。
「日本人である申請者は、トルコ美術史研究を客観的な立場から論ずることができる利点を有する」。
留学して数年。でもトルコ語も思うようにできないし、トルコが理解できているとも思えない。トルコ人と同じように考え、物事を見ようとしても、生まれつきの人に敵うわけがない。外国人といっても、英語やフランス語が母国語の人はいい。文献がすらすら読めるし、研究も豊富だ。
それなのに、わたしはどうだ。トルコ語のみならず、欧米語もしどろもどろである。日本語で書かれた先学の研究はあるとはいえ、わたしの関心分野、近代の美術や建築についての研究は皆無だ。オスマン帝国研究に限っていえば、日本人であることの利点はない。なぜわたしには、こんなに困難ばかりがあるのだろう。
そう思っていた矢先だった。不意を衝かれたような気がした。
オスマン美術史の研究は、良くも悪くも、研究者の立場によって、捉え方が大きく変わる。美術史に限らず、オスマン帝国研究がそもそも、欧米列強の植民地主義的な興味からはじまっている。最初に欧米の蓄積がある。
トルコ語で書かれた通史の出版が1970年代、というのには、そういう背景があるのだ。そして、その時代のトルコ人研究者には、欧米優勢の研究事情への批判が、強烈にあった。そういう意味では、非常に政治的である。
トルコへ留学したわたしは、そういう事情を行ってみて初めて知った。
ある年、トルコ美術国際学会でこういうことがあった。トルコ語を話さない研究者から、発表者がトルコ語で発表することに、クレームが入ったのである。興味深い内容なのに、一部の人は理解できないからもったいない、ということから始まったのだと思う。
が、参加者の一部からは、「国際トルコ美術史学会なのだからトルコ語ができるのは大前提ではないか」との反対意見が出た。これは例えていうならば、日本美術国際学会がどこか外国であったとして、日本語での発表にクレームが出て、日本美術史の研究者ならば、日本語を理解するのは当然ではないか、と押し返すのと同じだ。
外国での学会なのだから、外国語でやるのは当たり前なのではないか。そう思うのは自然かもしれない。しかしトルコの場合、ここが厄介である。「トルコ美術」といっても、実際はオスマン美術や、その前の中世のセルチュク美術などの研究者も、この学会に参加する。
そうすると、地理的範囲は現代のトルコ共和国よりも、ずっと大きくなる。西はバルカン半島、セルビア、ポーランド、オーストリア、東はアラビア半島、現在のイラン、インド付近まで広がるのである。そこにはオスマン帝国の植民地主義の問題もある。
たとえば、1878年にオスマン帝国から独立したブルガリアの伝統的木造住宅は、オスマン建築なのか、それともブルガリアの国家建築なのか? あるいは、19世紀にイタリアから移住した家族の子供として、イスタンブルで生まれ育った子供が、初等教育をイスタンブルで、イタリアで教育を受け、建築家になり、イスタンブルに建物を作った。これは、イタリア建築なのか、トルコ建築なのか、あるいはオスマン建築なのか?
トルコ美術にたいして外からの視点を持つ、とは、そういう意味である。トルコ側とブルガリア側、あるいはオスマン帝国とイタリアの、両方の視点を持つということ。


学会でどの言語を使用するか。AIが発達した現代では、それほど気にされなくなったが、これは確実に政治的文脈をもつ問題である。
アメリカの大学で教授を務めるある著名なアラブ人研究者が、自分の発表の冒頭で、「わざと」アラビア語で話した。そこにいた大半の人が、一体何が起こったのかとほんのひととき戸惑った。
すると、教授は大変流暢な英語でにこやかにこう言った。「ね、皆さんびっくりしたでしょう? トルコ語で発表されると、わたしは今皆さんが味わったような気分になるわけです」。
それは、オスマン帝国に支配されていたアラビア語圏と現代のトルコ共和国、愛憎と民族的誇り、コンプレックスがないまぜになった複雑な感情と、植民地主義的アプローチへの、ウィットに富んだ批判だった。
アフィーフェ先生がわたしへの推薦状に書いてくれたひとこと、「日本人だから客観的な視点を有する」とは、日本はオスマン帝国と周辺諸国との間の、歴史的因縁とも言える確執とは比較的遠いところにある、だから客観的になれる、という意味だった。
オスマン美術史研究に、日本人であることの利点を生かして、何ができるのか? それが、のちに手掛けることになったトルコ国立宮殿局所蔵の日本美術工芸品の調査や、本を出すことになった伊東忠太のオスマン帝国旅行の研究に連なることになる。
だがひとまずは、博士論文の完成に邁進する日々だった。 ブルサのイェシル・ジャーミイを修復したフランス人建築家、レオン・パルヴィッレという人物は、ほんとうに実在したのだろうか? 次回以降をお楽しみに。
(続く)
文・写真=ジラルデッリ青木美由紀
ジラルデッリ青木美由紀
1970年生まれ、美術史家。早稲田大学大学院博士課程単位取得退学。トルコ共和国国立イスタンブル工科大学博士課程修了、文学博士(美術史学)。イスタンブル工科大学准教授補。イスタンブルを拠点に、展覧会キュレーションのほか、テレビ出演でも活躍中。著書に『明治の建築家 伊東忠太 オスマン帝国をゆく』(ウェッジ)、『オスマン帝国と日本趣味/ジャポニスム』(思文閣)を近日刊行予定。
筆者のTwitterはこちら
▼この連載のバックナンバーを見る
よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。
