
清水寺の舞台から眺めた夕景と新劇運動の先駆者・島村抱月|偉人たちの見た京都
偉人たちが綴った随筆、紀行を通してかつての京都に思いを馳せ、その魅力をお伝えする連載「偉人たちの見た京都」。第16回は新劇運動の先駆者・島村抱月が窮地に追い込まれていた時期に京都を訪れ、鐘の音を聴きながら眺めた清水の舞台からの夕景です。薄紫色の夕靄の中に浮かぶ京都の街並み、眼下に広がる緑、黄金、赤、橙、深紅の紅葉。夕暮れが深まるにつれて変化する色彩。見事な絶景を語る美しい文章をぜひご一読ください。
1918(大正7)年に発生し、2年間にわたって全世界を席巻、当時の世界人口の3割に当たる5億人が感染したといわれるスペイン風邪。現在のコロナ禍と同様、日本国内でも大流行し、最終的に40万人以上の人々が亡くなったとされています。
このスペイン風邪への罹患が原因で、同年11月にわずか47歳で急逝したのが島村抱月です。抱月は文芸評論家、美学者、英文学者、小説家、劇作家、演出家、そして初期新劇運動の指導者として活躍した人物で、女優・松井須磨子との恋愛事件でもよく知られています。

抱月は1871(明治4)年に島根県那賀郡小国村(現・浜田市)に生まれました。旧姓は佐々山。父母に早く死なれたため、小学校卒業後に裁判所の給仕となり、後に養子となる島村家の援助を受けて上京。東京専門学校(現・早稲田大学)で坪内逍遙に師事し、文学、美学の教えを受けます。卒業後は母校の講師や読売新聞記者となり、文芸評論家として活動を開始します。
1902年から1905年にかけてヨーロッパに留学し、帰国後は早大教授に就任。「早稲田文学」の主宰者となる一方、近代的な演劇を日本に確立させようと志し、1909年に師の逍遙とともに新劇運動を開始。その指導者として活躍します。1911年にはイプセン作「人形の家」を演出家として上演。大評判となりました。
新劇運動家、演出家として大車輪の働きをする抱月でしたが、「人形の家」の主人公を演じた松井須磨子と不倫の恋に落ち、世間の批判を浴びてしまいます。演劇路線をめぐり、逍遙とも関係が悪化。精神的にも、肉体的にも次第に追い詰められていきました。ちょうどその時期の1912(大正元)年11月。抱月は京都を訪れ、京都市内の各地をめぐった印象を随筆に書き残します。その一節にこんな文章がありました。

京都の落ちついた味を髣髴しようとするには、新しい破壊力の及んでいないところにもぐり込むのがよいという。けれども人間の心がすでに荒んでいるのだから、その人間の出はいる限りたいていのところは、すでに精神において破壊せられていて、外形の幾分が残っているに過ぎない。われわれはただその残骸を見て、ありし昔を想像するほかはない。(略)
が、今一つの興味は京都の町全体を靄に包んで、正体の知れない距離から見ていることである。それには夜、三条の大橋辺に立って裏から平たく見るのも一興であるが、夕暮に清水の舞台から大きく広く見おろした景色が絶勝である。

絶勝とは、非常にすぐれていること。特に、景色がきわめてよいことを表す言葉です。抱月は清水寺の舞台から眺めた景色こそ、絶勝に値するものと断言しているのです。
清水寺は誰もが知る京都を代表する寺院のひとつ。開創は778(宝亀9)年。北法相宗の大本山です。創建以来、たびたび戦乱や火災にあって堂塔を焼失。現在の伽藍はそのほとんどが江戸時代の1633(寛永10)年に再建されたものです。
清水寺といえば、国宝である本堂の前面の崖に張り出した懸造の桧舞台があまりに有名です。高さは4階建てのビルに相当する約13メートル。釘を一本も使っていない70本以上の欅の柱が左右の翼廊と床を支えています。排水のため、わずかに前方に傾斜した舞台は不安定感から実際よりも高さを感じます。

ここから眺める京都の景色は、古くから人々を魅了してきました。抱月は特に夕暮の景色を絶賛して、こう記します。
はるかに西を限った山脈が地平線に沈んで、その上に舂きかけた夕日の光線が、薄雲の切れ目から眼もあやな尊い輝きを京外れの村々に射かけている。そのあたりの村一帯は光栄に染まって光っている。

それが京都の市街に近づくにしたがって次第に黒んでくる。そしてこの光の村から夕靄の都への移り目あたりに東寺の五重塔がふわりと浮かんでいる。塔の下半分はもう靄の中に溶け込んで、見わたす限りの町とともに夕暮の神秘の中に沈んでしまう。
あとはただ一面に薄紫の海を展べて、少女の秘密のようにひそかに、静かに柔らかである。それでいて所々に図ぬけて大きい寺の屋根が怪物のごとく蒼白く光ってそびえ立っている。
ちらちらと見えはじめた町の灯が、空気のせいか、その酔ったように美しい赤の色や、神経的に鋭い白の色に特殊な光沢を持って輝く。──総体京都の裸灯は、遠くから見ると涙ぐんだ美しい眼のように艶な光沢を持っている──。こうして京の町は次第に暮れていく。
美学者であり、小説も執筆していた抱月らしい美しい文章です。夕靄の中に浮ぶ京都の町並みが、目の前に見えてくるような気がします。
舞台からすぐ下はと見ると、灰色に乾いた一筋の路が紅葉の中を分けている。紅葉は青から橄欖に黄に紅に緋に、そして爛れて赤黒くなるまでの盛衰の色をすべて一目にあつめて、さらにその色と色との間に重なる光線の明暗を無限に複雑にしている。それが夕暮に近づくにつれてさらに色調を変えてみせる。

11月は京都の紅葉の最盛期。色づく前の葉から、黄色がかった緑、黄金、赤橙、深紅、赤銅、ピークを過ぎて黒くなり始めた葉まで、多種多彩な色を見ることができます。夕暮が深まるにつれ、太陽の光の変化でそれらの景色はさらに違った顔を見せていくのです。
その紅葉の中にビール会社に園遊会のような旗をかけた赤毛氈*の茶店が並んでいて、つい先ほどその一つから出た三人連れの客は、商人風の三十男が一人と若い女が二人。その一人の女はぽってりした肉付きの色が際だって白かった。
*日本の伝統的な敷物。緋色(赤)が多く、青、緑などもある。
それが酒に酔って眼の下を真っ赤にしている。よろけながら大声で男に甘ったれ甘ったれして紅葉の谷に隠れてしまった。はっきり見えた人顔はこれを最後にして、清水の山もまた暮れていく。
どこか遠くでわっという声は聞こえるか、それはただ車馬の音やあらゆる人間の音響が一つに溶け合った総高だけである。あたりも次第に静かになってくる。御堂には蝋燭の灯や種油の灯が暗い蔭の中にぽつりぽつりと赤い波紋を描いている。夜風がさすがに寒い。
薄紫の海と見えた眼界がいつか黒い夕の影を深めて、市街は燈火の林に変わる。そして夕暮の京都は夜の京都に移るのである。
時間をかけて眺めていた晩秋の京都の夕景も、すでに夜の景色となってしまいました。夕景色は本当に美しく、心を奪われるものがあります。ですが、京都の夕暮には、景観だけでなく、もう一つ他の場所にはない特別なものがあると抱月は言うのです。
さらに京都の夕暮を豊富にするものは鐘の音である。円く内に巻き込んで、無限に細く長く空気の間を舞いゆくあの響きは、とうてい東京などで聞かれないものである。じっと眼をつむって聞いていると、古来この世を去った幾千万の霊魂の秘密と悩みとを直ちにわれわれの霊魂に伝えるという、その鐘の音である。
それが一面の夕闇の中から、あちらに一筋、こちらに一筋と渦き上がってくる。その音をもとヘもとへと辿っていったら、皆何百年という由来を持った寺の鐘楼に淋しく吊るされている。銘と錆とのゆかしい大梵鐘なのであろう。そしてそれらの鐘の後ろには、女人の恨み、若僧の涙というような様々のローマンスが余韻を引いているのではないか。
かような光景が相寄って、夕暮の京都はセンチメンタルなものになる。
先にも述べましたが、抱月がこの京都の旅を書き記したのは、松井須磨子との道ならぬ恋に苦悩していた1912年の秋のことです。その背景を知ってから改めてこの文章を読むと、清水の舞台でどこからともなく響いてくる鐘の音を聞きながら、夕闇に包まれ始めた京都の街の灯を見ている孤独な抱月の姿が想像されてしまいます。
抱月は翌年の1913年、ついに逍遙と決別。教職、家庭も捨て、須磨子と劇団芸術座を結成し、新劇運動に邁進します。1914年にはトルストイの原作を抱月が脚色した「復活」が好評を博し、劇中で須磨子が歌った「カチューシャの唄」が大ヒット曲になるなど、新劇の大衆化に大きな功績を残しました。
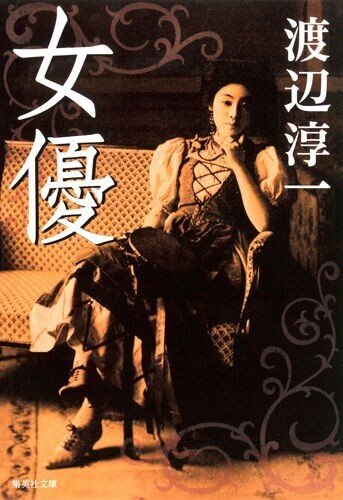
しかし、地方での興行や劇団運営、舞台演出などの活動で、抱月の身体には疲労が蓄積されていきます。そして、この随筆の執筆の6年後、志半ばにして抱月は現世を去ることになってしまいました。その2カ月後には、須磨子も彼の後を追って自ら死を選びました。
清水寺の舞台から抱月が見ていた夕景は、今では大きく様相が変わってしまったかもしれません。けれども、夕暮の京都の街に響く鐘の音だけは、昔と同じ音色が聞こえていることでしょう。抱月は故郷・島根県浜田市の浄光寺に眠っています。

出典:島村抱月『抱月随筆集』「京都より」
文=藤岡比左志
藤岡 比左志(ふじおか ひさし)
1957年東京都生まれ。ダイヤモンド社で雑誌編集者、書籍編集者として活動。同社取締役を経て、2008年より2016年まで海外旅行ガイドブック「地球の歩き方」発行元であるダイヤモンド・ビッグ社の経営を担う。現在は出版社等の企業や旅行関連団体の顧問・理事などを務める。趣味は読書と旅。移動中の乗り物の中で、ひたすら読書に没頭するのが至福の時。日本旅行作家協会理事。日本ペンクラブ会員。
清水寺
●秋の夜間特別拝観
11月30日まで
拝観時間=6:00~21:30 (21:00受付終了)
12月1日 〜 12月31日
拝観時間=6:00~18:00
https://www.kiyomizudera.or.jp/
▼連載バックナンバーはこちら
いいなと思ったら応援しよう!

