
怪物と僕、君と怪物
日蝕
それは夏のうだる様な暑さの中。
皆既日食の日の出来事である。
皆が日食に嬉々としている。
人々は黒い下敷きのようなメガネで太陽を見ていた。
1組のカップルの男性はキザな台詞をはき、女性はうっとりと太陽を見ていた。
また別の少年たちは、昼日中なのに暗くなった事にワクワクしているようだった。
明るくなるとお祭りムードの消し飛ぶ様な悲鳴が聞こえた。
ふと周りを見廻すと異様な生物がいる。
それは小さなこちらの悲鳴と共に叫びを上げた。
人と怪物は互いに牽制していたが、逃げる者と争う者に分かれた。
その日を境に、世の中が2つの価値観に分かれる。
醜い怪物と、人とに。
数日の混乱の後に政府から見解が為された。
怪物は人であり、相手からはコチラも怪物に見えると言う事だった。
これは決して醜いクリーチャーが現れたわけでもなければ、人が変異した訳ではない。
要は見え方の違いが顕著に表れたのだ。
多少の諍は絶えないものの、慣れとは恐ろしいもので段々と社会に溶け込んでいった。
そんな日常のなか、僕フジサキはいつものようにコンビニに出勤する。
混乱の時は荒らされたりして、停滞していた労働も復活している。
一時期は億劫で怖かった労働も、日常に戻りつつある今となっては、生活する為に必要不可欠な事だった。
逆に混乱が悪化したらと恐ろしくなる。
今日のシフトはヤマナカさんと組む事になっている。
ヤマナカさんは見た目は怖いが気配りがちゃんと出来る人で、尊敬出来る人である。
挨拶もそこそこに、来店客に声かけを始める。
「いらっしゃいませー」
「ホットスナックお安くなっています!お1ついかがですかー」
最初は爬虫類の声に聞こえていたヤマナカさんの声も、日を追うごとに綺麗でいて少しハスキーな女性の声に聞こえてきて、そこで初めて女性だと認識した。
その日の20時位お客さんもまばらになる時間、僕が休憩に入っていると、店内から大声が聞こえてきた。
「ちょっとーこのフランクフルト乾燥してるんだけどー。替えてくれない?」
「申し訳ありません!すぐ新しいものとお取り替え致します。」とヤマナカさん
「爬虫類だからって乾燥したもの出しちゃダメだよ〜。」
そのヒトに見える男性客は、さも面白いことを言ったぞという顔をしていて、一緒にいた女性もクスクス笑っている。
ヤマナカさんは潤んだ目で笑顔らしい表情をしながら申し訳ありませんと接客していた。
堪らなくなり、休憩室から出てレジを代わると、すみませんと一言言い品物を詰め直しお渡しする。
ヒトらしき男性客は気に食わなかったのか、「爬虫類と良い仲かよ!気色悪い!」と吐き捨てて帰っていった。
自分のプライドの為かヤマナカさんの為か分からなかったが、怒りに身を任せずに笑顔で見送った。
「ありがとうございました!」
「またのお越しお待ちしてます」を言わなかったのはせめてもの抵抗であった。
「フジサキさん見た目と違って優しいんですね。」
そう言われたのは仕事を上がった後である。
見た目はお互い様だよなぁ…
と言いかけたが飲み込んだ。
「ああいう人は何処にでもいるし気にしちゃダメだよ!」
本心ではあるが、自分も見え方に多少違和感があるから嘘っぽくなってないか心配した。
「そうですよね!同じ人間なんだし、人間同士でも残念だけど差別はありますもんね!気にしない気にしない!」
ヤマナカさんは自分に言い聞かせている様でもあった。
ヤマナカさんも僕や彼らが醜く見えているはずなのに、沈んでいたみたいだった。
そこで、ふとヤマナカさんにはどう見えているのか気になった。
「ヤマナカさんには僕はどう見えてるの?」
「え?うんと…仕事ができて頑張っている人ですかね。」
「じゃなくて、どんな姿に見えるのかな?」「…」
一瞬の沈黙で「あっ、言いづらいこと聞いてしまった」と思った。
「強いて言えば、怖い姿ですかね。
でも全然大丈夫ですよ!」
気を遣われたのか、ハッキリ言われたのか…
その後の仕事が少し気まずくなった。
その後、ヒトにはヒトが相手をする方が円滑に回ると気付いて、自ずとそうなっていった。

天使なヒト
彼女の気まぐれ、だったのかもしれない。
ある昼時、仕事場に向かって街を歩いていると、1人の女性とぶつかる。
よろめいた彼女を咄嗟に腰を支えると、見た目の華奢さは感じられなかった。
その感じたものを顔に出していないか気にしつつ、俯きがちに「すみません!」と言うと…
コチラを見て彼女はハニカミ
「いえ、ありがとうございます。」
と言う。
その姿を見た瞬間、懐かしいような感じと俗に言う電気が走る感覚が同時に起こった。
恋に落ちたらしいと、後で気付く。
その時は挨拶程度で、会うこともないかも知れないと思いつつ仕事へ急いだ。
その日から2、3日経った仕事の後。
お酒とツマミ、ご飯を買い、自転車の荷台に乗せ家に帰る。
30分ほどしてあと少しで家に着くと、意気揚々と自転車を走らせる。
最後の坂道を息も絶え絶え登っていると、上から来たヒトが立ち止まり話し掛けてきた。
「今晩は、偶然ですね。」
彼女だ!
居てもたまらず自転車を停め、怖がられない様に息を整え、自然に歩み寄る。
「こ、こんばんは。」
続きの言葉が出て来ない。
すると、
「家、近くなんですか?」
と自転車の荷物置きを指さす。
中からビールが覗いている。
「はい。家近くです。」
カタコトになる。
「家近くなんですか?」
オウム返になってしまう。
「それはどうかな。」
肩透かしを食らった様になり、恥ずかしくなってしまう。
「この前はすみませんでした。」と、取りつくろう。
「いえ。」
「もし良かったら、今度お茶しませんか?」
女性からの誘いに戸惑う。
意を決して「お願いします!」と言うと、不意に彼女が少し笑う。
何かまずい事言ったかなと思っていると…
「お願いしてるの私なんだけどな。」
と言う。
それを聞き、僕もクスッと笑ってしまう。
連絡先を交換した。
次の日曜。
お茶というはこんなに楽しいモノなのかと思った。自分の話した事はほとんど覚えていなかった。
彼女がハンドメイドのアクセサリーが好きな事、読書と音楽が好きで、近くの大学に通っている事など話してくれた。それは鮮明に覚えていた。
その後は、1日に一度連絡をするのが日課になっていった。
僕は一人暮らしをしながら、仕事とは別に趣味で小物を作る事がある。
アクセサリーではないのだが、模型や革細工などである。
将来的には、そちらを仕事にしたいが、そう上手く行かないのが世の中である。
世の中と言うかセンスの問題かもしれない。
その話をすると花のブローチを作って欲しいと、彼女から要望があった。
花のブローチなど作った事が無いのだがと渋っていると、"たんぽぽ"の形ならなんでもいいと言う。
できれば小さな鈴を入れたいので、中を空洞にして欲しい。と言う奇妙な要望だった。
その時は自信がなく、「たんぽぽが好きなんだねー」程度に話を済ませてしまっていた。
次の週水曜の話である。
小物作りの仲間と呑んでいると、ふと彼女の話になった。
そいつはホリキと言うのだが、偶然彼女と歩いているのを見たらしい。
彼は「あの子はやめたほうがいいぞ。いい噂を聞かない。」
深妙な顔をしている。
話を聞くと、「色んな男に貢がせてる。」だの「何股もかけてる。」と言って来た。
挙句は「詐欺師だぞ。」とまで言っている。
噂の出所が定かじゃなかったのと、あまりの言いように腹が立ち、殴ってしまった。
そして弱いモノ同志で取っ組み合いになる。
店を追い出された後、「お前のこと思ってるんだぞ。」と彼は言葉弱気に呟いた。
そう言われて僕は「すまなかった。でも、大丈夫だから。」と言う。
認めたくない自分の心は、ヒガミであろうと言っていたが、それを言葉にするのは避けた。
彼の後ろ姿が心なしか石像に見えた。
彼の話を聞いたからなのか分からないが、どうしてもブローチが作りたくなった。
彼女の要望に応えるべく、たんぽぽのブローチである。
ブローチ以外にも対応する様に、たんぽぽ部分だけ付け外し出来る様にして…
次の日約束してブローチを渡した。
彼女の喜ぶ姿が嘘には見えず、安堵した。
その日は忙しいらしく少ししか会えなかったので、次の日曜に約束を取り付けた。
日曜、彼女は来なかった。
その日には連絡さえ取れなくなっていた。

モノクローム
朝起きて、数年は他の人の入っていない部屋を片付けはじめた。
紙屑と赤い毛糸に足がつまずきそうになる。
沈んだ気持ちで片付けを進める。
ようやく終わり、姉の葬儀に向け身支度を始める。
アルバイト先の同僚のヒト達も葬儀に来てくれると言う。
一緒に働いている男の人は比較的に親しいと思っているので良いのだが…
他のヒト達は、興味本意な感じがして良い気分ではなかった。
身支度のおしまいに髪をみっともなくない様にポニーテールにし、髪留めで留める。
時間があるのでリビングの椅子に座り、さっき淹れたコーヒーを飲み始める。
すると、つい習慣でテレビをつけてしまった。
テレビではニュース特番が組まれていた。
重たい事件の解決と犯人の心理を、分かった様に解説するヒト。
これにも暗い気持ちになり、直ぐにテレビを消す。
姉の姿を思い浮かべる。
涙が出そうになり、コーヒーと一緒に身体の中に流し入れる。
もう行かないと。
今日はヤマナカさんのお姉さんの葬儀だ。
なんでも行方不明になっていたが、先日遺体で見つかったらしい。
痛ましい事だ。
僕はと言うと、失恋から抜けられずにいた。
そうは言っても普段よりお世話になってるヒトなので行かなければと思った。
何より、肉親を無くす事は本人でも分からない気持ちの沈みがあるのだと知っているからだ。
斎場に行くと葬儀上に似つかわしくない"たんぽぽ"が添えられている。その横ちヤマナカさんとお母さんらしきヒトが立っていた。喪主ではないが彼女は凛としていて、それ故に辛いのだと感じられた。
葬儀も終わりバイト先の人達は帰って行った。
僕も帰ろうと挨拶をしに行くと、
「フジサキくん、最後まで付き合ってもらえないかな?」
と言われた。
「え?」
「心細くて…」
何で僕なのか分からなかったが…
彼女が仲良くしている人を見た事がないので、火葬迄ついて行く事にした。
心なしかヤマナカさんのウロコがポロポロ落ちている様に見えた。
火葬場に入る棺桶、その前にある写真を見てハッと気付く。
あのヒトに似ていると。
その後他の参列者(おそらく親族が大半だろう)は「若いのに残念だ」とか「みっともない」とか思い思いの事をヒソヒソと話しながら、別室へと移動する。
写真の事を考えながら歩いていると、ヤマナカさんから声を掛けられた。
「少しだけ外に出ない?話したい事があるの。」
そう言われて、僕がモヤモヤし始めた事と同じ事かと思い、一緒に外に出る。
外ではまだ暑い中涼しい風が吹いている。
煙突からは煙が上がってい。
一瞬さっきまでの考えは風に吹かれた様に、「人はこうやって空に上がって行くのかな…」などと思っていると、
「ねえ、話したい事って言うのはね…」
ヤマナカさんの姿がほぼ人に見え、ポニーテールが分かる。
そこで髪留めに気付く。
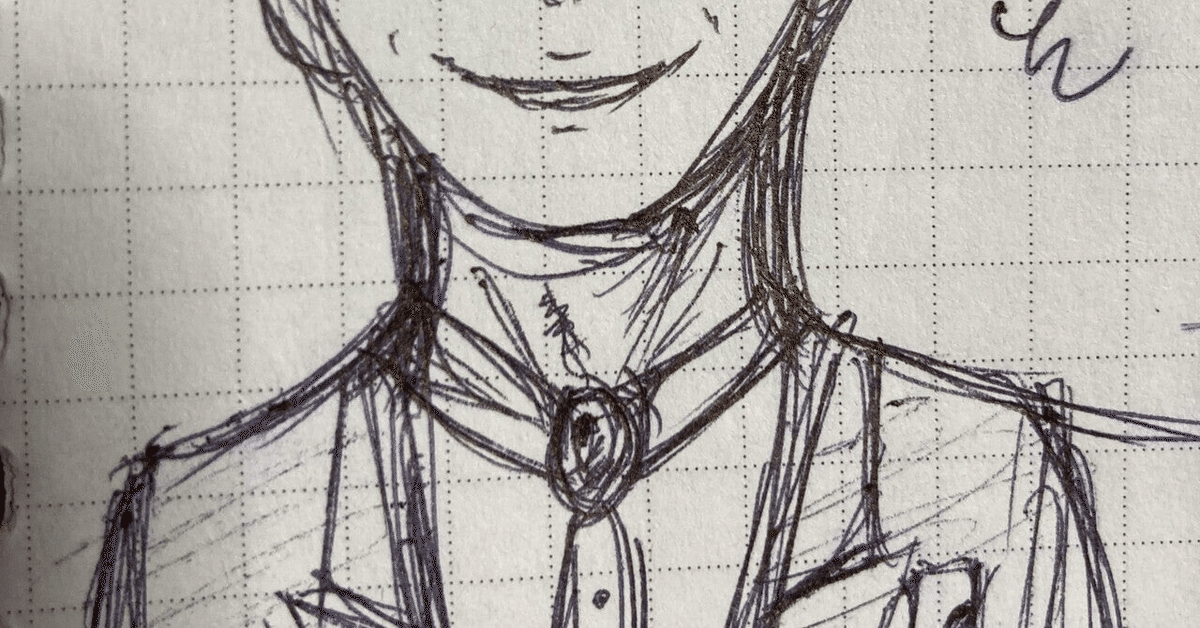
美麗な男
彼と出逢ったのは大学の構内だった。
彼は恐しいほど美しい顔立ちをしていた。
それまで色々なヒトを見て来たが、彼ほど美しく眼に知性を感じさせる男性はいなかった
声を掛けて来た時は驚いた。
未だ読みかけの"罪と罰"をネタを明かさず、葛藤や恐怖についての話を現代社会に例えて話してくれた。
話している内、成績は平凡だと分かり驚くくらいだった。
所謂普通の私には釣り合うとは思えない人なのだが。
音楽や本などの趣味が合い、その日のうちにデートの約束をして連絡先を交換した。
次の日のことを考えて2日後の土曜にした、不思議に思うくらい展開が早かった。
約束の日の夕方、彼は車で私のいるところまで迎えに来てくれた。
どこに行くか尋ねると、
「良いから任せて。」
とだけ言った。
街を離れ1時間ほど車に乗り、そろそろお尻が痛くなりそうだと思っていると車がゆっくり止まった。
「降りて。」
そう言われて降りると、彼は駐車場に車を停めた。
ふと見ると生垣に囲まれた、庭のある石造りの素朴な一軒家が建っていた。
「ここのご飯が身体にも良いし、美味しいんだよー」
落ち着いて見えた彼が、心なしか子供の様に嬉々としている。
中に入ると、素朴な外観を受け継ぎながらも、ブラックオークで揃えられたお洒落な家具と、セッティングされた机が目に入った。
木のいい匂いがする。
他にお客さんが居ないので、ドキドキして手持ち無沙汰になり付けていた髪飾りを触っていると…
それに気付いたのか、店員が来る前に椅子を後ろに引いた。
「どうぞ。」
気恥ずかしさで顔が赤くなってないか気にしながらも椅子に座る。
彼も今来た店員さんに椅子を引いてもらい、笑顔で座る。
その後は驚くほど美味しい食事と楽しい話で、どんどん時間が過ぎて気が付くと、あっという間に2時間が経っていた。
デザートも食べ終え、2人で食後のコーヒーを飲んでいると、
「これから素敵な所に連れて行きたいんだけど、時間あるかな?」
私は夢見心地でいたが、ハッと我に帰る。
と同時にさっき迄のドキドキがまた始まる。
「うん。」
「車でちょっと時間かかるんだけど大丈夫?」
「大丈夫。」
清水の舞台から飛び降りる気持ちだったが、務めて穏やかに返答した。
「じゃあ行こうか。」
店員さんにお礼を言い、店を出て車に乗る。
「眠ってても良いからね。」
ドキドキで眠れないと思ったが、満腹感で頭にモヤがかる様になり眠ってしまった。
目が覚めると、彼が満面の笑みでいるのが見える。
私は椅子に繋がれていて、周りにはライトアップされた"彫刻の様なもの"か幾つもある。
ガラス張りで、展示物にも見える。
暫くして頭がハッキリしてくると、その生々しい"彫刻の様なもの"が、何か分かる。
人だ…
私の表情を見て、彼は頷き耳元へ囁く。
「ようこそ、僕のミュージアムへ。」

ある店員の証言
ある小料理屋の店主マサユキという男は語る。
その"美麗な男"は優秀で、ヒトビトに分け隔てが無い。
しかし人の弱さを見つける事に長けていた。
彼は言う「この世は美しく、人の弱さも美しい。」と、
彼と初めて会ったのは、店の経営が上手く行かずコスト削減を料理にまで反映させ始めた時である。
少ないながらもお客様に恵まれていたのだが、この事が広がると信用に関わる。
彼はふと予約も無く入って来た。
もとよりお客様も減っていた矢先だったので、快く迎え入れた。
何よりこの美麗な男がSNSに紹介して、彼のフォロワーが押し寄せる事を期待したのは言うまでは無い。
それほど、彼の怪しい魅力は男でも見惚れるほどであった。
しかし、この浅知恵が良くなかった。
はじめ彼は料理に目を通して、「ワインの貯蔵庫を見たい。」と言って来た。
地価も安いので地下のワイン貯蔵庫は広く、ワインの質には自信があった。
彼は、料理に合うワインを自分で選んだ。
この瞬間マサユキの心に不安がよぎった。
その不安が経験に裏打ちされたモノだと後でハッキリ分かる。
彼は料理の内容に合う、私自身でもベストなワインを持ち出したのだ。
最初は料理を食べるのを楽しんでいたのだが、段々と笑顔が曇りはじめた。
彼はフォークとスプーンを置き、コチラを向き「少しだけお話ししたい。」と厨房に居る私に呼びかけた。
「なんでしょうか?」
すると、フォークとスプーンは片付けの合図を出している事に気付いた。
「何かありましたでしょうか?」
内心ヒヤヒヤしながら聞くと、彼は丁寧だが威厳を感じる口調で、料理や材料の穴を指摘して来た。そして最後に優しく笑顔でこう言った。
「経営も厳しいのでしょう。でも、少し工夫をすれば良いお店になりますよ。」
その後の彼のアドバイスは、的を得ていた。
客層の変化、料理の量、価格設定、から土地や材料費の運用にまで。
はじめは、「余計なお世話だ。」と思っていたのだが、調べていない素振りで言い当てるので、ある種、人として尊敬する域に達していた。
彼のいう通りにすると、利益が単純計算で10倍に上がった。
質の良い料理も提供できる様になった。
気持ちも右肩上がりになっていた。
彼が来るようになって2ヶ月くらい経ったある日。彼が地下のワイン貯蔵庫の改修を始めた。
コストがかかるからと彼1人でやると言う。
手伝うことがあるか聞くと、人差し指を立てる。
「出来てからのお楽しみ。」
そう言って潜っていった。
ワインを取りに行くと、カーテンが掛かっていて何やら作業しているのがうっすら見えた。
数週間経った日曜、彼が上がって来て、
「今日は僕の貸し切りにしてください。」
と言って出かけて行った。
5時間ほど経った頃だろうか。
彼が素敵な女性を連れて来た。
雰囲気を察し料理を提供する。
会話が弾んでいる。
不思議と彼にも"そういう女性"が居るのだなと思った。
デザートを食べ終え2人はヒソヒソと話をし始めた。
少しすると2人は笑顔でお礼を言い、彼はお金を支払い出て行った。
素敵な2人に嫉妬さえ感じた。
しかし、数時間すると彼は女性を抱えて入って来て、人差し指を立て地下へと潜って行く。
不安になり、少しして後を追う。
地下に入ると跡形も無く消えていた。
不安になりながら上で待っていると彼が1人で上がってくる。
人差し指を立て「ありがとう。」と笑顔で言う。
2ヶ月に一回の(決まって第二日曜)にそれが続いた。
男性らしきヒトの時もあった。
3回目ごろ言い知れぬ不安と恐怖に耐えられず、彼の後を追い地下に行くとまた誰もいない。
地下で待っているとかすかに物音がする。
その音に耳を傾け近づいているとワイン棚に頭をぶつけそうになる。
するとワイン棚がスライドし、彼が出てきた。
内心ギョッとなりながらも、彼に問う。
「あのヒトはどこへ?」
すると彼は「美しく有るよ。」
と訳の分からない言葉を発した。そして、
「見せてあげるよ。」と笑顔で言う。
不安の中、半分強制的にワイン棚の裏にある階段に案内される。
「ここは僕のミュージアムだ。」
見ると妖しくライトアップされた亡骸が、恐怖に顔を歪めている。それに反して生き生きとした肌艶、筋肉の張りで彫刻の様に飾られている様だった。
美しい…
一瞬の思いに不快感を感じ、吐きそうになる。
慌ててトイレに上がり胃の中のものを出し尽くしてしまった。
それからは手伝いと、彼曰く"美術品"と外の監視。が習慣になっていった。
スマホに何故か増えた監視カメラがアップロードされていた。
傍観者に成り果てていた。
ある日珍しく土曜、しかも第一土曜日に女性を連れて来た。
後で気づくのだが、どこと無く最初の女性に似ている。
いつものように料理を出し、送り出す。
地下に行った後に傍観していると、彼女からいつもと違う雰囲気が漂っていた。
最初こそ恐怖と悲しみが見えたものの、なかなか表情が歪まない。
彼の言葉も最初こそ雄弁だったが、だんだん疲れが見え始めると。
上からと物音がする。
慌てて監視カメラをスマホで見ると人が数人ドアをこじ開け入って来ているのが見えた。
彼らが地下に辿り着くまでそう時間がかからなかった。
彼らのベストには"SIT"と記載されていた。

彼女の想い
火葬場の外で、振り返った彼女は見知った顔だった。
彼女は話し始めた。
約一年前姉が姿を消した。
姉は大学に入り一人暮らしをしていた。
7月12日。
その日は姉の誕生日で例年の様に"おめでとう"をLINEを送っていたのだが、いつまでも返信が来ない。
母は「彼でも出来たのだろう。」と言っていた。気になる人がいる話も聞いていたので、その日は返信を待たずに休んだ。
しかし、2、3日経っても連絡がない。
心配になり、姉の家を訪ねた。
部屋は整頓されており。衣類が数点無くなっていた。
その月は家賃が振り込まれていたので、警察も「旅行だろう。」と相手しなかった。
確信を得たのは、姉が持っていたアクセサリーケースを見た時である。
祖母の形見のネックレスは有るのに、同じ位大事にしていた、"鈴入りのたんぽぽブローチ"が無くなっている事に気付いた。
警察は相手にしてくれないと思い自分で姉の"行方"を探す事にした。
男のカゲは見つからない。チャンスを逃したく無いと思い、必死に勉強して翌年姉と同じ大学に入った。
その頃にはある程度覚悟はしていたのだと思う。
姉と同じバイトをしながら大学通い、勉強と手掛かり探しに費やす日々。
人が怪物に見え出す様になると、更に疲弊していった。
男の人ビトに接する時は見抜く癖が付き、バイトでは気を遣う。
そんな中、彼と街で出会った。正確には出会って居たのだが…
疲れで足がもたつき人とぶつかる。
相手の声で男の気付き、優しくだけど鋭く微笑みかけると、彼はおどおとした様子で、しかしながら誠実に接してくれた。
ある時バイト先でフジサキ君が子どもに、しゃがんで「ありがとうね。」と優しく言い、頭に手を当てていた。
その瞬間彼の不気味な道化の様な仮面が崩れ、先日会った男の人の顔が見えた。
その瞬間から彼への信頼は大きくなっていった。
しかしながらバイト先で、彼の目に映る私は"冷酷なトカゲ"らしい。
その見え方はある種、私の心の冷たさを見抜かれているようで恥ずかしく、正体を明かす事はなかった。
しかし2日後、家の近くの坂を下っていると、彼が上がってくる。
私は嬉しくなり、立ち止まり声を掛ける。
そこからドキドキしながらお茶に誘った。
彼は話し下手だがお茶目で、私を気に掛けてくれる。
姉とお揃いの物が昔から欲しかった、お願いしてたんぽぽのブローチを頼んだら、最初は渋りながらも、何にでも使える様に工夫して作ってくれた。
それも嬉しかった。
その時彼と話していると、私に似た人がバイト先にいたことを聞く。
その人は姉だった。しかしおかしなことを言う。
姉はドストエフスキー作の"罪と罰"を読んでいたと。
姉は絶対に読まないのに…
そして手掛かりだと気付く。
もう少し話していたかったが、日曜に会う約束して別れた。
その足で警察へと向かった。
今まで調べたことなどを警察で話すと、親身になって聞いてくれた。
どうやら関連事件を調べているらしく。
状況から大学関係者とまで突き止めているが、誰か分からない。
私は協力を申し出た。
本の事は秘密にして、
「絶対に声を掛けて来ます!秘策があります。認めてくれないと勝手に動きます!」と言うと、話合いの結果、最新のGPSと盗聴機をつける事、直ぐに保護出来る範囲で見張る事を条件に協力させてくれる事になった。
次の日、本を読む事に力を注いだ。今思えばカケだった。
昼休み、恐しいほど美しい男が声を掛けて来た。
その知性と瞳の奥に冷たさが見えた。
私は直感した。
"この男だ!"と。
男は引きつけられるものがあり、女性の扱いに長けていた。
私はその誘いに乗った。
次の日大学から少し離れた所にで待っていると、男はミニで迎えに来た。
私は嬉しそうに車に乗る。
街を離れ、お尻が痛くなる頃に車が止まった。
降りると小さな石造りの一軒家が建っている。
中に入ると恥ずかしそうに演技し、ブローチを細工した髪飾りのスイッチを静かに入れる。
食事は美味しくて、話は楽しい。
雰囲気にのまれそうになる。
デザートを食べ終えた頃、彼から更なる誘いがある。
何があるか分からないし怖かったが、決心を胸に誘いに乗る。
店を出て車に乗ると、睡魔におそわれる。
不安と希望を胸に眠りに落ちた。
目が覚めると、恐怖と悲しみが襲って来た。
私の目の前にはガラス張りになっており、その奥には、男が"ミュージアム"と称する石造りの広間が広がっていた。
そこには布の切れ端で飾られた、人がライトアップされている。
その中に姉の姿があった。
私は気丈に振る舞い、男の文句に耳を傾けていた。
男は恐怖した顔が美しく見えるらしい。
男の狂気に負けない様に耐えていると、上から物音がした。
男は気付かない。
程なくすると、お洒落な薄着の私とは反対の物々しい格好をした警察の人達が入って来て、さっきの店の店員らしき人と、男は捕まった。
彼女はそこから先何をどう言おうか迷っていた。
「ブローチをこんな使い方をした事。
日曜に会いに行けなかった事。
ごめんなさい。」
その言葉が言いたい訳ではないが、その言葉しか出て来なかった。
フジサキは彼女の話を黙って聴いていた。
自分の中に驚きと安堵、モヤモヤした気持ちを感じたが、瞳を見てそれが本当の"言葉"だと分かった。
そして、ヤマナカの頭に手を乗せ、
「辛かったんだね。頑張ったんだね。」
涙が頬を伝うのが分かる。
彼女は嗚咽をもらしていた。
フジサキはそっと抱きしめた。嗚咽を覆い隠す様にして…

君と僕
ある晴れた日。
公園でシートを芝生に敷き、2人は木のカゴから出したサンドイッチを頬張り、水筒の麦茶を飲んでいる。
この頃は事件とは関係ない話が出来るようになり、くだらない話で盛り上がっていた。
ふと沈黙がよぎる。
彼は聞きたかった事を聞いてみる。
「ところで名前はなんで呼べばいいかな?」
彼女は下の名前を知らない事に感付き、眉をひそめる。
彼はそれに気づき、バツが悪くなるが、思い切って「教えて!」と、手を合わせる。
「リンネよ。山中凛音。」と笑顔で言う
「似合ってる。」彼はほほ笑む。
そして「僕の番だね。僕の名前は…」と言いかけると彼女は、
「知ってる。最初に覚えたよ!タカシ!藤崎隆!」と自慢げに言う。
彼は恥ずかしくなり「へへっ」と笑うと、彼女は大笑いで返してくれた。
ー夕暮れ時、秋の風と共に鈴虫が鳴いていたー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
