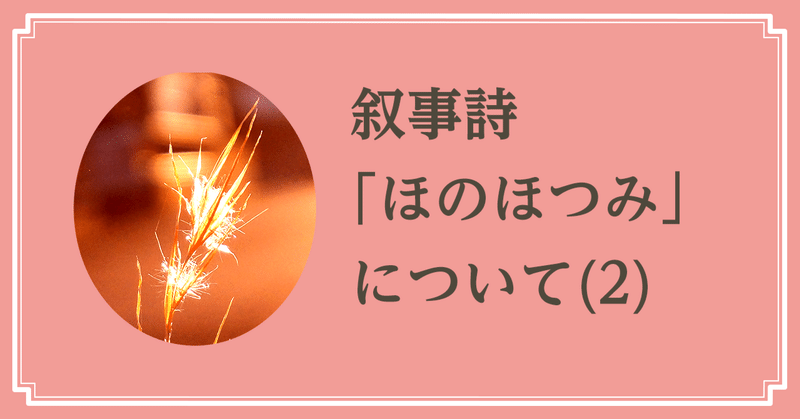
語り伝える「叙事詩」、「いま」なぜ必要なのでしょう?
「叙事詩ほのほつみ」の「叙事詩」って?
「叙事詩ほのほつみ」は、ことのはを風に伝える神、ほのほつみにまつわる叙事詩です。ことのはとは、ことばの古い言い現し方ですが、「事」の「葉」、つまり大切なことがらを書いた「葉っぱ」なのです。伝えたいものやことがらを、一枚の葉に託し、どこまでもどこまでも風に乗せて運んでいく、心許ないけど、ひとの思いを乗せて風に運ぶ、そんな役割を担う神、それが「ほのほつみ」であり、小さな小さな穂絮のような神なんですね。
そのほのほつみという神が見守り、伝える戦の物語が、「叙事詩ほのほつみ」です。では、「叙事詩」とはどんなスタイルをもっているのか。そして、古今東西、我々人類が共通の文芸として、叙事詩というスタイルをどう手に入れるべくして手にいれたのかを理解いただけると、この一風変わった物語をより深く、知り、「ほのほつみ」という小さな神をより好きになれるのではと思うのです。

叙事詩の古典といえば……
叙事詩といえば、古代ギリシャのホメーロスの「イーリアス」(呉茂一訳,2003,平凡社ライブラリー,上・下)、「オデュッセイアー」(呉茂一訳,1971,岩波文庫*)がよく知られます。
ほかに、フィンランドにリョンロットが蒐集した叙事詩「フィンランド国民的叙事詩・カレワラ 」(**森本覚丹訳,1983,講談社学術文庫,上・下)があります。
*「オデュッセイアー」の日本語の訳本は、呉茂一訳の語り口調が古風で格調が高くお薦めです。現在は岩波文庫の古書のみとなっているようです。
**訳者の森本覚丹は、明治29(1896)年生まれ、講談社文芸文庫は昭和13(1928)年の覚丹の訳本を復刻したものです。また、「カレワラ」を題材にした、フィンランドの作曲家、ヤン・シベリウスの交響詩「トゥオネラの白鳥」がよく知られます。
叙事詩のスタイルとは?
叙事詩のあらましをまとめれば、以下のようになるでしょうか?
・ある民族固有の
・口伝で、語り受け継がれてきた
・神の視点からの
・一定の韻律をもった詩(うた)
・詩の主題で多くは戦(いくさ)を扱っている
叙事詩が描いた戦の物語が、歴史上のほんとうの事実であるかどうか? 厳密にいえば100%の史実ではありません。叙事詩が生まれた時代、ことばのみで語り伝えなければならなかったはるか昔、映像をはじめ記録性に優れた現代と違い、伝える手段、メディアに限界があります。また、語り継がれゆくなかで、語り手が聞き手を意識し、少しずつ脚色が加えられていったと思われます。
ただ、事実でないからといって、史実を含まないかかといえば違います。
たとえば、世界史で一度はだれもが習った、ドイツの歴史学者、ハインリヒ・シュリーマンは、「イーリアス」の描くトロイア戦争は戦の真実を伝えていると直観し、トロイア遺跡を発掘しました。
また、ひとが理由のいかんを問わず、戦を繰り広げ、家族、一族がちりじりになり、ひととひとが殺し合う。なぜむごたらしい戦をしなくてはならないか、ひとがひとを殺めてしまう性、罪深さの真理を、神の視点から語っています。
わが国にも「叙事詩」はあった!?
では、わが国に叙事詩はあったのか? この疑問に、民俗学者の折口信夫(おりぐちしのぶ・1887~1953)が、「語部と叙事詩と」という短文で答えています。
ずばり、「私は、語部の職掌及び、其伝承した叙事詩の存在した事を、十数年以来主張して来た」。
折口は、「語部と叙事詩と」で、叙事詩の起源を以下のように指摘します。
「とこよのまれびとが名のりによつて、土地の精霊の名のりを促す形の一つ前の姿は、まれびと自身の種姓を名のつて地霊を脅かす方法と、地霊の種姓を、こちらから暴露する為方とがあつた」
この折口の一文は、冒頭の「とこよ」と「まれびと」がキーワードです。
叙事詩に出現する「とこよ」
「とこよ」は、「常世」と書きます。永遠の世界、死者の赴く世界と解釈されますが、それは通り一辺の解釈で、間違っていないが、もっと深く、広い意味を有しています。
折口の常世をより深掘りしたのが、民俗学者の谷川健一(1921~2013)です。折口が沖縄に行き大きなインスピレーションを得たように、谷川もまた、沖縄で「ある風景」に触発されます。その風景とは、沖縄のニライカナイの世界、サンゴ礁に囲まれた洞窟に眠る死者の「青」の世界です。そこは、人生を過ごした自分の島を見守りながら、遙か遠く、外海の陽が昇る東の永遠の世界、ニライカナイを臨む場です。
谷川は、沖縄を何度も訪れ、ニライカナイ、すなわち「常世」は、沖縄の島々にあるだけでなく、「古事記」「日本書記」の記紀神話が伝えるイザナミ、スクナヒコナなど異界の「常世」に赴く神とのつながりを見いだします。そして、津々浦々の常世の痕跡を求めて旅をします。各地の伝承、風土記を手がかりに、ときには考古学者のように緻密に、ときに想像のつばさを羽ばたかせて自由奔放に、常世の世界を求めてさまよいます。そして、谷川はそれらを「常世論」(1989,講談社学術文庫)にまとめました。
谷川は、常世に、仏教やキリスト教が入る前の日本列島に暮らすひとびとの根底に眠っている意識を見いだしました。常世は、黒潮に乗り、沖縄の島々から陽の昇る東へ、東へと広がって広がった、と。
インスピレーションの強かった折口信夫の「常世」を、谷川健一は、ひとつずつ痕跡を求め、いまでいうビーチコーミングのように細かな破片を探し当て、「常世」の実像を明らかにしていったといえるのかも知れません。

叙事詩を語る「まれびと」
折口のもう一つのキーワードは「まれびと」です。「まれびと」は、「客人」と漢字があてられますが、たんなる「客人」でなく、異界から一定のある時季に訪れる「神」を指します。
異界から訪れる客人は、畏怖されながらも客として大切にもてなされ、饗応されます。その場で、集まった連中を前になぜ私がこの場に来たかを語りはじめます。そして、なぜあなた方が、ここに「在る」のか、はるか昔からの先祖の来歴、いわれを「語り」ます。語る上で、口調は一定のリズムをともなう、つまりそれが「詩(うた)」です。「詩」に欠かせないのが楽器です。楽器は、竪琴であったり、口琴や太鼓など民族によりさまざまです。
「客人(まれびと)」が異界から現れて、「種姓(スジヤウ」を解き明かすスタイルは、どこかで見たと思いませんか?
そう、中世にできあがった能の構造そのものです。
シテという主人公は、異界からの出現を示す面を身につけ舞台に登場。見物人の代表であるワキに「あなたはだれか」と問われ、はじめて「種姓」を明かします。
能の仕組みや完成にいたる歴史や特長については、野上豊一郎「能の話」(1940,岩波新書)が、簡易明快に説明しています。
異界の客人の姿・形は、日ごろ見慣れない異形で、鬼であったり、奇妙な鳥であったりします。その非日常の異形ゆえに、ひとびとは畏怖し、敬います。
定期的に異形の客人が訪れる伝承は、日本列島のあちこちに
「来訪神」の行事として今も伝わります。
最近では全国に伝わる「来訪神」が、世界文化遺産に登録されました。「文化遺産の世界 Vol.34」(2019年, NPO法人文化遺産の世界)を見れば、現代社会にも、縁遠いものでなく、いやむしろ、神が暮らしのなかに脈々と伝えられていると気づきます。

わが国の叙事詩はどう語り伝えられてきたか?
折口の考察、それをより深めた谷川の考察などから、叙事詩というスタイルは、わが国にも、神語りとして古代以前から営々と受けつがれていた。それは、ひろく古代ギリシャやフィンランドなど世界各地の共通の語り文化、伝承文化であったのです。
8世紀に太安万侶が|編纂した「古事記」は、日本列島に伝わる数多くの詩と物語が収録されています。
「古事記」の序文によれば、その多くは、28歳の「聡明な」稗田阿礼に「誦み習はしめた」(武田祐吉訳注「古事記」,1977,角川文庫)といいます。
その編纂は大変だったようですが、ここで大切なのは、阿礼は口誦で伝えられてきた物語や詩を、「誦」むように、つまり「うたう」ように覚えたという点です。稗田という姓から、さほど身分は高くない人物像が浮かびますが、おそらく「語部」のような部民のイメージに近かったのではないでしょうか?
「語部」が古代の大和朝廷成立後に、天皇の即位の儀礼、大嘗祭で重要な位置を占め、なくたはならない存在としてむかえられた経緯は、歴史学者の井上辰雄(1928~2015)が「古代王権と語部」(1979,教育社)で詳しく述べています。
こうして、わが国の津々浦々に伝わる物語や詩、つまり叙事詩は中国から輸入された文字を用いて「古事記」、また「日本書記」やさらに各地の風土記などに書きとどめられ、後世に伝えられました。その意味で、メディアとしての文字の力は偉大です。
誤解を怖れずに言えば、中世の「平家物語」も、神語りとしての叙事詩です。平家と源氏という戦の憐れさ、ひとの世のはかなさを、琵琶法師がうたい、語る。構造上は、叙事詩です。もっとも、「平家物語」は、すでにわが国に広く信仰されていた仏教の世界観が反映されていますが。
戦の火が消えない「今」だからこそ語り文学の創造を
こうして視野を広げると、インドネシアでいまも演じられる影絵劇、ワヤンも、叙事詩のスタイルを受けついでいると、わかります。
ワヤンで語られる神々の多くは、インドの叙事詩「マハーバーラタ」に登場する神々で、松本亮「マハバーラタの蔭に-続ジャワ影絵劇芝居考」(1981,ワヤン教会)にワヤンの神物語の詳細が書かれています。
少し補足すれば、「叙事詩ほのほつみ」の第3場「ヒンジャブ国へ進軍、神宿りし鳥」の 5話「語り部の預言」は、ワヤンの影絵劇をモチーフにしました。
文字をもなかった時代、人びとは、語部が口伝えに語る物語を聞いた。そのモチーフは、多くは戦であった。そして、語りという文芸スタイルは、現代までも、さまざまな形を変えて生き続けてきた。そこに、「文字」を通して伝えるのでない、ひとを前に肉声で語る叙事詩の意味があります。
映像の世紀といわれる現代、インターネットという伝達手段を手に入れ、だれもが気軽に発信できる時代となりました。聴衆を前に語り伝える「叙事詩」は、もはや古くさい、前時代の黴の生えた文芸でしょうか?
ついこの間、約1世紀前の第二次世界大戦の体験を肉声で語る、「戦争語部」という伝承者が、地道に活動を続けています。人類史上稀な原子爆弾の被爆体験者の「語部」は、たいへん尊い存在です。しかし、1世紀という時代の流れに伴い、高齢化し、実体験を語れるひとは少なくなっています。
次の時代に悲惨な戦を語り、どう伝えるか?
2020年のロシアによるウクライナ侵略、2023年のハマスの攻撃を機にはじまったイスラエルのパレスチナ・ガザ地区への侵攻など、戦の火は世界でいまも燃え広がっています。それらは遠いところで起きた、映像で見るの世界の出来事でなく、わずか1世紀前に行われていたひとがひとを殺め合う、悲惨な出来事です。
繰り返す戦の悲惨、罪深さを、他人事でなく、自分事として受け入れるかが決めてです。私は、インターネットという気軽な情報発信ツールを手に入れた現代だからこそ、語り伝える詩、叙事詩の可能性が引き出せると感じています。
「叙事詩ほのほつみ」の5場にわたる物語は、ついこの間、約1世紀前の第二次世界大戦を、ことのはを風に伝える神、ほのほつみの視点で「語る」ために創作しました。
現代の文学や演劇は、「私」を主テーマに、書かれ、読まれます。それは、たとえば、スタイルを厳格に護る伝統的な形式への批判として起きました。表現は、本来自由なものなのではないか、そこを拠り所として現代の文学や演劇は生まれました。でも、自由とは別の意味でいえば「なんでもあり」で、手探りでゼロから産み出すのは大変で、それこそ命がけです。
まあ、それも悪くはないけど、歴史の荒波にもまれ、生き残った表現をすくい出し、光を当て、新たな価値を見いだす。それも「あり」なのではないか? 自由な表現でもあり、なおかつ、一定の形式を踏まえたスタイル、現代の次のポストモダンといわれる時代のスタイルとして、叙事詩を再生できないか、「叙事詩ほのほつみ」はそんな試みのひとつです。
「叙事詩ほのほつみ」は、戦の事実でなく、戦の真実を、語りを通して伝えたいと考え、創作しました。それは、現代の「いま」を生きるわれわれが、前古代に誘う風の声に耳を傾ける所作でもあるのです。
「叙事詩ほのほつみ」の5場ごとのあらましは
記事「叙事詩ほのほつみについて」をぜひお読みください。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
