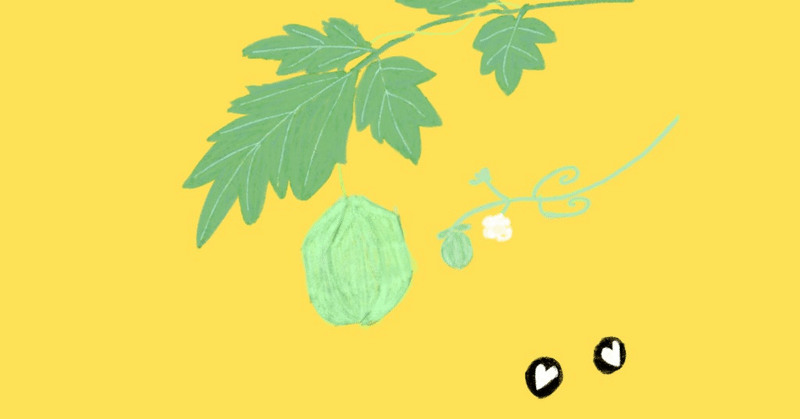
【短編小説6】子どもの情景
すずや町にある祖父母の家で奏が母と四人で暮らしていたのは、幼稚園に入る前。父が隣の県に単身赴任をしている数年間のことだった。物心がつくかつかないかの時分だったので、今では記憶は遠く断片的で、そのすべてが春の霞に守られているようだ。
奏のもっとも古い記憶は、祖父母の家にある。階段を上って右手にある角部屋。二階にはもちろん一人で上れなかったし、危ないからと滅多に連れて行ってもらえなかったのだろう。奏は自分がいま特別な場所にいるという高揚感と、心もとなさとに包まれていた。
そこは母の自室だったのだと思う。窓からは、遠くに大きな樹木の先が見えた。
やわらかい風に乗って、キジバトの鳴く声が聞こえてくる。あの樹に住んでいるのだろうか。
奏がせがむと母が抱きかかえてくれた。窓の下に続く近隣の家の屋根々々と、その向こうに、雲一つない青空に枝を広げる大きな緑の塊が見えた。背後では、先ほど母がかけてくれた「三びきの子ぶた」という童話の朗読レコードが、楽し気なピアノの音色とともに流れていた。
祖父は仕事をしており、夜にならないと帰宅しなかった。どっしりと威厳を感じさせる人だったが、根が陽気だったのだと思う。家にいるときはよく奏を膝に乗せて冗談を言いながら、藤で編まれた「はと車」や、木彫りの馬や太鼓など、趣味で集めている郷土玩具で遊んでくれた。
祖母は自宅でお華を教えていた。そのため、家にはいろいろな場所に花が生けてあったり、盆栽が飾ってあったりした。ほのかに届くいい香りに奏が振り向くと、茶の間の飾り棚で盆栽の梅がほころんでいる。こんなふうに、季節の移り変わりを感じて奏は育った。
記憶の中で、祖父母の家はいつもスッキリと片付いている。お華の生徒さんが出入りするせいもあるだろうが、何より祖母の性格によるものだと思う。振り返ってみると祖母は実によく片づけをしていて、家をこざっぱりと整えていた。奏は毎朝、祖母が玄関のタイルや茶の間の畳に箒をかける音で目覚めたものだ。その習慣は二〇年が経った今朝も繰り返されているのだろう。廊下の隅々から凛とした規律の気配が伺える。
「あれ? あの頃は、あんなに高く見えたのに」
奏は、祖父母の家の階段を見上げて驚いた。家の奥から祖母が聞き返すので、奏は手を拭きながら茶の間に戻る。ちょうど祖母が冷えた麦茶と梅のお茶菓子を二人分、お盆に乗せて持って来た。奏の記憶にある姿より一回りも二回りも小さく見えたが、相変わらず背筋がピンと伸びて、整った身なりをしていた。短い白髪にはきちんとパーマがかけられており、淡い紫色の洋服には小ぶりなユリのネックレスが揺れる。
「お婆ちゃん、あの階段ってそんなに段数が無かったんだね。それに、もっと急だと思ってた。距離も長くて、途中の少しだけ暗いところを過ぎると、別世界にワープしちゃうかもしれないって私、本気で思っていたんだよ」
奏がそう言うと、麦茶をグラスに注いでいた祖母は、華奢な眼鏡の奥で目を細めて笑った。
「だってあなた、前に奏ちゃんがこの家に来たのは、まだ子どもの頃だもの」
大きな一枚木のテーブルが、今日もつやつやと光っている。軽く腕を乗せると、ほどよく削られた縁がやわらかく触れる。右手には縁側があり、ちょっとした庭に松や南天の木が植えられている。そして、日除けにと張られた網には、風船カズラの細い蔓が這っている。小さな星くずのような白い花は咲き終わり、生き生きと茂った葉の間で小ぶりな風船が揺れている。
かつて祖母の手から、風船カズラの種をいく粒かもらった事が思い起こされた。白いハートの柄の入った小さな黒い球体を、奏は「きっと特別な品に違いない」と感じて見入ったものだ。
あの頃と変わらず、先ほどからずっとセミの声が聞こえている。不思議と家の中では、その静けさを引き立てて、耳に心地いい。
「あんなにおチビさんだったのに、すっかり立派になって」。奏をしげしげ見ながら祖母は言った。「今日はありがとうね」。
「ううん、とんでもない」
父の単身赴任が終了して、母とともに実家となる新居に引っ越してからも、奏は小学校を卒業するまでは毎年、夏休みや冬休みなどに数日ほど祖父母の家に泊まりに来ていた。母の弟である叔父さんが結婚を機に同居してからも、数年間は泊まりに来ては次々と生まれる従弟たちと遊んでいたが、中学に上がると正月の挨拶に立ち寄る程度になった。
いつの間にか、叔母さんが祖父母に話しかけるときに敬語ではなくなり、慣れた手つきでお茶を淹れてくれる。従弟たちも日頃そうしていると分かる様子で、部屋の中で自由にくつろいだり、去年までは無かった子ども向けのカラフルな棚から、勝手に本を取り出して見せてくれたりするーー。今や部外者は自分のほうであると肌で感じ、理解していったからだ。
奏の両親は仲が悪く、奏の家は常に荒れていた。どの部屋にも大量のモノがごちゃごちゃと積み上げられ、散らかり放題の家の中で、母は恨みがましく愚痴ばかり言う。彼女にしつこく責められ続けた父は苛立って、母と奏に暴力をふるうという日々だった。奏はたいてい泣いているか、アトピーで腫れあがった全身を搔きむしって血を滲ませていた。
そんな中で祖父母の家は、奏にとって両手をのびのびと伸ばして深呼吸ができる、唯一の場所だった。そこが、ゆっくりと自分だけの居場所でなくなっていく感触は恐怖であり、そこに自分の知らない日常があることを確信する瞬間は、耐えがたい絶望だった。
部活を理由に泊まりに行かなくなって、いつの間にか一〇年が経っていた。奏はすでに成人し、現在は東京で就職している。実家を出て以来一度も帰郷していなかったが、今年のお彼岸にふと思い立って祖父の墓参りをしたとき、祖母と久しぶりに再会した。
「奏ちゃんは、お掃除が上手ね」
墓石を磨く奏の手つきを見ながら、祖母はこう誉めてくれた。
「ありがとう。掃除が好きなんだ」
一瞬、敬語で話すべきか迷うほどに奏は距離を感じていた。それでも祖母は、「一人暮らしをしているんだって? 自分でお部屋を掃除しているの? えらいわねえ」「ごはんはちゃんと食べているの?」と、まるで子どもに接するように話しかけた。祖母は昔から使っている白い日傘をさしており、淡い紫色の着物には、白い彼岸花の帯留めがやわらかな陽に輝いていた。懐かしい。何より、奏のわずかな緊張をたやすく溶かすほど、あたたかいまなざしだった。
「掃除が好きなのは、お婆ちゃんの血が流れているからかも」
そう軽口をたたいたことがきっかけで話が弾み、ひょんなことから次の連休に祖母の家で片づけを手伝うことになった。低いところはいつも通り掃除できるのだが、納戸の高いところには手が届かず、来客用の食器なども一度見直して整理したいと言う。
お彼岸に交わした約束を守るべく、奏はこうして夏の休暇を使い祖母の家に来ているのだ。
麦茶を飲み終えると、祖母は茶の間の裏口にあたる襖を開けて、細い廊下を挟んで正面の曇りガラスの引き戸を開けた。
四畳半ほどの納戸には中央の棚も含めて、釣りの道具やら漬物用のカメやら、いろいろなものが所狭しと並んでいる。しかし、どれもいつでもすぐに取り出せるように整頓されている。
「悪いわね、お願いできるかしら」
そう言うと祖母は、壁側に立てかけていた小さな脚立を取り出した。
まずは二人並んで立ち、祖母の指示にそって不要なものを勝手口まで運ぶ。今後も使うものは、棚の低い段に移動することになった。
とはいえ、もともと重いものは入り口付近に収納されているし、すでに大半が低い段に片づけられている。上のほうにあるのは、虫取りカゴやらアイスボックスやら、軽くて簡単に取り出せるものばかりだった。
「もし奥のほうに何かあったら教えてね」
奏が脚立に手をかけると祖母は言った。見渡すと、確かに奥のほうでいくつか小さなものが薄っすらホコリを被っている。奏はそちらに手を伸ばすと、指先で手繰り寄せてみる。
「お婆ちゃん、ホットプレートの説明書があるよ」
「ちょっと見せて。ああ、これはお婆ちゃまがもらおうか。奏ちゃんがここで暮らしていた頃、みんなで縁側で焼肉をしたときの説明書だわ」
「古い!」
「ずいぶん懐かしいものが見つかった」
「みんなで焼肉をしたんだね」
「そうよ、奏ちゃんがアニメで山賊を見て、私も山賊パーティがしてみたいって言ったのよ。可愛らしいでしょう? それはおしゃまな子だったの」
祖母につられて、奏も笑った。
片づけをしている間、奏はほとんど脚立に上って棚の奥を覗き込んでいた。祖母は奏を見上げており、二人はものを通してあれこれと話した。作業の傍らの他愛ない会話だったお陰で、気負わずに済んで心地よかった。
すべて整理整頓し、薄く溜まっているホコリをハンディ掃除機で吸い取って水拭きまでしても、三〇分もかからずに片づけは完了した。
中央の棚には来客用の食器セットがいくつかあったが、春夏用と秋冬用を祖母が一セットずつ選ぶと、それ以外は勝手口まで運ぶ。これもすぐに終わった。
「わあ! お陰ですっかり片づいた」
小さく両手を上げて、祖母がおどける。
「それじゃ奏ちゃん、手を洗っていらっしゃい」
祖母はそう言うと、細い廊下の左奥にあるキッチンに向かった。奏は右手に進み、再び洗面所で手と顔を水で洗った。水は人肌まで温まっていたが、やわらかく、気持ちがよかった。
茶の間に戻るときに、再び階段を見上げる。目線の先で、二階の窓に夏の西日の気配を見た。輝きを増した夕方の光は今日も奏の心を躍らせるが、一方で、一日の終わりの気配に胸が締め付けられた。そろそろ、帰らなければならない。
「お盆が来る前に片づけられて、本当に助かったわ。ありがとう」
一枚木のテーブルでは、細長い葉っぱの描かれたガラスの皿に、食用花の寒天が乗っている。夏になるといつも祖母が作ってくれていた。銀色の箱型の器に流し込み冷蔵庫で冷やしていたのを、奏はわくわくしながら覗き込んだものだ。
寒天に沈んでいるのはキク科の食用花で、寒天は下のほうになるにつれて、透明からオレンジ色のグラデーションになっている。一口含むと、ひんやりと舌の上で崩れる。記憶の中と同じ味が広がった。スッキリとした甘さに、花びらを噛むとほんのり苦味が広がって大好きだった。
奏はふと、今日はどうしても祖母に伝えなければいけないことがあったと思い出した。しかし、それが何だったのか思い出せない。
「お婆ちゃん」
奏が顔を上げると、祖母は華奢な眼鏡を指先でそっと引き上げながら、微笑んでいる。
ずっと伝えたかったはずで、お彼岸に再会したときにもうっかり忘れてしまった。それをとても後悔していて、今日こそは伝えようと決めていたのに。どうしても思い出せない。
奏の顔を見つめたまま、祖母はうなずいた。
「もう、じゅうぶん。お陰様ですっかり片づいた」
違うの、お婆ちゃん。私ねーー。
今伝えなければ、絶対に後悔する。だって、何年もずっとそうだったのだ。叫びにも似た想いが、声にならずに喉で詰まる。祖母は相変わらず静かに微笑んでいる。
そこで、目が覚めた。
一瞬、すずや町にある実家の自室で目覚めたのだと本気で信じていた。それほど深い眠りに全身が浸っていたのだ。ゆっくりと身体に感覚が戻ってくると、ようやく東京の自宅で目覚めたのだと分かった。
「夢か」
当たり前ではないか、祖母は奏が中学三年生の秋に亡くなっているのだから。
枕元からスマホを手繰り寄せると、そろそろ明け方に差し掛かろうかという時刻だ。
「変な時間に起きちゃったな」
そうつぶやくと、もう一度眠ろうとタオルケットにもぐり込む。仕事に影響がないといいのだが。そんな思いが脳裏をよぎると、すぐに今はお盆休みの最中であったと思い出した。
何気なくスマホを開くと、眠りに落ちる直前まで見ていた画面が表示された。すずや町までの新幹線の料金、そして、すずや町にある寺の一覧だ。奏は毎年この季節になると同じことを検索し、そしていつも、遠い記憶で一度だけ見た祖父母の墓にはたどり着けないままだった。
何年か前、上京して以来初めて実家に電話をかけて、母に祖父母が眠る場所の名前や道順を尋ねたことがあった。しかし一分も経たずに口論になってしまい、叩き切った電話を再び奏がかけることはなかった。
母が嘘をついており、祖父母の墓の場所を知らないはずがないというのは、奏の思い込みだろうか。
先ほどまで全身を包んでいた、あたたかな光景が、まだ近くに感じられる。
祖母と最後に口を聞いたのも、奏が中学三年生の秋だった。
珍しく祖母が家を訪ねて来てくれて、学校にも行かず自堕落にすごしている奏に声をかけた。
自室で寝ていた奏は気づかなかったが、祖母はしばらく前から来ていたようで、客間で母と話し込んでいたそうだ。
「顔が見られてよかった。お婆ちゃまはそろそろ帰るからね。奏ちゃん、これを」
そう言うと、祖母はバッグから百貨店の袋に入った新品の白いソックスを取り出して、奏に手渡した。
どうしてこれを?
そう質問するよりも先に、奏は反射的にそのソックスを力任せに払い落としてしまっていた。
奏が通っていた中学校は校則の厳しい進学校で、奏は何一つ校則を守らなかった。成績だけはそこそこ良かったが、かえってそれが教師の癇に障ったのだろう、何をしても何をしなくても奏は悪目立ちして、毎日怒鳴られてばかりいた。
不登校になった直前に、奏は男性の美術教師からソックスの丈が短いことを執拗に責められて、とうとう怒鳴り合いの末に手を上げられそうになっていた。奏に何か信念があったわけではない。もともと買った時点でソックスの丈は校則の許容範囲のギリギリで、洗濯するうちにかなり縮んでしまった。それを放置していただけなのだ。きっと祖母は、この件を母から聞いたのだろう。そう思うと母の自己憐憫に酔った口調が浮かび、苛立ちが腹の中で煮えくり返った。
払い落とされたソックスを、祖母は拾い上げて近くの本棚にそっと置く。
「学校には、行きなさいね」
「うるせえんだよ」
そう言うと、祖母の淋しそうな目を睨みつけながら、奏はドアを乱暴に閉めた。
祖母に反抗的な態度をとったことなど、これまでに一度もなかった。本当に久しぶりに会えたのに。奏はすぐに後悔したが、どうにも感情を制御できなかった。
これが最後の会話になると知っていたならば、絶対にあんな態度はとらなかったのに。
祖母が、自宅で灯油を被って焼身自殺をしたのは、その翌日の事だった。母によると、その前の週に祖父が病気で倒れて入院しており、祖母は担当医から「寝たきりになる可能性が高い」との告知を受けていたそうだ。
あの日、祖母が家に来ていたのは、奏の非行について母から相談を受けていたのではなく、祖父の今後について母娘で相談していたのだという。そんなこととは夢にも思わず、奏は自分の感情ばかりを優先して、迂愚さのままに甘えていた。この日のことだけは、いくら悔やんでも悔やみきれない。先ほども、この事を祖母に詫びながら眠りについたのだ。そして、自分に都合の良い夢を見てしまったのだろう。
奏はベッドの傍らにスマホを置くと、ゆっくりと起き上がる。部屋のライトを点けるのも忘れて、気づくと常夜灯の中で手を合わせていた。せめてこれだけはと、毎年この時期になるとすずや町の方向に手を合わせているのだ。
夢の名残りが、今も安らぎで包んでくれている。奏と世界との境界が、あいまいに溶けていくようだ。
「ありがとう」
奏がつぶやくと、カツリ、と音がした。
目を開けるともう一度、カツリと鳴る。窓の外から聞こえるようだ。まだ外は暗かったが、奏は何の疑いも抱かずに窓を開けてみた。
その時、今度は奏の後方でカツリ、と小さな音がした。そして、カツ、カツと鳴りながら遠のいていく。振り返ってみるが何も見えない。ライトを点けると、小さな音がするのは部屋の奥だと分かった。目を凝らしてようやく見えるほどの、何やら黒い粒が小さく跳ねている。
虫が跳び込んできたのかもしれない。奏が慌ててティッシュを片手に粒を追うと、それは壁に当たってコロコロと奏のほうに転がって来る。
ティッシュで押さえてから一度、大きく呼吸をする。恐る恐る覗き込むと、その粒に奏は、懐かしい白地の柄を見つけた。手の中にあるのは、風船カズラの種だった。
「お婆ちゃん!」
奏は窓を振り返る。しかし、そこではただ空が、静かに白んでいくだけだった。
短編・掌編小説のマガジンに複数保存しています。
是非ご覧ください。
本になる前のこの文章とあなたとの間で、素敵な体験を共有できましたらうれしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
