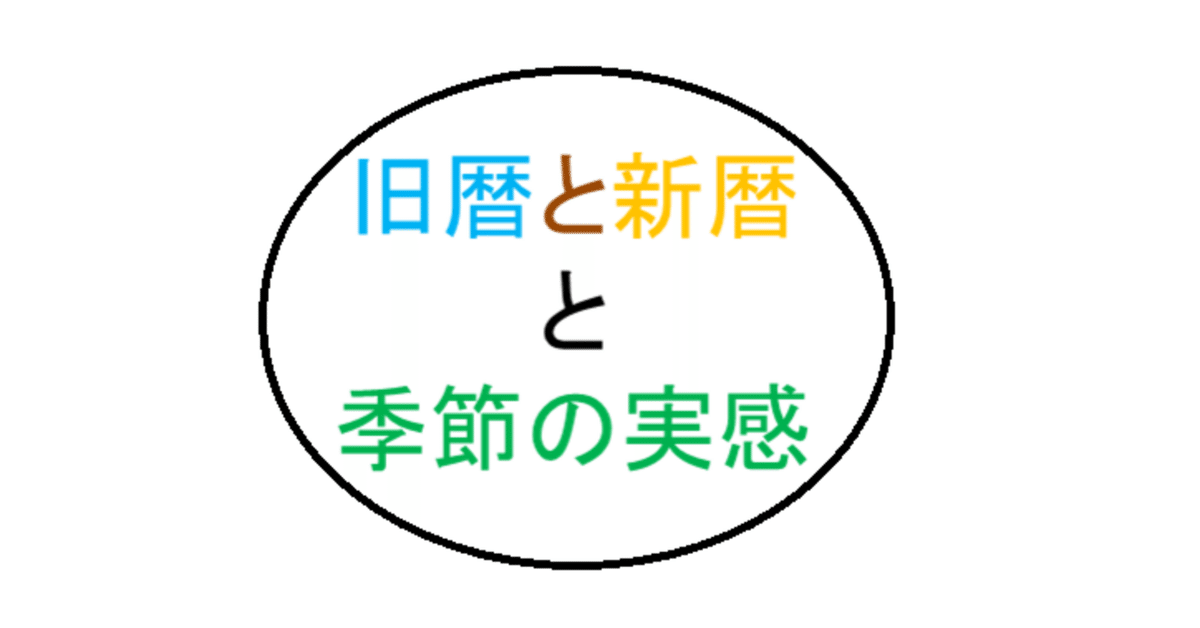
旧暦と新暦―季節の実感により近いのはどちら?
旧暦の元旦は、太陰暦(月の満ち欠け基準にした暦)によるので、それを太陽暦(太陽の巡りを基準にした暦)である新暦に当てはめると、毎年日付がずれることになる。2024年の旧暦元旦は2月10日、2023年の元旦は1月22日となる。新暦に当てはめると、旧暦の元旦の日付にはかなりのずれが出る。
旧暦では、元旦は1月1日に決まっている。そしてこの日から春になる。が、それを新暦に当てはめる際には、1月の下旬から2月上旬にかけて揺れ動くということになる。
新暦でも、元旦は1月1日に決まっている。
自然の様子の移り変わりに対して実際に感じる季節感により近いのは、どちらだろうか?
自然の寒暖は、月の満ち欠けよりも太陽光が地表にあたる角度の違いによるところが大きいので、太陽暦のほうが、より自然の季節感に応じやすい気がする。
今、多くの日本人にとっての「元旦」は新暦の1月1日であろう。しかし、新暦の元旦を「初春」とか「新春」とか称することにかすかな違和感を感じるのは、私だけではないであろう。
旧暦の元旦は、今の2月初め頃になる、そこから春が始まるという感じ方に違和感はない。自然の季節感と合致する。
新暦の感覚に慣れた大部分の日本人にとっては、七夕(七月七日)その他、文化的な季節感も新暦の日付と四季により近くなっていると思う。
私が「五七五句」と称して「自由季俳句」を実践している理由の一つがここにある。
旧暦による句を鑑賞する際に旧暦の知識が必要になるということは言うまでもない。
が、多くの人が太陽暦で日常生活を送る今、そして、太陽暦で人々が暮らした期間が1世紀を超える今、そんな現在を生きる人々が作る俳句に、旧暦による季語を埋め込む意味は、どこにあるのだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
