
振り返ったとき、そこにある場所
そろそろ卒業式のシーズン。今年はコロナウイルスの影響で見送り、というケースが増えそうで残念だ。
私は1991年3月、今から30年ほど前に高校を卒業した。
母校は愛知県立中村高校。中村は太閤さんの生まれ故郷だ。名古屋の北西に位置する、まぁ、どうということのない高校だ。
出身者で一番知名度の高い人は、亡くなった川島なお美さんだと思う。
ちょうど一回り上の子年なので、御存命なら今年で還暦だったのか。
高校合格後、部活の勧誘で、卓球部が盛んに「あの川島なお美さんが在籍していたのだ!」とアピールしていた。聞いている方としては、正直、「お笑いまんが道場は懐かしいけど、微妙やな」という感想しかなかった。
その後、川島なお美さんは色んな方面でブレイクなさったのはご存知の通り。なのだが、引き続き「母校の有名人として挙げるには微妙なヒト」というポジションは変わらなかった。
ちなみに、体育祭の花・部活対抗リレーでは、卓球部は卓球台を模した板を運んで卓球をしつつトラックを回り、部室に常設されていた水着姿の川島なお美先輩の等身大パネルを「バトン」として走っていた。今はどうか知らないが。
Wikipediaを見て、ものまね芸人のMr.シャチホコという方や、日本マクドナルドの社長の日色保さんも中村高校出身と今知った。
お二方ともよく存じ上げないので、私としてはこちらの投稿で紹介した、同級生のAnn Sallyさんが「わが校を代表する有名人」だ。
「アイコ十六歳」の学校
私が入学する時点で、中村高校のイメージと言えば、「アイコ十六歳」だった。少しWikipediaから引用します。
『1980アイコ十六歳』(1980あいこじゅうろくさい)は、堀田あけみの小説。名古屋を舞台に、弓道部に所属する高校生三田アイコの学園生活を描いた物語。堀田は愛知県立中村高校在学中の1981年、本作により当時史上最年少の17歳で文藝賞を受賞した。単行本は同年12月に河出書房新社より出版されている。
好きなおしゃべりをしているときの気持ちが描写されているなど、高校生の年代の女性の気持ちを描写した小説として、同世代の共感と、他世代の評価を得た。『アイコ十六歳』のタイトルでテレビドラマ・映画も作られ、テレビドラマは続編も制作されている。『1980アイコ16歳』のタイトルで漫画版が飯塚修子の作画で発表されている。
1983年の映画版の主役は、12万7000人が応募したオーディションから選ばれた富田靖子さん。富田さんはこれがデビュー作だったと今、知りました。

当然、これは弓道部の強力な勧誘材料であった。実際、人気ありました、弓道部。かっこいいですもんね。
と、思わず富田靖子さんの凛々しい姿に目を奪われてしまうわけだが、もう一度、引用部分にご注目願いたい。
堀田は愛知県立中村高校在学中の1981年、本作により当時史上最年少の17歳で文藝賞を受賞した。
原作者の堀田あけみさんは、在学中に文藝賞をとってしまった高校生作家だった。Wikipediaによりますと、現在は愛知の名門女子大・椙山女学園大学の教授となっておられる。随筆を中心に執筆も続けてらっしゃるようだ。
さあ、やっと高井さんお得意の長い前振りが終わりました(笑)
創立40周年記念誌への寄稿
本日ご紹介するのは、「引っ越しあるある」で発掘されたこちらでございます。なお、引っ越したのは昨年7月ですが、まだ荷解き終わってません。
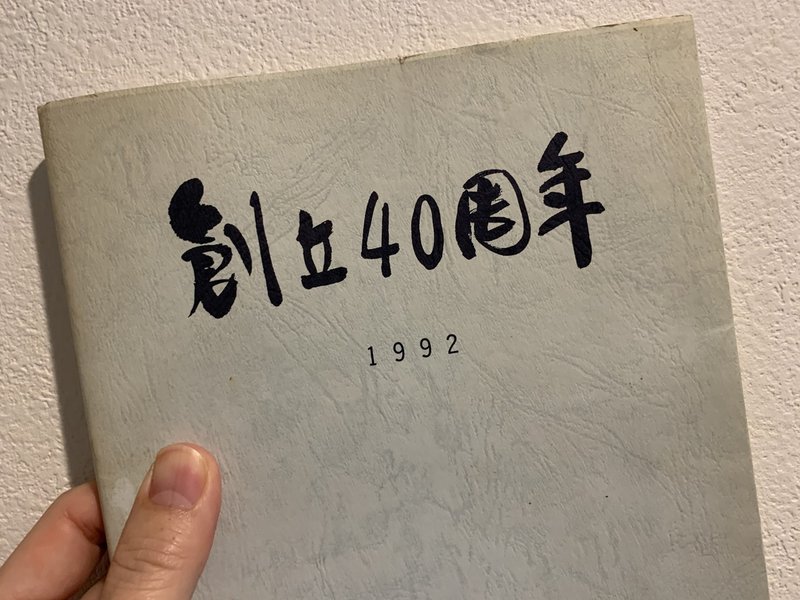
こちらの開校40周年記念誌、1992年の刊行ですので、ざっと30年モノ。
よくとってあったな、と自分を褒めてあげたい。
この記念誌には、母校の歴史的事件として堀田さんの受賞が記録されている。

記念誌は在籍した教職員や卒業生が母校の思い出について寄稿するという形式で、堀田さんは28回生代表として「幸福な場所」という一文を寄せておられる。
少しだけ引用してみる。
私の人生は、十七歳で大きな転機を迎えている。高校二年生の秋から、私は小説を書くことを仕事にするようになった。少しは名前も売れた。そこで、高校での友人が、先入観無しで私を見てくれる最後の友人となった。
在学中にそのような事件を起こした為に、周囲の人の有難みが一層わかったり、不必要に傷つくという経験もした。教育の場に動揺をきたしたことに対しては、申し訳ないと思っている。おまえのようなばい菌が一人いると、学校という組織全体が死ぬことになりかねない、と言われても仕方の無い存在だったのだろう。(しかし言った本人は忘れちゃってるんだろうなあ、この台詞。私は一生忘れないぞ)本当に悪いのは私じゃないんだけど。
高校生作家の誕生が巻き起こした騒動が目に浮かぶようだ。
引用部分以外では、堀田さんは「幸福な場所」というタイトル通り、高校時代の楽しい思い出と、卒業後10年を経てもその記憶が鮮明なことを綴っている。
卒業後は「私がとても幸福だった場所に、別の人間がいるのは、なんとなく見たくない」と母校をほとんど再訪したことがないと書いているのが面白い。
と、ここまでが「本題内の前振り」。振り過ぎである。すいません。
実は、この記念誌には、36回生代表として私も寄稿している。
なぜ私が選ばれたのか、どんな経緯で頼まれたのか、さっぱり覚えていない。3年で担任だったジャンボというニックネームの女性教師から電話がかかってきたような気もするし、別の先生だったような気もする。
卒業して2年、大学2年生の春ごろに書いた文章だ。20歳。今の長女と同じ年だ。ビックリしますね。
執筆したときの気分は何となく覚えている。
まず「卒業生の文章がずらーっと並ぶと、思い出話ばっかりだろうな」と予想して、ちょっと外したエッセイにしようと考え、3年生の時の教室が大好きだったので、そのことを書きたいと思った。
そこは3階の廊下のドンつきにあり、廊下の幅の分だけ他の教室より広くて、両サイドの窓から光が差し込む、とても明るい教室だった。何となく、「校内の特等席」を占めているような優越感があった。
自分が「母校」と感じるのは、この中村高校までだ。
大学はあまりちゃんと出席していなかったので、「ただ出ただけ」という感覚。
ということで、ようやく本題です(笑)
以下、ちょっと青臭くてお恥ずかしい出来ですが、若僧の文章を書き写しておきます。自分が読み返すのに便利なので。安部公房にハマってた頃だな。
誤字を直し、適宜、改行を入れておきます。
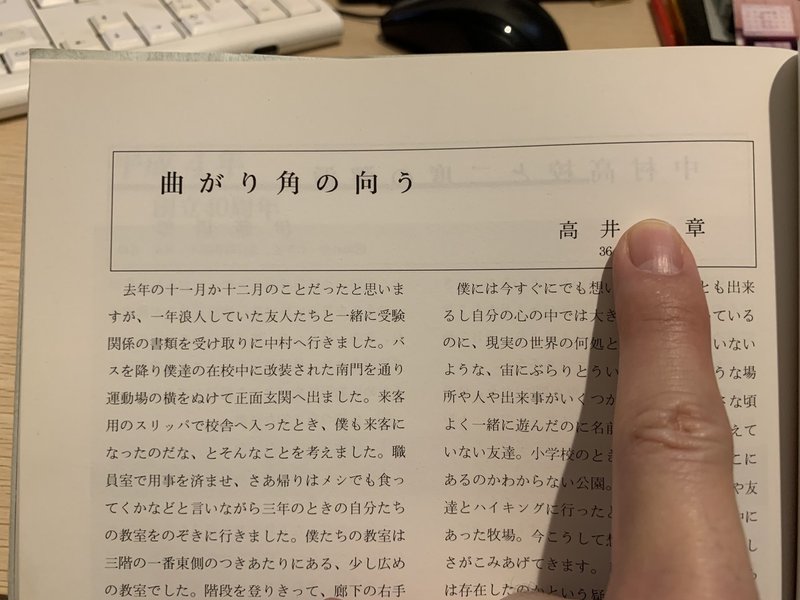
(本名なのでちょちょいとトリミング)
曲がり角の向こう
去年の十一月か十二月のことだったと思いますが、一年浪人していた友人たちと一緒に受験関係の書類を受け取りに中村に行きました。
バスを降り僕達の在学中に改装された南門を通り運動場の横をぬけて正面玄関に出ました。来客用のスリッパで校舎に入ったとき、僕も来客になったのだな、とそんなことを考えました。
職員室で用事を済ませ、さあ帰りはメシでも食っていくかなどと言いながら三年のときの自分たちの教室にをのぞきに行きました。
僕たちの教室は三階の一番東側のつきあたりにある、少し広めの教室でした。階段を登りきって、廊下の右手のつきあたりにあるはずだとわかっているのですが、踊り場にさしかかったあたりで何か奇妙な不安がよぎりました。
本当に今もまだあるのか?
以前のままの乱雑と整然の中間ぐらいの、陽当たりの良い、良すぎるくらいのあの教室が本当にまだあるのか?
くだらない、と思いつつもそんな疑念が胸の内に広がり、そしてそれは拭い難いものとなりました。
「カーブの向こう」という安部公房の短編があります。そのなかである男が、自分のよく知ったなじみの通りで突然、そのカーブの向こうの風景について確信を失い、もしかしたらその先には自分のまったく知らない異郷があり、自分はその中に埋没し、自分が知る、知っていたと思いこんでいた世界との繋がりを永久に失ってしまうのではないかと恐怖する一節があります。
それほど大げさではないにしろ、そのときの僕はこの男と同じような思いにとらわれました。
僕には今すぐにでも思いうかべることが出来るし自分の心の中では大きな位置を占めているのに、現実の世界の何処ともつながっていないような、宙にぶらりとういてしまったような場所や人や出来事がいくつかあります。
小さい頃よく一緒に遊んだのに名前も家もまるで覚えていない友達。
小学校のときに遊んだ、今はどこにあるのかわからない公園。
中学のときに先生や友達とハイキングに行ったとき、その山道の途中にあった牧場。
今こうして思いだしてみても懐かしさがこみあげてきます。しかし、本当にそれらは存在したのかという疑念も同時に生じるのです。本当にこの懐かしい道の曲がり角の向こうにはいつも心に浮かべるような風景があるのか。
階段を登りきり廊下に出て右のつきあたり、ドアを開くと、以前と変わらない整然と乱雑と明るさがありました。
僕は、考えてみれば当たり前じゃないかと思いながら、しかし、そんな当たり前のことが何か出来すぎたことのように思え、そしてその出来すぎたことに勇気づけられたような気がしました。
中村での三年間は僕にとって自分のなかでとても大切なものです。しかしその大切な通り馴れた未知の曲がり角の向こうに不安を感じることが、時にあります。
そんなときも中村は、存在しつづけることで、「お前はここに居たし、ここから出ていったし、ここから来たんだ」と僕に教えてくれるのです。
=========
ご愛読ありがとうございます。
ツイッターやってます。フォローはこちらから。
異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします
無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。
