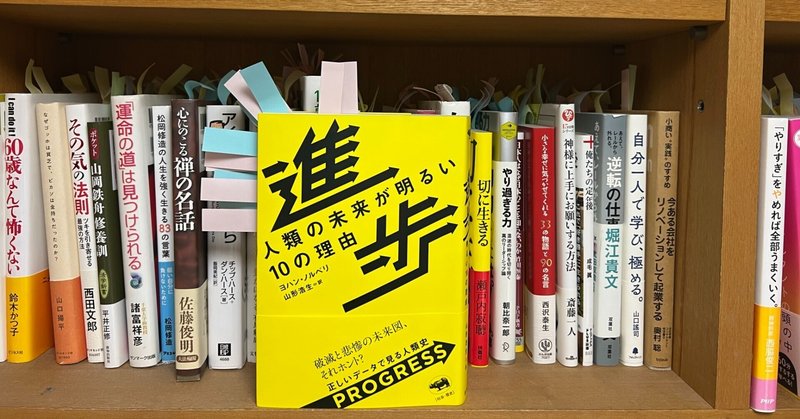
どうして進歩は起こるのか
今日のおすすめの一冊は、ヨハン・ノルベリ氏の『進歩 人類の未来が明るい10の理由』(晶文社)です。ブログも同名の「人類の未来が明るい10の理由」として書きました。
本書の中に「どうして進歩は起こるのか」という非常に興味深い文書がありました。
本書で描いた多くの成果 は、どれもこうした力(迷信と官僚制)で今なお阻害されかねない。過激派イスラム主義者は、権力を握ると少女たちが教育を受けるのを止め、奴隷制を復活させようとする。
ポリオワクチンがイスラム教徒を不妊化しようとする西洋の陰謀だというデマが流れ、数カ国でほとんど根絶しかかっていたポリオが復活してしまった。同様に、はしかワクチンが自閉症の原因になるという馬鹿げた発想のおかげで、アメリカでは反ワクチン運動が起き、このひどい病気が何度か大流行している。
人類進歩の原因は、すでにしっかり根付いている――科学と知識の成長、協力と貿易 の拡大、それに基づいて行動する自由だ。でも歴史的には、変化を受け入れない勢力によりこうしたものが妨害され、破壊されてきたこともある。かれらは、それが自分の立場を脅かすと恐れるのだ。
1000年前には、科学革命と産業革命が始まるのがヨー ロッパになるとは、だれも予想だにしなかったはずだ。シャルルマーニュが797年 にバグダッドのカリフから精巧な時計を贈られたとき、かれはそれが何だか理解できなかった。
この時代、科学と技術の面ではアラブ人がはるかに先を行っており、西洋ではほぼ忘れ去られていたギリシャ哲学を生かし続けたのもアラブ人だった。
同時期に、経済的にも文化的にも繁栄した中国を支配していたのは宋王朝だった。法治と高い経済的な自由のおかげで、イノベーションの気運が生まれた。中国人は活字や火薬や羅針盤を使っていた――これは1620年という時期になっても、三大発明としてフランシス・ベーコンが挙げたものだ。
でも14世紀に中国を支配した明王朝は、技術や外国人に敵対した。海洋航海を死罪にして、世界を発見したかもしれない大型船を焼き払った。同様に、イスラム世界は13世紀の蒙古侵略のあとで内向きとなり、科学と近代化の多くの発想を粛清した。
オスマン帝国では新技術は阻害され、印刷術は300年も遅れてしまい、タキ・アッディンが1577年に作ったイスタンブールの近代的な天文台は、たった3年しか続かずに、その後は神をスパイしようとしているといって破壊されてしまった。
別にヨーロッパの列強がマシだったわけではない。ヨーロッパのエリート層もまた新しいアイデアやイノベーションに反対した。でもこの大陸はあまりに断片化していた。地理的にも政治的にも言語的にも――おかげで、何か一つの集団や皇帝がそのすべてを支配はできなかった。
著書『ヨーロッパの奇跡』でエリック・ジョーンズは、14世紀にはヨーロッパに1000以上の政治単位があったと述べている。この複数主義はある意味で、競合する国民国家の体系を構築したときにもまだ残っていたといえる。
新しい理論や発明、ビジネスモデルは必ずどこかでは生き延びられたし、その優位性を実証できた。それが他の人々に模倣されて、広まる。進歩は常に命綱を得られたというわけだ。 つまりヨーロッパを豊かにしたのは、優れた思想家や発明家や企業ではなく、ヨーロッパのエリート層がそれを邪魔するのにあまり成功しなかったという事実なのだった。
アイデア、技術、資本は国から国へと移動できたので、国はお互いに競争して学び合うしかなく、お互いを近代化へと押しやった。これはいまのグローバリゼーションの時代と少し似ている。
ますます多くの場所の、ますます多くの国が、いまや人類の知識全体にアクセスできるし、他の場所での最高のイノベーションに開かれている。こうした世界では、もはや一人の皇帝の気まぐれで進歩が左右されたりはしない。どこかで進歩が邪魔されても、他の多くの場所が人類の進歩を引き継ぐことになる。
豊かさや人命は破壊できても、知識が消え去ることは滅多にない。知識は成長を続ける。だから、どんな逆風も人類の進歩を完全に破壊することはなさそうだ。
たとえば、このコロナ禍においても、いろいろなデマが飛び交った。歴史を振り返れば、迷信やデマを信じたため一度根絶した疫病が復活したことは枚挙にいとまがない。
そして、大事なのは、時の政府や政治が強権的すぎないことだ。何故なら、進歩が起こるのは必ず民間からで、政府からではないからだ。規制がゆるければゆるいほど、進歩は加速する。
だから、規制があまり効かないインターネットの世界で、進歩はすすむ。100年前のことを調べれば、誰もが今の方が進んでいると思うだろう。今一度、進歩とは何かを考えてみる必要がある。人類の未来は明るいのだから。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
