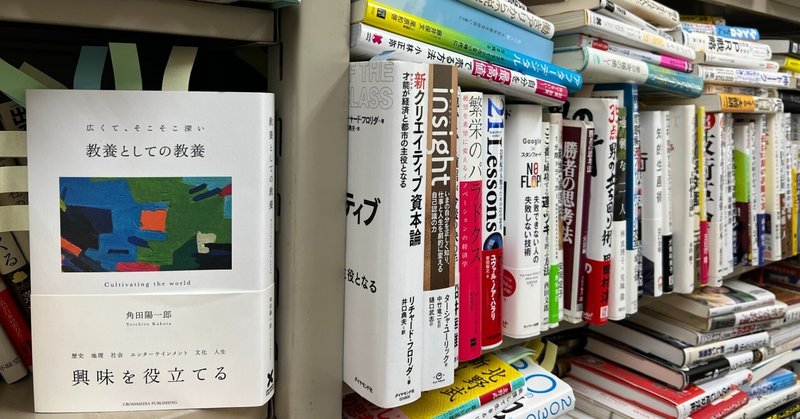
人口から日本の未来を考える
今日のおすすめの一冊は、角田陽一郎氏の『教養としての教養』(クロスメディア・パブリッシング)です。その中から「教養としての教養とは」という題でブログを書きました。
本書の中に「人口から日本の未来を考える」という心に響く文章がありました。
太平洋戦争に敗れた敗戦国・日本が高度経済成長を経て発展し、世界で2番目だと思えるくらいの国家でいられた理由が、実は自分たちの優秀さでも国民性でもなく、「ただ人口が多かったから」というシンプルな事実。
太古の昔から、稲作によって多くの人口を抱えることができるようになった日本人の先達が行なってきたことと、戦後に急激な経済成長を遂げたことについては、日本人の優秀さの賜物かもしれません。
しかし、地理思考で導き出されたこのシンプルな事実に立ち返った上で、では、その優位性が崩れてしまった21世紀の今、日本人が進むべき未来はどちらの方角にあるのか?もしかしたら、順位付け自体が無意味なことなのかもしれません。
例えば、定員とか合格とかレギュラーとか、ある枠に入るために私たちは努力しますが、なぜその枠に入らないとそもそもダメなんだろう? と考える時期が来ているんだと思います。
例えば野球なら9個のポジションしかないなら、そこを目指さなくても10個目のポジションを新しく生み出しちゃえばいい!・・・・・・最早それは野球じゃないかもしれませんが、そんな価値観の転換が必要なんだと思います。
例えば江戸時代は、人口3000万人だけど各地でいろんな文化が栄えていました。 スウェーデンは、人口1000万人だけど豊かな国です。 今の日本の人口減も実は私たち日本人の意識自体と、国や地方の分業化と効率重視のシステム自体をつくり変える本当の契機なのではないでしょうか?
「世界一幸せな国」と称されるブータンや、イギリスやアメリカのライフスタイル業界で流行の兆しを見せている「ヒュッゲ」という言葉を生み出したデンマークのように(ヒュッゲとはデンマーク語で「居心地がいい時間や空間」)、「経済力」ではなく、「人間の幸福度」で 自国を眺めることができるような、新たな価値観への転換が私たち日本人には求められてい るのかもしれません。
そのように俯瞰で考えることができるのは、地理思考で世の中を捉え直すことができる人なのです。
角田氏は日本が2番目だったのは、日本人が勤勉でよく働いたからではなく、実は「人口が世界で2番目」だったから、「経済が2番目」だったのだという。当時(70年代から80年代)でも人口の1位は中国、2位はインド、3位はアメリカで日本は6位だった。
それなのに何故2位かというと、それは先進国の中で2番目に多いということだった。ちなみに、現在の日本は11位。
しかし、現在は人口が急減してしまい、中国やアジアの国々も先進国と同じ(それ以上)の技術力があり、先進国としてという前提が成り立たなくなってしまった。
今後は今まで通りの考え方ではなくではなく、角田氏のいう「地理的思考」で世の中を捉えなおさなければ日本は成り立たなくなってくる。
まさに、教養としての教養が必要だ。
今日のブログはこちらから→人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
