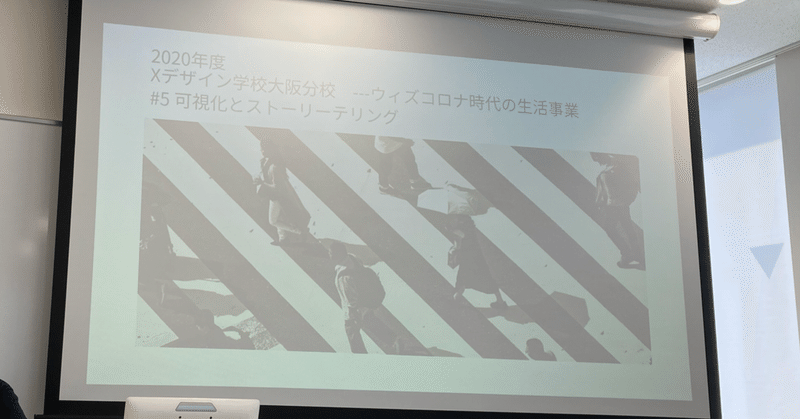
Xデザイン第5回:可視化とストーリーテリング
見事に罠にはまっていました。タイトルに「可視化とストーリーテリング」と書いていますが、この話は出てきません。というのも、ここまで進めてきたグループワークだが、ほぼ振り出しからもう一度始めることになりそう。今回はその嵌ってしまった罠について振り返る。
今回のキーワード
「ユーザー中心に設計すればするほどニッチになるのでスケールしない」
1.クライアント企業のアセットは何か?
UXデザインの前に、サービスデザイン。慈善事業ではなく、ビジネスを考えているので、クライアント企業のアセットを活用して、事業として成り立たせていくことを考えねばならない。
これまでのワークでは、ほぼユーザー分析ばかりを行ってきていて、クライアント企業のことがすっかり抜け落ちていた。UX(ユーザーエクスペリエンス)という言葉に惑わされていた部分があったかもしれない。結果、上位下位分析などを進めていっても収斂せず、むしろ話が発散してしまっていた。クライアント企業のアセットをしっかりと理解して、ビジネスを考えていないと、そもそもユーザーに何をインタビューすべきかがわからないし、ビジョンを組み立てられない。企業のアセットが念頭にあれば、インタビューの方向性が自然と絞り込まれる。ここが自分の中でも理解できていなかったポイントで、何か腑に落ちず、これまで進みながらもモヤモヤしていた点だったように思う。
2.インタビューをきちんとする
今回のワークでのビジネス検討は、「コロナ禍で生活の変わったところ」を各々が付箋に書き出したところから出発した。そう、インタビューできていない。今から思えば、何度も言われていたし、当たり前にやっておかねばならないことだった。インタビューの時に「自分の考えをいれない」と言われていたにもかかわらず、これでは自分の考えのみからスタートして、さらに自分の考えを重ねてしまっている。インタビューすることは相手の考えを引き出す、語ってもらうこと。改めてクライアント企業のアセットとは何かを意識して、ビジネスインタビューからリスタートしたい。
3.ビジョンの解像度は意外と低い
ユーザーの願いを全て叶えられる企業はない。そして、ユーザー中心に考えすぎると、ものすごくニッチな(どんどん解像度が高い)ところに落ちていってしまう。最近よく見かける、「ユーザー視点」だとか「ユーザー志向」とか「ユーザー」という言葉が乱発されている感があるが、これは完全な落とし穴だと思った。ビジネスとしては拡張性があって、できるだけいろんな場所で使える方が良いのだが、これでは逆方向になってしまう。あまり意識しすぎると、今度はいろいろ考えすぎてビジネスに寄りすぎると思うので、プロジェクトビジョンとしてのいい頃合いを探っていきたい。
おわりに
前回の講義まで、なんとなくモヤモヤしていたことがあったのだが、それが今回の講義での指摘によりスッと晴れたような気がした。(あくまでも気がした。実践を積み重ねていかないと本当の理解はできない。)今回の失敗はいい失敗。そのおかげで身をもってどうした方がいいのかに気づくことができた。この感覚を忘れないうちにリスタートを切りたい。
皆様、次回もまたよろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
