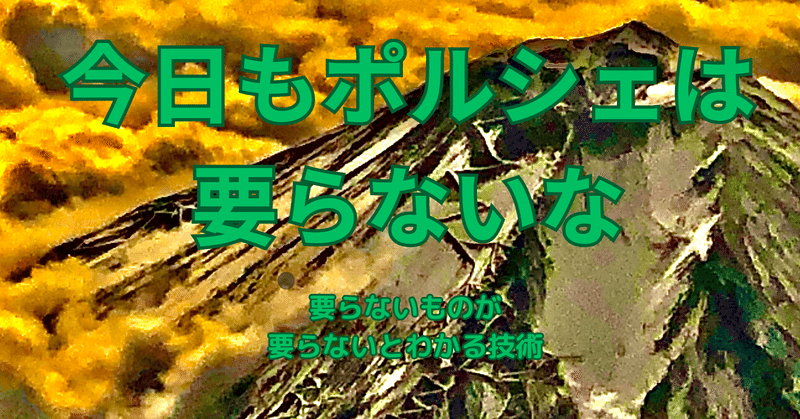
憧れの風景
ずっと行ってみたかった生まれ故郷のホテルに行った
そのホテルは海沿いにヨットの帆のように凛々しく立ち、隣には5万人を収容できるスタジアムがある
スタジアムの開閉式ドームは金属製で、光の入射角によって違う色の光を反射する
天気予報の映像のバックに必ず使われるので、東京にいて生まれ故郷を思う時、そこに素敵な世界があると思っていた
そのホテルができたのは私が上京した後だった
上京する直前はまだ更地の埋立地で、この後故郷がどんどん栄えていくことを知りながら、それでも東京に行くという選択になってしまったことを、自分でも咀嚼しきれないままの上京だった
故郷で過ごした方が楽で快適なことはわかっていて、故郷にも仕事はたくさんあった
それでも受かるはずがないと思って受けた東京の会社に受かったので上京することになった
しかし見えない力が、私を故郷に残るよう、引き留めた
今から30年以上前、私は受かるはずがないと思っていた東京の会社の内定をもらい、その内定書を着慣れないスーツの内ポケットに入れ故郷へ向かう飛行機に乗っていた
その飛行機が故郷の地にタッチダウンした瞬間、私は突然、胸が苦しくなった
息ができず、座席にうずくまった
それでもなんとか飛行機を降り、到着ロビーまで辿り着くと、そこに父が待っていた
夜の10時を過ぎていたが父に空いている病院に連れて行ってもらいレントゲンを撮ると、右の肺が破れていた
普通、肺が破れた状態では歩けないということで、その後は車椅子に乗せられ他の検査をした結果、緊急手術となった
このまま何もしなければ、酸素が欠乏し、死んでしまうというのだ
手術は二人の医師によって行われたが、二人とも専門外だったらしく、手術はたびたび中断した
あまりに長く中断したので、どういう状況なのか頭の先の見えない位置にいる医師二人を必死の思いで首を傾け確認すると、二人は分厚い本を開いて議論していた
本を見ながらやっているのか!と驚き、恐ろしくなったが、このままだと死んでしまうと言われたので文句は言えない
だが、次にどうするべきかという医師二人の議論はあまりに長すぎた
麻酔がだんだんと切れてきて、私は痛みに耐えられなくなってきた
議論を邪魔してはいけないと思いつつも、もうこれ以上はこの痛みに耐えられないと思った私は「すいません、麻酔が切れてきたみたいなんですけど」と申し訳なさそうに訴えた
すると一人の医師が「麻酔一本追加」と、居酒屋でビールを追加注文したとき、それを復唱する店員のような口調で言った
そして私の左肩に追加注文された麻酔が打たれ、私の意識はブラックアウトした
目が覚めた時、私はベッドに横になっていた
右の脇の下から太い管が出ていた
しばらくして担当の専門医が来て「うわ、太い管」と驚きの声を上げた
そういえば昨日、緊急手術をしていた医師二人組は管の太さを決める時、「この人、大きいからこれでいいんじゃない」というやりとりをしていた
やはり私は、全くの素人に手術されていたわけだった
だが、それはもう終わったことだ
大変なのはそれからだった
その管の長さは1メートルほどで、それから私の行動半径は、その管の長さに限られることとなった
無論、トイレには行けない
おまるというもので小便も大便もしなければならない
だが、術後は痛くて起き上がることができず、おまるさえ使えない
尿意を催したので尿瓶を用意されそれにするようにしたら、感覚がおかしくなっているので大便まで漏れてきた
半径1メートルの自由しかないと分かった早々、私は自分のベッドを大便で汚してしまったのだ
どうすればいいのか?
パニックになりかけたが、これは素直に訴えるしかない
「すみません、おしっこしようとしたら下まで出てきました」と私は看護婦に告げるしかなかった
22歳の男子にとって、そのような言葉を若い女性に向かって吐くのは屈辱である
我をなくすために、寺で座禅を組んで、坊主に棒で叩いてもらう映像を見たことがあるが、そんなことをしなくても、「すいません、おしっこしようとしたら下まで出てきました」と言う方が我などなくなる
私が発症した病気は肺気胸といい、肺に繋いだ管から酸素を送っていれば、自然に肺に空いた穴が塞がることが期待された
だが1ヶ月経っても肺に空いた穴は塞がらず、本格的な手術となった
脇の下を切り、そこから肺を取り出し破ける可能性がある部分を切り取り、残った部分を縫い合わせる
それでも破けてしまった時に肺が縮んでしまわないように、接着剤のようなもので肺の表面を肋骨に癒着させるというものだ
8時間の大手術で、その後の3日の高熱と痛みは凄まじかった
窓を見て、そこから飛び降りた方が楽だと思った
そんな入院生活を送りながら、私には心配なことがあった
大学の単位が足りていないのだ
8月末に入院したのだが、前期の試験で単位が揃わなかったら留年となり、内定は泡と消える
熱と痛みでうなされている最中にも勉強できるようにと、事前に教科書の内容を音読し、それをテープに吹き込んでいた
それがどれほどの効果をもたらしたのかはわからないが、とにかく卒業しなければ、という一心でやれることをやった
その結果、必修科目はギリギリ揃ったが、選択科目が一つ足りなかった
私は会社に電話し、卒業できないので入社できないと告げた
会社は、もう一度確認してみろ、と言う指示を出した
決まりなので確認しても同じですよ、と答えたが言われた通りに再度、大学に確認すると、今年から制度が変わり、選択科目は卒業までに取ればいいことになった、という
そんなわけで私はギリギリのところで卒業できるようになったのだ
だがそれだけでは終わらなかった
故郷に私を引き留めようとする偶然は、私が故郷から飛行機で飛び立つ瞬間まで起きた
結局、紙一重の決断で上京する方を選び、それから30年以上が経ち、ようやく私は天気予報のバックに映る憧れのホテルを訪れることができた
そのホテルには、当初、ディナーで行く予定だった
最上階のレストランを予約していたが帰省して母が美味しいものをたくさん食べさせてくれたので、胃を休めるためにディナーの予約はキャンセルした
だが、今回どうしても行ってみたくなって、とりあえず最上階まで上がって、そこからの景色を見てくることにした
最上階まで上がると、ホテルの人が予約を確認した
予約はないが空いているなら食事がしたい、と告げると空いているという
まだ昼の12時前で、待合用のソファーにいたのは1組だけだった
私と妻はもう一つの待合用のソファーで15分ほど待たされた
窓からは街と海が一望できた
私はその風景をずっと見たかったのだ
食事で案内された席からは、私が地元に残る決断をしたならば就職していただろう会社の建物が見えた
その建物は海沿いにあるので、私は家からジェットスキーで通おうと思っていた
当然、道中濡れることがあるのでウェットスーツを着る
沖に上がりウェットスーツを脱ぐと下にはスーツを着ていて、スーツにはウールマークがついているのでウェットスーツを脱いでもスーツにはシワはない
そんな風にして出勤する日常が、私のもう一つのあり得たかもしれない世界だった
ジェットスキーに乗って通勤しなくても、その会社の近くまで都市高速が通じている
実家で暮らせば給料は丸々自分のために使えるので、毎年高級車が買える
フェラーリ、ランボルギーニ、アストンマーチン
そんな車に乗って通勤するというあり得たかもしれない世界がそこにあった
そんないつくかの並行現実を、窓から見える風景に重ね合わせながら、私と妻は食事した
とても美しい風景だった
私はこの風景を30年間、ずっと見たいと思ってきたのだ
だが5分くらい過ぎて、あることに気づいた
それを言葉にするか、躊躇った
言葉にしてしまえば、その思いを認めたことになる
だが、私は言った
「なんか、飽きたね」
私はその風景に飽きていた
美しく、30年間ずっと見たかった風景であるのは頭でわかっているが、5分も見ていると飽きていた
そして、ジェットスキーやランボルギーニでで会社に通う並行現実に対し、それほど魅力を感じていないことに気づいた
それは、東京で暮らした30年には、東京で暮らさないと得られないものがあったからだ
食事を終える頃、私のその風景に対する執着は無くなっていた
結局、どこだっていいのだ
自分が自分というものを全うできるのなら、それはどこでもいい
肝心なのは自分に対する自分への想い
未だ自分で広げた大風呂敷は広がったままで、何ら形にはなっていない
全て未完の状態で、誇れるものは何もない
だが、それで構わない
それで当然だ
まだ、途中なのだ
なぜなら俺は、まだ先へ行けるから
ずっと憧れてきた風景に飽きたことで、私は自信を取り戻した
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
