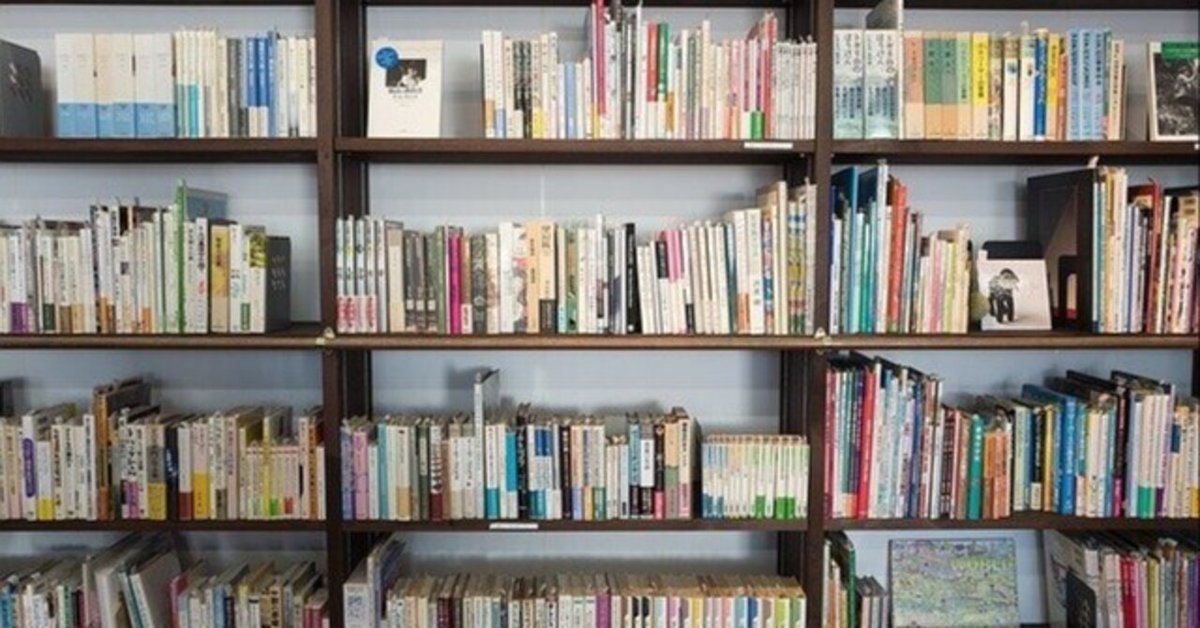
【読書】『シロクマのことだけは考えるな!』【心理的トラップを回避せよ】
みんな、エビデンスに基づいた、「本物の学問」を欲しているんだなあ。難しくてもいいから、心理学には「普遍的真実」を期待しているんだなあ。率直にそう感じさせられます。
いつの日か、とことんカジュアルなテーマを用いながらも、「本物の心理学」をエッセイのような形でまとめておきたいなあ。学術論文クラスの理論を織り交ぜながら、身近なことだけにフォーカスを当てた心理学の書籍を作ってみたいなあ。
心理学の本を読むと勉強になるメリットがあるのだが、異常に疲れるというデメリットがある。
過去の恨みつらみとか思い出してきて、ドンヨリドヨドヨしてくるからなのだが、植木さんはカジュアルなテーマを扱ってくれています。
「合コンの反省会は一人でやれ」
なんてカジュアルすぎると思われますが、思い当たるフシのある人は、やっぱりドンヨリドヨドヨしてしまうかもしれない。
心のモヤモヤに、いちばんてっとり早く結論を与えてくれるもの。自己とどう向き合い、他者とどう交わることが、お互いの幸福感を紡ぎ出すのか・・・・・、それを最も科学的に、明快に示してくれるもの。
それこそが、「認知心理学」と「記憶心理学」。この2つの学問ではないかと、私は強く信じています。この本は、2種類の心理学の膨大なデータの中から、一日でも迅速に、あなたの人生をもっとオモシロく、豊かにするためにエッセンスをギュギュッと圧縮したものなのです。
「言われてみればそうだなぁ」というところが多々あるので、チェックしておきましょう。
メンタルコントロールの皮肉
シロクマ実験
動物園で働いているわけではないから、日常的に考えることはないのだが「シロクマのことを考えるな」と言われてしまうと、かえって「シロクマ」の姿が脳裏にチラつく。
何かをうまくやろうと気張ることで、逆に失敗率の方が高まってしまう。そういうアマノジャクな現象のことを、心理学者は「メンタルコントロールの皮肉」と呼んでいます。
ここから導き出される答えは、自分に無理を強いるような、ストイックなメンタルコントロールや自己啓発といった鍛錬は、意外と逆効果になってしまうこと。
怒ったり、恨んだり、憎んだり、イライラしたり、ダイエット中なのにバクバク食べたり、禁酒宣言しても飲んじゃったり・・・・・
分かっているけどやめられない―――――それは、心理学的事実とは「正反対の努力」をしてしまうから。
不毛な努力やめて、効果的な努力をするためには、自分の心の中の「シロクマ」の存在を認め、上手く飼いならす方法を考えることです。
塩ぬり療法:いっそ考え続ける
それはズバリ、脳のメーターが振り切れるまで考えることです! 忘れようとしないことです! 考えて、考えて、思う存分考えまくってください。
植木さんが提唱するのは「塩ぬり療法」。辛く悲しい出来事を、詳細に日記につけること、そして自虐的に人に話すこと。
さらにとっておきの手は、日記に毎日、その出来事に対する感情をパーセンテージで記しておくこと。
そうこうしているうちにどうでもよくなってきて、「ああ、もうこういうことを考えるのが面倒だ!」とばかばかしくなる瞬間が、ある日必ずやって来ます。
ようするに「飽きた」ということ。
自分の傷口をしっかり見つめることによって、はじめて心の機能は健全に働くのです。
一刻も早く忘れたいのなら、悲しみに浸り、思う存分泣き、悲劇のヒロイン・ヒーローになること。これがトラウマ解消法の極意なのです。
パニックになったら実況する
実に4割以上の人が、「極めてひどいパニック発作を経験したことがある」と答えているので、パニックになること自体は恥ずかしいことではないのです。
人という字を手のひらに書いて飲み込んでみても、「パニック発作」で生じた身体症状を完全否定するだけ。
心理学では「回避的コントロール」と呼ばれるもので、効果は望めないのです。
それは、シロクマ実験と同様、緊張を高めてしまうだけ。
植木さんの提唱する対処法は「ひとり実況中継」。
苦しみから逃げようとせず、逆に「堪能」すること。苦しい状況から逃げずに、逆に詳しく言語化すること。
苦しみに抵抗するのではなく、苦しみに身をゆだねることが、パニックを脱出する近道なのです。
パニックという「出来事」そのものではなく、その状況に対する「考え方」を変えることで、落ち着きを取り戻すのです。
落ち込むだけ落ち込む
同様のことが、落ち込んでいるときにも言えます。
落ち込んでいるときに明るい曲を聴くのは、まったくの逆効果。
*気分がニュートラルな状態(高揚したり落ち込んだりしていない普通の状態)であれば、音楽に対して気分一致効果が働き、気持ちの誘導が可能になる。
*しかし。気持ちが滅入っているような人たちは、明るい音楽に対してむしろ気分“不”一致効果ともいうべき現象が起こり、より落ち込んでしまう。
気分がニュートラルな状態であれば効果的なことも、気分が落ち込んでいるときには逆効果なのです。
むしろ逆に、落ち込んでいるときは、悲しい音楽に思いっきり浸れば「気分不一致効果」で前向きになれるのです。
体がそんな休息を欲してるのなら、それを無理に邪魔せず、心に沿った悲しい音楽を聴いて気分を盛り下げまくる方が身のため。
ということで、落ち込んでいるときに「気晴らし」は逆効果になります。
落ち込んでいるということは、心が疲れているということ。疲れているのなら休息を取ればいい。それなら、落ち込んでいるときは、しっかり休みましょう。
そうこうしているうちに、バカバカしくなって、飽きてしまう。
落ち込んでいるときは、落ち込んでしまいましょう。飽きるまで。
記憶がウソをつく
カクテルパーティ効果
カクテルパーティのようなざわついた場所で誰かとおしゃべりしていても、自分の噂だけはバシッと耳に聞こえてきてしまう。
この「地獄耳」は「カクテルパーティ効果」と呼ばれている。
私たちの脳は、自分にとって重要な情報しか拾おうとしない。周囲の物事をまんべんなく記憶するのではなく、自分に関係あることだけに神経を研ぎ澄ましている。
脳が自動的に、エネルギーを「節約」していると考えれば、極めて効率的な方法なのです。
そう考えると、いわゆる「オタク」は、ヘンな人たちでもなんでもないのです。自らの「地獄耳」に極めて素直に応じ、自分の興味の向くジャンルの知識だけを、徹底的に集めていただけなのです。
もうひとつ「カクテルパーティ効果」の要因として考えられることは「自己愛」。
心理学の実験で、まったく同じ文章を読んでもらいます。しかし「それを誰が書いたか」という情報を加えることによって、評価が左右されるてしまうことがわかっています。
これは、ライバル意識をあおられると、途端に厳しい目になり、相手のあらさがしをするようになるからだと考えられています。
私たちの心は、自分自身の信念や哲学に反するような話は、敢えて(でも無意識に)耳に入れない、理解したくないような習性があるのです。
「自分の考えを変えたくない」「自己を肯定したい」という拭いがたい自己愛。
私たちの脳は、エネルギーの観点から言えば「ケチ脳」なのですが、自己愛の観点から言えば「イジワル脳」といえるのです。
「イジワル脳」をやめて、憎いライバルの話をどれだけちゃんと聞けるか。
自己愛が傷つくことを恐れずに、相手の話を聞けるかどうか。
これがデキル人間になれるかどうかの分かれ道。自己愛を脅かすような人とは会いたくない、気が引ける―――――
しかし、自己愛やイジワル脳を乗り越えれば、そこで新しい情報が得られる、これまで気がつかなかった考え方が見つかります。
営業マンの行動と営業成績の関係性を調べたところ、できる営業マンほど、同業他社の人と食事に出かけていることがわかったのです。
同業他社の人間とテーブルを囲む、なんて、イジワル脳的には、避けたいことこの上ありません。実際、これを実践できている営業マンは一握りです。
多くの人がしたくないことだからこそ、ちょっと勇気を出せば、簡単に一歩リードできてしまいます。イジワル脳に負けない。ケチ脳に負けない。贅沢に潤沢に、脳の全部をフル回転させましょう。
考えてみれば、同業他社を叩き潰すために働いているわけではないのです。
自分と、自分のビジネスを、成長させるために働いているはず。
いい話を聴けたのなら、それを自分のビジネスに取り入れればいい。失敗談を聞けたなら、自分がそうならないように対策をとればいい。
「カクテルパーティ効果」が「ケチ脳」の方向に働くのは仕方のないことかもしれません。しかし「イジワル脳」の方向に働くのは避けなければならないのです。
フォールス・メモリー・シンドローム
私たちはいつ「人」の評価をしているのか?
「インプット → キープ → アウトプット」の三段階を経て、評価をしているのですが、問題は「アウトプット」。
アウトプットでの間違いが非常に多いのです。心理学的に「フォールス・メモリー・シンドローム」と呼ばれるもの。日本語にすれば”偽りの記憶症候群”。
それは、記憶を無理やり思い出すと、他の記憶が混じってしまうからだと考えられています。
なので、心療内科や精神科でのカウンセリングにおいては、深層心理分析は下火傾向になっています。
むしろ「今、ここでの自分」にのみ焦点を当て、敢えて過去の分析を行わないカウンセリングが主流になっています。
しかも、アウトプットの失敗は、一人で思い出すより、複数人で思い出すときが圧倒的に多いので、要注意です。
複数人で人を思い出すとき、人の評価を語るときには、そこには「会話のやりとり」が介在します。
しかも、人間の記憶なんて、それを引き出す言葉の違いによって、たやすく歪んでしまいます。
だから、複数人で「会話しながら」人を思い出すなんて、トラップたっぷり。
なので、
合コンの反省会は一人でやれ
怪しげな記憶情報を頼りに、歪んだ情報を手に入れて、しかも「イジワル脳」まで働こうものなら、「選び間違い」が起きて当たり前。
そんな悲劇を起こさないようにするために、「合コンの反省会」は一人でやりましょう。
言語的隠蔽
自分の“感情”をすぐに言語化してしまうと、心の深い所にある“真の感情”が分からなくなることがあります。
言語化することでかえって感覚が鈍くなったり、自分の“真の感情”がわからなくなってしまう現象を、心理学では「言語的隠蔽」と呼んでいます。
世界トップクラスのソムリエは、沸き起こったワインへの賛辞を、言語化して定着させるよりも、モワッとしたまま放置しておいた方が、後になって正確に思い出せるそうです。
沸き起こった感情や感想は、すぐ言葉にしないほうが正確な判断ができる。
なので、メモを取るときは、客観的事実だけを、できるだけドライに、簡潔に。
この「言語的隠蔽」が日常的に起きやすいのは「口ゲンカ」。
頭にきた瞬間に発している言葉なんて、言語的隠蔽のカタマリのようなもの。自分の感情が正しく分からないまま、とにかく「負けたくない」ために言語化しているだけ。そして、それは相手も同じこと。
なので、ケンカの時はグッとこらえて「言葉にしないで」一晩寝かしましょう。
そのひと晩が言語的隠蔽を避け、より正しい「自分の気持ち」を相手に告げるための、貴重な時間になるのです。
心理的トラップを回避せよ
人は集団になると手抜きをする
「三人寄れば文殊の知恵」とも言いますが「船頭多くして船山に上る」とも言います。
“たくさんの人がいるのに”ではなく、“たくさんの人がいるからこそ”名案が浮かばないのです。
まず一人に拍手をしてもらいます。とにかく一生懸命に。そして、その音量を測定します。その後だんだん人数を増やしていき、それぞれに音量を測る。すると、人数が増えれば増えるほど、一人当たりの音量は減っていくことが判明したのです。
人数が増えるほど、その集団のパフォーマンスは衰えることがわかっています。
人間は無意識のうちに、集団で自分の力量が評価されにくい状況になると、手を抜く習性があるのです。
手を抜く習性を防ぎ、集団として高いパフォーマンスを発揮させるには、集団のメンバーそれぞれに役割を自覚させることです。
そこで、植木さんの提唱する、ダラダラ会議を避ける手段は、その場で考えないこと。
1.あらかじめそれぞれが考えた意見を持ち寄って会議すべし!
2.その会議は進行役に仕切らせるべし!
「アメとムチ」ではなく「アメとムシ」
マウスを使った実験として、次のようなものがあります。
まず、Tの字の縦棒の下の部分にマウスを置きます。
Tの字の上の横棒を次のような状態にします。その中で一番早く、マウスに左に行くことを覚えさせる方法を探します。
A:左にエサ(=アメ)、右には電気ショック(=ムチ)
B:左には何も置かず(=ムシ)、右には電気ショック(=ムチ)
C:左にはエサ(=アメ)、右には何も置かない(=ムシ)
実験結果は「C」でした。
この実験から得られた心理的事実は、
下手に動けば電気ショックを受ける。そのことで委縮してしまい、試行錯誤すること、トライすること自体をやめてしまう
次にどうしたらいいのか、修正するヒントが「ムチ」には、情報量が少ない
相手に「本当に成長してほしい」と思っているのであれば、だた叱るだけでは効果が低いことが分かります。成長のヒントを与えるようにしましょう。
心理的リアクタンス
なぜ不倫に走ってしまうのか?
人はままならぬ関係であるほど熱狂的で密接な関係性を築き、より離れがたくなってしまう傾向があるのです。
1980年に公開された『カリギュラ』という映画でも同じような現象が起きました。
この映画は、残虐シーンが多い、性的シーンが多い、ということでボストンでは上映禁止されました―――――上映禁止と言われたら、逆に見たくなって、多くのボストン市民が上映されている近隣の街の映画館に殺到したのです。
「禁止される」ということは、興味や関心をかき立てられるだけではく、禁止されたそのものを魅力的に見せ、価値まで高めてしまうという心理的現象があるのです。
やめろと言われるとやりたくなる。分かっちゃいるけどやめられない。
この「反発心」を心理学では「心理的リアクタンス」と呼んでいます。
「心理的リアクタンス」の正体は、「自分で決めたい」という本能。「自己効力感」と呼ばれる本能の表れです。
ヒトに限らず、高等な霊長類は「自分のことは自分で律したい」という本能を、遺伝子レベルで持っているのです。
だからこそ私たち人間は、好き嫌いや得意不得意を自ら選択し、能動性を持って自発的に学び働き、その結果として、高度で創造的な文化を築くことができたのではないか、と私は思うのです。
つまり、人間にとって、自己効力感を保つこと=人間らしく生きること、と言っても過言ではない。
集団になると手抜きする、という本能のままにおもむいていたら、大きな組織になればなるほど崩壊する危険性が増すだけ。それでは現代文明どころか、伝統的社会ですらまとまらなかったでしょう。
「アメ」が欲しいから働いている、「ムチ」が怖いから働いている。果たして人間とはその程度の存在なのでしょうか?
数多くの心理的トラップがあることは上述しました。しかし、そのトラップを避ける作戦を編み出し続けることができたから、人類はこれだけ高度な文明を築き上げたのです。
「自分のことは自分で決めたい」という「自己効力感」。これが人間を人間たらしめるもの。
とはいっても、人間の中には心理的トラップ―――――「シロクマ」がいます。
「シロクマ」の存在を認め、上手に飼いならしていく。
考えてみれば、思い出してみれば、種々の学問・古典・偉人賢人の言葉にも、心理的トラップにはまらず、上手く対処する方法が書かれています。
それが現代では「認知心理学」と「記憶心理学」として研究されています。
その研究成果を学べば、心理的トラップを回避して、より幸せに生きることができるのです。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
