
旅立ち ・・・死を看取る
今日は夜勤です。
11月には3人、今月に入ってお二人の方を見送りました。
昨日旅立たれたおふたりがまだお部屋にいらっしゃったので
先程までお部屋で、安らかなお顔を拝見しながら最後のお話をさせていただいていました。
先日、日勤のヘルパーさんに
「夜、怖くないの?」と聞かれました。
病院勤務時代から、度々聞かれる質問です。
「怖くないの?」
多分、そう聞く人は怖いのかもしれません。
夜の病院。
夜の薄暗い長い廊下。
昔から怪談話の舞台には欠かせない場所。
何故かと言えば、やはり「死」のイメージがつきまとうからなのでしょう。
私は怖くないよ、と答えます。
最初から怖くなかったのか、と聞かれたとしても
私は怖いことはなかったと答えます。
病院時代はそれこそ誰もが知る大病院勤務でしたし
救命、ICUという特殊性もあって、死は当たり前のように日々目の前にありました。
ご遺体の横で仮眠をとったこともあるし
深夜の病院の誰もいない薄暗い地下二階、霊安室を横切って職員用のお風呂にひとり浸かっていたし
空きベッドで寝ていて深夜目覚めたときに、白い服の血まみれの女が目を見開いて目の前にいる、なんて経験は一度もしたことはありません。
ただ、単なる慣れかと言われたら多分違うと思うのです。
星になる|hidejun2|note(ノート)https://note.mu/hidejun2/n/n1b395d6aad1f
のエントリーのコメントでも触れましたが
私がはじめて人の死に立ち会ったのは、まだほんの小さい子供の頃でした。
自宅の布団で、死へ向かい旅立った祖父。
あの頃はまだ、家で死ぬということがギリギリ当たり前の時代だったのでしょう。
「人はどうやって死んでいくのか」
それを日々肌で空気で感じながら、「その日」を受け入れる準備をしていくのです。
それは小さい子どもにとっても同じことで
身近な死を学ぶことは、また生を学ぶことでもあったのです。
今は、日常生活から死が消えてしまった。
人はいつか死ぬのだと、それだけは誰にでも平等に与えられた事実が
あまりにも現実から遠く離れたところに置き去りにされてしまったことによって
忌み嫌われ、恐れられ、到底受け入れられないものになってしまったのかもしれません。
そして死を知らない人間は
形は様々に、生をないがしろにする…

death educationという言葉はご存じでしょうか。
「死への準備教育」
こう言ってしまうと、ある限局した人たちへの教育と誤解されがちなのですが
全ての人にdeath educationを、という考えを持った活動です。
日本にこの考えを持ち込んだアルフォンス-デーケン上智大学教授は
「自分に与えられた死までの時間をどう生きるかを考えるための教育」と位置付け
さらに平山正実氏は、将来訪れる死に対する準備としてだけではなく
「死を思い 死を体験することを通して、現在の生き方そのものを問い直し、より充実した生を送ることを目指す」という意味において
「生と死の教育」と題字しています。
このような考え方というのは、もともと「いのちをたいせつにしましょう」といった形で
教育現場でもなされてきたことではあるのですが
より具体的に分かりやすく、心に届く形でということでは
私が「死生学」を学んだ10数年前からあまり進んでいないように思います。
ただ、このような「死」にまつわる特集は現在一般紙においてもなされ、
時には映画のテーマにもなるなど、専門分野の人間だけではなく一般の人たちも入り込めるような間口は広がっているようにも感じます。
難しい本を読んでわかる類いのことではないのですよね。
経験。
これがいちばん難しいのかもしれません。
ホスピスや老人ホームと、幼稚園、保育園を併設する。
まだ日本では少ないケースですが、これは本当に理想的なことで
死にゆく人、高齢者にとって小さな子どもたちから得る光とパワーははかり知れず生き甲斐となり
子どもは老いを自然に受け止め、昨日まで話していた誰かの死を知ることでdeath educationされ生命の尊さを学び
death educationはまた「生の準備教育」となるのです。
このような現場の機運の高まりは、そこここであるのですが
実現して当たり前になっていくには、まず大人たちの深い理解が必要なところが悩ましいです。
死や老いから離れてしまっている現代、そして少子化。
今の教育現場の現状や、親の望む価値観をみていると
反対さえ起こりそうな気もします。悲しいことです。
もちろん死生感はそれぞれで、非常にプライベートな問題でもあり
何がよくて何が悪いなんてことは言えないのですけれど。
日本ホスピス、緩和ケア研究振興財団の小冊子「旅立ち」から抜粋します。
ほとんどの人が自宅で死を迎えていた昔と比べて、現代人の多くは病院で死を迎えます。
日常生活から死が姿を消してしまったといっていいでしょう。
人がどのように弱り、どのように死を迎えるのかに関して、現代人は徹底的に経験不足です。
避けられない家族との別れに関して、あらかじめ心の準備をしておくことが大切です。
(中略)
それぼど詳細な知識でなくとも、知っていることと知らないことの間にはずいぶん大きな差があります。
家族と別れることはとてもつらいことですが、このつらさから逃れる事ができる人はひとりもいません。
それならば、あらかじめ別れの準備をしておくことが大事なのではないでしょうか。
この小冊子が多くの人に読まれ、
死という現実に目を背けず、死を受け入れる一助になることを願っています
**********
この小冊子「旅立ち 死を看取る」は
世界各国で無料配布されているものです。
簡単だけれども具体的な死についての記述があります。


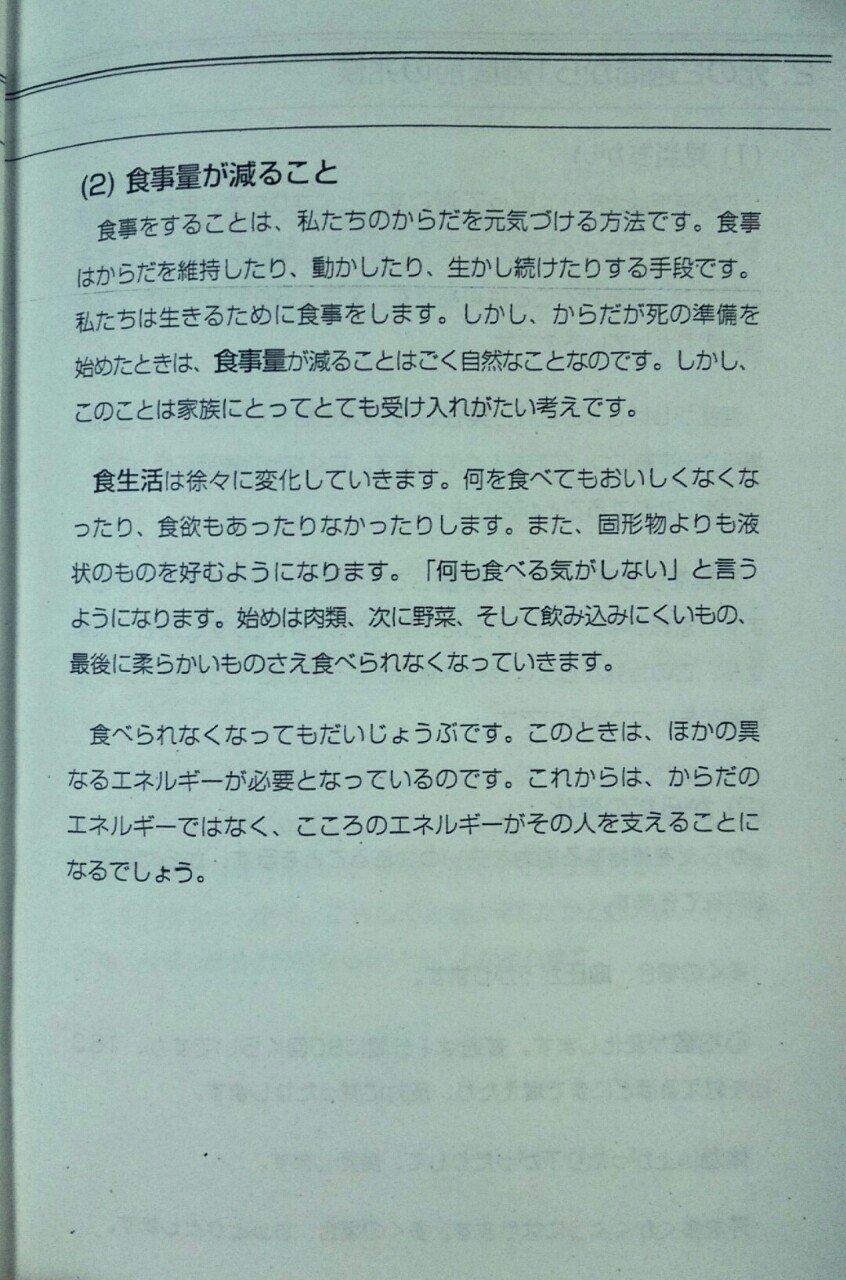

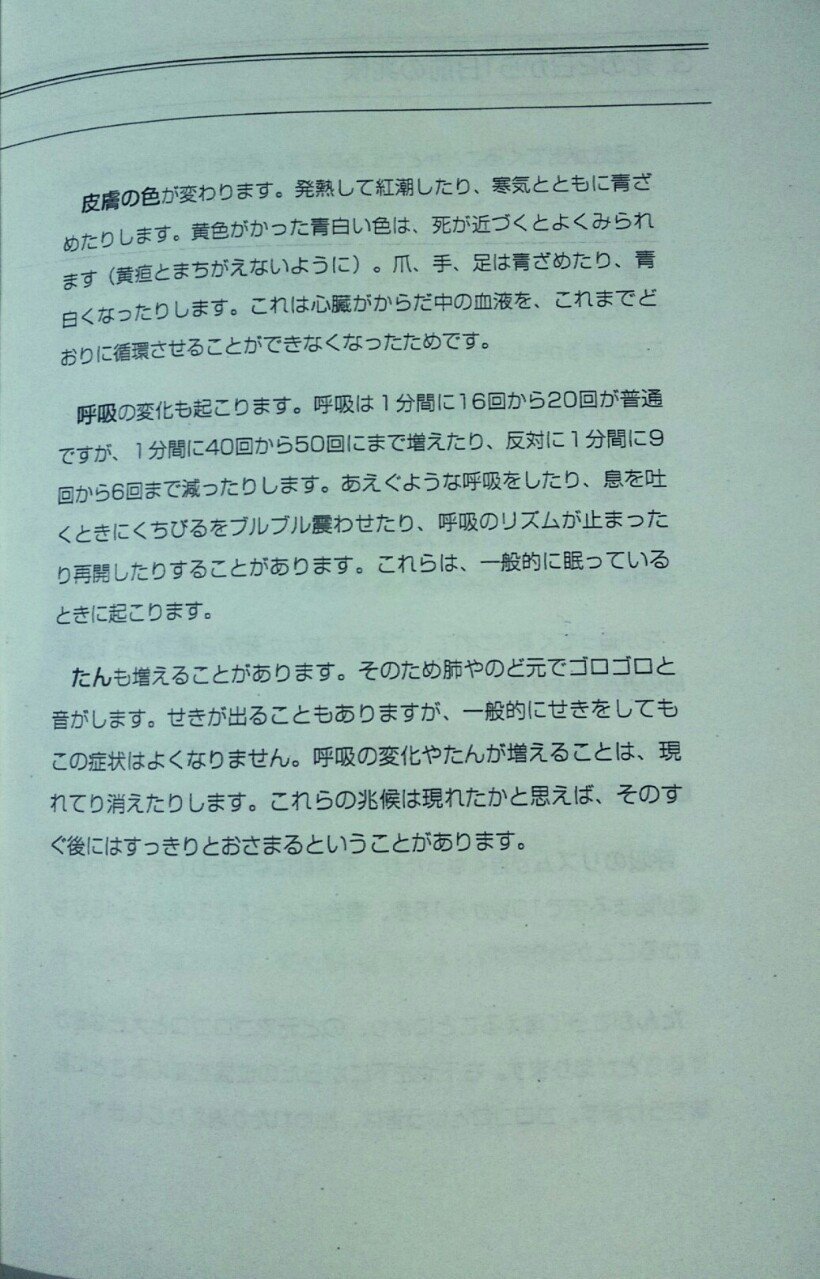
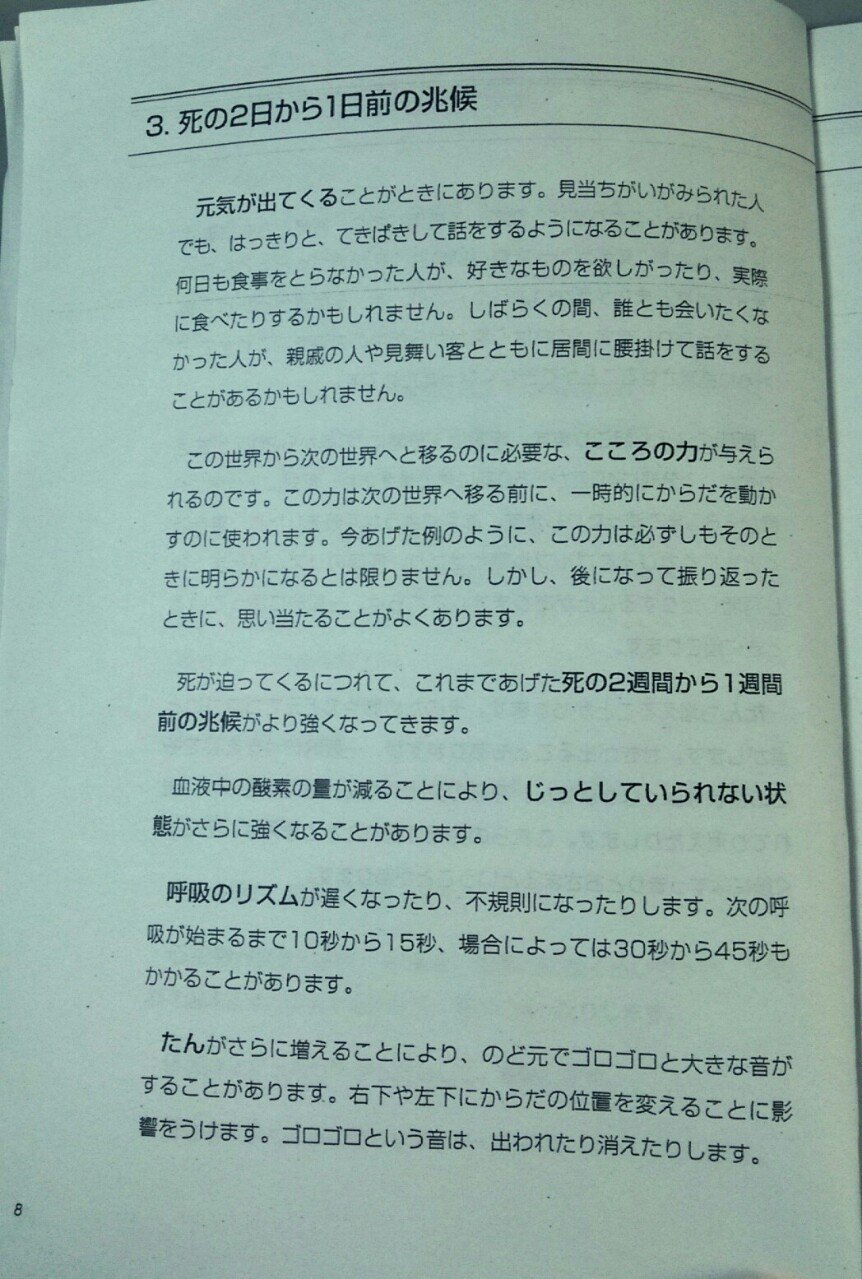
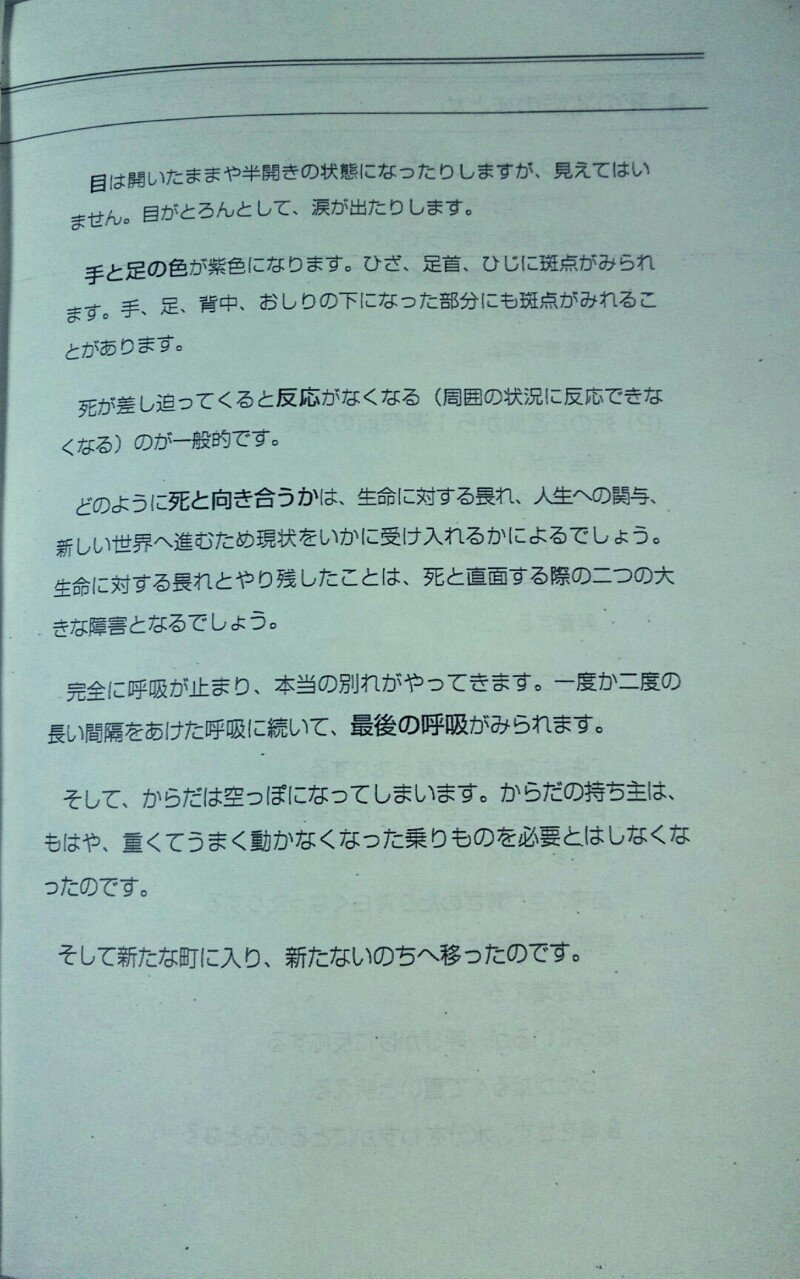




なかなか触れることない世界だと思いましたので、紹介させていただきました。
これをきっかけに、自分と家族と大切な人のいのちをまた、考えて欲しいと
この年の瀬も迫り、浮き足立つ季節にあえての話題を。
またしても仕事の合間に、星になったお二人のご冥福を心から祈りながらの乱文です。
わたしのいのちを、あなたのいのちを
慈しんで、しばしの休息に入らせていただきたいと思います。
長いお話、最後まで読んでくださって本当にありがとうございました。
感謝。
おやすみなさい、また明日お会いしましょう。
最後に、このうたを。

私は海辺に立っている。
海岸の船は白い帆を朝の潮風に広げ、紺碧の海へと向かってゆく。
船は美しく強い。
私は立ったままで眺める。
海と空が接するところで、船が白雲の点となりさまようのを。
そのとき海辺の誰かが言う。
「向こうへ行ってしまった!」。
「どこへ?」。
私の見えないところへ。
それだけなのだ。
船のマストも、船体も、海辺を出たときと同じ大きさのままだ。
そして、船は今までと同様に船荷を目指す港へと運ぶことができるのだ。
船が小さく見えなくなったのは私の中でのことであり、船が小さくなったのではない。
そして、海辺の誰かが
「向こうへ行ってしまった!」
と言ったとき、
向こうの岸の誰かが船を見て喜びの叫びをあげる。
「こちらに船がきたぞ!」。
そして、それが死ぬということなのだ。
そう、ひとつの水平線が私たちの視野を分かつだけのことなのだ。
ヘンリー・ヴァン・ダイク
神よ、もっと遠くまで見渡せるよう、どうか我々を高みまで引き上げてください(ブレント司祭)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
