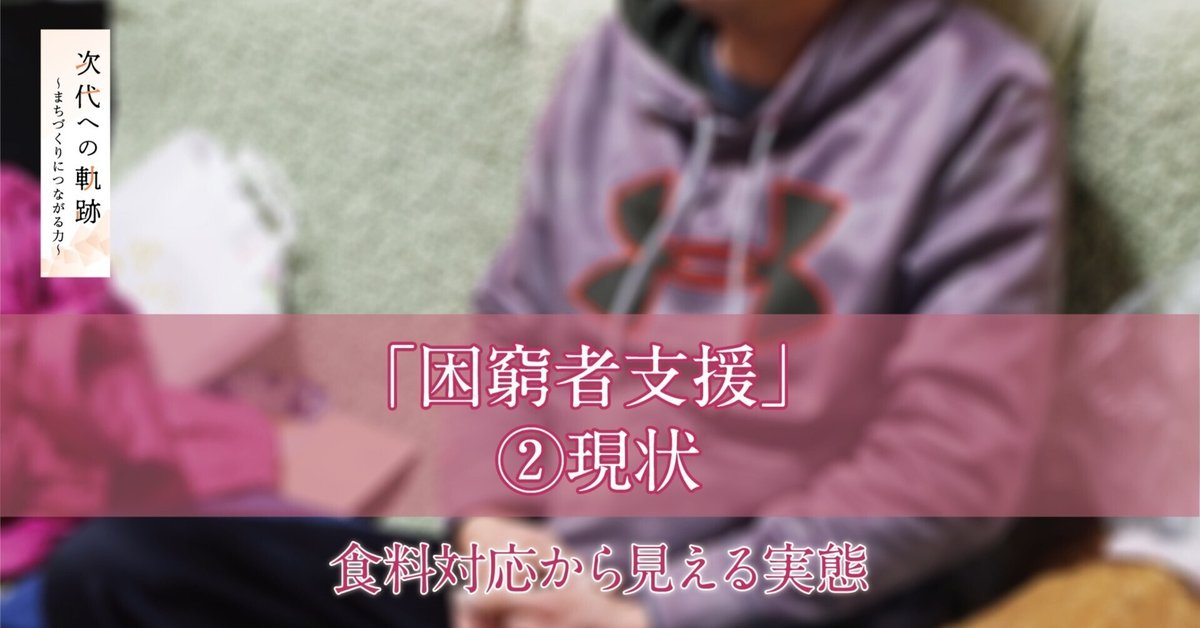
「困窮者支援」②現状 食料対応から見える実態
生活困窮者を把握するきっかけとなるのが食料支援と生活援護資金の貸し付けに関する相談だ。フードバンクや社会福祉協議会などに寄せられる声を足掛かりに関係を築き、対象者の状況調査や自立に向けた支援を進めている。特にフードバンクは一人親世帯への直接支援もしており、食料支援件数が地域の困窮世帯数把握の手掛かりとなっている。
県北部を管轄するフードバンクいしのまき(末永博代表)によると、令和元年度の食料支援要請数は約800件。それがコロナ禍に見舞われはじめた2年度には約1300件に増加。3年度は1月中旬時点で前年度の総数に近づき、オミクロン株の流行で新規の支援要請が増加中だ。
特に一人親世帯では、学校の休校や放課後児童クラブの閉鎖が生活の負担となっている。給食がないことで家庭での食費がかさみ、子どもの面倒を見るため働きに出ることも難しく、結果減収につながっているという人もいる。一人親以外も、失業と勤務日数減に伴う減収の影響を受けている人も多く、専門機関からの要請に基づいて支援を進めている。
支援する食品は、市民や企業などから寄せられる善意。近年は社会貢献とSDGs(持続可能な開発目標)を絡めて活動に取り組む企業や団体の動きがあり、「飢餓をなくす」「食品ロス削減」への貢献策として食品寄付が増えている。令和元年の寄付食品は11トン。2年度が27トン、3年度はすでに約30トンが寄せられている。2年前と比べて3倍だが、在庫過多でなく、それだけ支給対象がいる。
食品配送作業の負担も増えていることから、現在は地元のスーパー「あいのや」に協力をもらい、日配便を活用して石巻地域外の大崎市や栗原市に食料品を届けてもらっている。支援団体と民間の連携が一層広まれば対象者が増えても迅速な食料支援体制を維持することができる。
ただ、フードバンクは困窮者に対して永久に支援を続けるわけではない。「困窮者をおぼれている人だとすればフードバンクは浮き輪を投げるだけ。泳ぎを教え、岸にたどりつかせるのは専門機関の役割。浮き輪だけでは自立の足掛かりにはならない」と末永代表。
あくまで自立に向かう過程で食事に対する不安を緩和し、働き先の確保や生活保護を受けるまでの空白期間を補うための支援措置であることを強調する。
自立や保護制度とつながって初めて困窮者があすに向かうことができる。困窮者支援の要は、やはり相談窓口であり、相談という一歩をどう踏み出してもらうかが、困窮者の把握と早期対応の鍵となっている。【横井康彦】

現在、石巻Days(石巻日日新聞)では掲載記事を原則無料で公開しています。正確な情報が、新型コロナウイルス感染拡大への対応に役立ち、地域の皆さんが少しでも早く、日常生活を取り戻していくことを願っております。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。皆様から頂くサポートは、さらなる有益なコンテンツの作成に役立たせていきます。引き続き、石巻日日新聞社のコンテンツをお楽しみください。
