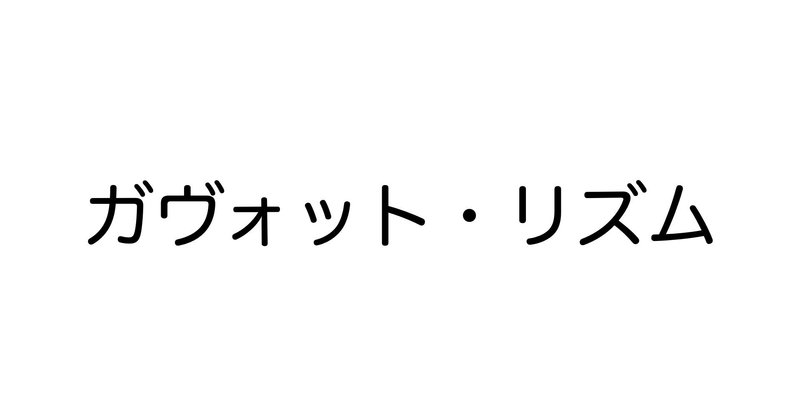
古典派のロンドにしばしば見られるリズム(ガヴォット・リズム)について
ロンドは舞曲ではない
最初に言っておくがクラシック音楽のロンドは舞曲ではない。ロンドはバロック時代のフランスで発達した形式であり、同じメロディーが同じ調で何度も戻ってくるような楽曲のことである。J.-B. リュリ(1632–87)や、F. クープラン(1668–1733)が好んで用いたためヨーロッパ中に広まり、極めてフランス的な意味を帯びた形式となった。フランス語ではrondeauと書くが、他の国ではrondo と書かれることが多い。
だからロンドを日本語で輪舞曲という場合があるがこれは間違いだ。実は輪舞曲という言葉はかつてはワルツを意味することもあった、円舞曲という用語が優勢になって輪舞曲をワルツの意味で使うことはなくなった。輪舞曲がロンドの意味で用いられるようになったのがいつからかは分からない。
(ただしロンドという言葉が生まれた13世紀にはロンドは舞曲の一種であった。そしてその語源はラテン語のrota「輪、車輪」であるので、中世のロンドの意味ならば輪舞曲という訳語が可能ではある。)
ロンドはしばしば特徴的なリズムを持つ
だが、舞曲ではないのにも関わらずロンドはしばしば特徴的なリズムを示す。これはフランスでよく使われていたリズムが、作曲家たちの間でいつのまにかロンドによくあるリズムとして認識されていったものと推測される。
この特徴的なリズムを、古典派オペラにおけるロンド・アリアの研究者たちは「ガヴォット・リズム」と呼んでいる。それにならって、ロンドでしばしば見られるリズムをガヴォット・リズムと呼ぶことにしよう。
ガヴォット・リズム
ガヴォットは間違いなく舞曲である。16世紀にブランルという踊りの一種として発展し、バロック時代に入ってから独立した舞曲としての地位を確立した。17世紀の半ば、おそらくリュリの出世と時を同じくして宮廷舞踏として発達し、18世紀の前半におおいに流行した。
ガヴォットのリズムの大きな特徴は、小節の半分を占めるアウフタクトから開始し、まるで全てが半小節ずらして書かれているかのように、そのアウフタクトから始まる区分を守り続けることである。ガヴォットは、ガヴォットと名の付く作品の99%以上が同じリズムを持つと思えるほど、均一性の高いジャンルなのだ。
次の譜例はJ. S. バッハ(1685–1750)のフランス組曲第5番からのもので、極めて典型的なガヴォットのリズムを持っている。(音源)

ただし、最も有名なガヴォットであろうF.-J. ゴセック(1734–1829)のガヴォットは典型的なガヴォットではない。作られた時代もフランス革命の数年前であり、ガヴォットとしてはかなり遅い時代のものである。(音源)

J.-P. ラモー(1683–1764)なども典型的でないガヴォットを多く書いている。
ロンドに見られるガヴォット・リズムとは例えば次のようなものだ。
ベートーヴェン(1770–1827) 作品51「2つのロンド」第1曲(1797作曲) (音源)

一見して奇妙さが分かるだろう。というのは、普通は次の譜例のような書き方をするものだからである。

ガヴォットの記譜法とその理由
このような記譜法はフランス的なものである。
16世紀にはそういう記譜法は見られなかった。こうした書き方が生じたのは1650年ごろのフランスであると推測される。推測というのは、17世紀前半はフランス音楽の楽譜の資料が乏しいため、生じた時期を特定できないからだ。
小節線を一定の間隔で引くようになるのもだいたいこのあたりの時代からである。
このころから、ことフランスのガヴォットに限ってはほぼ必ず、このような小節の真ん中から始まる書き方がなされた。そしてイタリアや、ウィーンではまだそのような書き方は見られなかった。
なぜフランスでそのような書き方をするようになったのか、はっきりとしたことは分からない。
ここでは私なりの仮説を述べておこう。それは、フランスで17世紀の半ばに、メロディの運動の到達点(カダンス)を小節線の直後に合わせるという考え方が生じた、というものだ。同じ頃のイタリアでは小節線はもっとまばらに引かれており、歌詞やメロディーのリズムとの関係も薄い。
また、運動と小節線を関連付ける場合も、フランス以外の地域では運動の開始の直前に小節線を引くのが普通だった。
次の譜例はJ.-B. リュリの『アルセスト』(1674)のガヴォットで、歌が付いているものである。小節線の直後に、歌詞の3〜4音節程度のまとまりの終わりに当たる強い音節が常に現れている。2小節ごとに脚韻が-アンドル (prendre, -tandre, -fendre) と-マン (-ments, -ments, -mants)というふうに踏まれているのでわかりやすいだろう。
(音源)

Jeunes cœurs laissez-vous prendre le péril est grand d'attendre
Vous perdez d'heureux moments en cherchant à vous défendre;
si l'amour a des tourments c'est la faute des amants.
漕ぎ出でよ若者たち、待っていてはならぬ。
お前たちは潮目を逃すのだ、自分を守らんとするばかりに。
もし愛に苦しみがあるなら、それは恋人たちあやまち。
ガヴォット式記譜法の限界
さらに時代が下って18世紀の初頭になると、F. クープラン(1668–1733)やJ.-F. ダンドリュー(1682–1738)といった人たちがこのような書き方をさらに徹底しようする。
例えば、この音源を聴いてみて欲しい。これはクープランの組曲20番(Ordre 20)からの1曲である。(音源)

多くの人は上の譜例のような譜面を想像するのではないだろうか?ところが実際の譜面は次のようなものである。

このような書き方が一貫しているのであれば、まだよい。だがこの後、音楽は下の譜例のように続くが、最後の16分音符による下降は明らかに小節の先頭から開始する運動に変わってしまっている。この譜例の後は再びほぼ冒頭と同じ形が始まる。

F. クープランではこのように、終止形に用いる記譜法と、そこに至るまでのメロディーの記譜法が異なっている場合が多く見られる。そのため、終止の前後に音が詰まったり、間が不自然に開いたりする場面が生じてしまう。
結局、ガヴォット式の記譜法は、ガヴォットという極めて規則的な音楽においてのみ持続可能な方法であるということが認識されていったのである。
こうしてクープランの死後、18世紀の半ばになるとガヴォット式の記譜法は偶数拍子で、規則的なフレーズ構成を持つ音楽でのみ生き残る結果となった。
ロンド形式の流行
このようなガヴォット式の記譜法の流行と同時期に起こったのが、ロンド形式の流行であった。実際、F. クープランのチェンバロ曲の多くは、ロンド形式で作られている。
クープランのチェンバロ曲は、多くが洒落たタイトルを持っていた。そして楽譜には、繰り返し現れるメロディーにはRondeau、その間のエピソードにはCoupletと書かれている。
このようにタイトルを付ける流行は、クープランが亡くなったころ(1733)には廃れ始めた。その一方で、ロンド形式の曲のタイトルにロンドーと添える書き方が広まっていった。
やがて洒落たタイトルを付ける習慣は消え失せ、曲のタイトルにはただロンドーとだけ書かれるようになった。
この結果、偶数拍子のロンドーはガヴォット的な記譜法を持つというイメージが形成されたのである。
もちろん、ガヴォットとは異なり、ロンドーは偶数拍子であっても必ずしもガヴォット的な記譜法を持つとは限らない。
また、洒落たタイトルが流行する前にも、ロンドーというタイトルを持つ曲はあったし、ガヴォット・リズムを持つ場合もあった、ということは言っておこう。
古典派時代
18世紀の半ばになっても、ロンドの流行は続いている。
同じメロディーを何度も聴くことができるロンドは、聴き手にとっても満足できる形式であったし、作曲家にとっても簡単に曲を引き伸ばすことができて都合が良かった。ソナタ形式が第1主題の再現を持つようになるのも、ロンドの影響が大いに考えられるところである。
イタリアオペラもこの形式を取り入れたアリアを採用していく。そのようなアリアは「ロンド・アリア」と呼ばれ、オペラ・セーリアでフィナーレの直前に歌われるアリアとしての地位を確立していくことになる。
そのようなロンド・アリアの初期の有名なものが、グルックのChe farò senza euridice (1762)である。
冒頭のリズムは異なるが、途中で小節の真ん中から始まるガヴォット的なメロディーが出てくる。これはフランスのロンドーの影響であると考えられる。
1760年代はロンドンでもロンドの流行が見られ、やはりしばしばガヴォット的なリズムを持っていた。
次の譜例はJ. Ch. バッハの作品5-5のソナタの3楽章である(1765年出版)。(音源)

バロック時代のガヴォットとは異なり、このころからロンドにはしばしば、メロディーだけ半小節ずれたリズムが見られるようになる。この曲のように、最初の半小節が完全なアナクルーシスに聞こえるようなリズムは、バロック時代のガヴォットとは全く違ったものである。
クレメンティ(1752–1832)
ムツィオ・クレメンティはイタリア生まれだが、14歳からイギリスに渡っているので、イギリスの作曲家とみなすべきだろう。
クレメンティの作品1のピアノソナタは1771年にロンドンで出版されたものであり、第4番の3楽章のロンド楽章にはガヴォット・リズムが見られる。(音源)

有名な作品36のピアノソナタも、4番、5番、6番のロンド楽章はガヴォット・リズムを持っている。(4番のロンド楽章)(5番のロンド楽章)(6番のロンド楽章(6/8拍子))
モーツァルト(1756–1791)
子供の頃からパリやロンドンへ演奏旅行に行っていたモーツァルトは、こうした流行も自然と取り入れていた。
ピアノ協奏曲第6番K.238(1776)の終楽章はロンド楽章であり、J. Ch. バッハの例で説明した新しいタイプのガヴォット・リズムを持つ。(音源)

モーツァルトはピアノソナタのロンド楽章などの他、オペラでもロンド・アリアを作曲している。次の例はコジ・ファン・トゥッテより『Per pietà, ben mio, perdona(恋人よ、許してください)』で、ガヴォット・リズムを持つロンド・アリアだ。ロンド・アリアはしばしば緩急の2部分からなり、2テンポ・ロンドと言われる。
ハイドン(1732–1809)
ハイドンがガヴォット・リズムを頻繁に使用するようになるのは1780年代に入ってからのようだ。
交響曲79番(1783–4)のロンド楽章を例に挙げておこう。(音源)

交響曲第89番(1787)のロンド楽章も挙げておく。(音源)

ベートーヴェン(1770–1827)
ベートーヴェンはピアノソナタのロンド楽章でしばしばガヴォット・リズムを用いた。伴奏は小節に一致する新しいタイプのガヴォット・リズムがよく見られる。
ピアノソナタ第4番(作品7)の第4楽章。(音源)

ピアノソナタ第9番(作品14の1)の第4楽章。(音源)

次の譜例は作品12の3のヴァイオリン・ソナタの第3楽章のロンドの冒頭で、小節の強拍を強調しようとする意図が明確である。(音源)

伝統的なガヴォット・リズムと、新しいガヴォット・リズムの違い
だがこのように表記上の小節の強拍を強調することは、本来のガヴォットやガヴォット式の記譜法には無かった特徴である。
バロック時代のガヴォットはどれも、まるで小節線を動かしただけのように感じられる。伴奏も最初の半小節から同時に始まるのが普通であった。
ところが新しいガヴォット・リズムでは、メロディーだけが半小節先行し、伴奏は小節線の枠組み通りのリズムを持つ。
編曲によって歪められたガヴォット・リズム
マラン・マレー(1656–1728)によるロンドー(1686年出版)は、誤って『リュリのガヴォット』として知られており、20世紀初頭にピアノソロやピアノ伴奏のヴァイオリン曲などとして広まったようだ。この編曲者は本来のガヴォット・リズムではなく、新しいガヴォット・リズムとして伴奏を加えたため、この曲は伴奏とメロディーがずれたちぐはぐな曲に聞こえる。
次の譜例が、マレーによるロンドーの譜面である。(音源)

次の動画はピアノソロ版である。
アマリリス
有名な『アマリリス』は19世紀にヘンリー・ギースHenri Ghysが「ルイ13世(1601–43)が作った」との触れ込みで売り出したものであるが、伴奏との関係が新しいガヴォット・リズムになっており、到底17世紀前半に作られたものとは思えない出来であることが分かるだろう。しかも17世紀前半にガヴォット式の記譜法が普及していたのかどうか分からない。なおこの曲の4手版は7歳のモーリス・ラヴェルに献呈されている。
カテゴリー:音楽理論
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
