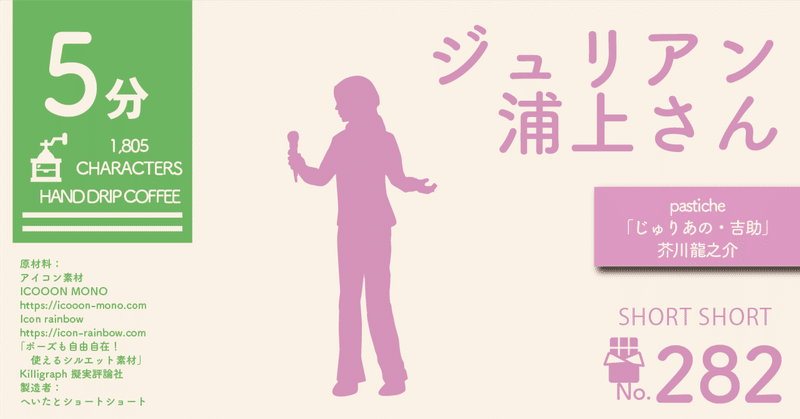
ショートショート ジュリアン浦上さん【じゅりあの•吉助|芥川龍之介】
コーヒー屋で、浦上さんという方と何回めかのミーティングをする。助成金の申込書類を作る手伝いをするためだ。
ジュリアン浦上というのが浦上さんのステージネームだ。生粋の日本人で、「ジュリアン」部分は仮名。「浦上」の部分が名字。本当の名前は「善雄」。どうして「ジュリアン」にしたかは知らない。
大変に背の高い人で、よくステージの天井に引っかかる。帽子を被ると柱に引っかけて、必ず帽子が落ちる。その度にステージ上で右往左往する。突然カツラを被ったり、髪を銀色に染めたりもする。白髪が嫌いなのだろう。『帽子を被らなければいい』とは言い出せない。
ジャズから童謡まで幅広いジャンルを歌う。音域も広い。特に高音域が強い。女性の歌でも平気で歌う。昔はもっと高い声出たのにとよく悔しそうに言う。
何度か聞いたが、要領を得ない。それでもざっくりとまとめると、浦上さんは帰国子女だ。小さい頃からほとんど海外にいたらしい。だから英語もフランス語もドイツ語もできる。頭の良い方だ。
どこがどうなるとそうなるのか分からないが、日本語は不得意で、話すと品のいいおばさまみたいな喋り方になる。お母さんの話し方なんだろうか。『日本語が苦手』ということを本人も自覚しており、自分が咄嗟にメモを書くと英語と日本語がぐちゃぐちゃになる。それを見返す度に悲しいのと泣きそうな顔で言うのを聞いた。
ニューヨーク、ニューオリンズ、ボストン、ブルックリン。浦上さんの話はうさぎのように跳ね回る。経緯はわからないが、若い頃の彼は神様に出会う。マイルス・デイビス。モダンジャスの帝王だ。ジャズに取り憑かれた浦上さんは単身アメリカに渡る。声とピアノの腕を磨く。いくつかの武勇伝を懐かしそうに話してくれる。
ここまでは本当だ。多分。
ニューヨークで浦上さんは、ちょっとした事故にあう。ビルが丸ごと崩壊するようなやつだ。テロですか?と言いかける私を浦上さんが止める。
「UFOよ。宇宙人がワタシを迎えに来たの。」
そう。そうか。
私は口をつぐむ。浦上さんは、仕事で知り合った人だ。上に手伝ってやってくれと言われている。私が手伝うのは浦上さんの個人事業主として必要な書類の事務であり、記憶の整理ではない。
それに、実は事前に調べてある。テロの現場にいた浦上さんは事故のショックで精神を壊し、歌手なのに声が出なくなった。彼のミュージシャンとしての人生はそこで一端死んだ。リハビリ。暗闇を這いずり回るような。長い長いトンネル。ようやく声が出た頃には身体が衰えていた。髪が白髪で埋まるほどに。
「これの領収書は、ちゃんとありますか?」
仕事の話を。私は仕事に来たのだ。カウンセリングに来たのではない。
浦上さんの話をまとめると、おおよそこうなる。
浦上さんは何万光年か離れたなんとかいう星の第8王子である。なんとかいう星は王様の後継問題で争いが絶えない。心優しい浦上さんはその争いに酷く心を痛めた。自分がここから消えれば、争い事がひとつ減る。そこで地球に逃げてきたのだ。
『マイルス・デイビスに憧れてニューヨークに渡った』と言う時と同じ口調、同じ調子、同じ熱心さで、浦上さんは星を追われた話を続ける。
最初は自分にその記憶はなかった。けれどあの時、ビルの爆炎を見た時、全てを一斉に思い出した。あれは故郷の宇宙船だ。ワタシを連れ戻しにやってきたんだ。争いは嫌だ。隠れなくては。
そう。浦上さんの記憶では、声を出すためのリハビリは、故郷の星から見つからないための逃走劇だ。暗闇を這いずり回るような。事実は変わらない。何が真実かは知らない。
書類を整え、今日はこれで終わりですよというと、チケットをくれた。浦上さんの出るコンサートのチケットだ。丁寧に頭を下げてお断りする。行ける場所かを確認し、一枚買い求める。
同情ではない。
聴いたら、きっと分かる。
少なくとも「ニューヨークで歌っていた」までは真実であることが。
もし、分からなくても、コンサートまで足を運べば、天使の歌声に涙する人を目の当たりにすることができる。
コーヒー屋を出ると、もう日が暮れようとしていた。
遠くで星がきらりと光った。
いつか私にも、故郷の星の迎えが来てしまうのだろうか。背筋が寒くなる。そうしたら、狂気は私を毛布みたいに優しく包むのだろうか。
書類の入ったカバンの持ち手を握り直す。ここにあるのは事実だけだ。
真実は、分からない。
ショートショート No.282
本作は芥川龍之介の短編「じゅりあの・吉助」のパスティーシュです。
「鼻」でもなく「羅生門」でもなく「薮の中」でもなく、多分かなりマイナーであろうこの作品が、芥川龍之介の短編の中で一番好きです。
隠れキリシタンを題材にしており、この時代の作品としてはそんなに珍しいテーマではないと思うのだけれど、主人公の信仰が『間違っている』と言う点で、他と一線を画します。そして、物語の語り手はそのことについて主人公を責めたりはしません。『正しい』信仰をする者と同じように、もしかするとそれよりも美しい奇跡を主人公にもたらします。
信仰ではなく、信じる、という行為そのものにもたらされる祝福です。
たまに仕事(因みにショートショートはパスティーシュ用に作られたもので、私はこういう仕事に従事している者ではありません。)で、まったく接点のない方と二人きりで数時間に渡り話をしなくてはいけない時があります。
そして、ごくたまに、相手の方の話の奥の方に、自分にはまったく理解のできない信仰(宗教に限ったものではなく、何か強烈に信じているもの)の気配を感じて、怖くなる時があるのです。
目の前にいる人(そこにいるその人に限らず)の心の奥は底なしの闇で、理解しきることなどできないのだという僅かな感触、そういうことを、私はとても恐ろしく感じてしまう。
理解できる信仰の美しさと、理解できない信仰への恐怖が隣り合わせに描かれていること。
私は、この話のそこが、きっと好きなのです。
※不定期で古典作品のパスティーシュを作っています。
前回の作品は坂口安吾「桜の森の満開の下」です。
