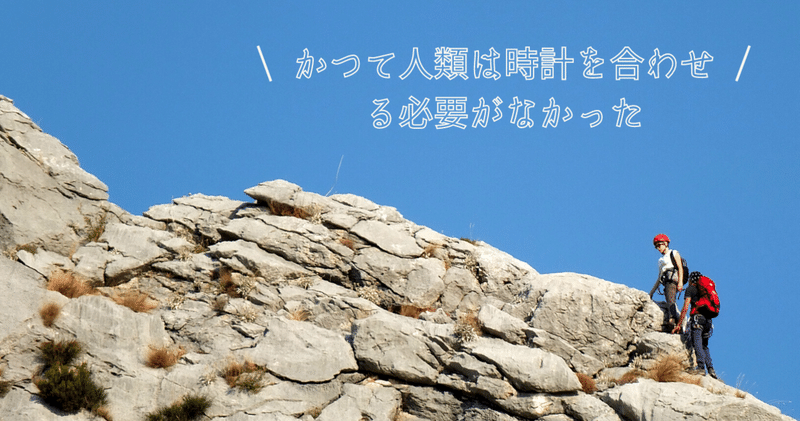
かつて人類は時計を合わせる必要がなかった
かつて人類は時計を合わせる必要がなかった。パリに行けばパリの太陽が時間だったし、北京に行けば北京の月が時間だった。かなり時代が下がって鉄道が走るようになっても、初期のパリ駅の時間は、遠い他の駅とは違う独自のものだった。
夏の時間は冬の時間よりも長かったし、秋の時間と春の時間とは違う意味を持っていた。時はかつて普遍でなく体感であり、意味を告げるものでもあった。

「時間の流れが違う人のそばにいると、深く癒される気がします」
私の好きなアーティスト、遥奈さんがそう話してくれたことがある。
そういえば私も生徒に、そんなことを感じていた気がする。
とてもゆっくりゆっくりと勉強を進める生徒A。あいつはあいつ独自の時間を感じているのだろう。彼の時間、リズムとかその速さを感じながら教えると、優等生になることはないけれど学校で心底困るということもなくなる。それをしなければ五教科の合計が、2点とか4点だったと思うけれど。
彼の時間と私の時間を合わせると、本当に信頼して感謝してくれる。そんな生徒たちがいてくれると、私もなにか正気に戻ることができるのだ。

アリストテレスは「時間とは変化である」と言っていたそうだ。すなわちである。変化がなかったならば、時間が経過していないことになる。私が引きこもっていた時には、まるで周囲の時間まで止まってしまった気がした。それはたまらなく悲しく、気が焦る時間であったけれども。
しかし、その日に流れる時間をしっかり感じてみると、たしかに落ち着く。太陽がくれる時間を感じて話を切り出すと、安心してもらえるのだ。スーパーのおばちゃん、ホテルのクラーク、彼岸の墓参りに来ていた老夫婦。今日出会った方は、みんなそうだった。
ひきこもりの私は、カウントダウンの時間にばかりはやらされてしまっていたんだと思う。

敬愛する井坂康志先生が、いつかこう言っていた。
「私は、あるときから詩人と名乗ることにしました」
研究者や編集者という誰から見ても通用する普遍的な職業でなく、自分がこうありたいと心から願っている職業を名乗ったのだと。
「その時から気持ちがとても安定するようになりました」
そうおっしゃっていた。
先生は先生の時間をとても大切にされている。私が先生の講座をとても好きで毎回ほぼ欠かさず出席させていただいているのも、井坂先生のまわりに流れている時間を感じたいからかもしれない。私自身も芯から癒やされるのだ。

もし、どこへ行っても時間は一様であると考えるのなら、それは学校で習う時間に慣れてしまっているからだ、と『The order of time』のカルロ・ロベッリは言う。体感できる、意味のある時間の存在を人は忘れてしまっているのかもしれない。
起業家がトラウマから復活し自らのすべき仕事を掴むとき、これまでとは趣向が違った音楽を聴くようになることがある。Jポップを聞いていた人がレゲエを聴いたり、ゲームミュージックを好んでいた人が、ヒーリング音楽を聴いたりと。
リズムを変えて時間を捉えているのではないかと思う。強制的にカウントダウンされる時間でなくて、自らが身に纏うべき時間を。そして、自らが纏った時間とは、事務所を経営される先生の場合、詩人と表現すべきものだったと私は思うのだ。

ならば、私自身は自分のまわりに流れる時間を、どう表現すればいいだろうか。
考えてみたけれども、それは中学の時に好きだったイギリスのあの有名な探偵なのだと思う。私はシャーロック・ホームズを自分なりにアレンジした時間に存在しているのだ。いやはや、いろいろとトラブルが多いはずである。
ならば、あなたはあなたの周りに流れる時間を、どういう職業で表現するだろうか。
メカニック、整体師、音楽家、セラピスト、医者、泥棒、地球防衛軍???
井坂先生の場合は、詩人ゲーテが念頭にあるのではないかと想像している。
「人からどう見られたいのかを考えられる人。自己中心的でない方とはそういう方なのである」
とは、いにしえの心理学者ピアジェの言だ。
自分が身に纏っている時間。それを感じ取って表現できる職業を、自分勝手に考えてみること。私は自分勝手に陥らない手段として、それも一興なことだと思うのである。

お読みくださいまして、誠にありがとうございます!
めっちゃ嬉しいです😃
起業家研究所・学習塾omiiko 代表 松井勇人(まつい はやと)
下のリンクの書籍出させていただきました。
ご感想いただけましたら、この上ない幸いです😃
サポートありがとうございます!とっても嬉しいです(^▽^)/
