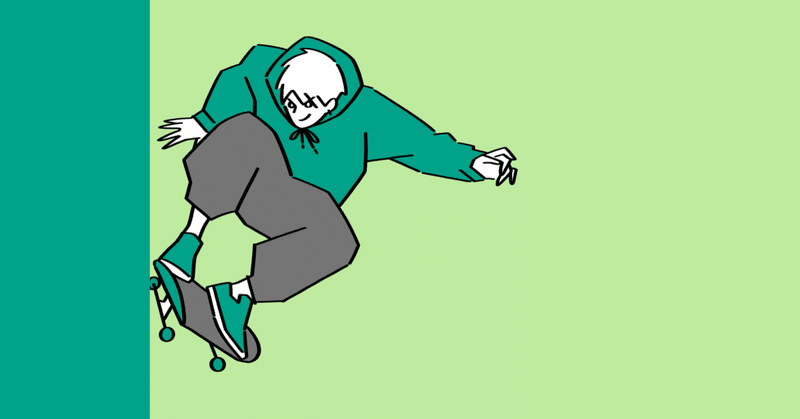
コロナ禍で実践!ハイパフォーマンスを出し続ける、効果的な在宅勤務と出社の使い分けとは
おはようございます!健康で幸せにはたらく人を増やしたい、現役サラリーマン【はたらくオクノ】です。
9月最終週の月曜日ですね!半期決算を控え、繁忙期に突入されてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、ハイパフォーマンスを出し続けるための在宅勤務と出社勤務の使い分け方について、産業医科大学による大規模調査結果より考察してみたいと思います。
こちらの調査は、2020年12月ごろの新型コロナ「第三波」時に、全国の労働者3万人を対象に、コロナの健康影響を調査したものです。
論文発表された8つの知見のうち、相互に関係があると考えられうる因子を紐付け、ハイパフォーマンスを出し続けるポイント三つにまとめました。
ポイントその1:在宅勤務の頻度は、本人が自分で決める
コロナ以前の在宅勤務は、育児・介護者で希望者のみ実施できる、在宅勤務可能な習熟度・業務を持った従業員が希望すれば選択できる、といった対象者に制限がある「働き方の新しい選択肢」でした。
入社から年次の浅い新入社員や、在宅勤務に適さない職種の社員は、そもそも選択できなかったりしたんですね。
ところが、コロナ禍になり、会社の方針として感染症対策を徹底するために、本人の希望に関わらず在宅勤務を推奨する場面が多くみられるようになりました。
背景には、政府が企業に対し出社率を3割に抑制することを推奨したことと、それを受け産業界(経団連などの業界団体)が応じる形で、企業には在宅勤務の状況などをHPやニュースリリースで情報開示することを求めた、という事情がありました。
ここで、産業医科大の大規模調査より得られた知見をみてみましょう。
①在宅勤務を望まない人ほど、在宅勤務が増えるとメンタルヘルスが悪化
②月1日〜週3日程度の適度な在宅勤務はワーク・エンゲージメントを高めるが、週4日以上の高頻度はワーク・エンゲージメントを高めなかった
ワーク・エンゲージメントとは、主に従業員のメンタル面の健康度を示すもので、主体的に仕事に取り組んでいる心理状態を示す言葉です。ワーク・エンゲージメントが高い状態とは、「熱意・没頭・活力」の3尺度が高い状態を表します。
こちらの知見からは、本人が「どこで」働くかという場所の裁量と、「どれくらいの期間」在宅勤務で働くかという時間の裁量が、ハイパフォーマンスにとって重要な要素であることがわかります。
感染症リスクを抑えるために、移動や物理的接触を最小限にできる在宅勤務は有効な手段です。一方で、長期的にパフォーマンスを発揮し続けるためには、次の二つを意識するといいでしょう。
①会社の方針で「在宅勤務をさせられている」感覚を持たないよう、自分が希望するタイミングで希望する働き方を選択すること
②出社が億劫になるタイミングがあっても、たまには出社して同僚と対面コミュニュケーションをとること
高頻度での在宅勤務が悪いということでは決してなく、「自分で主体的に選択できている」という感覚が、パフォーマンスにとっては重要であると言うことですね。
ポイントその2:自宅の仕事環境を整える
産業医科大の調査では、次の知見が指摘されています。
仕事環境が不適切な場合、在宅労働は労働生産性を低下させる
企業では、什器やプリンターなどの設備投資や、休憩室の設置など、働きやすい執務環境へある程度投資されています。
一方、自宅はそもそも働くためではなく、暮らすため・生活のための空間であるため、人間工学的に「働くこと」に不向きな場合が多くあります。
たとえば、ダイニングテーブルは、食事をするための道具として設計されており、そこでそのままPC作業をしてしまうと、目線が下がって肩こり・頭痛の原因になるなど、働く場所としては工夫が必要なんですね。
新しく在宅勤務用の机・椅子を購入できる、スペースがある方はいいのですが、なかなか難しい方もいらっしゃるはずです。そんな時は、便利グッズで整えていきましょう。
一番大事なのは、目線の高さを水平に保つこと。PC作業で目線が下になることを防ぐため、「パソコンスタンド」を使ってみてください!私も使っているのですが、今年1番のいい買い物だったと思います。
価格は1,000〜5,000円ほど。折りたためる・高さ調節ができる・切り替え調節が二段階になっているものをお勧めします。
ポイントその3:職場での感染症対策を徹底する
①通勤や職場での感染不安がメンタルヘルスに影響
②感染対策の取り組みが少ない職場で働く人は、精神的不調を抱えるリスクが増加
③特に中小企業は、大企業に比べ職場での感染対策の実施率が低かった
なんと、職場で感染対策をしているかどうかが、働く人のメンタルヘルスに大きな影響を及ぼしていたのです。これは結構衝撃でした。企業ができる努力がある、と言うことですね。
感染対策とは、マスク着用の徹底、発熱時の出社禁止などのルール化など、費用をかけなくても、呼びかけにより実施できるものも多くあります。
打ち合わせは密閉空間ではなく換気を意識する、打ち合わせで対面する人数を減らし、着席するときは真正面を避けて入れ違いに座る、など、運用上のルールでできる対策もあります。
会社で推奨していなくても、自分たちのチームではやってみよう、とリーダーや一人ひとりが意識することで、メンタルヘルスが良好になる可能性があると言うことです。
特に、対策が進んでいる大企業より、中小企業に勤める方は、注意が必要ということですので、自分からできる行動でみんなのメンタルヘルスを守っていきましょう!
まとめ
以上、本日はハイパフォーマンスを出し続けるための在宅勤務と出社勤務の使い分け方について考察してみました。
ポイントその1:在宅勤務の頻度は、本人が自分で決める
ポイントその2:自宅の仕事環境を整える
ポイントその3:職場での感染症対策を徹底する
職場でも、自宅でも、高いパフォーマンスを発揮するために、できることから取り組んでいきましょう!本日も、読んでくださってありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
