
棘の森と手を繋ぐ
心は、柔い。
どんなに鉄壁の防御で守っていても、その深層部にあるのは驚くほど繊細で柔らかで、不確かなものだ。普段なら有効に活用されるはずの防御壁も、何かしらの要因が重なると案外呆気なくひび割れたり崩れたりする。それはときに悲しみであったり、怒りであったり、憎しみであったり、はたまた愛情であったりする。
防御壁が崩れているときに、さらなる追い打ちをかけるかのように新たに誰かの悪意ある言葉や何の気なしの一言が入り込んできた場合、人の心は容易く棘を孕む。その棘の切っ先の行方は、本人だけが握っている。他者に向けるか、自分に向けるか。それともどうにかその先端を丸くするのか。どれが正解かは、実際のところ分からない。
私は、その先端を随分長いこと両親から向けられて生きてきた。両親の棘の正体を大人になって理解した今、それでも「何故、自分だけが」と思ってしまうのを止められずにいる。兄もいた。姉もいた。両親のサンドバッグになったのが、何故私だけだったのか。その理由は、未だに分からない。おそらく死ぬまで分かることはないだろう。
こういう事象は、特に珍しいことでもない。家族のなかで一人だけをスケープゴートにする。その一人に”負”のすべてを被せ、他の家族の平穏を保つ。表面的には何の問題もない、むしろよくできた”家族”の出来上がりだ。
スケープゴートにされた私は、自身のなかに少しずつ棘を蓄え続けた。その痛みを持て余し、怒りの対象である両親に向けようと思ったこともある。しかしそれは、妄想の域を出ることはなかった。
真っ暗闇の台所の床は、ひんやりと冷たかった。ぎしりと軋む床をぐっと踏みしめながら、目の前に光る銀色の刃を呆けたような目で眺めている。そんな自分の背中を、今でも夢に見る。
家を出て両親から離れられれば、自身のなかに巣食う棘の森は抜け落ちていくものだと思っていた。抱えきれない怒りも、憎しみも、きれいに溶けだして流れていくものと思っていた。しかし、現実は真逆だった。
虐待から解放された私を一番初めに襲った最も大きな感情は、”怒り”だった。
抑え込み、飲み込み、吐き戻してもまた飲み込む。その繰り返しで溜め込まれてきた抱えきれないほどの大きな怒りが、私の内部を侵食していた。棘の森は私のなかの一部なのだと思っていたのに、その範囲は私の想像をはるかに越えて、外側までにょきにょきと蔓を伸ばす有様だった。
必死に抑え込もうとした。自分がされてきたのと同じ方法で誰かを傷つけてしまうくらいなら、もうすべて終わらせてしまったほうがよほどマシだと思った。しかし、一度外れたブレーキは、もう元通りにはならなかった。
解放された。自由になった。そう思っていた。でもそれは同時に、「怒っていい」自由をも手にすることだった。抑え込むしか術のない17年を生きてきた私は、正しい怒り方を知らなかった。
仕方なしに、棘の切っ先を自身に向けた。痛みはあったが、慣れ親しんだそれは、哀しいほどに私に安寧をもたらすものでもあった。
自分が悪い。そう思う一方で、そんな自分を哀れにも思っていた。でもそれを表に出すことはなかった。
同情なんてされたくない。上から見下ろして、安全なところから「可哀想に」と言われる。そんなのはまっぴらだった。「可哀想」と言うくせに、助けてはくれない。そんな大人をたくさん見てきた。どこかで分かっていた。自分もいずれは、そういう大人になることに。でもそれを、当時の私は認めたくなかった。
いつも人前ではしっかりと立っていた。倒れるときも、泣くときも、自身を刻むときも、私はいつも一人だった。痛みは晒すものではなく、ただ隣にあるものだった。家の冷蔵庫に納豆や卵が入っているみたいに。雨の日に傘をさすみたいに。それは珍しいものでも何でもなく、当たり前に私の横でじっとりとした笑みを携えて手を伸ばしてきた。
怒りが腐敗すると、憎しみになる。私のなかで感情が移行するまでに、さほど時間はかからなかった。腐敗したそれは、酷い臭いを放っていた。饐えたような、それでいて禍々しい臭い。
感情を放出するために書き殴る癖は、この頃にはすでに板についていた。でもそこに書かれているのは、文字でしかなかった。言葉でも文章でもない。ただの、悪臭を放つ文字の羅列。それらを眺めながら泣くときもあれば、憎しみをぶつけるように上からぐるぐると色を塗りつぶすときもあった。
いつも最初に塗る色は、黒だった。そのあとで、必ずといっていいほど後悔した。青にすれば良かった。青で塗れば、その憎しみも溶け出してくれるかもしれないのに。海と同じ色の、青なら。そう思って上から色を重ねてみても、やっぱり黒のまんまだった。
変われない。
そう思った。どこにいても、何をしていても、過去が付いて回る。べったりとまとわりつく怒りは、姿こそ変化するものの、大きさそのものが変わることはなかった。大きな面積の棘の森は、蕾を付けることも花を咲かせることもなく、日陰と痛みと嫌な臭いだけを私に与え続けた。
文字が並んだノートは赤黒い色に染まり、びりびりに破られたり焼き捨てられたりした。そんな自分を、どこか遠くから見つめている自分がいた。怒りが膨れ上がるほどに心が遠のく。
焼ききれそうな感情の奥に、じっと蹲る小さな女の子がいた。その子は、泣いていた。声も立てず、身動き一つすることなく。その子は、私だった。口がゆっくりと動く。でも、聞き取ることができない。その子が何を言いたいのか、私にはどうしても読み取れない。聞こえない。はたと気付く。そのとき私は、目を瞑って耳を塞いでいた。その子の声を、私は聞きたくなかった。叶えてやれない願い。それを聞いてしまったら、自分が壊れる。
タスケテ。
その子の唇は、間違いなくそう言っていた。でも、私には見えなかった。見えなかった、と、そう思わなければ、朝ご飯を食べることすらできなかった。
両親への怒りは、いつからか自身への怒りに変わっていた。あの頃の自分を助けてやれなかった。どうにかできたかもしれない。何か方法があったかもしれない。そう思えば思うほど、脳内がぐつぐつと熱くなった。沸騰しそうな怒りが私を焦がす。熱い。痛い。でもあの頃の私は、もっと熱くて痛かった。それなのに、私は何もしなかった。あの子を助けなかった。されるがまま、ただじっと耐えるだけの毎日を強いた。
あの子の声は、虐待されていた当時から聞こえていた。聞こえないふりをしていただけだ。私は痛みをずっと、あの子に押し付けてきた。その子は、私だった。でも、私ではなかった。
*
「お前は悪くないって言ってんだろ」
「何回言わすんだよ、お前は悪くない」
「バカか、お前は。死んだほうがいいのはお前じゃなくて、お前の親のほうだろ」
実家に住んでいた頃、両親に虐げられていることを知りながら寄り添ってくれていた、幼馴染がいた。地獄のような日々のなかで、彼がかけてくれた言葉。それだけが、光だった。その光だけを頼りに、ぎりぎりのところで踏みとどまった。
彼が私にくれたものは、”杭”だった。自分を薄めることで生き延びた。でも薄めれば薄めるほどに、命の色も弱まった。生への執着が消えかかるたびに、強い力で引き戻される。その力に抗って終わらせようとしても、どうにもあと一歩が思いきれなかった。彼がくれた杭が、私をこの世に踏みとどまらせた。
大量の薬を服薬して、気が付いたら病院の白い天井を見上げていたこともある。腕には点滴の針が食い込むように刺さっていて、でも、痛みはなかった。生きるための水分が血管から流れ込むのをぼんやりと眺めながら、またか、と思う。また、生き残ったのか、と。100錠の安定剤は、致死量ではなかった。少なくとも、私にとっては。私より若い親戚は、もっと少ない容量でこの世を去ったのに。生きる人と、死ぬ人。そこに明確な境目なんてない。それをまざまざと思い知らされる。
生きたい人が生きれるわけでもないし、死にたい人が死ねるわけでもない。聖人君子が長生きするわけでもなければ、悪人が早死にするわけでもない。そもそもが理不尽なのだ。生も死も、人にはどうにもできない。抗えない強い力がたしかに存在していて、それを人々は”神さま”と呼ぶ。私は神さまを信じていない。叫ぶように祈ったけど、助けてくれなかった。だから、信じない。でも、幼馴染の言葉だけは信じられた。
「何でお前は自分を傷付けるんだよ。親がお前を傷付けるからって、お前までお前を傷付ることないだろ。そんなことしたって、痛いだけだろ。なんで傷付いたぶん、優しくしてやらないんだよ。優しくしてやれよ。憎む相手、間違ってるだろ。お前は、お前を傷付けた親を憎んでいいんだよ」
怒りに飲まれ、憎しみに駆られ、自身の中に巣食う棘の森に飲み込まれそうになる。でもそのたびに僅かに差し込む光に気付いた。
私はいつしか、その光を思い出しながら書くようになっていた。それは日記であったり、エッセイであったり、小説であったりした。それは、文章だった。文字の羅列ではなく、過去の自分に向けた言葉であり、手紙だった。誰にも見えない場所でそれを書いては、何度も何度も読み返した。
その頃、私はもう幼馴染と連絡を取っていなかった。互いに、互いを想う。想うが故に、苦しかった。そうして、私たちは手を離した。それでもその後の私を救い続けてくれたのは、紛れもなく彼の言葉だった。
”憎んでいいんだよ”
そう言ってくれた人がいた。憎しみの感情を、許してくれた人がいた。溺れそうになるほどの強い感情。怒りを根源にした、腐敗した感情。でもそれを、単純に良くないものとして切り捨てずに認めてくれた人がいた。そのことを書いて、読んで、書いて、繰り返し自身に染み込ませた。何年かが経った頃、ふと気づいた。棘の森が、小さくなっていたことに。
怒りの感情。それは、自尊心の裏返しでもある。守るべきものを犯されたとき。理不尽な痛みを植え付けられたとき。人は、怒っていい。
怒りと悪意は違う。悪意は人を傷付けるだけのものだが、怒りは自身を守るために必要なものだ。
もちろん、伝え方は考えるべきだ。どのようなカタチで表に出すか、それを考慮するひと手間を省いてしまえば、怒りは簡単に新たな憎しみを生む暴力へとすり替わる。
怒ることが悪なんじゃない。怒り方が問題なのだ。
抑えつけられてきた感情は、暴発しやすい。出し方も分からなければ、ほどよい抑え方も分からない。何事も極端によりがちだ。時間をかけて、じっくり向き合っていくしか術はない。
未だに怒りの感情を扱うのは苦手だ。一度自分のなかで爆発させる。煮えたぎっているそれを、すべて飲み込む。消化する。整理する。そこからようやく表に出すので、いつもワンテンポ、ツーテンポ遅れてしまう。結果、とても怒っているのだけど、それが相手になかなか伝わらなかったりする。
激情型のくせに、瞬発力がない。厄介なものだけど、色々あったわりには今の自分の感情コントロールはまぁまぁ上出来だとも思っている。
*
小さな女の子は、もういない。私であって私ではなかったその子は、私のなかに溶けた。
棘の森は今でも内部に存在している。時々その棘を剥き出しの心に食い込ませてくることもある。痛みは、なくならない。
それでも、もうその痛みに飲まれることはない。杭だった彼の言葉は、今も私のなかに生きている。昨年末再会したとき、彼は言った。
「生きててくれて、良かった」
私たちが互いに望んでいたのは、それだけだった。たったの、それだけだった。
私を生かしてくれた人が、ちゃんと生きていた。私も、ちゃんと生きている。それで、十分だ。
命は理不尽で、世界は残酷で、人の悪意はなくならない。それでも、やっぱりこの世界はきれいだと、怒りを体内に抱え込みながらもそう思いたい私がいる。
生きろと言ってくれた人がいた。そんな人がたった一人でもいたこの世界は、今も昔もきっときれいで、でも私はそれを見ようとはしなかった。ただ怖くて、強く目を瞑っていた。
目を開く。耳を澄ます。手を繋ぐ。”怒り”とだって、きっと手を取り合うことはできる。
怒りは、私だ。私が抗い続けてきた証でもあり、生き延びるために必要な原動力だった。今も隣にいる。でももう、変な暴れかたはしない。
これからも仲良くしよう。あなたは私で、私はあなただ。もう、嫌ったりしない。
ありがとう。あなたは、私を守ってくれた。
*
こちらのコンテストに参加させて頂きます。
ずっと向き合い続けてきた、自身のなかにある怒り。その感情を言葉にするきっかけを与えてくださり、ありがとうございました。
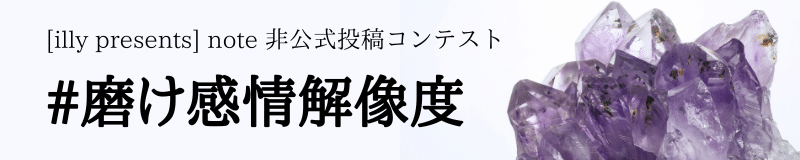
最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。 頂いたサポートは、今後の作品作りの為に使わせて頂きます。 私の作品が少しでもあなたの心に痕を残してくれたなら、こんなにも嬉しいことはありません。
