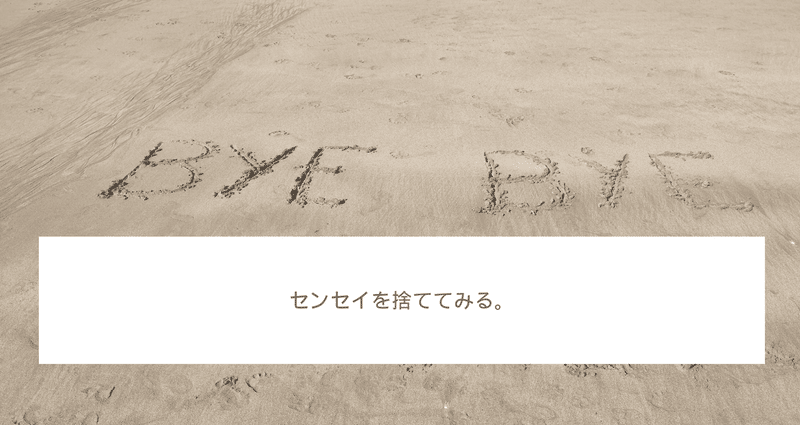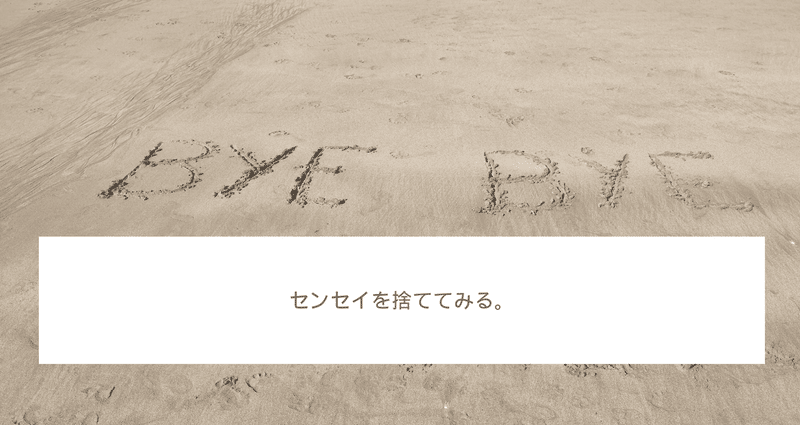いじめをなくすのは、私たちではなかった。 #センセイを捨ててみる。
多様であることが自然であり、
多様であることが生き残りにつながり、
多様であるからこそ刺激的で、
多様であるからこそ惹かれ合い、
多様であるから自己の相対化が図れる。
日本の学校教育が多様性から距離を置こうとするのは
何千年もの間続いてきた島国根性が、いまだに抜け切れていないからです。
他国との関係にとどまらず、
隣県と、
隣の市町村と、
隣のブロックに住む人と、
隣の学校と、
隣の席に座っている人とでさえ、つながらない。
身近なところで、
きわめて狭いエリアで、
自分