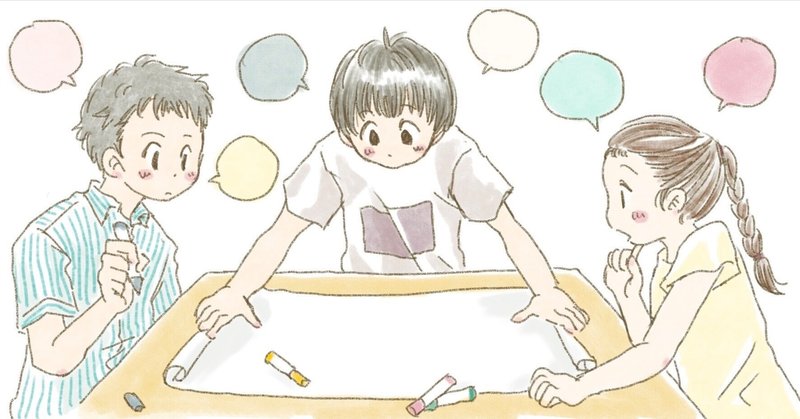
「子供の声を聴く」ということ
金曜担当のりょーさんです。前回は教育や子育てって何だ?!って話をしましたが、今回は自分の子育て体験から考えたことを書いていきます。
朝起きてこない、息子…
小学6年生の息子が朝起きてこない日が続いていました。
多分学校行きたくないんだろうなって思いつつ、親としては、あまり気にしないようにしていました。触れてなかったというか、、、。
とりあえず親からでる言葉は「起きなさーい!」です。
嗚呼、、、ガミガミは親の永遠のテーマなり笑。
でもでも、自分たち夫婦なりに、そんなガミガミを抑制しつつ、、、「なんかあるんだったら話してね」って種まきだけしておいて待ちの姿勢です。
先日、ついに「休みたい」と。
こういう時、親はまあ、、、不安なもんです。
が、なるべく「話聴こう!」「話を聴くチャンス!」って思うことにしています。
徹底的に受容的に声を聴くことが大事っていうのが仕事から得た経験則、、、でも、相手が自分の子供だと別のものが付き纏う…それは「不安・心配」と「長期で休まれたら困る」っていう家庭の事情。
そんな思いもあるから焦るし頭ごなしに否定したくもなる。「行きなさい!」って怒ってしまう可能性もある。
できるだけ、本人の前では、そんな気持ちは覆い隠して、とにかく寄り添って聴く!からスタートです。
本人の主張は、「学校がつまらない」ということでした。
つまらない理由は、
・委員会活動で楽しいことがつぶれるし、その話し合いがあまり成立していない。
・友達と喧嘩した。嫌な気持ちになる。人と関わるのがしんどい。
・クラス目標をみんな真面目にやらない。
・授業中、自分は率先して発表するけどやらない人がいる。
受容的に「ふむふむ、それで?」「それのどこが嫌なの?」って感じで聴いていくと色々出てきます。
親として言いたいこともあるけども保留!…出てくる言葉をぐっと喉元に留めて、一通り聴く。その後に聴いた最後に「1番嫌なのは何?」って聴いてみるのです。
「クラス目標に向かって、自分は頑張って発表しているけど、みんなが思ったように反応してくれない、何人かの子が発表してくれない!」ってことでした。
先生がクラスメイトと話し合って決めたことを率先して頑張る、って悪いことではないです。
その目標に対して、クラスメイトが納得しているかどうかわからないですが、話を聞くと、先生はトップダウンでなく対話によって合意しようとしている感じがあります。
だからこそ率先する息子がいて、それ自体は素晴らしい!って思います。
でも、息子なりに頑張るからこそ息子の「やらない子」に対する視線は厳しい。「やらない子」にもきっと事情がある。
これもなかなか難しい問題です。
父、いろいろ思うけど飲み込んで聴く
判断は挟まないようにしつつ、僕としてはいくつかの視点を持って聴いていました。
「率先して発表している息子は自分を押し殺していないか?」「役割が固定化されてプレッシャーに変わっていないか?」 一方で「本人は実はそれに役割を感じてワクワクしているのではないか?」
また、息子が率先することでみんなも頑張ろうとしていると聞いて、それは親として誇らしいことでもあるけども、それによって追い詰められる生徒がいないか?
誰かが「自分らしく」いられたとしても、それによって「自分らしさ」を押し殺す人もいる、これが「他者と共に生きる」ってことの難しさであり重要な視点です。
そんなことをボヤボヤ考えながら、話を聴いていました。
泣きながら一通りお話したあと、「こういうクラスにしたいんだ!」って言葉が出てきました。そして息子はスッキリした顔で「やっぱり行く」って言って、4時間目から学校に向かいました。
「子供の声を聴く」ということ
仕事上、不登校の子供たちに出逢います。
多くが育て方のせいでも本人のせいでもないです。
あえて言えば発達段階と環境と関係性などの複雑な組み合わせのエラーみないなもののせいです。
だから、誰にでもそれは起きうる。「うちの子に限って…」はないのデス。
そして、事例をいくら知っていても、やはり自分の息子がそうなるってことは、(色々大変なのもわかっているので)不安ではあります。
親として今回、ちょっとした不安に直面して、やはり思うことは「子供の声を聴く」ことの大切さです。
「絶対に怒らないし、考えていることも否定しない」という前提で話を聴く。
子供はそれがわかると安心し、自分の言葉で語り出します。その言葉は必ずしも「大人にとっての正解」ではないかもしれません。そこも一切評価を入れないようにまずは聴いてみる。
その時に子供は、他者との対話だけでなく、自分との対話をしているのです。
そしてそれを受け止めてくれる他者がいることで、そこで初めて他者の声も聴こうとする。そういう営み・プロセスが、「他者」という存在を信頼し、「共に生きていく」ための基盤作りをしていくものになるのだと僕は考えています。
「聴く」が教育や子育ての基盤になる営みなのです。

ま、そんな自分もまだまだできてないんだけどね!
そして自分の子供の声を聴くのは、今回みたいな何かあった時だけ。「普段から、俺は聴こうとしているか??」とちょっと内省的に考える時間となりました。
普段は「学校どう?」って投げかけても、反応は「別に」「何も」です。
めっちゃむずいーーー笑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
