
日常の対義語は? 『ぼくの死体をよろしくたのむ』を読んで。
コピーライティングを仕事にしていると、「なんでもなさそうなことをおもしろく書いてほしい(要約)」といった要望がたびたびある。
しかしながらこの場合、なんでもなさそうなことを、あからさまな虚飾によって見所のある言葉に構成することは、ほとんどない。
物事に二面性を求めるコピーライターの性(?)が作るフィルターを通せば、面白くないものを探す方が難しいからだ。
正義の反対には不義が、美点の反対には欠点が、生の反対には死が存在するように、実際にはなんでもないことの反対、というか裏面というか中面には必ず相応の魅力が存在している。
そして、おおよその場合、実際にはその事実に気がついていたとしても、実態を掴むことは難しい。
それが、ぼくたちのような表現者に仕事が与えられる理由である、とも考えられそうだ。
『ぼくの死体をよろしくたのむ』は川上弘美先生の短編集で、合わせて18篇の物語が収録されている。
川上先生の作品は『溺レル』『パスタマシーンの幽霊』『猫を拾いに』『神様』『センセイの鞄』等々etcetc読ませていただいているけれど、当書は川上先生の魅力が際立つ、とても贅沢な内容だった。
川上先生の作品は、日常に潜む非日常、生と死、愛と憎悪なんかを織り交ぜて表現されているのが常だ。
ただ、ぼくが思うに川上先生のこうした作風は、対義的な表現を軸にしている。とは、言い切れない。
先に記した「面白くないものはない」という主張にも関わってくるのだけれど、川上先生の場合は、物事の反対を見つめているのではなく、裏面(背後、とも言えるか)を表現していると考えたほうが、すっきりする。
「日常と非日常を暖簾一枚の気軽さで行き来する」と美村里江氏が評した帯コメントが絶品で、川上先生の作品は、全体を通してシュルレアリスム表現が差し込まれる割には、純文学作品にありがちな重たさが存在しない。
思うにそれは、穿った視点で、遠く離れた場所から観測した物事の反対を表現するのではなく、そこにぴったりと張り付く、裏面の存在を浮かび上がらせることに徹しているからなのではないだろうか。
反対ではなく裏面ならば、そこにギャップは存在しない。
それゆえに、抵抗感を持たせない。
余計なことを考える隙間が、ない。
美しい後ろ姿のホームレスに恋をする『鍵』でも、小人を救うために銀座で巨大な猫と闘う『銀座 午後二時 歌舞伎座あたり』でも、あまりに異常な設定や登場人物やストーリーラインを、読者はなんの違和感もなく受け容れてしまう。
そもそも裏面とは何処や? という疑問がぼくの中にもあるのだけれども、しかしそれはどこでもない、という表現が適切なのかもしれない。
歴史にその助言を求めるならば、古事記が伝える真経津八咫鏡(まふつやたかがみ)は、真実、つまりは心の裏面を見せる鏡らしい。
当書は、鏡に写った自分を見るがごとく、ごく自然な人の営みを読者に見せる。しかし実のところその虚像は、とんでもない非日常を隠し持った裏面の物語であった。というような感覚だ。
なぜ当たり前のようにこの世界観を受け容れてしまうのか自分でもよくわからないけれど、しかしそれでいて、心地よさを感じる魅力がある。
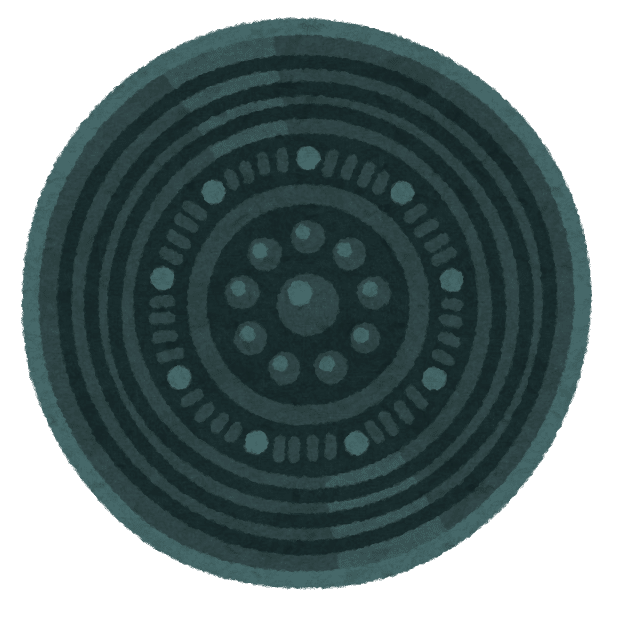
「読後感」とか「余韻」のような言葉があるけれども、当書では、どうも煙に巻かれたような感覚を持って本を閉じることになる。
例えばコピーライターの文章に求められるのは、確実な余韻というか、保証された感想であったりするわけだけれども、川上先生の作品はその点、とても自由だと感じる。読者に感想をわざわざ求めない、と言っているような気さえしてしまう。
本を閉じた時、なぜだか上手い感想を言えないのはこの物語を、まるで自分の体験であるように、つまり自分自身の裏面であるかのように感じてしまっているから、なのかもしれない。
日常の対義語はなんだろう。
と定期的に考える。
しかしまぁ、試しにオンライン辞書なんかで調べていただきたいのだけれど、答えがない。
非常、異常、奇跡、特別、緊急、異変。
対義として挙げられる言葉の数々によって、日常が構成されているらしい。
とするならば、果たして自分は、日常と呼べる環境に身を置いているのか疑問になる。
日常の反対があるとするならば、それはもうひとつの日常がそこにあるだけなのかもしれない。つまり、鏡に写った虚像のように。
『ぼくの死体をよろしくたのむ』は、気楽にそんな世界を覗き見れる一冊だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
