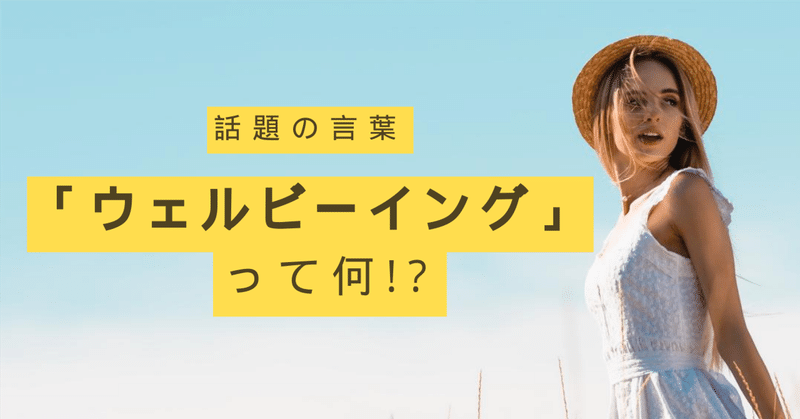
話題の言葉「ウェルビーイング」って何?
現在、「Well-being(ウェルビーイング)」という言葉が、より身近なものになってきましたね。
でも、あなたはWell-beingについてどのくらい知っていますか?
well-beingとは
「well-being(ウェルビーイング)」は、身体的・精神的・社会的に全てが満たされた状態のこと。
well-being直訳すると、をWell(よい)とBeing(状態)が組み合わさった言葉で、「よく在る」「よく居る」状態、心身ともに満たされた状態を表します。元々は「健康的な・幸せな」を意味する、16世紀のイタリア語「benessere(ベネッセレ)」を始源としています。
1946年のWHO設立に際して、設立者の1人であるスーミン・スー博士が定義づけした「健康」にWell-beingという言葉がはじめて登場します。
Well-beingの指針
ギャラップ社の調査で、Well-beingの幸福度をはかる調査軸に体験と評価があります。評価の項目は、世界幸福度ランキングの指標の1つにもなっているほどです。こういった調査をもとに導き出した5つの指針が以下になります。
1.キャリアに対する幸福
ボランティア活動や家事、育児、勉強などもキャリアの一部として捉え、仕事とキャリア面での幸福を構築すること。自分の1日の過ごし方に満足しているかという意味もあります。
2.人間関係に対する幸福
交友関係の量だけでなく、信頼でき、愛情のある人間関係であるかどうかがポイントです。
3.経済的幸福
報酬を得る手段があるのか、報酬を得られているか、報酬に納得しているか、資産を自己管理できているかなどがポイントです。
4.身体的な幸福
心身ともに健康で、思った通りに行動することが出来ているか、ポジティブな感情をもって働くことが出来ているかがポイントです。
5.コミュニティに関する幸福
主なコミュニティ(居住地や家族、親戚、友達、学校、職場)でコミュニティを形成できているかがポイントです。
上記5つの指針によって成り立ち、各個人の働き方が変わりつつある中で、それぞれのwell-beingについて考えていかなければならないとされ始めています。
well-beingが注目されている背景
SDGsの目標3番目「GOOD HEALTH AND WELL-BEING(すべての人に健康と福祉を)」といったようにwell-beingを推進することが掲げられています。
宗教や人種、生まれ育った環境、LGBTQなど異なる人々の価値観の多様化により、何を「良い・悪い」と感じるかは人によって違い、これが幸せであるという完全な指標がありません。そのため、それぞれの価値観で心身ともに幸せを感じることが大切で、より重要視されるようになってきています。この考え方はますます強くなり、SDGsのゴールでもある2030年には、well-beingの考え方が世の中の前提になるとも言われているそうです。
人手不足の深刻化。日本では労働人口が減少し、人材も流動化しているため、ますます人材を確保しづらい状況になっていくと見込まれます。こうした状況下で必要な人材を確保するためには、給与や福利厚生の充実に加え、働きやすい環境づくりや達成感を得られる職場づくりを行っていくことが大切です。
↓SDGsについての記事はこちら↓
みなさんのファッションや生活を網羅したライフスタイルの中にもwell-beingとして雑誌やテレビでも特集が組まれていますね。日本企業でも、働く職場や環境にwell-beingを導入する企業も増えています。従業員一人ひとりが日々の仕事の中で、「望む働き方」で「人や社会の役に立っている」という充実感を感じることができれば個人も社会も、もっと多様で豊かになれるはず。
世界中で広まりはじめたこのwell-being。将来どんな人も笑顔になれる世界になれる価値観になればいいなと思っています。
一緒にデザインやサスティナブルやウェルビーイングについて学びましょう♪楽しみましょう♪ いただいたサポートは活動資金に使わせていただきます!
